

概要
製造業の最新トレンドを学べる「ものづくり ワールド [大阪] セミナー」を10/1(水)~3(金)にインテックス大阪にて開催!(順次追加講演を公開予定)
「生成AI活用・DX推進」「開発・製造事例」「ロボット・自動化」「人材育成」「メタバース」など、課題に合わせて学べます。ものづくり業界のキーパーソンが毎日登壇するこの機会をお見逃しなく。
【ご注意ください】特別講演の申込みは展示会の「来場登録」とは連動していません。聴講希望の方は新規でお申し込みください。
AFEELAにおけるモビリティの新たな価値基準の創造

|
ソニー・ホンダモビリティ(株) 代表取締役 社長 兼 COO 川西 泉 |

|

ソニー・ホンダモビリティは、2023年CESにて、EVの新ブランド「AFEELA(アフィーラ)」とそのプロトタイプ車両を発表しました。車載センサー等の先進技術やエンタテインメントの強みを生かし、クラウドと連携した新たなモビリティの価値創造に挑んでいます。本講演では、2025年CES発表の情報を交え、モビリティの進化や先端AI技術を活用した取り組みなどをご紹介します。
講演者プロフィール
1986年ソニー株式会社入社。1995年にソニー・コンピュータエンタテインメントに出向、『PSP』『PS3』など主にソフトウェア開発を担当した。FeliCa事業部長等を歴任し、2014年にソニー株式会社業務執行役員SVP、2015年にソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の取締役に就任。2016年以降は『aibo』事業、『VISION-S』の試作車開発責任者としてAIロボティクス事業を牽引してきた。2022年にソニー・ホンダモビリティ株式会社代表取締役社長兼COOに就任。現在に至る。
ソニー・ホンダモビリティは、2023年CESにて、EVの新ブランド「AFEELA(アフィーラ)」とそのプロトタイプ車両を発表しました。車載センサー等の先進技術やエンタテインメントの強みを生かし、クラウドと連携した新たなモビリティの価値創造に挑んでいます。本講演では、2025年CES発表の情報を交え、モビリティの進化や先端AI技術を活用した取り組みなどをご紹介します。
講演者プロフィール
1986年ソニー株式会社入社。1995年にソニー・コンピュータエンタテインメントに出向、『PSP』『PS3』など主にソフトウェア開発を担当した。FeliCa事業部長等を歴任し、2014年にソニー株式会社業務執行役員SVP、2015年にソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の取締役に就任。2016年以降は『aibo』事業、『VISION-S』の試作車開発責任者としてAIロボティクス事業を牽引してきた。2022年にソニー・ホンダモビリティ株式会社代表取締役社長兼COOに就任。現在に至る。
※本講演を受講される方は9:30頃から展示会場にご入場いただけます
製造DXを実現するHILLTOPが描く「ものづくりの未来」

|
HILLTOP(株) 代表取締役社長 山本 勇輝 |

|

大手自動車メーカーの孫請けとして量産一筋だった町工場が、思い切った方針転換により試作製造業へ。属人的な職人技として受け継がれてきた暗黙知をデータ化し、誰もが扱える製造ノウハウへと昇華。DXの挑戦を続けるHILLTOPの革新の全貌を明かす。
講演者プロフィール
2006年、HILLTOP株式会社へ入社。現場経験/製造部長を経験し、2013年、米国法人HILLTOP Technology Laboratory, Inc.を設立。2022年、HILLTOP株式会社の代表取締役に就任。同年、高効率モータ向け、アモルファス積層コアメーカーである、ネクストコアテクノロジーズ株式会社を設立。低損失モータコア及び高性能希土類磁石事業を開始。
大手自動車メーカーの孫請けとして量産一筋だった町工場が、思い切った方針転換により試作製造業へ。属人的な職人技として受け継がれてきた暗黙知をデータ化し、誰もが扱える製造ノウハウへと昇華。DXの挑戦を続けるHILLTOPの革新の全貌を明かす。
講演者プロフィール
2006年、HILLTOP株式会社へ入社。現場経験/製造部長を経験し、2013年、米国法人HILLTOP Technology Laboratory, Inc.を設立。2022年、HILLTOP株式会社の代表取締役に就任。同年、高効率モータ向け、アモルファス積層コアメーカーである、ネクストコアテクノロジーズ株式会社を設立。低損失モータコア及び高性能希土類磁石事業を開始。
※本講演を受講される方は9:30頃から展示会場にご入場いただけます
フィジカル AI & デジタルツインの最前線 ~製造業における事例紹介~

|
エヌビディア(同) エンタープライズ事業本部 プロフェッショナルビジュアライゼーション ビジネスデベロップメントマネージャー 高橋 想 |

|

デジタルツインアプリケーションを構築するための開発プラットフォーム NVIDIA Omniverse についての概要、及び、NVIDIA がフォーカスするユースケースやリファレンスアプリケーションとなるBlueprint、生成 AI を活用した事例についても、導入例を交えてご紹介をします。
講演者プロフィール
大学で中国語を専攻後、国内商社での法人営業、外資系ワークステーションメーカーでの市場開発を経て、2020年よりNVIDIAにてプロフェッショナルビジュアライゼーション製品の市場開発に従事
デジタルツインアプリケーションを構築するための開発プラットフォーム NVIDIA Omniverse についての概要、及び、NVIDIA がフォーカスするユースケースやリファレンスアプリケーションとなるBlueprint、生成 AI を活用した事例についても、導入例を交えてご紹介をします。
講演者プロフィール
大学で中国語を専攻後、国内商社での法人営業、外資系ワークステーションメーカーでの市場開発を経て、2020年よりNVIDIAにてプロフェッショナルビジュアライゼーション製品の市場開発に従事
現場主導の取り組みが企業を変える ~現場発AI活用の真価、そのポイントとは~

|
ダイハツ工業(株) DX推進室 デジタル変革グループ長 (兼) 東京LABOシニアデータサイエンティスト 太古 無限 |

|

2017年に非公式のワーキングチーム3人で始めたAI活用の取り組みが、「仲間を増やす、テーマを集め、事例を作る」によって、今では全社のデータ利活用まで広がっています。今後は今までのボトムアップに追加し、トップダウンでより大きなテーマにも挑んでいくため、2023年1月にDXビジョンハウスを打ち出し、企業変革へと挑戦しています。製造業における現場主導のAI活用と成功のためのポイントを紹介いただきます。
講演者プロフィール
2007年ダイハツ工業入社後は開発部にて小型車用エンジンの制御開発を担当。2020年から東京LABOデータサイエンスグループ長、2021年からDX推進室データサイエンスグループ長(兼務)を得て、DX推進室デジタル変革グループ長(兼)東京LABOシニアデータサイエンティストとして、全社のDX推進する業務に従事。その他に、滋賀大学データサイエンス部インダストリーアドバイザーとして、社外におけるAI活用の普及活動にも努める。経営学修士。「Forbes JAPAN CIO Award 2024-25」にて、次世代のテクノロジーリーダーのひとりとして「チェンジレガシー賞」を受賞。
2017年に非公式のワーキングチーム3人で始めたAI活用の取り組みが、「仲間を増やす、テーマを集め、事例を作る」によって、今では全社のデータ利活用まで広がっています。今後は今までのボトムアップに追加し、トップダウンでより大きなテーマにも挑んでいくため、2023年1月にDXビジョンハウスを打ち出し、企業変革へと挑戦しています。製造業における現場主導のAI活用と成功のためのポイントを紹介いただきます。
講演者プロフィール
2007年ダイハツ工業入社後は開発部にて小型車用エンジンの制御開発を担当。2020年から東京LABOデータサイエンスグループ長、2021年からDX推進室データサイエンスグループ長(兼務)を得て、DX推進室デジタル変革グループ長(兼)東京LABOシニアデータサイエンティストとして、全社のDX推進する業務に従事。その他に、滋賀大学データサイエンス部インダストリーアドバイザーとして、社外におけるAI活用の普及活動にも努める。経営学修士。「Forbes JAPAN CIO Award 2024-25」にて、次世代のテクノロジーリーダーのひとりとして「チェンジレガシー賞」を受賞。
MAXIMIZE VALUE – 中長期経営計画「MLMAP2028」におけるDX戦略ロードマップ

|
(株)堀場製作所 ディストリビューション&DX本部 DX戦略センター センター長 栗田 英正 |

|

堀場製作所がMAXIMIZE VALUEのスローガンのもと推進する中長期経営計画「MLMAP2028」。中長期経営計画を支えるDX戦略の概要と、その一環であるグローバル情報基盤の展開やAIによるプロセス変革への挑戦を紹介する。
講演者プロフィール
1993年堀場製作所に入社、情報システム部門にてICT基盤構築に従事。1999年にドイツ駐在、2003年より自社グローバルERP展開に従事。2020年に情報システム部長に就任、2023年4月より現職。
堀場製作所がMAXIMIZE VALUEのスローガンのもと推進する中長期経営計画「MLMAP2028」。中長期経営計画を支えるDX戦略の概要と、その一環であるグローバル情報基盤の展開やAIによるプロセス変革への挑戦を紹介する。
講演者プロフィール
1993年堀場製作所に入社、情報システム部門にてICT基盤構築に従事。1999年にドイツ駐在、2003年より自社グローバルERP展開に従事。2020年に情報システム部長に就任、2023年4月より現職。
生成AIとロボティクス ~ロボットに生成AIを搭載するのではなく、生成AIをロボティクスでリアル世界に召喚する~

|
(株)デンソー 研究開発センター シニアアドバイザー/岐阜大学 客員教授 成迫 剛志 |

|

既に多くの企業が生成AIのインパクトの大きさに気づき、様々な取り組みを行っている。本講演では、生成AIとロボティクスを掛け合わせることの意義と可能性について、取り組み事例を含めてご紹介し、みなさんと議論を深めたい。
講演者プロフィール
IBM、伊藤忠商事、香港CISD、独SAP、中国方正集団、米ビットアイルエクイニクスなどを経て、2016年デンソー入社。クラウド利活用とアジャイルソフトウェア開発を担うデジタルイノベーション室を新設し、同室長に就任。2新設のMaaS開発部長を経て、2021年から執行幹部・クラウドサービス開発部長。2025年1月から研究開発センター シニアアドバイザー。また、トヨタ自動車・デジタルソフト開発センター主査/トヨタソフトウェアアカデミー チーフエバンジェリストを兼務。
既に多くの企業が生成AIのインパクトの大きさに気づき、様々な取り組みを行っている。本講演では、生成AIとロボティクスを掛け合わせることの意義と可能性について、取り組み事例を含めてご紹介し、みなさんと議論を深めたい。
講演者プロフィール
IBM、伊藤忠商事、香港CISD、独SAP、中国方正集団、米ビットアイルエクイニクスなどを経て、2016年デンソー入社。クラウド利活用とアジャイルソフトウェア開発を担うデジタルイノベーション室を新設し、同室長に就任。2新設のMaaS開発部長を経て、2021年から執行幹部・クラウドサービス開発部長。2025年1月から研究開発センター シニアアドバイザー。また、トヨタ自動車・デジタルソフト開発センター主査/トヨタソフトウェアアカデミー チーフエバンジェリストを兼務。

オープニングスピーチ ~我が国の医療機器・ヘルスケア領域の動向の紹介~

|
(国研)国立循環器病研究センター 名誉所員 妙中 義之 |
|
京都大学医学部附属病院における医療機器開発:イノベーションの実装戦略

|
京都大学医学部附属病院 医療開発部 部長、教授 永井 純正 |
|
講演内容
京都大学は複数の公的事業費の獲得により、医療機器開発及びその支援の体制を構築、拡充してきており、京都大学の研究者による開発への伴走支援だけでなく、スタートアップに対する支援も行っている。医療機器メーカーとの包括連携も締結しているが、実用化をさらに前進させるためには更なる産学連携が欠かせない。
講演者プロフィール
<妙中氏>
1976年 阪大医学部卒。同年同大第一外科入局。大阪厚生年金病院、大阪府立病院を経て、'80年 国立循環器病センター人工臓器部研究員。米国ユタ大、米国テキサス心臓研究所に留学。帰国後、国立循環器病センター研究所 人工臓器部室長、部長を経て、'07年より研究所副所長。'10年から研究開発基盤センター長を併任、'17年に定年退職。30年にわたり最先端の人工肺、人工心臓開発に取組む。'09年に「日本の技術をいのちのために委員会」を設立。ものづくり企業の製造技術を医療機器の開発に役立てる活動を支援し、幅広く提言活動を行っている。'15年から'25年、日本医療研究開発機構、医工連携事業化推進事業のプログラムスーパーバイザー。'20年から'25年、医療機器・ヘルスケアプロジェクトのプログラムディレクター。産学官連携功労者表彰、科学技術分野の文部科学大臣表彰など各賞受賞。
<永井氏>
2003年3月、東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院血液・腫瘍内科を経て、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)新薬審査第五部(コンパニオン診断薬WG兼務)で治験相談、承認審査に従事。東京大学医科学研究所遺伝子治療開発分野講師、東京大学医学部附属病院トランスレーショナルリサーチセンター講師を経て、2021年4月より現職。
講演内容
京都大学は複数の公的事業費の獲得により、医療機器開発及びその支援の体制を構築、拡充してきており、京都大学の研究者による開発への伴走支援だけでなく、スタートアップに対する支援も行っている。医療機器メーカーとの包括連携も締結しているが、実用化をさらに前進させるためには更なる産学連携が欠かせない。
講演者プロフィール
<妙中氏>
1976年 阪大医学部卒。同年同大第一外科入局。大阪厚生年金病院、大阪府立病院を経て、'80年 国立循環器病センター人工臓器部研究員。米国ユタ大、米国テキサス心臓研究所に留学。帰国後、国立循環器病センター研究所 人工臓器部室長、部長を経て、'07年より研究所副所長。'10年から研究開発基盤センター長を併任、'17年に定年退職。30年にわたり最先端の人工肺、人工心臓開発に取組む。'09年に「日本の技術をいのちのために委員会」を設立。ものづくり企業の製造技術を医療機器の開発に役立てる活動を支援し、幅広く提言活動を行っている。'15年から'25年、日本医療研究開発機構、医工連携事業化推進事業のプログラムスーパーバイザー。'20年から'25年、医療機器・ヘルスケアプロジェクトのプログラムディレクター。産学官連携功労者表彰、科学技術分野の文部科学大臣表彰など各賞受賞。
<永井氏>
2003年3月、東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院血液・腫瘍内科を経て、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)新薬審査第五部(コンパニオン診断薬WG兼務)で治験相談、承認審査に従事。東京大学医科学研究所遺伝子治療開発分野講師、東京大学医学部附属病院トランスレーショナルリサーチセンター講師を経て、2021年4月より現職。

医療機器業界への挑戦の経緯と新たな挑戦

|
朝日インテック(株) 常務取締役 メディカル事業統括本部長 兼 チーフデジタルオフィサー 西内 誠 |

|

産業機器の部材メーカであった朝日インテックが医療機器業界に挑戦し、悪戦苦闘の末、グローバル展開にまでつなげてきた経緯を紹介するとともに、現状と今後10年先をにらんだ新たな挑戦について紹介する。
講演者プロフィール
大手輸送機器の航空宇宙機器部門で勤務。その後、2005年に朝日インテックに入社。
朝日インテックでは医療機器の開発部門においてガイドワイヤーなどの開発に従事した後、研究開発部門の責任者を経て、執行役員、取締役を歴任。
現在、常務取締役、メディカル事業統括本部長 兼 チーフデジタルオフィサー。
産業機器の部材メーカであった朝日インテックが医療機器業界に挑戦し、悪戦苦闘の末、グローバル展開にまでつなげてきた経緯を紹介するとともに、現状と今後10年先をにらんだ新たな挑戦について紹介する。
講演者プロフィール
大手輸送機器の航空宇宙機器部門で勤務。その後、2005年に朝日インテックに入社。
朝日インテックでは医療機器の開発部門においてガイドワイヤーなどの開発に従事した後、研究開発部門の責任者を経て、執行役員、取締役を歴任。
現在、常務取締役、メディカル事業統括本部長 兼 チーフデジタルオフィサー。
※本講演を受講される方は9:30頃から展示会場にご入場いただけます
進化するHondaのものづくり ~電動化に向けた新たな挑戦~

|
本田技研工業(株) 執行役 四輪生産本部長 小沼 隆史 |

|

Hondaは四輪・二輪・汎用・HondaJetといった多岐にわたる製品群を支える独自の生産技術を進化させてきた。本講演ではハイブリッド・バッテリーEVの進化、メガキャスト等の先進生産技術の導入事例、更に生産の自動化・知能化への取り組みを通じて、Hondaのものづくりの将来への進化を紹介する。
講演者プロフィール
2000年、本田技術研究所に入社。米国での開発業務も含め主に自動車ボディ設計に従事。2021年に北米新機種開発部門の責任者、2023年に帰国後は四輪開発センター副センター長 兼 生産技術統括部長を経て、2024年より現職。グローバル四輪生産の責任者を務める。
Hondaは四輪・二輪・汎用・HondaJetといった多岐にわたる製品群を支える独自の生産技術を進化させてきた。本講演ではハイブリッド・バッテリーEVの進化、メガキャスト等の先進生産技術の導入事例、更に生産の自動化・知能化への取り組みを通じて、Hondaのものづくりの将来への進化を紹介する。
講演者プロフィール
2000年、本田技術研究所に入社。米国での開発業務も含め主に自動車ボディ設計に従事。2021年に北米新機種開発部門の責任者、2023年に帰国後は四輪開発センター副センター長 兼 生産技術統括部長を経て、2024年より現職。グローバル四輪生産の責任者を務める。
※本講演を受講される方は9:30頃から展示会場にご入場いただけます
AIエージェント活用によるフロントラインワーカーの生産性向上

|
(株)日立製作所 デジタルシステム&サービスセクター AICoE Generative AIセンター 本部長 兼 Chief AI Transformation Officer 吉田 順 |

|

製造業や交通、社会インフラなど現場の最前線で働くフロントラインワーカーの人手不足が社会課題となっている。この状況に対し、急速に進化している生成AIやAIエージェントを活用することにより、現場の生産性を上げることができる。そこでフロントラインワーカーが生き生きと働くウェルビーイング向上をめざした取り組みや事例についてご紹介する。
講演者プロフィール
1998年日立製作所に入社。2012年、AI/ビッグデータ利活用を支援する「データ・アナリティクス・マイスター・サービス」を立ち上げる。
銀行・保険、流通・小売、製造業、鉄道などさまざまなお客さまとともに、多数のAI/ビッグデータ利活用プロジェクトを推進。社内外のデータサイエンティスト育成にも関わる。
2023年5月からGenerative AIセンターのセンター長を務める。
著書に『実践 データ分析の教科書』『実践 生成AIの教科書』。
製造業や交通、社会インフラなど現場の最前線で働くフロントラインワーカーの人手不足が社会課題となっている。この状況に対し、急速に進化している生成AIやAIエージェントを活用することにより、現場の生産性を上げることができる。そこでフロントラインワーカーが生き生きと働くウェルビーイング向上をめざした取り組みや事例についてご紹介する。
講演者プロフィール
1998年日立製作所に入社。2012年、AI/ビッグデータ利活用を支援する「データ・アナリティクス・マイスター・サービス」を立ち上げる。
銀行・保険、流通・小売、製造業、鉄道などさまざまなお客さまとともに、多数のAI/ビッグデータ利活用プロジェクトを推進。社内外のデータサイエンティスト育成にも関わる。
2023年5月からGenerative AIセンターのセンター長を務める。
著書に『実践 データ分析の教科書』『実践 生成AIの教科書』。
製造業におけるAI外観検査の導入と課題への対応 ~省人化と品質向上を実現するAIソリューション~

|
(株)VRAIN Solution 執行役員 ソリューション事業部部長 石原 慎也 |

|

製造業の現場では、人手不足や品質のばらつき、検査工数の増大が深刻化している。AI外観検査を導入することで省人化・精度向上・工数削減となるため、導入前の課題整理から、その成果と導入のポイントをわかりやすく解説する。
講演者プロフィール
2022年に株式会社VRAIN Solution入社後、同年執行役員に就任。現在はソリューション事業部部長として、多くのユーザー様との取り組みで培った経験をもとに、製造業向けAIソリューションの提供を行っている。
製造業の現場では、人手不足や品質のばらつき、検査工数の増大が深刻化している。AI外観検査を導入することで省人化・精度向上・工数削減となるため、導入前の課題整理から、その成果と導入のポイントをわかりやすく解説する。
講演者プロフィール
2022年に株式会社VRAIN Solution入社後、同年執行役員に就任。現在はソリューション事業部部長として、多くのユーザー様との取り組みで培った経験をもとに、製造業向けAIソリューションの提供を行っている。
自動車生産技術が求めるAM技術 -チャレンジとゲームチェンジ-

|
日産自動車(株) パワートレイン・EVコンポーネント生産技術開発本部 技術企画部 技術企画・技術統括グループ エキスパートリーダー(新商品工法開発) 塩飽 紀之 |

|

商品としての自動車は今まさに大きな転換期の真っただ中におり、様々な潮流の中で新たなチャレンジが求められている。先達の築き上げた貴重なナレッジには敬意を払うも、そのナレッジを基に、新たな世界へ果敢に挑むことが生産技術者に求められていると考えます。この講演を通じて、自動車が求めるAM技術のチャレンジについてお話させていただきます。
講演者プロフィール
・1986年日産自動車株式会社入社 パワートレイン生産技術部署にて、塑性加工技術開発を担当、主としてエンジン、トランスミッション、ドライブトレーンなど、主運動部品の新材料、新工法開発を推進。
・2014年~パワートレイン新商品工法技術開発エキスパートリーダーとして新パワートレイン商品のConcurrent Engineering並びに、新工法開発を担当。(神奈川県 勤務)
商品としての自動車は今まさに大きな転換期の真っただ中におり、様々な潮流の中で新たなチャレンジが求められている。先達の築き上げた貴重なナレッジには敬意を払うも、そのナレッジを基に、新たな世界へ果敢に挑むことが生産技術者に求められていると考えます。この講演を通じて、自動車が求めるAM技術のチャレンジについてお話させていただきます。
講演者プロフィール
・1986年日産自動車株式会社入社 パワートレイン生産技術部署にて、塑性加工技術開発を担当、主としてエンジン、トランスミッション、ドライブトレーンなど、主運動部品の新材料、新工法開発を推進。
・2014年~パワートレイン新商品工法技術開発エキスパートリーダーとして新パワートレイン商品のConcurrent Engineering並びに、新工法開発を担当。(神奈川県 勤務)
止まらない工場を目指して:ダイキンの設備保全DX

|
ダイキン工業(株) 常務執行役員 空調生産本部長 堺製作所長 森田 重樹 |

|

工場の稼働停止理由の大きな要因の一つが、設備故障によるライン停止が挙げられます。故障時の迅速な対応はもとより、故障する前に対応する「予防保全」や「予知保全」をデジタルを活用し進めてきました。加えて、自動化、デジタル化がラインに多く導入されてきている中、保全マンの人材不足も顕在化してきております。保全マンの育成、サポートを生成AIを使いこの問題についても着手し始めております。事例を交えながら当社の取組みをご説明いたします。
講演者プロフィール
1985年ダイキン工業入社。2005年からダイキンインダストリーズチェコ社取締役、2007年同社社長として海外事業統括を担当。2009年帰任後、空調生産本部企画部長、2010年ダイキンヨーロッパ社取締役副社長などを歴任し、2018年空調生産本部長 堺製作所長として帰任し、現在に至る。
工場の稼働停止理由の大きな要因の一つが、設備故障によるライン停止が挙げられます。故障時の迅速な対応はもとより、故障する前に対応する「予防保全」や「予知保全」をデジタルを活用し進めてきました。加えて、自動化、デジタル化がラインに多く導入されてきている中、保全マンの人材不足も顕在化してきております。保全マンの育成、サポートを生成AIを使いこの問題についても着手し始めております。事例を交えながら当社の取組みをご説明いたします。
講演者プロフィール
1985年ダイキン工業入社。2005年からダイキンインダストリーズチェコ社取締役、2007年同社社長として海外事業統括を担当。2009年帰任後、空調生産本部企画部長、2010年ダイキンヨーロッパ社取締役副社長などを歴任し、2018年空調生産本部長 堺製作所長として帰任し、現在に至る。
モノづくりのまち東大阪の取組みと支援策

|
東大阪市 都市魅力産業スポーツ部 モノづくり支援室 主査 中西 隆史 |

|

日本を代表する”モノづくりのまち”東大阪。本講演では、東大阪市の特徴や強み、支援体制や充実した施策についてご紹介する。また、大阪万博との関わりや、今後のビジョンを交えながら、ビジネス展開における東大阪とのコラボの有用さをお伝えする。
講演者プロフィール
2005年3月、京都大学法学部卒業。東大阪市へ入庁。市立病院に所属し、病院運営・医療安全・地方独立行政法人化に従事。2023年より製造業支援・住工共生・医工連携を担当。2024年より大阪大学大学院医学系研究科・医学部附属病院 産学連携・クロスイノベーションイニシアティブ 産学連携コーディネーターを兼務。現在に至る。
日本を代表する”モノづくりのまち”東大阪。本講演では、東大阪市の特徴や強み、支援体制や充実した施策についてご紹介する。また、大阪万博との関わりや、今後のビジョンを交えながら、ビジネス展開における東大阪とのコラボの有用さをお伝えする。
講演者プロフィール
2005年3月、京都大学法学部卒業。東大阪市へ入庁。市立病院に所属し、病院運営・医療安全・地方独立行政法人化に従事。2023年より製造業支援・住工共生・医工連携を担当。2024年より大阪大学大学院医学系研究科・医学部附属病院 産学連携・クロスイノベーションイニシアティブ 産学連携コーディネーターを兼務。現在に至る。
デジタルツールを最大限活用し業務効率向上

|
アイシン九州(株) DX推進室 室長 熊谷 隆之 |

|

レトロフィットとスモール投資で最大の効果を生み出そうをスローガンのもと、自社に合ったスマート工場を目指し、可視化することが目的ではなく、改善の畑を見つけるツールとしてデータを活用している。素早く効果を刈りとるため、安速単で推進し飛躍的な生産性の向上を図る。
講演者プロフィール
1986年、株式会社アイシン入社
1995年、アイシン九州株式会社へ転籍
生産技術、設備保全、製造、品質管理を経て現在、DX推進室に所属
レトロフィットとスモール投資で最大の効果を生み出そうをスローガンのもと、自社に合ったスマート工場を目指し、可視化することが目的ではなく、改善の畑を見つけるツールとしてデータを活用している。素早く効果を刈りとるため、安速単で推進し飛躍的な生産性の向上を図る。
講演者プロフィール
1986年、株式会社アイシン入社
1995年、アイシン九州株式会社へ転籍
生産技術、設備保全、製造、品質管理を経て現在、DX推進室に所属
※本講演を受講される方は9:30頃から展示会場にご入場いただけます
加速するXR/メタバース活用 ~設計や製造支援と産業DXの転換期を支える技術~

|
クラスター(株) 事業共創本部 マネージャー 亀谷 拓史 |

|

本講演では、XR/メタバース技術が、机上のDXから現場のDXへと移行する「転換期」の今、いかにして設計・製造プロセスを根本から革新していくか、実際の現場での事例を交えながらご紹介します。
講演者プロフィール
岐阜県出身。慶應義塾大学卒業後、株式会社サイバーエージェントにて広告営業/アカウントプランナーとして従事したのち、株式会社Airporterにて執行役員兼マーケティング・ディレクターとしてマーケティング全般を担当。2020年10月にクラスターに入社し、ビジネスプランニング事業部でプランナーを勤める。2022年よりエンタープライズ事業部マネージャー、2025年には新たに設置された事業共創部にてインダストリアルメタバースチームを立ち上げる。
本講演では、XR/メタバース技術が、机上のDXから現場のDXへと移行する「転換期」の今、いかにして設計・製造プロセスを根本から革新していくか、実際の現場での事例を交えながらご紹介します。
講演者プロフィール
岐阜県出身。慶應義塾大学卒業後、株式会社サイバーエージェントにて広告営業/アカウントプランナーとして従事したのち、株式会社Airporterにて執行役員兼マーケティング・ディレクターとしてマーケティング全般を担当。2020年10月にクラスターに入社し、ビジネスプランニング事業部でプランナーを勤める。2022年よりエンタープライズ事業部マネージャー、2025年には新たに設置された事業共創部にてインダストリアルメタバースチームを立ち上げる。
※本講演を受講される方は9:30頃から展示会場にご入場いただけます
ロボットを活用した海外のユニークな自動化事例

|
ABB(株) ロボティクス&ディスクリート・オートメーション事業本部 インダストリー事業部長 菅井 康介 |

|

世界53ヵ国でロボット事業を展開するABBが、世界各国の挑戦的な自動化案件に臨んだ事例を、実際の動画を交えて紹介する。併せて、海外事例をもとに国内でテストを重ね、日本のユーザー向けにカスタマイズしたロボット導入の事例について解説を行う。
講演者プロフィール
2013年、ABB株式会社に入社。食品業界向けロボットシステムの提案営業に従事。
2020年、一般産業事業部(現インダストリー事業部)セールスマネージャー
2022年、一般産業事業部長に就任
世界53ヵ国でロボット事業を展開するABBが、世界各国の挑戦的な自動化案件に臨んだ事例を、実際の動画を交えて紹介する。併せて、海外事例をもとに国内でテストを重ね、日本のユーザー向けにカスタマイズしたロボット導入の事例について解説を行う。
講演者プロフィール
2013年、ABB株式会社に入社。食品業界向けロボットシステムの提案営業に従事。
2020年、一般産業事業部(現インダストリー事業部)セールスマネージャー
2022年、一般産業事業部長に就任
製造現場の「ノウハウの可視化」のポイント ~事例から見た人材教育と技術伝承~

|
Tebiki(株) マーケティング 堀中 敦志 |

|

ものづくりの現場KPIである安全性、品質、効率などを向上させるための基本的なアプローチは、現場のノウハウを広く浸透させる人材教育です。しかし、多くの現場ではそのノウハウを可視化できず、個々のスキルに依存したOJTが主流になっています。本講演では、デジタル技術を活用した現場ノウハウを可視化する取り組みについて事例を中心に解説します。
講演者プロフィール
大手ISP、ソフトウェアデベロッパーを経て、2022年より現職。デスクレスワーカーの教育DXを支援するクラウドサービス「tebiki」のマーケティングやイベント企画を担当し、品質向上や技術伝承など、ものづくり現場における教育課題の解決に従事。
ものづくりの現場KPIである安全性、品質、効率などを向上させるための基本的なアプローチは、現場のノウハウを広く浸透させる人材教育です。しかし、多くの現場ではそのノウハウを可視化できず、個々のスキルに依存したOJTが主流になっています。本講演では、デジタル技術を活用した現場ノウハウを可視化する取り組みについて事例を中心に解説します。
講演者プロフィール
大手ISP、ソフトウェアデベロッパーを経て、2022年より現職。デスクレスワーカーの教育DXを支援するクラウドサービス「tebiki」のマーケティングやイベント企画を担当し、品質向上や技術伝承など、ものづくり現場における教育課題の解決に従事。
設備保全DX!トラブルが止まない現場を変えるAI時代の実践ロードマップ

|
(株)M2X 代表取締役 岡部 晋太郎 |

|

突発的な設備トラブルはなぜ繰り返し起こるのか、事後保全から予防保全へ移行できない現場には、どのような構造的課題が潜んでいるのか。本講演では、多くの設備保全DXを支援してきた経験をもとに豊富な事例を交えながら、AI活用を見据えた保全改革のロードマップを提示します。
講演者プロフィール
東京大学卒業後、総務省にてIT政策の企画立案を担当。その後、外資系コンサルティング会社のボストン・コンサルティング・グループに入社し、製造業における中長期の戦略立案、DX等を担当。メンテナンスの重要性と可能性に惹かれ、2022年に株式会社M2Xを創業。
突発的な設備トラブルはなぜ繰り返し起こるのか、事後保全から予防保全へ移行できない現場には、どのような構造的課題が潜んでいるのか。本講演では、多くの設備保全DXを支援してきた経験をもとに豊富な事例を交えながら、AI活用を見据えた保全改革のロードマップを提示します。
講演者プロフィール
東京大学卒業後、総務省にてIT政策の企画立案を担当。その後、外資系コンサルティング会社のボストン・コンサルティング・グループに入社し、製造業における中長期の戦略立案、DX等を担当。メンテナンスの重要性と可能性に惹かれ、2022年に株式会社M2Xを創業。
村田製作所が進めるDXの現在地と今後の展望

|
(株)村田製作所 上席執行役員 経営DX本部 本部長 兼 同本部 経営管理統括部 統括部長 須知 史行 |
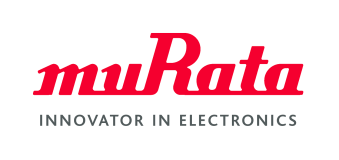
|
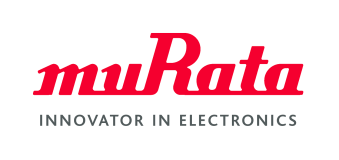
村田製作所は、自律分散型の組織運営を標榜し、垂直統合型のモノづくりを強みとする電子部品メーカーです。当社は、2021年策定のVISION2030でDX推進を経営変革テーマに位置づけ、試行錯誤しつつ推進しています。当社の特徴と取組みの現在地、今後の展望と課題についてご紹介します。
講演者プロフィール
1994年4月に株式会社村田製作所に入社。経理部門、経営企画部門を経て2008年からは積層コンデンサ事業部で事業企画や商品企画に従事。
2017年にMurata Electronics Singapore (Pte.) Ltd.の製造部門責任者、2019年より経営戦略部長を歴任。
2023年7月より執行役員 情報システム統括部の統括部長、2025年7月より上席執行役員 経営DX本部本部長に就任し、現在に至る。
村田製作所は、自律分散型の組織運営を標榜し、垂直統合型のモノづくりを強みとする電子部品メーカーです。当社は、2021年策定のVISION2030でDX推進を経営変革テーマに位置づけ、試行錯誤しつつ推進しています。当社の特徴と取組みの現在地、今後の展望と課題についてご紹介します。
講演者プロフィール
1994年4月に株式会社村田製作所に入社。経理部門、経営企画部門を経て2008年からは積層コンデンサ事業部で事業企画や商品企画に従事。
2017年にMurata Electronics Singapore (Pte.) Ltd.の製造部門責任者、2019年より経営戦略部長を歴任。
2023年7月より執行役員 情報システム統括部の統括部長、2025年7月より上席執行役員 経営DX本部本部長に就任し、現在に至る。
コニカミノルタにおけるAM生産適用事例

|
コニカミノルタ(株) デジタルワークプレイス事業本部 生産・調達統括部 AM生産技術開発チーム チームリーダー 高木 信 |

|

コニカミノルタでは販売製品の部品製造のためにAMの量産適用を目指しPBF方式の造形機を導入し、生産技術と設計技術の両面から開発を進めている。AMに適した設計手法やAM設計自由度を活かしたCAEを活用した最適形状設計手法など、具体的事例を交え報告する。
講演者プロフィール
2001年3月千葉大学卒業。ミノルタ株式会社(現コニカミノルタ株式会社)に入社。生産技術開発部署に所属し、超精密加工技術開発業務に従事。2022年1月よりAM生産技術を担当し、現在に至る。
コニカミノルタでは販売製品の部品製造のためにAMの量産適用を目指しPBF方式の造形機を導入し、生産技術と設計技術の両面から開発を進めている。AMに適した設計手法やAM設計自由度を活かしたCAEを活用した最適形状設計手法など、具体的事例を交え報告する。
講演者プロフィール
2001年3月千葉大学卒業。ミノルタ株式会社(現コニカミノルタ株式会社)に入社。生産技術開発部署に所属し、超精密加工技術開発業務に従事。2022年1月よりAM生産技術を担当し、現在に至る。
DX推進のための攻めのサイバーセキュリティ対策への挑戦

|
ヤマハ発動機(株) IT本部 本部長(兼)IT本部サイバーセキュリティ推進部 部長 小野 豊土 |
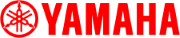
|
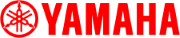
デジタルトランスフォーメーションのスピードを弱めることなく、サイバーセキュリティ対策を進める必要性やリスクテイクの判断について、ヤマハ発動機のサイバーセキュリティを担う部門としてのチャレンジや失敗経験を皆さんと共有したい。
講演者プロフィール
1999年にヤマハ発動機株式会社に入社。インドネシアや米国の拠点での駐在を経験した後、ヤマハモーターソリューションの代表取締役社長に就任。
ヤマハ発動機のグローバルSAP導入のプロジェクトリードをなどを経験し、2024年1月からIT本部長に就任。
2025年1月からはサイバーセキュリティ推進部長を兼務。
デジタルトランスフォーメーションのスピードを弱めることなく、サイバーセキュリティ対策を進める必要性やリスクテイクの判断について、ヤマハ発動機のサイバーセキュリティを担う部門としてのチャレンジや失敗経験を皆さんと共有したい。
講演者プロフィール
1999年にヤマハ発動機株式会社に入社。インドネシアや米国の拠点での駐在を経験した後、ヤマハモーターソリューションの代表取締役社長に就任。
ヤマハ発動機のグローバルSAP導入のプロジェクトリードをなどを経験し、2024年1月からIT本部長に就任。
2025年1月からはサイバーセキュリティ推進部長を兼務。
受講券の発行方法をお選びください。
