

概要
【前回プログラム】本セミナーの開催は終了いたしました。
ご来場誠にありがとうございました。
次回は、2026年5月20日(水) ~22日(金)幕張メッセにて開催いたします。
For English users, please select "English" from the button on the right side.

|
厚生労働省 医政局 医薬産業振興・医療情報企画課 医薬品産業・ベンチャー等支援政策室 室長 藤井 大資 |

|

【講演内容】
近年、後発医薬品を中心とした医薬品の供給問題が生じている。厚生労働省においては、医薬品の安定供給に向け、足下の供給不安解消と中長期的な後発医薬品の産業構造改革の双方の観点から取組を行ってきた。本講演においては、医薬品の安定供給に係る行政の取組みについて説明する。
【講演者プロフィール】
厚生労働省入省以後、医薬品製造業者等に対する監視業務や、市販後安全対策業務、薬価制度等、医薬品・医療機器に関連する業務に幅広く担当。現在は、医薬品の安定供給業務に従事しつつ、医療系ベンチャー企業等の振興業務を担当。
【講演内容】
近年、後発医薬品を中心とした医薬品の供給問題が生じている。厚生労働省においては、医薬品の安定供給に向け、足下の供給不安解消と中長期的な後発医薬品の産業構造改革の双方の観点から取組を行ってきた。本講演においては、医薬品の安定供給に係る行政の取組みについて説明する。
【講演者プロフィール】
厚生労働省入省以後、医薬品製造業者等に対する監視業務や、市販後安全対策業務、薬価制度等、医薬品・医療機器に関連する業務に幅広く担当。現在は、医薬品の安定供給業務に従事しつつ、医療系ベンチャー企業等の振興業務を担当。
座長:岐阜薬科大学 竹内 洋文
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
東京理科大学 薬学部 医薬品等品質・GMP講座 教授 櫻井 信豪 |

|

【講演内容】
昨今の製薬企業の品質問題事案の発生やワクチン等の国内製造への移行などを踏まえると、GMP製造に関する精通者をさらに増やす取り組みがますます必要となります。これらの課題の解決のために、私たちが進めている取り組みについて解説を行います。
【講演者プロフィール】
1985年 東京理科大学大学院薬学研究科 修了(薬剤師)、1985年~19年間、製薬企業勤務し、医薬品の研究・技術開発、品質管理、品質保証に携わる。2004年~16年間 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にてGMP等の品質管理業務を担当。2020年7月~現在、東京理科大学薬学部にて医薬品等品質・GMP講座 教授。
【講演内容】
昨今の製薬企業の品質問題事案の発生やワクチン等の国内製造への移行などを踏まえると、GMP製造に関する精通者をさらに増やす取り組みがますます必要となります。これらの課題の解決のために、私たちが進めている取り組みについて解説を行います。
【講演者プロフィール】
1985年 東京理科大学大学院薬学研究科 修了(薬剤師)、1985年~19年間、製薬企業勤務し、医薬品の研究・技術開発、品質管理、品質保証に携わる。2004年~16年間 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にてGMP等の品質管理業務を担当。2020年7月~現在、東京理科大学薬学部にて医薬品等品質・GMP講座 教授。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
厚生労働省 医薬局監視指導・麻薬対策課 監視指導室長・麻薬対策企画官 山本 剛 |

|

【講演内容】
令和3年以降相次ぐ医薬品製造業の製造管理における不備等を踏まえた、製造管理・品質管理や企業ガバナンスの徹底に向けた行政の取組について、医薬品医療機器改正法案の概要も含めつつ概説する。
【講演者プロフィール】
平成17年厚生労働省入省後、医薬食品局安全対策課副作用情報専門官、同局審査管理課審査調整官、(独)医薬品医療機器総合機構経営企画部広報課長・医療情報活用部調査役、医政局医薬産業振興・医療情報企画課医薬品産業・ベンチャー等支援政策室長等を歴任。令和6年7月より現職。
【講演内容】
令和3年以降相次ぐ医薬品製造業の製造管理における不備等を踏まえた、製造管理・品質管理や企業ガバナンスの徹底に向けた行政の取組について、医薬品医療機器改正法案の概要も含めつつ概説する。
【講演者プロフィール】
平成17年厚生労働省入省後、医薬食品局安全対策課副作用情報専門官、同局審査管理課審査調整官、(独)医薬品医療機器総合機構経営企画部広報課長・医療情報活用部調査役、医政局医薬産業振興・医療情報企画課医薬品産業・ベンチャー等支援政策室長等を歴任。令和6年7月より現職。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
東京大学 大学院工学系研究科化学システム工学専攻 教授 杉山 弘和 |

|

【講演内容】
デジタル技術、とりわけ数理モデリング・シミュレーション技術を用いたプロセス開発について発表する。最新の研究成果を紹介しつつ、機能的理解やAI・データ駆動手法、それらを統合したハイブリッド・アプローチの役割と可能性について考える。
【講演者プロフィール】
2001年東京大学工学部化学システム工学科卒業、2003年同大学院工学系研究科化学システム工学専攻修士課程修了、2007年ETH Zurich, Institute for Chemical and Bioengineeringで博士号取得。同年、F. Hoffmann-La Rocheに入社し、バイオ医薬品注射剤新工場の立ち上げと実生産に従事。2013年東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻准教授に着任し、以来、医薬品製造プロセスの設計・運転に関する研究に取り組む。2021年より現職。
【講演内容】
デジタル技術、とりわけ数理モデリング・シミュレーション技術を用いたプロセス開発について発表する。最新の研究成果を紹介しつつ、機能的理解やAI・データ駆動手法、それらを統合したハイブリッド・アプローチの役割と可能性について考える。
【講演者プロフィール】
2001年東京大学工学部化学システム工学科卒業、2003年同大学院工学系研究科化学システム工学専攻修士課程修了、2007年ETH Zurich, Institute for Chemical and Bioengineeringで博士号取得。同年、F. Hoffmann-La Rocheに入社し、バイオ医薬品注射剤新工場の立ち上げと実生産に従事。2013年東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻准教授に着任し、以来、医薬品製造プロセスの設計・運転に関する研究に取り組む。2021年より現職。
● コースリーダー:バイエル薬品(株) 鈴木 博文
● サブリーダー:(株)パウレック 長谷川 浩司
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
第一三共(株) テクノロジー本部 生産統括部 生産管理第二部 生産DXグループ グループ長 小林 礼 |

|

【講演内容】
第一三共が考えるスマートファクトリー化構想について、そのアプローチから具体的な取り組みまで、その活動概要を紹介する。
【講演者プロフィール】
1998年4月 入社。
エンジニアリング部門に配属され、各種設備設計、プラント建設、プロジェクトマネジメントを担当(原薬プラント、製剤棟、動物実験施設他)
その後、本社戦略部門へ配属となり、経営企画、技術移管、設備調達などを担当。
近年は、DXを中心に活動中。
【講演内容】
第一三共が考えるスマートファクトリー化構想について、そのアプローチから具体的な取り組みまで、その活動概要を紹介する。
【講演者プロフィール】
1998年4月 入社。
エンジニアリング部門に配属され、各種設備設計、プラント建設、プロジェクトマネジメントを担当(原薬プラント、製剤棟、動物実験施設他)
その後、本社戦略部門へ配属となり、経営企画、技術移管、設備調達などを担当。
近年は、DXを中心に活動中。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
(国研)国立がん研究センター中央病院 副院長 山本 昇 |
|
【講演内容】
激変する世界の抗がん剤開発において、日本の対応は必ずしも十分とは言えないのが現状である。この状況がドラッグラグ・ロスを生み出す原因にもなっていると言える。日本でできることは何か?どこまでが求められるのか?など、医療現場の視点から抗がん剤開発のトレンドと日本の課題について情報共有させていただく。
【講演者プロフィール】
1991年に広島大学医学部を卒業後、国立がんセンター中央病院にてレジデント、がん専門修練医を経て、呼吸器内科にて医療に従事。現在は、同病院で副院長(研究担当)のほか、呼吸器内科医長、先端医療科長、臨床研究支援部門長、臨床開発推進部門長を兼務。
【講演内容】
激変する世界の抗がん剤開発において、日本の対応は必ずしも十分とは言えないのが現状である。この状況がドラッグラグ・ロスを生み出す原因にもなっていると言える。日本でできることは何か?どこまでが求められるのか?など、医療現場の視点から抗がん剤開発のトレンドと日本の課題について情報共有させていただく。
【講演者プロフィール】
1991年に広島大学医学部を卒業後、国立がんセンター中央病院にてレジデント、がん専門修練医を経て、呼吸器内科にて医療に従事。現在は、同病院で副院長(研究担当)のほか、呼吸器内科医長、先端医療科長、臨床研究支援部門長、臨床開発推進部門長を兼務。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
花王(株) 研究開発部門研究戦略・企画部 部長(リサイクリエーション担当) 瀬戸 啓二 |

|

【講演内容】
「リサイクリエーション」とは、「リサイクル」と「クリエーション」を組み合わせた概念。他企業・行政・生活者とともにつめかえパックを集め、身近なものに再生し、資源循環を可視化することで啓発に活用している。また、社内の研究プラントでパックのリサイクル技術を開発し、「水平リサイクル」を2023年に実現した。これらの成果と課題を紹介する。
【講演者プロフィール】
1997年鐘紡入社。化粧品研究所に所属し、処方開発、研究マネジメントに従事。2019年より、花王研究戦略・企画部にて、リサイクリエーションのリーダーを担当し、現在に至る。
【講演内容】
「リサイクリエーション」とは、「リサイクル」と「クリエーション」を組み合わせた概念。他企業・行政・生活者とともにつめかえパックを集め、身近なものに再生し、資源循環を可視化することで啓発に活用している。また、社内の研究プラントでパックのリサイクル技術を開発し、「水平リサイクル」を2023年に実現した。これらの成果と課題を紹介する。
【講演者プロフィール】
1997年鐘紡入社。化粧品研究所に所属し、処方開発、研究マネジメントに従事。2019年より、花王研究戦略・企画部にて、リサイクリエーションのリーダーを担当し、現在に至る。

|
花王(株) 包装技術研究所 研究員 片柳 豪太 |

|

【講演者プロフィール】
2018年花王入社。包装技術研究所に所属し、容器開発等に従事。2020年より、つめかえパックのリサイクル技術開発業務を担当し、現在に至る。
【講演者プロフィール】
2018年花王入社。包装技術研究所に所属し、容器開発等に従事。2020年より、つめかえパックのリサイクル技術開発業務を担当し、現在に至る。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
ライオン(株) 執行役員 全社デジタル戦略担当 中林 紀彦 |

|

【講演内容】
130年以上の歴史を誇るライオンは、2030年に向けて大きな変革を進めています。2025年からスタートした中期経営計画2ndステージでは、生成AIなどの最先端テクノロジーを活用し、R&Dやモノづくりのトランスフォーメーションを進めています。本セッションでは、ライオンにおける生成AIの活用事例を具体的に紹介しその可能性と未来への展望をご紹介します。
【講演者プロフィール】
日本アイ・ビー・エム株式会社においてデータサイエンティストとして企業の様々な課題を解決。その後、株式会社オプトホールディング データサイエンスラボ副所長、SOMPOホールディングス株式会社チーフ・データサイエンティスト、ヤマトホールディングス株式会社の執行役員を歴任し、2024年4月にライオン株式会社の執行役員に就任。全社デジタル戦略担当としてグループ全体のIT・デジタル・データに関する戦略立案と実行を担う。
【講演内容】
130年以上の歴史を誇るライオンは、2030年に向けて大きな変革を進めています。2025年からスタートした中期経営計画2ndステージでは、生成AIなどの最先端テクノロジーを活用し、R&Dやモノづくりのトランスフォーメーションを進めています。本セッションでは、ライオンにおける生成AIの活用事例を具体的に紹介しその可能性と未来への展望をご紹介します。
【講演者プロフィール】
日本アイ・ビー・エム株式会社においてデータサイエンティストとして企業の様々な課題を解決。その後、株式会社オプトホールディング データサイエンスラボ副所長、SOMPOホールディングス株式会社チーフ・データサイエンティスト、ヤマトホールディングス株式会社の執行役員を歴任し、2024年4月にライオン株式会社の執行役員に就任。全社デジタル戦略担当としてグループ全体のIT・デジタル・データに関する戦略立案と実行を担う。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
Adragos Pharma GmbH CCO ヘニー ジルストラ |

|

【講演内容】
製薬業界での女性の活躍をテーマに、国内外の取り組みや登壇者の経験を共有しながら、キャリア形成や支援のあり方を多角的に考えるパネルディスカッションです。組織・個人が一歩踏み出すヒントを提供します。
【講演者プロフィール】
2018年3月、オランダの大学にて国際ビジネス学士号およびマーケティング修士号を取得。製薬業界でのキャリアをスタートし、アムステルダムで営業職に従事。その後、PHARMA MATCH、HETERO、DSM、LONZAなど多様な国際企業と関わりながら、商業戦略やマーケティング分野で経験を積む。
2012年よりスペイン・バルセロナ在住。
2024年よりAdragos Pharmaに参画し、最高商業責任者としてグローバル戦略を推進中。
【講演内容】
製薬業界での女性の活躍をテーマに、国内外の取り組みや登壇者の経験を共有しながら、キャリア形成や支援のあり方を多角的に考えるパネルディスカッションです。組織・個人が一歩踏み出すヒントを提供します。
【講演者プロフィール】
2018年3月、オランダの大学にて国際ビジネス学士号およびマーケティング修士号を取得。製薬業界でのキャリアをスタートし、アムステルダムで営業職に従事。その後、PHARMA MATCH、HETERO、DSM、LONZAなど多様な国際企業と関わりながら、商業戦略やマーケティング分野で経験を積む。
2012年よりスペイン・バルセロナ在住。
2024年よりAdragos Pharmaに参画し、最高商業責任者としてグローバル戦略を推進中。

|
アドラゴスファーマ(株) アメリカ・アジア太平洋地域 営業統括責任者 田中 秀幸 |

|

【講演者プロフィール】
東北大学大学院 薬品化学専攻 修了。Bond大学(オーストラリア)にてMBA取得。味の素バイオファーマサービスに入社し、ベルギー・サンディエゴ・大阪にて事業開発に従事。 その後、武州製薬にてグローバル営業・マーケティング本部の執行役員を務める。 2024年よりアドラゴスファーマに入社。米国・アジア太平洋地域の商業統括責任者として、グローバル展開をリードし、現在に至る。
【講演者プロフィール】
東北大学大学院 薬品化学専攻 修了。Bond大学(オーストラリア)にてMBA取得。味の素バイオファーマサービスに入社し、ベルギー・サンディエゴ・大阪にて事業開発に従事。 その後、武州製薬にてグローバル営業・マーケティング本部の執行役員を務める。 2024年よりアドラゴスファーマに入社。米国・アジア太平洋地域の商業統括責任者として、グローバル展開をリードし、現在に至る。
【パネルディスカッション】
本セッションはパネルディスカッション形式で開催いたします。
日本と海外における取り組みや課題を比較しながら、
製薬業界における女性のキャリア形成や活躍推進の現状を共有、次世代の人材にとってのロールモデルやヒントを提供いたします。
製薬業界で活躍される女性の方はもちろん、
女性とともに働かれている男性の方も、ぜひご参加ください。
エーザイにおける連続生産技術を用いた新薬2製品上市で得た知見と課題

|
エーザイ(株) PST 製剤研究部 主幹研究員 小川 真裕 |

|

【講演内容】
エーザイは連続生産技術を用いて新薬2製品(タズベリク錠、タスフィゴ錠)を上市し、さらに本技術の活用を広げようとしている。上市の過程で直面した連続生産特有の課題と得た知見について、審査と実地査察などの情報を含め、主に研究開発の視点から紹介する。
【講演者プロフィール】
2006年岐阜薬科大学博士前期課程修了後,エーザイ株式会社に入社し,製剤研究部にて固形剤の製剤設計に従事。タズベリク錠及びタスフィゴ錠の開発リードを務め連続生産技術を実用化。2022年日本薬剤学会旭化成創剤開発技術賞,2024年新製剤技術とエンジニアリング振興基金パーティクルデザイン賞を受賞。
【講演内容】
エーザイは連続生産技術を用いて新薬2製品(タズベリク錠、タスフィゴ錠)を上市し、さらに本技術の活用を広げようとしている。上市の過程で直面した連続生産特有の課題と得た知見について、審査と実地査察などの情報を含め、主に研究開発の視点から紹介する。
【講演者プロフィール】
2006年岐阜薬科大学博士前期課程修了後,エーザイ株式会社に入社し,製剤研究部にて固形剤の製剤設計に従事。タズベリク錠及びタスフィゴ錠の開発リードを務め連続生産技術を実用化。2022年日本薬剤学会旭化成創剤開発技術賞,2024年新製剤技術とエンジニアリング振興基金パーティクルデザイン賞を受賞。
シオノギファーマでの連続生産 ~商用生産の経験を経た現在と未来~

|
シオノギファーマ(株) 第二生産本部 摂津工場長 田中 良介 |

|

【講演内容】
シオノギファーマでは2021年9月に連続生産によるインフルエンザ薬の製造承認を取得し、それ以来、連続生産で商用生産を行っている。本講演では、製造実績が蓄積された現在において、連続生産のメリットと課題点を考察し、将来目指す姿についても紹介する。
【講演者プロフィール】
2003年3月京都大学大学院工学研究科 合成・生物化学専攻 修士課程修了。2003年4月に塩野義製薬株式会社 製剤研究部に入社する。それ以来、固形製剤、注射製剤に関しての製品開発、工業化研究、工場の工程改善業務に従事する。2017年より連続生産を用いたインフルエンザ薬の製造プロセス開発に携わる。2020年、CMC研究本部 製剤研究センター部門長、2023年、シオノギファーマ(株) 先進技術部長等を経て、2024年よりシオノギファーマ(株) 摂津工場長(現職)
【講演内容】
シオノギファーマでは2021年9月に連続生産によるインフルエンザ薬の製造承認を取得し、それ以来、連続生産で商用生産を行っている。本講演では、製造実績が蓄積された現在において、連続生産のメリットと課題点を考察し、将来目指す姿についても紹介する。
【講演者プロフィール】
2003年3月京都大学大学院工学研究科 合成・生物化学専攻 修士課程修了。2003年4月に塩野義製薬株式会社 製剤研究部に入社する。それ以来、固形製剤、注射製剤に関しての製品開発、工業化研究、工場の工程改善業務に従事する。2017年より連続生産を用いたインフルエンザ薬の製造プロセス開発に携わる。2020年、CMC研究本部 製剤研究センター部門長、2023年、シオノギファーマ(株) 先進技術部長等を経て、2024年よりシオノギファーマ(株) 摂津工場長(現職)
● コースリーダー:エーザイ(株) 鵜飼 宏治
● サブリーダー:塩野義製薬(株) 石川 いずみ
<講演資料について>
当日、受付後にマイページより、PDFデータにてダウンロードいただけます。
講演資料を見ながら聴講をされたい方は、PCまたはスマートフォンをご持参ください。
※冊子での配布はございませんので、ご了承くださいませ。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
世界を揺るがすニトロソアミンとの攻防

|
東和薬品(株) 常務取締役/ 大地化成(株) 取締役会長 内川 治 |

|

【講演内容】
発がん性が認められているNDMAが薬剤に混入しているとの報道を耳にして7年、現在は原薬が直にニトロソ化されたNDSRIs が全世界の製薬業界を揺るがしている。“東和品質を貫くべく果敢に挑戦したニトロソアミンとの攻防の軌跡” を時間の許す限り紹介したい。
【講演者プロフィール】
1984年3月、九州大学大学院理学研究科修士課程修了。同年4月に武田薬品工業株式会社入社。医薬研究本部化学研究所にて新薬探索研究業務に従事。不眠症治療薬ロゼレム/ラメルテオン(世界初のメラトニン受容体作動薬)を創製し、2009年3月に日本薬学会創薬科学賞受賞。2011年4月、化学研究所長就任。2017年4月、立命館大学グローバルイノベーション研究機構教授に就任。2018年4月、東和薬品株式会社入社、執行役員原薬事業本部長就任。2021年6月、グループ会社の大地化成株式会社代表取締役会長就任(兼任)。2022年4月、東和薬品株式会社上席執行役員、2023年6月に同社取締役就任、現在に至る。
【講演内容】
発がん性が認められているNDMAが薬剤に混入しているとの報道を耳にして7年、現在は原薬が直にニトロソ化されたNDSRIs が全世界の製薬業界を揺るがしている。“東和品質を貫くべく果敢に挑戦したニトロソアミンとの攻防の軌跡” を時間の許す限り紹介したい。
【講演者プロフィール】
1984年3月、九州大学大学院理学研究科修士課程修了。同年4月に武田薬品工業株式会社入社。医薬研究本部化学研究所にて新薬探索研究業務に従事。不眠症治療薬ロゼレム/ラメルテオン(世界初のメラトニン受容体作動薬)を創製し、2009年3月に日本薬学会創薬科学賞受賞。2011年4月、化学研究所長就任。2017年4月、立命館大学グローバルイノベーション研究機構教授に就任。2018年4月、東和薬品株式会社入社、執行役員原薬事業本部長就任。2021年6月、グループ会社の大地化成株式会社代表取締役会長就任(兼任)。2022年4月、東和薬品株式会社上席執行役員、2023年6月に同社取締役就任、現在に至る。
ニトロソアミン問題のカオスの中で:ジェネリック医薬品開発におけるR&D部門の取り組み

|
沢井製薬(株) 研究開発本部 物性研究部 理事 部長 三村 尚志 |

|

【講演内容】
医薬品添加剤に起因するニトロソアミンリスクを評価する技術(NOXANA)の他、ジェネリック医薬品(既存製品および開発品目)の二トロソアミン問題に対する弊社R&D部門の様々な取り組みについて紹介する。業界内の協力体制構築の可能性についても触れたい。
【講演者プロフィール】
1989年3月 大阪大学大学院 薬学研究科 博士前期課程を修了。同年4月 藤沢薬品工業(株)に入社し、物性研究所に配属。2005年4月 山之内製薬(株)との合併によりアステラス製薬(株) に社名変更。2007年3月 東邦大学薬学部 寺田勝英教授のご指導の下、同大学より博士号(薬学)を取得。2013年4月 物性研究所 所長に就任。2018年3月 アステラス製薬(株)を退社し、同年4月 沢井製薬(株)に入社。同年7月 物性研究部 部長に就任し、現在に至る。
【講演内容】
医薬品添加剤に起因するニトロソアミンリスクを評価する技術(NOXANA)の他、ジェネリック医薬品(既存製品および開発品目)の二トロソアミン問題に対する弊社R&D部門の様々な取り組みについて紹介する。業界内の協力体制構築の可能性についても触れたい。
【講演者プロフィール】
1989年3月 大阪大学大学院 薬学研究科 博士前期課程を修了。同年4月 藤沢薬品工業(株)に入社し、物性研究所に配属。2005年4月 山之内製薬(株)との合併によりアステラス製薬(株) に社名変更。2007年3月 東邦大学薬学部 寺田勝英教授のご指導の下、同大学より博士号(薬学)を取得。2013年4月 物性研究所 所長に就任。2018年3月 アステラス製薬(株)を退社し、同年4月 沢井製薬(株)に入社。同年7月 物性研究部 部長に就任し、現在に至る。
● コースリーダー:(株)パウレック 長谷川 浩司
● サブリーダー:アステラス製薬(株) 小島 宏行
<講演資料について>
当日、受付後にマイページより、PDFデータにてダウンロードいただけます。
講演資料を見ながら聴講をされたい方は、PCまたはスマートフォンをご持参ください。
※冊子での配布はございませんので、ご了承くださいませ。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
日本初のmRNA CDMO:工場立ち上げから商用生産への軌跡

|
(株)ARCALIS 代表取締役社長CEO 髙松 聡 |

|

【講演内容】
日本初のmRNA医薬品専門CDMOとして、ARCALISが工場立ち上げから商用生産に至るまでに直面した課題と解決策、そして今後の展望についてご紹介する。
【講演者プロフィール】
東北大学大学院理学研究科 博士(理学)。大学院卒業後、30年以上一貫して医薬品の受託開発製造(CDMO)、製薬ビジネス、ライフサイエンス事業に、味の素、富士フイルム、AGCの各社で従事。味の素在職中は、CDMO分野での研究開発、製造、販売、事業管理といった業務を国内外において歴任。富士フイルムでは統括マネージャーとして、バイオCDMOの事業拡大と、医薬ライセンシング業務を牽引。2018年には米国の富士フイルムアーバインサイエンティフィック社で、CPO(チーフプラニングオフィサー)として経理・財務、人事、法務、経営企画部門を統括し、買収企業のPMIを実行。2019年にはAGCへ転じ、ファインケミカルズ事業部長として、低分子医農薬CDMO事業を拡大。2023年より現職。
【講演内容】
日本初のmRNA医薬品専門CDMOとして、ARCALISが工場立ち上げから商用生産に至るまでに直面した課題と解決策、そして今後の展望についてご紹介する。
【講演者プロフィール】
東北大学大学院理学研究科 博士(理学)。大学院卒業後、30年以上一貫して医薬品の受託開発製造(CDMO)、製薬ビジネス、ライフサイエンス事業に、味の素、富士フイルム、AGCの各社で従事。味の素在職中は、CDMO分野での研究開発、製造、販売、事業管理といった業務を国内外において歴任。富士フイルムでは統括マネージャーとして、バイオCDMOの事業拡大と、医薬ライセンシング業務を牽引。2018年には米国の富士フイルムアーバインサイエンティフィック社で、CPO(チーフプラニングオフィサー)として経理・財務、人事、法務、経営企画部門を統括し、買収企業のPMIを実行。2019年にはAGCへ転じ、ファインケミカルズ事業部長として、低分子医農薬CDMO事業を拡大。2023年より現職。
革新的医薬品の迅速な社会実装への挑戦

|
ネクスレッジ(株) 代表取締役 / NPS(株) 代表取締役会長 安本 篤史 |

|

【講演内容】
世界初の自己増殖型mRNAワクチンが日本で先駆けて承認され、本年2月に欧州(EMA)でも承認された。この次世代型mRNAワクチンの日本国内での迅速な開発、製造、申請に関し、ネクスレッジ社がどのように支援を行い、国内承認取得をサポートしたかについて当時を振り返る。
【講演者プロフィール】
2001年財団法人化血研(現kmb バイオロジクス)入所、試作研究部、生産技術部に所属し、研究開発や工場の設計・立ち上げ・管理・査察対応などに従事。
2013年株式会社シーエムプラスに入社、国内外のエンジニアリング、GMPコンサルティング事業をリード。
2015年にネクスレッジ株式会社を設立、医薬品開発・製造・薬事・GXP、M&Aや訴訟対応など医薬品事業を支援するプロフェッショナルサービスを提供。近年では後発医薬品の品質問題や供給問題について現場から政策立案まで広範囲に取り組み、日本の医薬品供給・品質改善に取り組んでいる。
【講演内容】
世界初の自己増殖型mRNAワクチンが日本で先駆けて承認され、本年2月に欧州(EMA)でも承認された。この次世代型mRNAワクチンの日本国内での迅速な開発、製造、申請に関し、ネクスレッジ社がどのように支援を行い、国内承認取得をサポートしたかについて当時を振り返る。
【講演者プロフィール】
2001年財団法人化血研(現kmb バイオロジクス)入所、試作研究部、生産技術部に所属し、研究開発や工場の設計・立ち上げ・管理・査察対応などに従事。
2013年株式会社シーエムプラスに入社、国内外のエンジニアリング、GMPコンサルティング事業をリード。
2015年にネクスレッジ株式会社を設立、医薬品開発・製造・薬事・GXP、M&Aや訴訟対応など医薬品事業を支援するプロフェッショナルサービスを提供。近年では後発医薬品の品質問題や供給問題について現場から政策立案まで広範囲に取り組み、日本の医薬品供給・品質改善に取り組んでいる。
● コースリーダー:(株)竹中工務店 川下 泰範
● サブリーダー:日揮(株) 潮崎 洋
<講演資料について>
当日、受付後にマイページより、PDFデータにてダウンロードいただけます。
講演資料を見ながら聴講をされたい方は、PCまたはスマートフォンをご持参ください。
※冊子での配布はございませんので、ご了承くださいませ。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
能力を最大化する組織変革:Quality CultureとDXの共鳴

|
中外製薬工業(株) 生産QA部 品質システム1グループ グループマネジャー 宮崎 礼子 |

|

【講演内容】
中外が実践する、プロフェッショナル人材の真価を引き出す環境構築の核心に迫る。Quality Cultureの醸成とDXの戦略的融合により、個の強みを活かしたリーダーシップが集団の力へと昇華する革新的組織変革を説明する。
【講演者プロフィール】
2005年中外製薬工業株式会社に入社、浮間工場の品質保証業務に携わる。2021年、品質保証機能のサイト横断組織化に伴い、宇都宮・浮間・藤枝の3サイトに関する文書管理・教育訓練を推進する部署に所属。2025年より当グループのグループマネージャーに就任、現在に至る。
【講演内容】
中外が実践する、プロフェッショナル人材の真価を引き出す環境構築の核心に迫る。Quality Cultureの醸成とDXの戦略的融合により、個の強みを活かしたリーダーシップが集団の力へと昇華する革新的組織変革を説明する。
【講演者プロフィール】
2005年中外製薬工業株式会社に入社、浮間工場の品質保証業務に携わる。2021年、品質保証機能のサイト横断組織化に伴い、宇都宮・浮間・藤枝の3サイトに関する文書管理・教育訓練を推進する部署に所属。2025年より当グループのグループマネージャーに就任、現在に至る。
Future Readyに向けた製造品質DXの取り組み

|
武田薬品工業(株) グローバルクオリティ 製薬品質センター 光製薬品質部 品質プロジェクトマネジメント ヘッド 西村 翔太 |

|

【講演内容】
武田薬品工業の製造・品質部門におけるグローバルストラテジー、Future Readyの実現に向け、データ・デジタル&テクノロジーの活用を推進しています。本講演では、光工場におけるDXを用いた製造・品質管理のトランスフォーメーションについて紹介します。
【講演者プロフィール】
2009年4月 武田薬品工業株式会社に入社。医薬品の製造部門に所属し、無菌製造に従事。
2012年から2020年まで品質部門にて品質試験および試験法開発を担当。2024年よりDXを用いた業務改善を推進する現職に至る。
【講演内容】
武田薬品工業の製造・品質部門におけるグローバルストラテジー、Future Readyの実現に向け、データ・デジタル&テクノロジーの活用を推進しています。本講演では、光工場におけるDXを用いた製造・品質管理のトランスフォーメーションについて紹介します。
【講演者プロフィール】
2009年4月 武田薬品工業株式会社に入社。医薬品の製造部門に所属し、無菌製造に従事。
2012年から2020年まで品質部門にて品質試験および試験法開発を担当。2024年よりDXを用いた業務改善を推進する現職に至る。
武田薬品工業(株)については、講師が変更になりました。
● コースリーダー:第一三共(株) 長谷川 晋
● サブリーダー:バイエル薬品(株) 鈴木 博文
<講演資料について>
当日、受付後にマイページより、PDFデータにてダウンロードいただけます。
講演資料を見ながら聴講をされたい方は、PCまたはスマートフォンをご持参ください。
※冊子での配布はございませんので、ご了承くださいませ。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
沢井製薬(株)第二九州工場新固形剤棟の建設事例

|
沢井製薬(株) 第二九州工場長 荒木 照男 |

|

【講演内容】
先発医薬品からジェネリック医薬品への置き換え率が9割を超え、ジェネリック医薬品の使用が定着する一方で、長年続く供給不安の解消が急務となっている。
厳格な品質保証や生産性向上といったニーズに応えるため、安定的な生産を可能にする堅牢な新固形剤棟を建設した。その取り組みについて説明する。
【講演者プロフィール】
1997年徳島大学大学院修了、沢井製薬(株)入社。製剤研究部に所属し処方設計に従事。
2000年九州工場、2018年第二九州工場へ異動し生産技術・製造を担当し、2021年新固形剤棟建設の立ち上げに参画し10月工場長、現在に至る。
【講演内容】
先発医薬品からジェネリック医薬品への置き換え率が9割を超え、ジェネリック医薬品の使用が定着する一方で、長年続く供給不安の解消が急務となっている。
厳格な品質保証や生産性向上といったニーズに応えるため、安定的な生産を可能にする堅牢な新固形剤棟を建設した。その取り組みについて説明する。
【講演者プロフィール】
1997年徳島大学大学院修了、沢井製薬(株)入社。製剤研究部に所属し処方設計に従事。
2000年九州工場、2018年第二九州工場へ異動し生産技術・製造を担当し、2021年新固形剤棟建設の立ち上げに参画し10月工場長、現在に至る。
中外製薬グループの環境への取り組み

|
中外製薬工業(株) デジタルエンジニアリング部 エンジニアリングプロフェッショナル(環境対策技術) 副部長 筆坂 将人 |

|

【講演内容】
中外製薬グループにおけるエンジニアリング/現場視点での環境に関する取り組みについて、脱炭素・脱フロンを中心に、事例の紹介や推進のハードル等について共有いたします。
【講演者プロフィール】
2004年に中外製薬(株)に入社。合成原薬のプロセス開発に従事した後、2019年に中外製薬工業(株)浮間工場の設備管理部門に異動。2021年よりデジタルエンジニアリング部に移り、中外製薬グループの中期環境目標2030の達成に向け、各種施策の企画立案、実行を推進中。
【講演内容】
中外製薬グループにおけるエンジニアリング/現場視点での環境に関する取り組みについて、脱炭素・脱フロンを中心に、事例の紹介や推進のハードル等について共有いたします。
【講演者プロフィール】
2004年に中外製薬(株)に入社。合成原薬のプロセス開発に従事した後、2019年に中外製薬工業(株)浮間工場の設備管理部門に異動。2021年よりデジタルエンジニアリング部に移り、中外製薬グループの中期環境目標2030の達成に向け、各種施策の企画立案、実行を推進中。
● コースリーダー:大成建設(株) 古谷 仁
● サブリーダー:フロイント産業(株) 伏島 巖
<講演資料について>
当日、受付後にマイページより、PDFデータにてダウンロードいただけます。
講演資料を見ながら聴講をされたい方は、PCまたはスマートフォンをご持参ください。
※冊子での配布はございませんので、ご了承くださいませ。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
ビッグデータで切り拓く次世代型製剤開発・生産 ~製剤ライフサイクルを通じたDX~

|
アステラス製薬(株) CMCディベロップメント 製剤研究所 製剤開発研究室 主任研究員 梅本 佳昭 |

|

【講演内容】
アステラスでは、製剤のライフサイクルを通じて得られるビッグデータを活用したDXに挑戦している。製剤開発でのデータで構築した「製剤設計AI」、及び商用生産でのデータを蓄積・見える化・活用するデータマイニングシステム「DAIMON」について、バイオ医薬品への適用など最新の事例を含めて紹介する。
【講演者プロフィール】
2012年3月、京都大学薬学部薬学科卒業。同年4月よりアステラス製薬株式会社に入社し、現在に至る。主に経口医薬品の製剤開発、新規製剤技術開発に従事。並行して製剤設計AIの開発を担当。2020年3月、静岡県立大学大学院薬学研究院博士課程修了(薬科学博士)。
【講演内容】
アステラスでは、製剤のライフサイクルを通じて得られるビッグデータを活用したDXに挑戦している。製剤開発でのデータで構築した「製剤設計AI」、及び商用生産でのデータを蓄積・見える化・活用するデータマイニングシステム「DAIMON」について、バイオ医薬品への適用など最新の事例を含めて紹介する。
【講演者プロフィール】
2012年3月、京都大学薬学部薬学科卒業。同年4月よりアステラス製薬株式会社に入社し、現在に至る。主に経口医薬品の製剤開発、新規製剤技術開発に従事。並行して製剤設計AIの開発を担当。2020年3月、静岡県立大学大学院薬学研究院博士課程修了(薬科学博士)。
未来に向けたタケダのデジタル人材育成:リスキリングと内製化が創る組織変革の現在地

|
武田薬品工業(株) ジャパンファーマビジネスユニット、データ・デジタル&テクノロジー部 ヘッド 松野 玲子 |

|

【講演内容】
2022年にタケダが実施したリスキリングプログラムは、従業員のスキル向上と企業文化の進化を通じて、組織変革を加速させる基盤となる重要な取り組みであった。本セッションでは、この3年間の成果を振り返り、人材育成を通じた戦略的な組織改革と具体的な実例を紹介する。
業務を知り尽くした社内人材がリスキリング(新たなスキルの獲得)とアップスキリング(既存スキルの強化)を2軸で展開することで、従業員一人ひとりの能力を最大化。また、テクノロジーの進歩に合わせたAI活用や特化型プログラムを通じて、次世代のデジタル人材を継続的に育成。さらにはグローバルとの連携を強化し、日本におけるイノベーションケイパビリティセンターの設立を進めている。
本セッションでは、私たちが大切にする「継続的な学びと成長」という文化が従業員体験にもたらす影響について、具体的に社内外に提供するサービスの質の向上、スピードの改善、コスト削減などの成果を共有する。そして、日本のヘルスケアを支える取り組みの中で、デジタル人材を内製化することで得られる意義と可能性を掘り下げ、未来へのビジョンを共有する。
【講演者プロフィール】
外資系製薬において、日本およびJPACリージョンのITヘッドなどを務めた後、2020年に武田へ入社。ヘルスケア業界の特にコマーシャル分野でのデジタル活用において長きにわたる知見を持つ。現在は同社の国内ビジネス部門におけるデータ・デジタル&テクノロジー(DD&T)部のトップとして、デジタル人材育成やデータを活用したイノベーションを統括する。
【講演内容】
2022年にタケダが実施したリスキリングプログラムは、従業員のスキル向上と企業文化の進化を通じて、組織変革を加速させる基盤となる重要な取り組みであった。本セッションでは、この3年間の成果を振り返り、人材育成を通じた戦略的な組織改革と具体的な実例を紹介する。
業務を知り尽くした社内人材がリスキリング(新たなスキルの獲得)とアップスキリング(既存スキルの強化)を2軸で展開することで、従業員一人ひとりの能力を最大化。また、テクノロジーの進歩に合わせたAI活用や特化型プログラムを通じて、次世代のデジタル人材を継続的に育成。さらにはグローバルとの連携を強化し、日本におけるイノベーションケイパビリティセンターの設立を進めている。
本セッションでは、私たちが大切にする「継続的な学びと成長」という文化が従業員体験にもたらす影響について、具体的に社内外に提供するサービスの質の向上、スピードの改善、コスト削減などの成果を共有する。そして、日本のヘルスケアを支える取り組みの中で、デジタル人材を内製化することで得られる意義と可能性を掘り下げ、未来へのビジョンを共有する。
【講演者プロフィール】
外資系製薬において、日本およびJPACリージョンのITヘッドなどを務めた後、2020年に武田へ入社。ヘルスケア業界の特にコマーシャル分野でのデジタル活用において長きにわたる知見を持つ。現在は同社の国内ビジネス部門におけるデータ・デジタル&テクノロジー(DD&T)部のトップとして、デジタル人材育成やデータを活用したイノベーションを統括する。
● コースリーダー:武田薬品工業(株) 丹羽 雅裕
● サブリーダー:第一三共(株) 長谷川 晋
<講演資料について>
当日、受付後にマイページより、PDFデータにてダウンロードいただけます。
講演資料を見ながら聴講をされたい方は、PCまたはスマートフォンをご持参ください。
※冊子での配布はございませんので、ご了承くださいませ。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
Catalent - Global CDMO ~ Patient First (全てはPatientのために)

|
キャタレント・ジャパン(株) 代表取締役社長 松村 忠浩 |

|

【講演内容】
Global CDMOであるキャタレントでの約11年の経験をもとに、キャタレントの医薬品、バイオ医薬品、健康食品の分野における先進的なデリバリー技術の概要とグローバルネットワークの強みについて説明する。
【講演者プロフィール】
1983年4月大学卒業後、日本ヴィックス社に入社、マーケティングを中心にキャリアを積み、P&G、フィリップ モリス ジャパンなどを経て、1999年からジョンソン・エンド・ジョンソンの一員となる。同社において、日本の使い捨てコンタクトレンズ市場の構築に携わり、後に営業責任者としてトップの市場シェア堅持に貢献した。2014年6月にキャタレント・ジャパンに代表取締役社長として入社。外資系ソフトカプセル受託製造業者として、国内売上規模を順調に伸ばし、治験関連事業拡大に伴い、2020年滋賀工場の設立などさまざまな成果をあげている。
【講演内容】
Global CDMOであるキャタレントでの約11年の経験をもとに、キャタレントの医薬品、バイオ医薬品、健康食品の分野における先進的なデリバリー技術の概要とグローバルネットワークの強みについて説明する。
【講演者プロフィール】
1983年4月大学卒業後、日本ヴィックス社に入社、マーケティングを中心にキャリアを積み、P&G、フィリップ モリス ジャパンなどを経て、1999年からジョンソン・エンド・ジョンソンの一員となる。同社において、日本の使い捨てコンタクトレンズ市場の構築に携わり、後に営業責任者としてトップの市場シェア堅持に貢献した。2014年6月にキャタレント・ジャパンに代表取締役社長として入社。外資系ソフトカプセル受託製造業者として、国内売上規模を順調に伸ばし、治験関連事業拡大に伴い、2020年滋賀工場の設立などさまざまな成果をあげている。
連続フロー生産技術の工業製造への運用実績と今後の発展

|
Asymchem Laboratories 日本事業部 部長 朱 明文 |

|

【講演内容】
連続フロー生産技術は抜群の生産性を持ち、近年世界中の研究者たちに注目され、開発活動は盛んに行われれています。
Asymchem社は、15年以上の連続フロー製造経験に基づいて、自社工場にフロー製造システムを装備するだけではなく、各業界の製造メーカーにも積極的に技術導出を行い、全製造業界の連続製造能力の向上を目指しています。
【講演者プロフィール】
2013年京都大学 博士号獲得
2020年Asymchem社入社、日本マーケット責任者として技術営業を担当し、現在に至る
【講演内容】
連続フロー生産技術は抜群の生産性を持ち、近年世界中の研究者たちに注目され、開発活動は盛んに行われれています。
Asymchem社は、15年以上の連続フロー製造経験に基づいて、自社工場にフロー製造システムを装備するだけではなく、各業界の製造メーカーにも積極的に技術導出を行い、全製造業界の連続製造能力の向上を目指しています。
【講演者プロフィール】
2013年京都大学 博士号獲得
2020年Asymchem社入社、日本マーケット責任者として技術営業を担当し、現在に至る
● コースリーダー:フロイント産業(株) 伏島 巖
● サブリーダー:千代田化工建設(株) 西田 真二
<講演資料について>
当日、受付後にマイページより、PDFデータにてダウンロードいただけます。
講演資料を見ながら聴講をされたい方は、PCまたはスマートフォンをご持参ください。
※冊子での配布はございませんので、ご了承くださいませ。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
注射製剤における投与デバイスの適用に関する動向

|
アステラス製薬(株) CMC ディベロップメント 製剤研究所 包装&デバイス研究室 主任研究員 中村 幸誠 |

|

【講演内容】
プレフィルドシリンジやオートインジェクターなどの投与デバイスを注射製剤に適用することで、安全性やユーザビリティが向上し、さらには製品の市場拡大も期待される。投与デバイス選定~上市~市販後対応の製品ライフサイクルにおける検討項目や関連規制などについて紹介する。
【講演者プロフィール】
2017年アステラス製薬入社。製剤研究所に所属し,グローバル製品の開発品・商用品の包装設計・技術移転ならびにコンビネーション製品・医療機器の開発に従事。デバイス設計・開発を学ぶため,イリノイ大学シカゴ校にて海外留学経験。
【講演内容】
プレフィルドシリンジやオートインジェクターなどの投与デバイスを注射製剤に適用することで、安全性やユーザビリティが向上し、さらには製品の市場拡大も期待される。投与デバイス選定~上市~市販後対応の製品ライフサイクルにおける検討項目や関連規制などについて紹介する。
【講演者プロフィール】
2017年アステラス製薬入社。製剤研究所に所属し,グローバル製品の開発品・商用品の包装設計・技術移転ならびにコンビネーション製品・医療機器の開発に従事。デバイス設計・開発を学ぶため,イリノイ大学シカゴ校にて海外留学経験。
PFS (Pre-Filled Syringe)/AI (Auto-Injector)におけるHuman Factors Studyのポイント ~FDA draft guidanceを基に~

|
エマーゴ・ジャパン・コンサルティング(株) ヒューマンファクタリサーチ&デザイン マネージングヒューマンファクタスペシャリスト 吉田 賢 |

|

【講演内容】
本講演では、米国FDAのHFE(Human Factors Engineering)ガイダンス文書を中心に、実際のFDAからのユーザビリティに関する指摘事項、及び最近のFDAの傾向について解説し、多数のバリデーション試験実施してきた経験より得た実践的なインサイトを紹介する。
【講演者プロフィール】
2012年米国ミネソタ大学大学院博士課程修了。大手医療機器会社にて開発及び薬事を経験後、2015年UL Japanに入社。医療機器、製薬、IVDなど幅広い国内外の企業に対してHFE関連の規制対応、技術支援などを提供し、ワークショップやウェビナーなどを様々な媒体を通して、国内のHFE普及にも貢献。
【講演内容】
本講演では、米国FDAのHFE(Human Factors Engineering)ガイダンス文書を中心に、実際のFDAからのユーザビリティに関する指摘事項、及び最近のFDAの傾向について解説し、多数のバリデーション試験実施してきた経験より得た実践的なインサイトを紹介する。
【講演者プロフィール】
2012年米国ミネソタ大学大学院博士課程修了。大手医療機器会社にて開発及び薬事を経験後、2015年UL Japanに入社。医療機器、製薬、IVDなど幅広い国内外の企業に対してHFE関連の規制対応、技術支援などを提供し、ワークショップやウェビナーなどを様々な媒体を通して、国内のHFE普及にも貢献。
● コースリーダー:アステラス製薬(株) 小島 宏行
● サブリーダー:中外製薬(株) 橋本 大輔
<講演資料について>
当日、受付後にマイページより、PDFデータにてダウンロードいただけます。
講演資料を見ながら聴講をされたい方は、PCまたはスマートフォンをご持参ください。
※冊子での配布はございませんので、ご了承くださいませ。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
構内物流改革と乳化機の自動運転に取り組んだスマートファクトリーの建設事例

|
ホーユー(株) 生産本部 生産統括室 購買統括課 課長 松林 通 |

|

【講演内容】
スマートファクトリーを建設にあたり、素案作成から採用までの工程とスマートファクトリー建設の要求事項の作成から基本設計、詳細設計へと進む中での予算と戦いながら5年かけて完成した工場の建設事例を紹介する。
【講演者プロフィール】
1997年3月三重大学卒業。同年4月ホーユー(株)入社。研究所に9年在籍し、包材開発。その後、品質保証部、生産技術部で新製品の立ち上げ、2017年から生産統括室にて工場建設に携わり現在に至る。
【講演内容】
スマートファクトリーを建設にあたり、素案作成から採用までの工程とスマートファクトリー建設の要求事項の作成から基本設計、詳細設計へと進む中での予算と戦いながら5年かけて完成した工場の建設事例を紹介する。
【講演者プロフィール】
1997年3月三重大学卒業。同年4月ホーユー(株)入社。研究所に9年在籍し、包材開発。その後、品質保証部、生産技術部で新製品の立ち上げ、2017年から生産統括室にて工場建設に携わり現在に至る。
製薬会社から見た建設プロジェクトの進め方

|
中外製薬工業(株) デジタルエンジニアリング部 エンジニアリング統括マネージャー 斎藤 誠司 |

|

【講演内容】
中外製薬工業における建設プロジェクトのプロジェクトマネジメント手法・課題や難しさ・気を付けているポイントについて、製薬会社のエンジニア視点で紹介する。
【講演者プロフィール】
中外製薬工業の設備エンジニアとして20年以上の実務経験を持つ。種々の設備投資プロジェクトを担当し、現在は中外製薬工業3サイトの設備投資プロジェクトを統括している。
【講演内容】
中外製薬工業における建設プロジェクトのプロジェクトマネジメント手法・課題や難しさ・気を付けているポイントについて、製薬会社のエンジニア視点で紹介する。
【講演者プロフィール】
中外製薬工業の設備エンジニアとして20年以上の実務経験を持つ。種々の設備投資プロジェクトを担当し、現在は中外製薬工業3サイトの設備投資プロジェクトを統括している。
● コースリーダー:日揮(株) 潮崎 洋
● サブリーダー:大成建設(株) 古谷 仁
<講演資料について>
当日、受付後にマイページより、PDFデータにてダウンロードいただけます。
講演資料を見ながら聴講をされたい方は、PCまたはスマートフォンをご持参ください。
※冊子での配布はございませんので、ご了承くださいませ。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
QP制度から学ぶ品質保証のための人材育成

|
富山県立大学 バイオ医薬品人材育成講座 客員教授 鳴瀬 諒子 |

|

【講演内容】
欧州の医薬品の市場出荷認証を担うQualified Person(QP)は、薬剤師の他、大学院のQPコース修了などの資格要件が法的に定められている。そのGMP人材を確保するための教育システムの実際を解説するとともに、国内のアカデミアのGMP人材育成の取組みも紹介する。
【講演者プロフィール】
薬学部卒業後、製薬企業の品質管理・品質保証に12年間従事。2005年PMDAに入構し、医薬品のGMP調査及びバイオ医薬品審査などを担当。2022年にPMDAより富山大学薬学部に出向し、開設された医薬品品質保証・評価学講座でGMP教育研究に従事。引き続き2025年4月に開設された富山県立大学バイオ医薬品人材育成講座でGMP人材育成の教育研究に携わり、現在に至る。
【講演内容】
欧州の医薬品の市場出荷認証を担うQualified Person(QP)は、薬剤師の他、大学院のQPコース修了などの資格要件が法的に定められている。そのGMP人材を確保するための教育システムの実際を解説するとともに、国内のアカデミアのGMP人材育成の取組みも紹介する。
【講演者プロフィール】
薬学部卒業後、製薬企業の品質管理・品質保証に12年間従事。2005年PMDAに入構し、医薬品のGMP調査及びバイオ医薬品審査などを担当。2022年にPMDAより富山大学薬学部に出向し、開設された医薬品品質保証・評価学講座でGMP教育研究に従事。引き続き2025年4月に開設された富山県立大学バイオ医薬品人材育成講座でGMP人材育成の教育研究に携わり、現在に至る。
協和キリンにおけるGMP 人材育成の取り組み事例

|
協和キリン(株) 品質本部高崎品質ユニット品質保証部 部長 山本 誠 |

|

【講演内容】
協和キリンでは日本発のGlobal Specialty Pharmaへの飛躍を推進すべく、事業の拡大と人材の採用を加速してきた。高崎工場では、このような環境下において優先すべき課題として、人的資本の充実を主眼に置き人材育成に注力してきた。
今回、協和キリン高崎工場でのGMP人材育成について、クオリティカレッジの活動を中心に紹介する。
【講演者プロフィール】
富山医科薬科大学を卒業後、内資系製薬会社の品質管理部に就職。その後、工場のQualityとして数回の合併・分社化を経て、2021年に協和キリン株式会社へ転職。内資・外資の先発及び後発会社のサイトQualityを経験。
【講演内容】
協和キリンでは日本発のGlobal Specialty Pharmaへの飛躍を推進すべく、事業の拡大と人材の採用を加速してきた。高崎工場では、このような環境下において優先すべき課題として、人的資本の充実を主眼に置き人材育成に注力してきた。
今回、協和キリン高崎工場でのGMP人材育成について、クオリティカレッジの活動を中心に紹介する。
【講演者プロフィール】
富山医科薬科大学を卒業後、内資系製薬会社の品質管理部に就職。その後、工場のQualityとして数回の合併・分社化を経て、2021年に協和キリン株式会社へ転職。内資・外資の先発及び後発会社のサイトQualityを経験。
● コースリーダー:塩野義製薬(株) 石川 いずみ
● サブリーダー:(株)竹中工務店 川下 泰範
<講演資料について>
当日、受付後にマイページより、PDFデータにてダウンロードいただけます。
講演資料を見ながら聴講をされたい方は、PCまたはスマートフォンをご持参ください。
※冊子での配布はございませんので、ご了承くださいませ。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
医薬品包装プラスチックの環境対応に向けた国内外の政策動向と素材選択

|
三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) 環境・自然ユニット 地球環境部 主任研究員 植田 洋行 |

|

【講演内容】
欧州の包装・包装廃棄物規則(PPWR)や国内のプラスチック資源循環法等、包装プラスチックの環境対応を求める政策を受け、各業界での対応が加速しつつある。本講演では、プラスチックの環境対応に関係する国内外の政策の動向と素材選択について概説する。
【講演者プロフィール】
1997年京都大学工学部卒業、1999年京都大学大学院工学研究科修了(環境工学)、技術士(環境部門・衛生工学部門)、環境計量士(濃度関係)、UNFCCCインベントリ審査官(廃棄物分野)。
民間コンサルを経て、2012年より三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)において、主に中央省庁をクライアントに、プラスチック資源循環や地球温暖化対策に関する政策・調査支援業務に携わる。
【講演内容】
欧州の包装・包装廃棄物規則(PPWR)や国内のプラスチック資源循環法等、包装プラスチックの環境対応を求める政策を受け、各業界での対応が加速しつつある。本講演では、プラスチックの環境対応に関係する国内外の政策の動向と素材選択について概説する。
【講演者プロフィール】
1997年京都大学工学部卒業、1999年京都大学大学院工学研究科修了(環境工学)、技術士(環境部門・衛生工学部門)、環境計量士(濃度関係)、UNFCCCインベントリ審査官(廃棄物分野)。
民間コンサルを経て、2012年より三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)において、主に中央省庁をクライアントに、プラスチック資源循環や地球温暖化対策に関する政策・調査支援業務に携わる。
中外製薬における環境配慮型医薬品包装の開発事例紹介

|
中外製薬(株) 製薬技術本部 製剤研究部 企画・包装グループ 尾家 弘昭 |

|

【講演内容】
今後の医薬品包装において環境配慮包材の活用は重要である。中外製薬は従来のプラスチック削減に加え、PTP、ボトル、ブリスタートレイ、アルミピローの主要4種の包装資材にバイオマス材料や再生材料を用いて環境負荷低減を実現してきた。本講演では、これら包装の開発事例を紹介する。
【講演者プロフィール】
2008年に中外製薬株式会社入社後、経口剤及び注射剤の製剤開発における開発品目の包装設計・技術検討、既存品包装改良・工場への技術移管を担当。包装専士を取得し、現在は同社の包装開発における技術構築の推進・承認申請等に従事。これまでに製品パッケージへのバイオマス材料や再生材料等の環境配慮包材の適用を推進してきた。
【講演内容】
今後の医薬品包装において環境配慮包材の活用は重要である。中外製薬は従来のプラスチック削減に加え、PTP、ボトル、ブリスタートレイ、アルミピローの主要4種の包装資材にバイオマス材料や再生材料を用いて環境負荷低減を実現してきた。本講演では、これら包装の開発事例を紹介する。
【講演者プロフィール】
2008年に中外製薬株式会社入社後、経口剤及び注射剤の製剤開発における開発品目の包装設計・技術検討、既存品包装改良・工場への技術移管を担当。包装専士を取得し、現在は同社の包装開発における技術構築の推進・承認申請等に従事。これまでに製品パッケージへのバイオマス材料や再生材料等の環境配慮包材の適用を推進してきた。
● コースリーダー:中外製薬(株) 橋本 大輔
● サブリーダー:エーザイ(株) 鵜飼 宏治
<講演資料について>
当日、受付後にマイページより、PDFデータにてダウンロードいただけます。
講演資料を見ながら聴講をされたい方は、PCまたはスマートフォンをご持参ください。
※冊子での配布はございませんので、ご了承くださいませ。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
医薬品製造メーカーの視点から見る「持続可能な医薬品サプライチェーンの構築」

|
武田薬品工業(株) グローバルマニュファクチュアリングサプライジャパン サプライチェーンマネジメント部 部長 吉成 友宏 |

|

【講演内容】
この発表は、GDPに準拠した持続可能な医薬品流通システムをDX技術も活用して開発することを目的としている。ブロックチェーンを使用したリアルタイムの流通情報共有、先進的な在庫管理、物流データ統合による需要予測の利点、CO2削減のための戦略方法も含まれる。さらに、今後の産業界の課題についても取り上げる。
【講演者プロフィール】
1993 年武田薬品に入社後、 旧CMC研究センター( 現Pharmaceutical Sciences)にて、製剤設計研究を担当、その後、製品戦略部、製品ポートフォリオマネジメントを経て、2016 年より、現職、サプライチェーンマネジメント部長として従事。
岐阜薬科大学修士(1993年)、英国ブラッドフォード大学博士 (2002年)、神戸大学経営学研究科専門職学位課程(MBA)(2007年)
【講演内容】
この発表は、GDPに準拠した持続可能な医薬品流通システムをDX技術も活用して開発することを目的としている。ブロックチェーンを使用したリアルタイムの流通情報共有、先進的な在庫管理、物流データ統合による需要予測の利点、CO2削減のための戦略方法も含まれる。さらに、今後の産業界の課題についても取り上げる。
【講演者プロフィール】
1993 年武田薬品に入社後、 旧CMC研究センター( 現Pharmaceutical Sciences)にて、製剤設計研究を担当、その後、製品戦略部、製品ポートフォリオマネジメントを経て、2016 年より、現職、サプライチェーンマネジメント部長として従事。
岐阜薬科大学修士(1993年)、英国ブラッドフォード大学博士 (2002年)、神戸大学経営学研究科専門職学位課程(MBA)(2007年)

|
武田薬品工業(株) グローバルマニュファクチュアリングサプライジャパン サプライチェーンマネジメント部 淵田 麻由 |

|

【講演者プロフィール】
2019年3月早稲田大学先進理工学部卒業。
2019年4月武田薬品工業株式会社に入社し、MRとして神奈川県西部エリアを担当。
2023年10月サプライチェーンマネジメント部に異動し、現在に至る。
【講演者プロフィール】
2019年3月早稲田大学先進理工学部卒業。
2019年4月武田薬品工業株式会社に入社し、MRとして神奈川県西部エリアを担当。
2023年10月サプライチェーンマネジメント部に異動し、現在に至る。
再生医療における物流プロセス展望

|
三井倉庫ホールディングス(株) 事業開発部 シニアマネージャー 朽木 謙一 |

|

【講演内容】
再生医療の技術は進化を加速しており、様々なモダリティが生まれています。それに伴いサプライチェーンにも多様なニーズが求められています。再生医療物流の現況を踏まえ、今後の展望について発表いたします。
【講演者プロフィール】
1987年大学卒業後、精密機械メーカー、小売業、外食産業、港湾運送業等にて輸出入、物流担当として従事。2007年9月三井倉庫株式会社に入社、営業開発担当として従事。2009年6月治験薬物流の担当、2010年より再生医療物流の担当となる。2014年10月より持株会社制移行に伴い、三井倉庫ホールディングス株式会社に所属、現在に至る。
【講演内容】
再生医療の技術は進化を加速しており、様々なモダリティが生まれています。それに伴いサプライチェーンにも多様なニーズが求められています。再生医療物流の現況を踏まえ、今後の展望について発表いたします。
【講演者プロフィール】
1987年大学卒業後、精密機械メーカー、小売業、外食産業、港湾運送業等にて輸出入、物流担当として従事。2007年9月三井倉庫株式会社に入社、営業開発担当として従事。2009年6月治験薬物流の担当、2010年より再生医療物流の担当となる。2014年10月より持株会社制移行に伴い、三井倉庫ホールディングス株式会社に所属、現在に至る。
● コースリーダー:千代田化工建設(株) 西田 真二
● サブリーダー:武田薬品工業(株) 丹羽 雅裕
<講演資料について>
当日、受付後にマイページより、PDFデータにてダウンロードいただけます。
講演資料を見ながら聴講をされたい方は、PCまたはスマートフォンをご持参ください。
※冊子での配布はございませんので、ご了承くださいませ。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
SMBC日興証券(株) 株式調査部 シニアアナリスト ヘルスケア担当 徳本 進之介 |

|

【講演内容】
製薬企業を取り巻くDX(デジタル・トランスフォーメーション)はこれからどうなるのか。注目企業の動向や課題を踏まえ、未来予想図やシナリオから逆算する形で、2025年の注目点を展望します。マーケティング、臨床開発・治験、創薬、患者向けサービスの最新動向も紹介します。
【講演者プロフィール】
SMBC日興証券株式会社 株式調査部 シニアアナリスト ヘルスケア担当(医療機器、医療IT)。一般社団法人 代表理事を経て、2016年4月SMBC日興証券入社。リテール業務に従事し、2018年4月より現職。医療デバイスは治療、検査診断、歯科眼科機器の動向を調査。特に米国、中国、日本企業の戦略、政策や規制動向の分析に注力する。医療ITは、未上場企業含めたヘルステック業界の動向を分析。製薬DX、治験DX、医療DX、健保DX、健康・医療データ動向などが専門。Institutional Investor(2024年3月)医療技術・サービス第1位
【講演内容】
製薬企業を取り巻くDX(デジタル・トランスフォーメーション)はこれからどうなるのか。注目企業の動向や課題を踏まえ、未来予想図やシナリオから逆算する形で、2025年の注目点を展望します。マーケティング、臨床開発・治験、創薬、患者向けサービスの最新動向も紹介します。
【講演者プロフィール】
SMBC日興証券株式会社 株式調査部 シニアアナリスト ヘルスケア担当(医療機器、医療IT)。一般社団法人 代表理事を経て、2016年4月SMBC日興証券入社。リテール業務に従事し、2018年4月より現職。医療デバイスは治療、検査診断、歯科眼科機器の動向を調査。特に米国、中国、日本企業の戦略、政策や規制動向の分析に注力する。医療ITは、未上場企業含めたヘルステック業界の動向を分析。製薬DX、治験DX、医療DX、健保DX、健康・医療データ動向などが専門。Institutional Investor(2024年3月)医療技術・サービス第1位

|
住友ファーマ(株) IT&データアナリティクス部 データアナリティクス&デジタルソリューショングループマネジャー 菅原 秀和 |

|

【講演内容】
人々の健康で豊かな生活のために、研究開発を基盤とした新たな価値の創造により、広く社会に貢献する。この理念の実践と更なる高みを目指し「デジタル・データ活用が当たり前の世界」をキーワードにDXを推進する住友ファーマ。先端エンジニアが研究開発の第一線と協働し独自の生成AI活用にも取り組んでいる。その実体は?
皆さんが広く採用できるよう技術詳細は控えめに、弊社のDX推進と生成AI活用のアウトラインをお届けします。
【講演者プロフィール】
2005年 内資系IT企業入社。システムエンジニアとして、主に流通・製造系のシステム開発とインフラ構築および運用を担当。2013年 大日本住友製薬(現 住友ファーマ)入社。電子実験ノート(ELN)等各事業部門向けシステムから全社向けスマートワークツールの導入やDX推進まで幅広く担当。2019年よりアジャイル・コーチとしてアジャイルな働き方の展開と、DX人材育成に携わり、社内講師も多数経験。2024年よりデータサイエンティストとITエンジニアで構成される内製部隊のマネージャーを務めている。
【講演内容】
人々の健康で豊かな生活のために、研究開発を基盤とした新たな価値の創造により、広く社会に貢献する。この理念の実践と更なる高みを目指し「デジタル・データ活用が当たり前の世界」をキーワードにDXを推進する住友ファーマ。先端エンジニアが研究開発の第一線と協働し独自の生成AI活用にも取り組んでいる。その実体は?
皆さんが広く採用できるよう技術詳細は控えめに、弊社のDX推進と生成AI活用のアウトラインをお届けします。
【講演者プロフィール】
2005年 内資系IT企業入社。システムエンジニアとして、主に流通・製造系のシステム開発とインフラ構築および運用を担当。2013年 大日本住友製薬(現 住友ファーマ)入社。電子実験ノート(ELN)等各事業部門向けシステムから全社向けスマートワークツールの導入やDX推進まで幅広く担当。2019年よりアジャイル・コーチとしてアジャイルな働き方の展開と、DX人材育成に携わり、社内講師も多数経験。2024年よりデータサイエンティストとITエンジニアで構成される内製部隊のマネージャーを務めている。

|
沢井製薬(株) 研究開発本部 製剤研究部 製剤Ⅱグループ 研究員 木全 崚太 |

|

【講演内容】
業務プロセス改革に、様々なデジタル技術を活用。
社内の豊富な研究データをもとに、AI エージェントを構築した。
そのAIエージェントをベテラン研究員の代わりとして活用することで、効率的な知識伝承を体系化し、スピード感を持った研究開発に取り組む。
【講演者プロフィール】
2016年 沢井製薬(株)に入社。
製剤研究部に配属、ジェネリック医薬品の経口固形製剤の処方設計に従事。
2022年に製剤研究部内のDX推進チームを発足させ、製剤研究業務の傍ら、GASや生成AIなどを用いたデジタルツールを作成し、現在に至る。
【講演内容】
業務プロセス改革に、様々なデジタル技術を活用。
社内の豊富な研究データをもとに、AI エージェントを構築した。
そのAIエージェントをベテラン研究員の代わりとして活用することで、効率的な知識伝承を体系化し、スピード感を持った研究開発に取り組む。
【講演者プロフィール】
2016年 沢井製薬(株)に入社。
製剤研究部に配属、ジェネリック医薬品の経口固形製剤の処方設計に従事。
2022年に製剤研究部内のDX推進チームを発足させ、製剤研究業務の傍ら、GASや生成AIなどを用いたデジタルツールを作成し、現在に至る。

|
デロイト トーマツ グループ 量子技術統括 寺部 雅能 |

|

【講演内容】
近年急速な発展を遂げる量子コンピュータ。将来創薬プロセスを劇的に変えていく可能性があり、メガファーマたちが開発競争を繰り広げています。このセッションでは量子コンピュータ技術の基礎から応用領域、ビジネストレンド、デロイトが取り組む創薬研究事例をご紹介します。
【講演者プロフィール】
自動車系メーカー、総合商社の量子プロジェクトリーダー、兼務として東北大学客員准教授を経て現職。量子分野において数々の世界初実証や日本で最多件数となる海外スタートアップ投資支援を行い、広いグローバル人脈を保有。国際会議の基調講演やTV等メディア発信も行い量子業界の振興にも貢献。著書「量子コンピュータが変える未来」。
官民の量子プロジェクト支援のほか、量子アルゴリズム研究、量子エコシステム構築にも取り組む。
一般社団法人量子フォーラム 量子コンピュータ推進委員会 幹事、経済産業省・NEDO 量子・古典ハイブリッド技術のサイバ-・フィジカル開発事業の技術推進委員長など複数の委員、文科省・JSTの量子人材育成プログラムQ-Quest講師も務める。
【講演内容】
近年急速な発展を遂げる量子コンピュータ。将来創薬プロセスを劇的に変えていく可能性があり、メガファーマたちが開発競争を繰り広げています。このセッションでは量子コンピュータ技術の基礎から応用領域、ビジネストレンド、デロイトが取り組む創薬研究事例をご紹介します。
【講演者プロフィール】
自動車系メーカー、総合商社の量子プロジェクトリーダー、兼務として東北大学客員准教授を経て現職。量子分野において数々の世界初実証や日本で最多件数となる海外スタートアップ投資支援を行い、広いグローバル人脈を保有。国際会議の基調講演やTV等メディア発信も行い量子業界の振興にも貢献。著書「量子コンピュータが変える未来」。
官民の量子プロジェクト支援のほか、量子アルゴリズム研究、量子エコシステム構築にも取り組む。
一般社団法人量子フォーラム 量子コンピュータ推進委員会 幹事、経済産業省・NEDO 量子・古典ハイブリッド技術のサイバ-・フィジカル開発事業の技術推進委員長など複数の委員、文科省・JSTの量子人材育成プログラムQ-Quest講師も務める。

|
中外製薬(株) 渉外調査部 パブリックアフェアーズグループ 課長 岡本 哲 |

|

【講演内容】
中外製薬の患者団体との協働の取組みを紹介する。「患者中心」の価値観のもと、患者さんの声を聞き相互理解を目指し共有価値創造に取り組む活動「PHARMONY」を中心に、CEOダイアログや臨床試験情報へのアクセス向上など、一人ひとりに最適な医療の実現に向けた事例を紹介する。
【講演者プロフィール】
2002年3月、成蹊大学卒業。同年4月に日本ロシュに入社後、中外製薬とRocheの戦略的アライアンス締結により中外製薬社員となり、腎臓領域専門MRとして透析専門病院、大学病院を担当。2013年から2021年まで中外製薬労働組合の専従役員を務め、2024年9月までは薬粧連合(医薬品化粧品の産業別労働団体)へ出向し、事務局長として組織運営の中核を担当。2024年10月より会社へ復職、渉外調査部パブリックアフェアーズグループに異動し、血友病領域等における患者協働活動に取り組む。MRと労組役員の経験を活かし、「病とともに生きる人々の夢を叶える一助になる」という自身の夢の実現に向け、患者中心の医療環境構築に尽力している。
【講演内容】
中外製薬の患者団体との協働の取組みを紹介する。「患者中心」の価値観のもと、患者さんの声を聞き相互理解を目指し共有価値創造に取り組む活動「PHARMONY」を中心に、CEOダイアログや臨床試験情報へのアクセス向上など、一人ひとりに最適な医療の実現に向けた事例を紹介する。
【講演者プロフィール】
2002年3月、成蹊大学卒業。同年4月に日本ロシュに入社後、中外製薬とRocheの戦略的アライアンス締結により中外製薬社員となり、腎臓領域専門MRとして透析専門病院、大学病院を担当。2013年から2021年まで中外製薬労働組合の専従役員を務め、2024年9月までは薬粧連合(医薬品化粧品の産業別労働団体)へ出向し、事務局長として組織運営の中核を担当。2024年10月より会社へ復職、渉外調査部パブリックアフェアーズグループに異動し、血友病領域等における患者協働活動に取り組む。MRと労組役員の経験を活かし、「病とともに生きる人々の夢を叶える一助になる」という自身の夢の実現に向け、患者中心の医療環境構築に尽力している。

|
済生会神奈川県病院 病院長 長島 敦 |

|

【講演内容】
本セミナーでは、「患者中心の医療」の実現に向けて、地域医療を取り巻く現実と製薬企業が果たし得る役割について、多角的な視点から議論を深めていく。冒頭の講演では、現役医師が病院経営の厳しい現状、医療現場が抱える構造的課題、そして地域連携やデジタルトランスフォーメーション(DX)の必要性とその障壁について、実体験に基づいた視点で語る。
その後のパネルディスカッションでは、製薬企業の関係者と業界識者を迎え、現場と企業の間に存在する“認識のギャップ”を紐解きながら、製薬企業が今後、どのように地域医療に貢献できるのかを議論していく。
とりわけ、MR(医薬情報担当者)が単なる製品情報提供者から、地域医療の課題解決に寄与する“パートナー”へと進化していくために必要な視点や行動についても掘り下げていく。
本セミナーは、製薬企業にとって、医療現場のリアルな課題を深く理解し、自社の提供価値を再定義する契機となる場である。
【講演者プロフィール】
1985年浜松医科大学医学部卒業後、慶應義塾大学病院外科、浜松赤十字病院外科を経て、1988年慶應義塾大学外科学教室助手となる。1991年より済生会神奈川県病院外科医員、2003年には同外科部長に就任。 2007年に済生会横浜市東部病院開院と同時に同病院外科部長に就任。2012年より同副院長兼消化器センター長兼医療連携センター長に就任。2016年10月より済生会神奈川県院 病院長に就任、現在に至る。
また、2013年より慶應義塾大学客員准教授、2017年より同大学客員教授を兼務。
【講演内容】
本セミナーでは、「患者中心の医療」の実現に向けて、地域医療を取り巻く現実と製薬企業が果たし得る役割について、多角的な視点から議論を深めていく。冒頭の講演では、現役医師が病院経営の厳しい現状、医療現場が抱える構造的課題、そして地域連携やデジタルトランスフォーメーション(DX)の必要性とその障壁について、実体験に基づいた視点で語る。
その後のパネルディスカッションでは、製薬企業の関係者と業界識者を迎え、現場と企業の間に存在する“認識のギャップ”を紐解きながら、製薬企業が今後、どのように地域医療に貢献できるのかを議論していく。
とりわけ、MR(医薬情報担当者)が単なる製品情報提供者から、地域医療の課題解決に寄与する“パートナー”へと進化していくために必要な視点や行動についても掘り下げていく。
本セミナーは、製薬企業にとって、医療現場のリアルな課題を深く理解し、自社の提供価値を再定義する契機となる場である。
【講演者プロフィール】
1985年浜松医科大学医学部卒業後、慶應義塾大学病院外科、浜松赤十字病院外科を経て、1988年慶應義塾大学外科学教室助手となる。1991年より済生会神奈川県病院外科医員、2003年には同外科部長に就任。 2007年に済生会横浜市東部病院開院と同時に同病院外科部長に就任。2012年より同副院長兼消化器センター長兼医療連携センター長に就任。2016年10月より済生会神奈川県院 病院長に就任、現在に至る。
また、2013年より慶應義塾大学客員准教授、2017年より同大学客員教授を兼務。

|
アストラゼネカ(株) ディレクター 北垣 瑞穂 |

|

【講演者プロフィール】
新卒でアストラゼネカに入社し、プライマリーケア領域のMRとして従事。その後本社に異動し、eマーケティングチームの立ち上げメンバーとしてデジタルマーケティング業務やCRMプラットフォーム戦略の立案や実行に携わる。現在はワクチン・免疫療法事業本部の営業推進部にて、営業活動に必要なKPI管理や今後のビジネスを見据えた営業組織モデルの検討に取り組んでいる。
【講演者プロフィール】
新卒でアストラゼネカに入社し、プライマリーケア領域のMRとして従事。その後本社に異動し、eマーケティングチームの立ち上げメンバーとしてデジタルマーケティング業務やCRMプラットフォーム戦略の立案や実行に携わる。現在はワクチン・免疫療法事業本部の営業推進部にて、営業活動に必要なKPI管理や今後のビジネスを見据えた営業組織モデルの検討に取り組んでいる。

|
(株)ミクス 代表取締役/ミクス編集長 沼田 佳之 |

|

【講演者プロフィール】
大学を卒業後、外資系製薬企業に入社し、MRとして活動。
この経験を踏まえ、1992 年から製薬業界向け日刊紙の記者としての取材に従事。キャップ、デスク、編集長を経て、2008年12月にエルゼビア・ジャパン株式会社に移籍、同月からMonthly ミクスの編集長に就任。
2017年7月より株式会社ミクス 代表取締役/ミクス編集長に就任、現在に至る。
【講演者プロフィール】
大学を卒業後、外資系製薬企業に入社し、MRとして活動。
この経験を踏まえ、1992 年から製薬業界向け日刊紙の記者としての取材に従事。キャップ、デスク、編集長を経て、2008年12月にエルゼビア・ジャパン株式会社に移籍、同月からMonthly ミクスの編集長に就任。
2017年7月より株式会社ミクス 代表取締役/ミクス編集長に就任、現在に至る。
【交流会】講演終了後、交流会開催(参加無料)

|
飲み物、軽食をご用意しております 参加対象者:講師、聴講者全員 |
|
【講演+パネルディスカッション+交流会】
本セッションは講演、パネルディスカッション、交流会がセットになったセミナーです。
済生会神奈川県病院 長島先生にご講演をいただいた後、
長島先生、アストラゼネカ 北垣様、ミクス 沼田様の3名により、
ペイシェントセントリシティをテーマによるパネルディスカッションを開催いたします。
セミナーの終了後、講師と受講者による交流会を開催しております。
他社との情報交換やアイデア共有ができる場としてぜひご参加ください。
※本セッションは講演開始から交流会終了まで、スタンディング形式となっておりますが、
お体の不自由な方向けにお席のご用意もございます。

|
塩野義製薬(株) DX推進本部 データサイエンス部 理事 データサイエンス部長 北西 由武 |

|

【講演内容】
サイエンスの基本は、観察し、仮説を立て、実験、検証し、意思決定をするサイクルであり、これらをどれだけ忠実にできるかにある。データサイエンス部では、これらのサイクルをデータに基づいて実践し、日々の業務に活かしている。これらのコンセプトを事例と共に紹介する。
【講演者プロフィール】
2003年塩野義製薬入社。 解析センターにて臨床統計に従事し、統計解析プログラミングやシステム構築に携わる。 データ解析を軸として他組織・他機能と連携を深めながら全社的なデータ活用を推進し、2020年にデータサイエンス室長に就任。 2021年よりデータサイエンス部長として、社内外のデータ活用を推進し、現在に至る。
【講演内容】
サイエンスの基本は、観察し、仮説を立て、実験、検証し、意思決定をするサイクルであり、これらをどれだけ忠実にできるかにある。データサイエンス部では、これらのサイクルをデータに基づいて実践し、日々の業務に活かしている。これらのコンセプトを事例と共に紹介する。
【講演者プロフィール】
2003年塩野義製薬入社。 解析センターにて臨床統計に従事し、統計解析プログラミングやシステム構築に携わる。 データ解析を軸として他組織・他機能と連携を深めながら全社的なデータ活用を推進し、2020年にデータサイエンス室長に就任。 2021年よりデータサイエンス部長として、社内外のデータ活用を推進し、現在に至る。

|
(株)CureApp 高血圧症領域 執行役員 馬場 継 |

|

【講演者プロフィール】
名古屋⼤学⼤学院修了。製薬業界において20年以上にわたりマーケティング、営業、経営戦略等で要職を歴任後、2018年以降、複数の製薬企業にて執⾏役員兼事業本部⻑として営業・マーケティング・事業開発を中⼼とした事業マネジメントに従事しながらも、経営⼤学院にてマーケティングや経営戦略の講師を務める。2023年7⽉より現職。
【講演者プロフィール】
名古屋⼤学⼤学院修了。製薬業界において20年以上にわたりマーケティング、営業、経営戦略等で要職を歴任後、2018年以降、複数の製薬企業にて執⾏役員兼事業本部⻑として営業・マーケティング・事業開発を中⼼とした事業マネジメントに従事しながらも、経営⼤学院にてマーケティングや経営戦略の講師を務める。2023年7⽉より現職。

|
アトピヨ(同) 代表 赤穂 亮太郎 |

|

【講演者プロフィール】
代表・アプリエンジニア・工学修士・公認会計士。EY新日本有限責任監査法人、株式会社レノバを経て、自身のアトピー、喘息、鼻炎という3つのアレルギー疾患の経験から、「アトピー見える化アプリ-アトピヨ」を開発し、2021年にアトピヨ合同会社を設立。厚労省「健康寿命をのばそう!アワード」、経産省「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト」、総務省「異能vation」など11の賞を受賞。
現在は6万枚の画像と5万件の口コミを活用し、7大学・国立病院と連携してAI画像解析・自然言語処理による個別化医療の研究を推進。新薬切替タイミングと症状変化の可視化、患者プラットフォームを利用した疾患啓発を実施。
【講演者プロフィール】
代表・アプリエンジニア・工学修士・公認会計士。EY新日本有限責任監査法人、株式会社レノバを経て、自身のアトピー、喘息、鼻炎という3つのアレルギー疾患の経験から、「アトピー見える化アプリ-アトピヨ」を開発し、2021年にアトピヨ合同会社を設立。厚労省「健康寿命をのばそう!アワード」、経産省「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト」、総務省「異能vation」など11の賞を受賞。
現在は6万枚の画像と5万件の口コミを活用し、7大学・国立病院と連携してAI画像解析・自然言語処理による個別化医療の研究を推進。新薬切替タイミングと症状変化の可視化、患者プラットフォームを利用した疾患啓発を実施。

|
(一社)ヘルスケアイノベーション協会 代表理事 天野 達郎 |

|

【講演者プロフィール】
大阪大学工学部卒、早稲田大学大学院経営管理研究科(MBA)修了、博士課程に在学中。三井物産では、欧州・中東・アフリカ地域を中心にインフラおよびモビリティ分野のプロジェクト開発・運営に従事し、経営企画や新規事業の創出、人事制度改革など多様な経営課題に取り組んできた。国内外の多様な関係者と連携しながら、次世代の組織と人材の在り方についての実践的知見を蓄積。早稲田大学オープンイノベ―ション機構では招聘研究員として産学連携や知財戦略に携わり、ベンチャー支援やオープンイノベーションにも積極的に関与している。また、一般社団法人ヘルスケアイノベーション協会を設立し、医療法人の経営支援や医療DXの推進など、ヘルスケア領域における新事業創出・資金調達・組織開発・経営支援に尽力している。
【講演者プロフィール】
大阪大学工学部卒、早稲田大学大学院経営管理研究科(MBA)修了、博士課程に在学中。三井物産では、欧州・中東・アフリカ地域を中心にインフラおよびモビリティ分野のプロジェクト開発・運営に従事し、経営企画や新規事業の創出、人事制度改革など多様な経営課題に取り組んできた。国内外の多様な関係者と連携しながら、次世代の組織と人材の在り方についての実践的知見を蓄積。早稲田大学オープンイノベ―ション機構では招聘研究員として産学連携や知財戦略に携わり、ベンチャー支援やオープンイノベーションにも積極的に関与している。また、一般社団法人ヘルスケアイノベーション協会を設立し、医療法人の経営支援や医療DXの推進など、ヘルスケア領域における新事業創出・資金調達・組織開発・経営支援に尽力している。

|
(一社)ヘルスケアイノベーション協会 代表理事 大角 知也 |

|

【講演者プロフィール】
早稲田大学ビジネススクールで経営学修士号(MBA)を取得。IQVIAにてセールス/マーケティング支援やメディカル関連プロジェクトを多数推進し、新規事業として患者支援や看護師サービスを立ち上げる。FRONTEOでは医療DXの責任者としてAIソリューションを提供。現在はTXP Medicalにて医療データ事業部長として、製薬企業向けのデータ活用サービスを牽引。
【講演者プロフィール】
早稲田大学ビジネススクールで経営学修士号(MBA)を取得。IQVIAにてセールス/マーケティング支援やメディカル関連プロジェクトを多数推進し、新規事業として患者支援や看護師サービスを立ち上げる。FRONTEOでは医療DXの責任者としてAIソリューションを提供。現在はTXP Medicalにて医療データ事業部長として、製薬企業向けのデータ活用サービスを牽引。
【講演内容】
デジタルヘルスの社会実装に向け、スタートアップの視点から新規事業の進め方やエビデンス構築の重要性、実装の障壁と突破口を探ります。
【講演+パネルディスカッション】
前半では、各社のデジタルヘルスの取り組みについてショートプレゼンをいただき、
後半では、新規事業の進め方を大企業とスタートアップの視点で協議します。
また、デジタルヘルスの社会実装の障壁と進め方やエビデンス構築の重要性について
パネルディスカッションを予定しております。

|
(一財)日本製薬医学会(JAPhMed) 副理事長・メディカルアフェアーズ部会長/ (株)ニシウマ 代表取締役 西馬 信一 |

|

【講演内容】
RWDから得られるRWEの利活用が製薬業界で注目されています。新薬開発や臨床試験の最適化、市販後調査、医療経済評価、安全性・有効性の検証など、RWEの応用範囲は広がり続けています。本講演では、次世代医療基盤法の整備やICHによるGCP改訂の動向を踏まえつつ、製薬企業の視点からRWD/RWEの現状と今後の展望、さらに利活用に向けた課題と実践例を紹介しながら、今後のリアルワールドデータの利活用の可能性について語りたい。
【講演者プロフィール】
1997年に神戸大学医学部を卒業後、神戸市立医療センター中央市民病院にて内科研修医および消化器内科の臨床医として診療に従事。C型肝炎治療薬のドラッグ・ラグに課題意識を抱き、製薬業界へ転身。外資系製薬企業にて、臨床開発、メディカルアフェアーズ、安全性部門の各領域で要職を歴任し、リアルワールドデータ(RWD)を活用した多くのプロジェクトを主導してきた。2022年には、日本発のスタートアップ製薬企業であるアキュリスファーマ株式会社のチーフ・メディカル・オフィサー(CMO)に就任。ジャズファーマシューティカルズを経て、2025年に株式会社ニシウマの代表取締役に就任。現在は、同社を通じてCROやメドテック企業との業務委託・コンサルティングを行うとともに、日本発のスタートアップ製薬企業の支援に注力している。
また、日本製薬医学会の副理事長・メディカルアフェアーズ部会長として、製薬医学の啓発・発展にも尽力しており、大阪大学大学院薬学研究科「製薬医学」コースの講師としても教育活動を行っている。
【講演内容】
RWDから得られるRWEの利活用が製薬業界で注目されています。新薬開発や臨床試験の最適化、市販後調査、医療経済評価、安全性・有効性の検証など、RWEの応用範囲は広がり続けています。本講演では、次世代医療基盤法の整備やICHによるGCP改訂の動向を踏まえつつ、製薬企業の視点からRWD/RWEの現状と今後の展望、さらに利活用に向けた課題と実践例を紹介しながら、今後のリアルワールドデータの利活用の可能性について語りたい。
【講演者プロフィール】
1997年に神戸大学医学部を卒業後、神戸市立医療センター中央市民病院にて内科研修医および消化器内科の臨床医として診療に従事。C型肝炎治療薬のドラッグ・ラグに課題意識を抱き、製薬業界へ転身。外資系製薬企業にて、臨床開発、メディカルアフェアーズ、安全性部門の各領域で要職を歴任し、リアルワールドデータ(RWD)を活用した多くのプロジェクトを主導してきた。2022年には、日本発のスタートアップ製薬企業であるアキュリスファーマ株式会社のチーフ・メディカル・オフィサー(CMO)に就任。ジャズファーマシューティカルズを経て、2025年に株式会社ニシウマの代表取締役に就任。現在は、同社を通じてCROやメドテック企業との業務委託・コンサルティングを行うとともに、日本発のスタートアップ製薬企業の支援に注力している。
また、日本製薬医学会の副理事長・メディカルアフェアーズ部会長として、製薬医学の啓発・発展にも尽力しており、大阪大学大学院薬学研究科「製薬医学」コースの講師としても教育活動を行っている。

|
TXP Medical(株) 医療データ事業部 戦略推進責任者(Strategic Development Officer)兼 Medical Data Lab所長 大角 知也 |

|

【講演者プロフィール】
早稲田大学ビジネススクールで経営学修士号(MBA)を取得。IQVIAにてセールス/マーケティング支援やメディカル関連プロジェクトを多数推進し、新規事業として患者支援や看護師サービスを立ち上げる。FRONTEOでは医療DXの責任者としてAIソリューションを提供。現在はTXP Medicalにて医療データ事業部長として、製薬企業向けのデータ活用サービスを牽引。
【講演者プロフィール】
早稲田大学ビジネススクールで経営学修士号(MBA)を取得。IQVIAにてセールス/マーケティング支援やメディカル関連プロジェクトを多数推進し、新規事業として患者支援や看護師サービスを立ち上げる。FRONTEOでは医療DXの責任者としてAIソリューションを提供。現在はTXP Medicalにて医療データ事業部長として、製薬企業向けのデータ活用サービスを牽引。

|
花王(株) SCM部門 ロジスティクスセンター ロジスティクス改革部 マネジャー(物流DX担当) 田坂 晃一 |

|

【講演内容】
花王の目指すサプライチェーンの姿や現在ロジスティクス関連での取り組んでいる最適化・自動化に関連する活動について講演する。
具体的な事例として、2023年に稼働した豊橋工場の新倉庫について取り上げ、労働力不足やホワイト物流への対応について説明する。
【講演者プロフィール】
2007年に花王に入社し、ロジスティクス部門にて国内の物流拠点の見える化システム開発やコスト解析や作業改善に従事。その後、海外の物流拠点政策の立案・推進を実施。
2017年7月から経済産業省商務・サービスグループ物流企画室に出向し、日本の物流政策の立案・実行に従事。
2019年7月に花王に帰任し、ロジスティクスセンターにて国内の物流拠点政策を担当。最適サプライチェーンネットワークの策定や新たな物流拠点の設計を実施。
2021年7月にデジタルイノベーションプロジェクトが発足し、チーフデータサイエンティストとして、ロジスティクスを中心としたサプライチェーン全体の高度化を推進。
2025年1月にロジスティクスセンターに異動し、現職。
【講演内容】
花王の目指すサプライチェーンの姿や現在ロジスティクス関連での取り組んでいる最適化・自動化に関連する活動について講演する。
具体的な事例として、2023年に稼働した豊橋工場の新倉庫について取り上げ、労働力不足やホワイト物流への対応について説明する。
【講演者プロフィール】
2007年に花王に入社し、ロジスティクス部門にて国内の物流拠点の見える化システム開発やコスト解析や作業改善に従事。その後、海外の物流拠点政策の立案・推進を実施。
2017年7月から経済産業省商務・サービスグループ物流企画室に出向し、日本の物流政策の立案・実行に従事。
2019年7月に花王に帰任し、ロジスティクスセンターにて国内の物流拠点政策を担当。最適サプライチェーンネットワークの策定や新たな物流拠点の設計を実施。
2021年7月にデジタルイノベーションプロジェクトが発足し、チーフデータサイエンティストとして、ロジスティクスを中心としたサプライチェーン全体の高度化を推進。
2025年1月にロジスティクスセンターに異動し、現職。

|
エーザイ(株) ファーマシューティカルサイエンス&テクノロジー 原薬研究部 部長 阿部 太一 |

|

【講演内容】
私達は良いクスリをより早く世の中へ送り出すことを目指し、日々原薬研究を展開している。本講演では、エーザイのこれまでの原薬研究と今後の原薬研究力向上のための取り組み、目指すところを紹介する。
【講演者プロフィール】
1997年3月千葉大学工学研究科修了後、同年4月エーザイ化学(株)入社。1998年エーザイ(株)現原薬研究部に配属。初期から後期の低分子医薬品プロセス研究、承認申請書作成、原材料調達、CMO/CROマネジメント、研究推進業務等を担当し、現在、原薬研究部部長に従事。 博士(工学,2015年千葉大学)。
【講演内容】
私達は良いクスリをより早く世の中へ送り出すことを目指し、日々原薬研究を展開している。本講演では、エーザイのこれまでの原薬研究と今後の原薬研究力向上のための取り組み、目指すところを紹介する。
【講演者プロフィール】
1997年3月千葉大学工学研究科修了後、同年4月エーザイ化学(株)入社。1998年エーザイ(株)現原薬研究部に配属。初期から後期の低分子医薬品プロセス研究、承認申請書作成、原材料調達、CMO/CROマネジメント、研究推進業務等を担当し、現在、原薬研究部部長に従事。 博士(工学,2015年千葉大学)。

|
田辺三菱製薬工場(株) 小野田工場 工場長 杉本 昌陽 |

|

【講演内容】
田辺三菱製薬工場は、同じ事業所内にある田辺三菱製薬のCMC研究部門との間で、CMC研究から商用生産に亘る連携体制を強化することによって、研究開発のスピードアップと医薬原薬・医薬品の品質改善・コスト低減を図っている。本講演では、実例を交えて、その活動の内容を紹介する。
【講演者プロフィール】
1992年3月に京都大学大学院農学研究科修士課程を修了し、田辺製薬株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)に入社し、主に経口固形製剤の研究開発やCMCプロジェクトマネジメントに関わる業務に従事。2007年3月に京都大学薬学部薬学研究科にて博士(薬学)を取得。その後、コーポレート部門、CMC企画部門等での企画管理業務を経験した後、製剤研究部長、製品技術研究所長を歴任し、現在に至る。
【講演内容】
田辺三菱製薬工場は、同じ事業所内にある田辺三菱製薬のCMC研究部門との間で、CMC研究から商用生産に亘る連携体制を強化することによって、研究開発のスピードアップと医薬原薬・医薬品の品質改善・コスト低減を図っている。本講演では、実例を交えて、その活動の内容を紹介する。
【講演者プロフィール】
1992年3月に京都大学大学院農学研究科修士課程を修了し、田辺製薬株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)に入社し、主に経口固形製剤の研究開発やCMCプロジェクトマネジメントに関わる業務に従事。2007年3月に京都大学薬学部薬学研究科にて博士(薬学)を取得。その後、コーポレート部門、CMC企画部門等での企画管理業務を経験した後、製剤研究部長、製品技術研究所長を歴任し、現在に至る。

|
スペラファーマ(株) 大阪研究センター 製薬研究所 所長 森田 暁 |

|

【講演内容】
アカデミアやベンチャー企業から大手製薬企業まで、幅広い範囲の製薬開発パートナーであるCDMOは、対象化合物の開発ステージや各社の戦略に応じた柔軟な対応力が求められる。また、検討においては限られた予算および期間内で業務を完遂する必要がある。本講演では、具体的な事例も交えて紹介する。
【講演者プロフィール】
2009年3月、東北大学大学院 農学研究科を修了後、同年4月に武田薬品工業株式会社に入社し、CMC研究センター 製薬研究所に配属され、原薬のプロセス開発研究を担当。その後、2017年に会社分割に伴い、現所属に転籍し、2025年6月より現職として従事。
【講演内容】
アカデミアやベンチャー企業から大手製薬企業まで、幅広い範囲の製薬開発パートナーであるCDMOは、対象化合物の開発ステージや各社の戦略に応じた柔軟な対応力が求められる。また、検討においては限られた予算および期間内で業務を完遂する必要がある。本講演では、具体的な事例も交えて紹介する。
【講演者プロフィール】
2009年3月、東北大学大学院 農学研究科を修了後、同年4月に武田薬品工業株式会社に入社し、CMC研究センター 製薬研究所に配属され、原薬のプロセス開発研究を担当。その後、2017年に会社分割に伴い、現所属に転籍し、2025年6月より現職として従事。
講師が変更になりました。

|
中外製薬(株) 製薬研究部長 前田 賢二 |

|

【講演内容】
当社では、経口投与可能で細胞内浸透性と高結合活性を持つ環状ペプチドを中分子創薬として開発している。非天然アミノ酸を多く含む複雑な構造が製造上の課題であったが、独自の製薬技術により環境負荷・コスト・製造期間の大幅な削減の目途が立ちつつある。本講演では中外製薬の中分子ペプチド創薬における製薬技術戦略、技術イノベーション、そして今後の挑戦について紹介する。
【講演者プロフィール】
2000年3月に東北大学大学院理学研究科博士課程を修了。同年4月に万有製薬(株)に入社し、ケミカル原薬の製造プロセス開発に従事。2006年2月より中外製薬(株)に転じ、2006年から2012年および2015年から2017年までケミカル原薬の製造プロセス開発を担当。2012年から2014年にはR&Dポートフォリオマネジメント業務に携わる。2018年から2020年まで合成技術統括マネジャーを務め、2020年より現職の製薬研究部長としてケミカル&バイオ原薬の製造プロセス開発を統括。専門分野は有機合成化学およびプロセス化学。
【講演内容】
当社では、経口投与可能で細胞内浸透性と高結合活性を持つ環状ペプチドを中分子創薬として開発している。非天然アミノ酸を多く含む複雑な構造が製造上の課題であったが、独自の製薬技術により環境負荷・コスト・製造期間の大幅な削減の目途が立ちつつある。本講演では中外製薬の中分子ペプチド創薬における製薬技術戦略、技術イノベーション、そして今後の挑戦について紹介する。
【講演者プロフィール】
2000年3月に東北大学大学院理学研究科博士課程を修了。同年4月に万有製薬(株)に入社し、ケミカル原薬の製造プロセス開発に従事。2006年2月より中外製薬(株)に転じ、2006年から2012年および2015年から2017年までケミカル原薬の製造プロセス開発を担当。2012年から2014年にはR&Dポートフォリオマネジメント業務に携わる。2018年から2020年まで合成技術統括マネジャーを務め、2020年より現職の製薬研究部長としてケミカル&バイオ原薬の製造プロセス開発を統括。専門分野は有機合成化学およびプロセス化学。

|
協和キリン(株) バイオ生産技術研究所 所長 黒田 康介 |

|

【講演内容】
協和キリン株式会社(KKC)は製品開発の加速化を目的に、初期臨床試験用原薬製造棟である高崎工場HB7棟の稼働を開始し、後期臨床試験/上市用原薬の製造を行うサンフォード工場(ノースカロライナ州、アメリカ)の建設を進めている。本講演では、KKCにおけるプロセス開発から上市生産に至るまでの開発・生産体制の構築戦略及び連続生産技術に関する取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
・2002年 キリンビール株式会社(現協和キリン株式会社)に入社しバイオ医薬品の生産技術とCMC開発に従事、2018年に同社退職
・2018年 富士フイルム株式会社に入社しCDMOビジネスに従事、2020年に同社退職
・2020年 協和キリン株式会社に復職しバイオ医薬品のCMC開発に従事、2025年4月よりバイオ生産技術研究所の所長に就任し現在に至る
【講演内容】
協和キリン株式会社(KKC)は製品開発の加速化を目的に、初期臨床試験用原薬製造棟である高崎工場HB7棟の稼働を開始し、後期臨床試験/上市用原薬の製造を行うサンフォード工場(ノースカロライナ州、アメリカ)の建設を進めている。本講演では、KKCにおけるプロセス開発から上市生産に至るまでの開発・生産体制の構築戦略及び連続生産技術に関する取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
・2002年 キリンビール株式会社(現協和キリン株式会社)に入社しバイオ医薬品の生産技術とCMC開発に従事、2018年に同社退職
・2018年 富士フイルム株式会社に入社しCDMOビジネスに従事、2020年に同社退職
・2020年 協和キリン株式会社に復職しバイオ医薬品のCMC開発に従事、2025年4月よりバイオ生産技術研究所の所長に就任し現在に至る
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
Tokyo-1:AI創薬を加速するGPUスパコンとイノベーションハブ

|
(株)ゼウレカ 執行役員CTO 牧口 大旭 |

|

【講演内容】
AIによる創薬研究の加速を目指す、GPUスパコン基盤とコミュニティからなる「Tokyo-1」。その設立に至る背景や提供するサービス内容に加え、昨年2月のローンチ以降、参画企業と共に進めてきた1年間の取組みを紹介する。2年目を迎える中での今後の展望についても示す。
【講演者プロフィール】
2002年4月、三井情報開発株式会社(現:三井情報株式会社)に入社。国内の多くの大学法人、独立研究開発法人、製薬企業、食品・化学・装置メーカー等の研究部門にて、生命情報学の側面から研究支援業務、システム開発、並びにサービス化などに従事。
2017年4月、同社バイオメディカル室室長に就任し、がんゲノムクリニカルシーケンスや質量分析器のSW開発などを含めた同社におけるバイオサイエンス部門を統括。2020年4月、同社にて創薬事業室を組成しAI創薬事業を模索。三井物産と連携しPoC等を推進しゼウレカ社設立に至る。
2022年1月、株式会社ゼウレカへ入社。技術及びサービス開発、受託研究などに従事、2024年4月同社CTOに就任し、現在に至る。
【講演内容】
AIによる創薬研究の加速を目指す、GPUスパコン基盤とコミュニティからなる「Tokyo-1」。その設立に至る背景や提供するサービス内容に加え、昨年2月のローンチ以降、参画企業と共に進めてきた1年間の取組みを紹介する。2年目を迎える中での今後の展望についても示す。
【講演者プロフィール】
2002年4月、三井情報開発株式会社(現:三井情報株式会社)に入社。国内の多くの大学法人、独立研究開発法人、製薬企業、食品・化学・装置メーカー等の研究部門にて、生命情報学の側面から研究支援業務、システム開発、並びにサービス化などに従事。
2017年4月、同社バイオメディカル室室長に就任し、がんゲノムクリニカルシーケンスや質量分析器のSW開発などを含めた同社におけるバイオサイエンス部門を統括。2020年4月、同社にて創薬事業室を組成しAI創薬事業を模索。三井物産と連携しPoC等を推進しゼウレカ社設立に至る。
2022年1月、株式会社ゼウレカへ入社。技術及びサービス開発、受託研究などに従事、2024年4月同社CTOに就任し、現在に至る。
Tokyo-1を活用したAI創薬の加速化

|
アステラス製薬(株) デジタルX R&DX 次長 森 健一 |

|

【講演内容】
アステラス製薬では創薬研究DXの一環としてAI創薬技術の開発と活用を進め、治験に至る低分子化合物を創出するまでの水準に至っている。本講演では、様々な分子モダリティのAI創薬をいかにTokyo-1を活用して加速化しているかについて紹介する。
【講演者プロフィール】
2007年3月、千葉大学大学院医学薬学府創薬生命科学専攻卒業。博士(薬学)
2007年4月、万有製薬株式会社に入社。 化学研究所に入所し、in silico創薬研究に従事。
2009年5月、アステラス製薬株式会社に入社。化学研究所に入所し、in silico創薬研究に従事。
2017年10月より、AI創薬を推進する部署に異動し、現在に至る。
【講演内容】
アステラス製薬では創薬研究DXの一環としてAI創薬技術の開発と活用を進め、治験に至る低分子化合物を創出するまでの水準に至っている。本講演では、様々な分子モダリティのAI創薬をいかにTokyo-1を活用して加速化しているかについて紹介する。
【講演者プロフィール】
2007年3月、千葉大学大学院医学薬学府創薬生命科学専攻卒業。博士(薬学)
2007年4月、万有製薬株式会社に入社。 化学研究所に入所し、in silico創薬研究に従事。
2009年5月、アステラス製薬株式会社に入社。化学研究所に入所し、in silico創薬研究に従事。
2017年10月より、AI創薬を推進する部署に異動し、現在に至る。
小野薬品におけるTokyo-1プロジェクトの取り組み

|
小野薬品工業(株) 創薬ケミストリー研究部 部長 江頭 啓 |

|

【講演内容】
小野薬品はNVIDIA DGX H100を計算基盤とした創薬イノベーションプロジェクトTokyo-1に参画しています。GPUを活用した大規模ドッキング、高精度タンパク質-リガンド結合予測の高速化、タンパク質言語モデルの活用、新規標的探索などを行って、AI創薬を加速させています。
【講演者プロフィール】
1996年3月、九州大学薬学研究科修了。小野薬品工業株式会社に入社。医薬品化学研究所に所属し、合成研究にに従事。2000年より計算化学グループに所属、2011年より同グループヘッド。2022年より創薬DX推進室・室長、2025年1月より現職。
【講演内容】
小野薬品はNVIDIA DGX H100を計算基盤とした創薬イノベーションプロジェクトTokyo-1に参画しています。GPUを活用した大規模ドッキング、高精度タンパク質-リガンド結合予測の高速化、タンパク質言語モデルの活用、新規標的探索などを行って、AI創薬を加速させています。
【講演者プロフィール】
1996年3月、九州大学薬学研究科修了。小野薬品工業株式会社に入社。医薬品化学研究所に所属し、合成研究にに従事。2000年より計算化学グループに所属、2011年より同グループヘッド。2022年より創薬DX推進室・室長、2025年1月より現職。
第一三共の研究DXへの取り組み

|
第一三共(株) モダリティ第一研究所 研究所長 戸田 成洋 |

|

【講演内容】
AI創薬などのデジタルテクノロジーは医薬品開発の成功確率および生産性向上に不可欠な技術となりつつある。弊社のAI創薬、自動化、人材育成などの取り組みを俯瞰的に紹介する。
【講演者プロフィール】
1999年4月、三共株式会社入社。メディシナルケミストとして低分子創薬研究に従事。2011年より2年間、アメリカ・スクリプス研究所へ派遣留学。2013年よりADC化学研究などのモダリティ研究に従事。2023年4月モダリティ研究所長、2024年4月よりモダリティ第一研究所長、現在に至る。
【講演内容】
AI創薬などのデジタルテクノロジーは医薬品開発の成功確率および生産性向上に不可欠な技術となりつつある。弊社のAI創薬、自動化、人材育成などの取り組みを俯瞰的に紹介する。
【講演者プロフィール】
1999年4月、三共株式会社入社。メディシナルケミストとして低分子創薬研究に従事。2011年より2年間、アメリカ・スクリプス研究所へ派遣留学。2013年よりADC化学研究などのモダリティ研究に従事。2023年4月モダリティ研究所長、2024年4月よりモダリティ第一研究所長、現在に至る。
<パネルディスカッション>

|
アステラス製薬(株) デジタルX R&DX アソシエイトマネージャー 井手 圭吾 |

|

【講演者プロフィール】
2022年3月に早稲田大学大学院博士課程を単位取得満期退学後、同年10月に博士(工学)を取得。同年4月、bitBiome株式会社に入社し、研究開発部にてバイオインフォマティクス及びAI技術を活用した酵素探索・改変研究に従事。
2023年8月よりアステラス製薬株式会社に移籍し、現在は遺伝子治療、ファージセラピー、抗体などのバイオロジカルモダリティに関するバイオインフォマティクス・AI研究、および同分野における研究DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を担当し、現在に至る。
【講演者プロフィール】
2022年3月に早稲田大学大学院博士課程を単位取得満期退学後、同年10月に博士(工学)を取得。同年4月、bitBiome株式会社に入社し、研究開発部にてバイオインフォマティクス及びAI技術を活用した酵素探索・改変研究に従事。
2023年8月よりアステラス製薬株式会社に移籍し、現在は遺伝子治療、ファージセラピー、抗体などのバイオロジカルモダリティに関するバイオインフォマティクス・AI研究、および同分野における研究DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を担当し、現在に至る。

|
小野薬品工業(株) 創薬ケミストリー研究部 計算化学グループ グループヘッド 黒野 昌邦 |

|

【講演者プロフィール】
2004年名古屋大学大学院生命農学研究科博士課程修了、同年小野薬品工業(株)入社し、メディシナルケミストとして業務に従事する。2007年に計算化学グループに異動、京都大学大学院薬学研究科で計算化学技術を学ぶ。2015年にONO PHARMA UK LTD.で1年間勤務。2022年より計算化学グループヘッドとして、AI・シミュレーション技術を活用した創薬業務に従事し、現在に至る。博士(農学)
【講演者プロフィール】
2004年名古屋大学大学院生命農学研究科博士課程修了、同年小野薬品工業(株)入社し、メディシナルケミストとして業務に従事する。2007年に計算化学グループに異動、京都大学大学院薬学研究科で計算化学技術を学ぶ。2015年にONO PHARMA UK LTD.で1年間勤務。2022年より計算化学グループヘッドとして、AI・シミュレーション技術を活用した創薬業務に従事し、現在に至る。博士(農学)

|
第一三共(株) 研究開発本部 研究統括部 モダリティ第一研究所 第一グループ グループ長 芹沢 貴之 |

|

【講演者プロフィール】
2003年3月 東京工業大学 修了
2003年4月 旭化成ファーマに入社、創薬化学者として研究に従事
2019年2月~2020年3月 旭化成ファーマ 計算科学のチームにてインフォマティクス業務に従事
2020年3月~ 第一三共株式会社に入社、データ駆動型創薬(D4)の推進に従事、現在に至る
【講演者プロフィール】
2003年3月 東京工業大学 修了
2003年4月 旭化成ファーマに入社、創薬化学者として研究に従事
2019年2月~2020年3月 旭化成ファーマ 計算科学のチームにてインフォマティクス業務に従事
2020年3月~ 第一三共株式会社に入社、データ駆動型創薬(D4)の推進に従事、現在に至る
モデレーター:

|
エヌビディア(同) シニア事業開発マネージャー 平畠 浩司 |

|

【講演者プロフィール】
2005年より国内大手製薬会社にてセールスおよび海外マーケティングに従事。その後、海外バイオテクノロジー企業の開発パイプラインの導入・導出の事業開発アドバイザー、医療AIベンチャー企業を経て、2021年にNVIDIAに入社。NVIDIAではライフサイエンスと金融業界におけるAI活用の活性化を推進
【講演者プロフィール】
2005年より国内大手製薬会社にてセールスおよび海外マーケティングに従事。その後、海外バイオテクノロジー企業の開発パイプラインの導入・導出の事業開発アドバイザー、医療AIベンチャー企業を経て、2021年にNVIDIAに入社。NVIDIAではライフサイエンスと金融業界におけるAI活用の活性化を推進
【講演+パネルディスカッション】
本セッションは、創薬研究をデジタルで変革するプロジェクト『Tokyo-1』に関するセミナーです(2部構成)。
前半では、AI創薬のマネジメント層の方々の取り組み、
そしてどのようなリーダーシップ発揮しているかのショートプレゼンをいただき、
後半では、日々のAI研究を中心として進められている若手研究者同士の熱量を感じられる
パネルディスカッションを予定しております。
AI創薬の最前線を学べる、ここでしか聞けない講演となりますので、
満席になる前にぜひお申込みください。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
既知から未知を発見するAI「KIBIT」を活用した創薬の標的探索、DRとその仮説生成

|
(株)FRONTEO 取締役/CSO 豊柴 博義 |

|

【講演内容】
創薬においては成功確率の低下や開発費の高騰など様々な課題解決のため、AI活用が注目されている。本講演では特にAI活用が遅れている標的探索に焦点を当て、疾患関連性が未報告の標的分子選定やドラッグリポジショニング、その仮説生成を可能にするAI技術や解析手法を、創薬の課題やトレンドと共に解説する。
【講演者プロフィール】
理学博士(数学)。2000年よりアメリカ国立環境健康科学研究所(NIEHS)において、データ解析による発がんプロセスの研究などに参加。2006年に武田薬品工業に入社し、バイオインフォマティクス分野の研究員、グローバルデータサイエンス研究所・日本サイトバイオインフォマティクスヘッド、サイエンスフェローを歴任。2017年よりFRONTEOに入社し、ライフサイエンスの領域に特化したAIアルゴリズムを開発。現在までに論文探索、創薬支援、認知症診断支援、転倒予測などのさまざまなAIソリューションをこのアルゴリズムをベースに製品化している。 2019年よりライフサイエンスAI CTO、2024年より取締役に就任。
【講演内容】
創薬においては成功確率の低下や開発費の高騰など様々な課題解決のため、AI活用が注目されている。本講演では特にAI活用が遅れている標的探索に焦点を当て、疾患関連性が未報告の標的分子選定やドラッグリポジショニング、その仮説生成を可能にするAI技術や解析手法を、創薬の課題やトレンドと共に解説する。
【講演者プロフィール】
理学博士(数学)。2000年よりアメリカ国立環境健康科学研究所(NIEHS)において、データ解析による発がんプロセスの研究などに参加。2006年に武田薬品工業に入社し、バイオインフォマティクス分野の研究員、グローバルデータサイエンス研究所・日本サイトバイオインフォマティクスヘッド、サイエンスフェローを歴任。2017年よりFRONTEOに入社し、ライフサイエンスの領域に特化したAIアルゴリズムを開発。現在までに論文探索、創薬支援、認知症診断支援、転倒予測などのさまざまなAIソリューションをこのアルゴリズムをベースに製品化している。 2019年よりライフサイエンスAI CTO、2024年より取締役に就任。
人・AI・ロボットが共創する未来の創薬へ:アステラスのラボ自動化革新

|
アステラス製薬(株) イノベーションラボ アドバンスモデリング&アッセイズ アドバンスモデリング&アッセイズヘッド 岩岡 はるな |

|

【講演内容】
アステラス製薬は、人とAI、ロボットを融合した医薬品創製プラットフォーム「Mahol-A-Ba」を開発し、創薬研究の質とスピードを向上させている。このラボオートメーションは、グローバル拠点やオープンイノベーション、製造に広がっている。本講演では、活用例や課題、今後の展望を紹介する。
【講演者プロフィール】
1994年に山之内製薬(現アステラス製薬)に入社し、疾患関連遺伝子・メカニズム研究、薬理研究、抗体創薬と創薬研究に一貫して従事。2017年、モダリティ研究所アッセイテクノロジー室の室長となり、「Mahol-A-Ba」の開発を開始。2022年よりディスカバリーインテリジェンス、アドバンスモデリング&アッセイ研究室の室長を務め、現在はHead, Advanced Modeling & Assays, Innovation Lab。東京医科歯科大学(現東京科学大学)で非常勤講師、名古屋市立大学で客員教授を務める。博士(農芸化学)。
【講演内容】
アステラス製薬は、人とAI、ロボットを融合した医薬品創製プラットフォーム「Mahol-A-Ba」を開発し、創薬研究の質とスピードを向上させている。このラボオートメーションは、グローバル拠点やオープンイノベーション、製造に広がっている。本講演では、活用例や課題、今後の展望を紹介する。
【講演者プロフィール】
1994年に山之内製薬(現アステラス製薬)に入社し、疾患関連遺伝子・メカニズム研究、薬理研究、抗体創薬と創薬研究に一貫して従事。2017年、モダリティ研究所アッセイテクノロジー室の室長となり、「Mahol-A-Ba」の開発を開始。2022年よりディスカバリーインテリジェンス、アドバンスモデリング&アッセイ研究室の室長を務め、現在はHead, Advanced Modeling & Assays, Innovation Lab。東京医科歯科大学(現東京科学大学)で非常勤講師、名古屋市立大学で客員教授を務める。博士(農芸化学)。
座長:協和キリン(株) 森 聖寿
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
大阪大学免疫学フロンティア研究センター 特任教授 坂口 志文 |
|
【講演内容】
がん抗原の多くは自己抗原(あるいは変異自己抗原)である。従って、自己抗原に対する免疫応答を抑制する制御性T細胞(Treg)は、十分ながん免疫応答の誘導を阻害する。本講演では、Tregを標的とするがん免疫療法の可能性について議論する。
【講演者プロフィール】
1976年京都大学医学部卒業.京大病理,愛知癌センター研究所,京大免疫研究施設を経て1983年医学博士取得。1983年よりJohns Hopkins大学、Stanford大学博士研究員、1989年Scripps研究所Assistant Professor、1992年科学技術振興事業団「さきがけ」研究専任研究員、1995年東京都老人総合研究所免疫病理部門・部門長、1999年より京都大学再生医科学研究所教授、2007年より同研究所長、2011年4月より大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授、2017年より大阪大学栄誉教授。2004年William B. Corey Award、2008年慶応医学賞、2009年紫綬褒章、2012年学士院賞、2015年Canada Gairdner International Award、2017年Crafoord Prize受賞、2019年文化勲章、2020年Paul Elrich and Ludwig Darmstaedter Prize、Robert Koch Award受賞。
【講演内容】
がん抗原の多くは自己抗原(あるいは変異自己抗原)である。従って、自己抗原に対する免疫応答を抑制する制御性T細胞(Treg)は、十分ながん免疫応答の誘導を阻害する。本講演では、Tregを標的とするがん免疫療法の可能性について議論する。
【講演者プロフィール】
1976年京都大学医学部卒業.京大病理,愛知癌センター研究所,京大免疫研究施設を経て1983年医学博士取得。1983年よりJohns Hopkins大学、Stanford大学博士研究員、1989年Scripps研究所Assistant Professor、1992年科学技術振興事業団「さきがけ」研究専任研究員、1995年東京都老人総合研究所免疫病理部門・部門長、1999年より京都大学再生医科学研究所教授、2007年より同研究所長、2011年4月より大阪大学免疫学フロンティア研究センター教授、2017年より大阪大学栄誉教授。2004年William B. Corey Award、2008年慶応医学賞、2009年紫綬褒章、2012年学士院賞、2015年Canada Gairdner International Award、2017年Crafoord Prize受賞、2019年文化勲章、2020年Paul Elrich and Ludwig Darmstaedter Prize、Robert Koch Award受賞。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
アステラス製薬のDX戦略と再生医療の社会実装に向けた取り組み

|
アステラス製薬(株) 代表取締役社長 CEO 岡村 直樹 |

|

【講演内容】
アステラス製薬は「科学の進歩を患者さんの『価値』に変える」をVISIONに掲げ、DX戦略を通じて次世代医療の社会実装を推進している。AIやロボティクスを含む他分野の技術を融合し、革新的な医薬品とヘルスケアソリューションをより迅速に世界の患者さんに届けていく。
【講演者プロフィール】
1986年、山之内製薬株式会社(現・アステラス製薬株式会社)に入社。2010年に買収した米国子会社のCEOに就任。2012年にAstellas Pharma Europe Ltd.に出向し、欧州・中東・アフリカ事業の経営戦略担当Senior Vice Presidentを務める。アステラス製薬帰任後は、事業開発部長、経営企画部長、経営戦略担当役員などの要職を歴任。2019年6月から代表取締役副社長経営戦略担当。2023年4月に代表取締役社長CEOに就任。
【講演内容】
アステラス製薬は「科学の進歩を患者さんの『価値』に変える」をVISIONに掲げ、DX戦略を通じて次世代医療の社会実装を推進している。AIやロボティクスを含む他分野の技術を融合し、革新的な医薬品とヘルスケアソリューションをより迅速に世界の患者さんに届けていく。
【講演者プロフィール】
1986年、山之内製薬株式会社(現・アステラス製薬株式会社)に入社。2010年に買収した米国子会社のCEOに就任。2012年にAstellas Pharma Europe Ltd.に出向し、欧州・中東・アフリカ事業の経営戦略担当Senior Vice Presidentを務める。アステラス製薬帰任後は、事業開発部長、経営企画部長、経営戦略担当役員などの要職を歴任。2019年6月から代表取締役副社長経営戦略担当。2023年4月に代表取締役社長CEOに就任。
ロボティクスによる細胞製造DXへの貢献

|
(株)安川電機 代表取締役社長 小川 昌寛 |

|

【講演内容】
医薬品の開発、製造分野において期待が高まるAIを始めとするデジタル技術活用のためには、サイバー領域とフィジカル領域の接点である「作業」を自動化しシームレスにデータで繋ぐ事が不可欠となる。これまで難しかった熟練作業の自動化を可能にする安川電機の取り組みを紹介する。
【講演者プロフィール】
1987年、安川電機製作所(現安川電機)に入社。入社以降、ロボットのマニピュレータ設計や応用技術など開発技術領域を中心にロボット事業に従事。2010年米国安川株式会社に会長として赴任し、米州における全事業領域を統括。2016年執行役員ロボット事業部長に就任し、2019年取締役執行役員、2020年取締役常務執行役員、2022年代表取締役専務執行役員を経て、2023年3月に代表取締役社長に就任、現在に至る。
【講演内容】
医薬品の開発、製造分野において期待が高まるAIを始めとするデジタル技術活用のためには、サイバー領域とフィジカル領域の接点である「作業」を自動化しシームレスにデータで繋ぐ事が不可欠となる。これまで難しかった熟練作業の自動化を可能にする安川電機の取り組みを紹介する。
【講演者プロフィール】
1987年、安川電機製作所(現安川電機)に入社。入社以降、ロボットのマニピュレータ設計や応用技術など開発技術領域を中心にロボット事業に従事。2010年米国安川株式会社に会長として赴任し、米州における全事業領域を統括。2016年執行役員ロボット事業部長に就任し、2019年取締役執行役員、2020年取締役常務執行役員、2022年代表取締役専務執行役員を経て、2023年3月に代表取締役社長に就任、現在に至る。
座長:アステラス製薬(株) 志鷹 義嗣
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
協和キリン(株) 生産本部 CMC開発部 プロジェクト&プロダクトマネジメント3グループ マネージャー 佐藤 秀尚 |

|

【講演内容】
抗体薬物複合体(ADC)は従来の抗体と異なる治療モダリティーであり、研究、サプライチェーン、製造工程、バイオ・化学分野に新たな挑戦が存在する。協和キリンはオープンイノベーションを活用し、早期パイプライン創出、チームビルディング、外部連携、製造・分析体制の確立を推進している。本講演ではADCの概要、特徴、市場環境及び研究から製造までの総合的取り組みを共有し、さらに協和キリンの現場実例を通じて実践的視点を提供する。
【講演者プロフィール】
・1998年 協和発酵工業株式会社(現 協和キリン株式会社)に入社。研究本部・東京研究所にて抗体パイプラインおよび技術開発に従事
・2000~2004年 東海大学医学部・細胞移植センターおよび血液リウマチ内科、産業技術総合研究所ディッシュエンジニアリング総合センター、大阪大学医学部、慶應義塾大学医学部に派遣
・2010年 探索研究所(富士リサーチパーク)にて低分子パイプライン研究に従事
・2013年 開発研究所(富士リサーチパーク)にて抗体・低分子パイプラインの非臨床試験・研究に従事
・2014年 オープンイノベーション部(本社)にて研究開発戦略の策定およびアライアンス業務に従事。併せてADCチームリーダーを担当
・2017年 疾患サイエンス第2研究所(富士リサーチパーク)にてADCの研究チームリーダーおよびプロジェクトリーダーに従事
・2021年 生産本部CMC開発部(本社)にてADCのCMCチームリーダーおよびCMCリードを担当(現在まで)
【講演内容】
抗体薬物複合体(ADC)は従来の抗体と異なる治療モダリティーであり、研究、サプライチェーン、製造工程、バイオ・化学分野に新たな挑戦が存在する。協和キリンはオープンイノベーションを活用し、早期パイプライン創出、チームビルディング、外部連携、製造・分析体制の確立を推進している。本講演ではADCの概要、特徴、市場環境及び研究から製造までの総合的取り組みを共有し、さらに協和キリンの現場実例を通じて実践的視点を提供する。
【講演者プロフィール】
・1998年 協和発酵工業株式会社(現 協和キリン株式会社)に入社。研究本部・東京研究所にて抗体パイプラインおよび技術開発に従事
・2000~2004年 東海大学医学部・細胞移植センターおよび血液リウマチ内科、産業技術総合研究所ディッシュエンジニアリング総合センター、大阪大学医学部、慶應義塾大学医学部に派遣
・2010年 探索研究所(富士リサーチパーク)にて低分子パイプライン研究に従事
・2013年 開発研究所(富士リサーチパーク)にて抗体・低分子パイプラインの非臨床試験・研究に従事
・2014年 オープンイノベーション部(本社)にて研究開発戦略の策定およびアライアンス業務に従事。併せてADCチームリーダーを担当
・2017年 疾患サイエンス第2研究所(富士リサーチパーク)にてADCの研究チームリーダーおよびプロジェクトリーダーに従事
・2021年 生産本部CMC開発部(本社)にてADCのCMCチームリーダーおよびCMCリードを担当(現在まで)
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
中外製薬(株) バイオロジー基盤研究部 創薬クロステックグループ グループマネジャー 須山 英悟 |

|

【講演内容】
ロボティクスやデジタル技術を活用して実験を自動化するラボオートメーションは、創薬研究を支える基盤技術の一つである。創薬研究者のニーズに応えるべく進化を続けるラボオートメーションの現状と課題、そして今後の展望について、会場の皆様と共に考えたい。
【講演者プロフィール】
2003 年、東京大学大学院工学系研究科後期博士課程修了。ノバルティス ゲノム研究所、バーナム医学研究所(ともに米国)にてファンクショナルゲノミクス、ケミカルゲノミクス研究に取り組む。2014 年に帰国、中外製薬株式会社に入社し、がん薬理研究に従事。2019 年より創薬基盤研究部・グループマネジャーを経て、2023 年より現職。低分子や抗体を中心とするスクリーニング技術開発並びに実験業務全般の自動化・効率化を推進に従事。
【講演内容】
ロボティクスやデジタル技術を活用して実験を自動化するラボオートメーションは、創薬研究を支える基盤技術の一つである。創薬研究者のニーズに応えるべく進化を続けるラボオートメーションの現状と課題、そして今後の展望について、会場の皆様と共に考えたい。
【講演者プロフィール】
2003 年、東京大学大学院工学系研究科後期博士課程修了。ノバルティス ゲノム研究所、バーナム医学研究所(ともに米国)にてファンクショナルゲノミクス、ケミカルゲノミクス研究に取り組む。2014 年に帰国、中外製薬株式会社に入社し、がん薬理研究に従事。2019 年より創薬基盤研究部・グループマネジャーを経て、2023 年より現職。低分子や抗体を中心とするスクリーニング技術開発並びに実験業務全般の自動化・効率化を推進に従事。
核医学治療の現状、課題及び今後の展望

|
(国研)国立がん研究センター 先端医療開発センター 機能診断開発分野 分野長 稲木 杏吏 |
|
【講演内容】
放射性同位元素を標識した放射性薬剤を用いて治療を行う核医学治療は、ラジオリガンド療法(Radioligand therapy: RLT)とも言い、さまざまながんに対して欧米主導で開発が急速に進んでいる。本講演では、RLTの概要と当研究施設における取り組みについて説明し、今後の課題と展望についての私見を述べる。
【講演者プロフィール】
2013年金沢大学大学院医学系研究科修了。金沢大学附属病院核医学診療科に勤務し、2017年から人事交流として厚生労働省医政局地域医療計画課に勤務。人事交流終了後に金沢大学附属病院に再度勤務し、2023年1月から国立がん研究センター先端医療開発センター機能診断開発分野長を務める。
【講演内容】
放射性同位元素を標識した放射性薬剤を用いて治療を行う核医学治療は、ラジオリガンド療法(Radioligand therapy: RLT)とも言い、さまざまながんに対して欧米主導で開発が急速に進んでいる。本講演では、RLTの概要と当研究施設における取り組みについて説明し、今後の課題と展望についての私見を述べる。
【講演者プロフィール】
2013年金沢大学大学院医学系研究科修了。金沢大学附属病院核医学診療科に勤務し、2017年から人事交流として厚生労働省医政局地域医療計画課に勤務。人事交流終了後に金沢大学附属病院に再度勤務し、2023年1月から国立がん研究センター先端医療開発センター機能診断開発分野長を務める。
放射性医薬品領域の動向と今後の開発展望

|
ペプチドリーム(株) 取締役 副社長CFO 金城 聖文 |

|

【講演内容】
ペプチドリームは継続的にビジネスモデルを進化させることで成長を重ねてきた。成長の柱として放射性医薬品に着目した背景は何か。グローバルの業界動向や成功要因。また当社が進める開発パイプライン、今後の展望についてお話ししたい。
【講演者プロフィール】
東京大学大学院工学系研究科博士課程修了(工学博士)。がん領域の研究員として勤務した後、経営戦略ファームのボストン・コンサルティング・グループ(BCG)にて12年間勤務。BCGでは、製薬業界を中心に成長戦略、M&A、製品マーケティング、新規事業立ち上げなど100を超えるプロジェクトをリード。同パートナー&マネージングディレクターを経て、2018年ペプチドリーム取締役就任。2022年、放射性医薬品事業のM&AによりPDRファーマを経営統合。経営戦略+熱い思いで、国内で最も成長する創薬ベンチャーとして新薬創出に取り組む。一つでも二つでも日本発の治療薬を世に届けたい。
【講演内容】
ペプチドリームは継続的にビジネスモデルを進化させることで成長を重ねてきた。成長の柱として放射性医薬品に着目した背景は何か。グローバルの業界動向や成功要因。また当社が進める開発パイプライン、今後の展望についてお話ししたい。
【講演者プロフィール】
東京大学大学院工学系研究科博士課程修了(工学博士)。がん領域の研究員として勤務した後、経営戦略ファームのボストン・コンサルティング・グループ(BCG)にて12年間勤務。BCGでは、製薬業界を中心に成長戦略、M&A、製品マーケティング、新規事業立ち上げなど100を超えるプロジェクトをリード。同パートナー&マネージングディレクターを経て、2018年ペプチドリーム取締役就任。2022年、放射性医薬品事業のM&AによりPDRファーマを経営統合。経営戦略+熱い思いで、国内で最も成長する創薬ベンチャーとして新薬創出に取り組む。一つでも二つでも日本発の治療薬を世に届けたい。
新規フェロトーシス誘導性抗がん剤の開発

|
(株)FerroptoCure 代表取締役 大槻 雄士 |

|

【講演内容】
FerroptoCureは、酸化ストレスによる細胞死(ferroptosis)を標的とした新規抗がん剤の開発に取り組んでいる。本講演では、当社の創薬目的や背景技術について紹介し、FerroptoCureのアプローチが、がん治療の新たな可能性をどのように広げていくのかについて説明する。
【講演者プロフィール】
外科医として診療に取り組む中で新しいがん治療開発の必要性を切実に感じ、がん研究者の道へ。その後、がん領域でのフェロトーシスの研究を経て抗ガン剤シーズを獲得。現在は、株式会社FerroptoCureを設立し、その社会実装を目指す。医師・博士(医学)
【講演内容】
FerroptoCureは、酸化ストレスによる細胞死(ferroptosis)を標的とした新規抗がん剤の開発に取り組んでいる。本講演では、当社の創薬目的や背景技術について紹介し、FerroptoCureのアプローチが、がん治療の新たな可能性をどのように広げていくのかについて説明する。
【講演者プロフィール】
外科医として診療に取り組む中で新しいがん治療開発の必要性を切実に感じ、がん研究者の道へ。その後、がん領域でのフェロトーシスの研究を経て抗ガン剤シーズを獲得。現在は、株式会社FerroptoCureを設立し、その社会実装を目指す。医師・博士(医学)
製薬企業発スタートアップの挑戦:カーブアウトから上場までの軌跡

|
Chordia Therapeutics(株) 共同創業者、最高科学責任者 森下 大輔 |

|

【講演内容】
武田薬品工業からカーブアウトされたChordia Therapeuticsは、RNAスプライシングを標的としたがん治療薬の開発を推進する創薬ベンチャーである。本講演では、その設立の背景、成長戦略、そしてIPO達成に至るまでの歩みを紹介する。
【講演者プロフィール】
学位取得後に武田薬品工業株式会社に入社し、現在まで継続してがんの治療薬の研究開発に従事。この間Harvard大学へ留学し研鑽を積んだ。帰国後AMED産官学連携プログラム研究代表者としてMALT1阻害薬の研究開発を牽引、現在は武田薬品工業株式会社から独立し設立したChordia Therapeutics株式会社においてChief Scientific Officerとして研究開発を推進している。2022年に大学発ベンチャー表彰2022で文部科学大臣賞受賞。熊本大学客員教授、名古屋市立大学客員教授、京都大学特定准教授、国立がん研究センター研究所客員研究員を兼任。
【講演内容】
武田薬品工業からカーブアウトされたChordia Therapeuticsは、RNAスプライシングを標的としたがん治療薬の開発を推進する創薬ベンチャーである。本講演では、その設立の背景、成長戦略、そしてIPO達成に至るまでの歩みを紹介する。
【講演者プロフィール】
学位取得後に武田薬品工業株式会社に入社し、現在まで継続してがんの治療薬の研究開発に従事。この間Harvard大学へ留学し研鑽を積んだ。帰国後AMED産官学連携プログラム研究代表者としてMALT1阻害薬の研究開発を牽引、現在は武田薬品工業株式会社から独立し設立したChordia Therapeutics株式会社においてChief Scientific Officerとして研究開発を推進している。2022年に大学発ベンチャー表彰2022で文部科学大臣賞受賞。熊本大学客員教授、名古屋市立大学客員教授、京都大学特定准教授、国立がん研究センター研究所客員研究員を兼任。

|
タカラバイオ(株) 取締役副社長 峰野 純一 |

|

【講演内容】
当社は新モダリティという言葉が認知される以前から遺伝子治療領域における基盤技術の提供者としてビジネスを展開してきた。本講演では再生医療・遺伝子治療の発展のためのソリューションプロバイダーとして、当社施設や技術を用いた最新の取り組みを紹介する。
【講演者プロフィール】
1984年京都大学農学部食品工学科修了、2007年学位取得(鹿児島大学大学院連合農学研究科)。1984年寶酒造株式会社(現タカラバイオ株式会社)に入社し、医薬品原末の製造管理と培養スケールアップに5年間従事。その後遺伝子工学用研究試薬の開発、大腸菌ゲノム解析プロジェクト参画、遺伝子工学・細胞工学研究用試薬の導入・ライセンスイン・マーケティング、DNAマイクロアレイ・DNAマイクロビーズの開発業務、等を経て、2003年から同社細胞・遺伝子治療センターにて遺伝子治療用ベクター・細胞の研究開発並びにGMP製造・品質管理システムの構築、CDMO事業に従事。2011年同社執行役員、2014年同社取締役、2022年同社副社長執行役員、2023年同社取締役副社長。
【講演内容】
当社は新モダリティという言葉が認知される以前から遺伝子治療領域における基盤技術の提供者としてビジネスを展開してきた。本講演では再生医療・遺伝子治療の発展のためのソリューションプロバイダーとして、当社施設や技術を用いた最新の取り組みを紹介する。
【講演者プロフィール】
1984年京都大学農学部食品工学科修了、2007年学位取得(鹿児島大学大学院連合農学研究科)。1984年寶酒造株式会社(現タカラバイオ株式会社)に入社し、医薬品原末の製造管理と培養スケールアップに5年間従事。その後遺伝子工学用研究試薬の開発、大腸菌ゲノム解析プロジェクト参画、遺伝子工学・細胞工学研究用試薬の導入・ライセンスイン・マーケティング、DNAマイクロアレイ・DNAマイクロビーズの開発業務、等を経て、2003年から同社細胞・遺伝子治療センターにて遺伝子治療用ベクター・細胞の研究開発並びにGMP製造・品質管理システムの構築、CDMO事業に従事。2011年同社執行役員、2014年同社取締役、2022年同社副社長執行役員、2023年同社取締役副社長。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
厚生労働省 医政局 研究開発政策課 再生医療等研究推進室 再生医療等対策専門官 伯井 秀行 |

|

【講演内容】
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生法)は、再生医療等の安全な提供を図ることなどを目的に、平成26年に施行された。また、近年の医療技術および研究開発の発展に対応するため、令和7年5月31日に改正再生法が施行された。本講演では、法改正事項の要点について紹介する。
【講演者プロフィール】
大阪大学医学部卒。循環器内科医として大阪急性期・総合医療センターに勤務。その後、大阪大学大学院博士課程へ進学し、心筋症のゲノム解析および心不全における病態分子の探索研究を行い、拡張型心筋症の新規原因遺伝子を同定する。米国オレゴン健康科学大学へ博士研究員として留学し、アデノ随伴ウイルスベクターのカプシド工学に関する基礎研究に従事した後に、厚生労働省へ入省、現在に至る。
【講演内容】
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生法)は、再生医療等の安全な提供を図ることなどを目的に、平成26年に施行された。また、近年の医療技術および研究開発の発展に対応するため、令和7年5月31日に改正再生法が施行された。本講演では、法改正事項の要点について紹介する。
【講演者プロフィール】
大阪大学医学部卒。循環器内科医として大阪急性期・総合医療センターに勤務。その後、大阪大学大学院博士課程へ進学し、心筋症のゲノム解析および心不全における病態分子の探索研究を行い、拡張型心筋症の新規原因遺伝子を同定する。米国オレゴン健康科学大学へ博士研究員として留学し、アデノ随伴ウイルスベクターのカプシド工学に関する基礎研究に従事した後に、厚生労働省へ入省、現在に至る。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
住友ファーマ(株) 理事 再生医療推進室担当/ (株)RACTHERA 代表取締役社長 池田 篤史 |

|

【講演内容】
iPS細胞を用いた再生医療がいよいよ実現しつつある。今後、再生医療が産業として確立し、広く医療に貢献するためには、様々なステークホルダーがより緊密に連携していく必要がある。本講演では、iPS細胞を用いた再生医療の動向や、我々の取り組みを紹介したい。
【講演者プロフィール】
2001年京都大学大学院 薬学研究科博士後期課程修了、京都大学 博士(薬学)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校博士研究員、大阪大学大学院特任研究員、京都大学大学院助教を経て、2008年大日本住友製薬株式会社(現住友ファーマ株式会社)入社。神経疾患に対する創薬研究、iPS細胞を用いた創薬・再生医療の研究を担当し、現在に至る。
【講演内容】
iPS細胞を用いた再生医療がいよいよ実現しつつある。今後、再生医療が産業として確立し、広く医療に貢献するためには、様々なステークホルダーがより緊密に連携していく必要がある。本講演では、iPS細胞を用いた再生医療の動向や、我々の取り組みを紹介したい。
【講演者プロフィール】
2001年京都大学大学院 薬学研究科博士後期課程修了、京都大学 博士(薬学)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校博士研究員、大阪大学大学院特任研究員、京都大学大学院助教を経て、2008年大日本住友製薬株式会社(現住友ファーマ株式会社)入社。神経疾患に対する創薬研究、iPS細胞を用いた創薬・再生医療の研究を担当し、現在に至る。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
(公財)京都大学iPS細胞研究財団 研究開発センター ユニット長 林 洋平 |
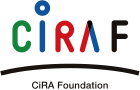
|
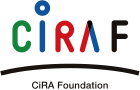
【講演内容】
ヒトiPS細胞を用いた再生医療と創薬が進展する中、私はこれまで一貫してiPS細胞の研究開発と産業化に従事してきた。今回の講演では、前職と現職における研究用と再生医療用のiPS細胞の整備状況と私自身が行ったiPS細胞を用いた病態モデル研究や再生医療に向けた大量培養開発について紹介する。
【講演者プロフィール】
2004年、東京大学教養学部生命・認知科学科卒業。2009年まで東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の浅島誠研究室にて哺乳類多能性幹細胞の研究を行い、博士課程を修了。2009年から2015年まで、Gladstone Institute of Cardiovascular Diseaseの山中伸弥研究室にてPostdoctoral FellowとしてiPS細胞の研究に従事。日本に帰国後は、筑波大学医学医療系助教、理化学研究所バイオリソース研究センター iPS細胞高次特性解析開発チームチームリーダー、筑波大学医学医療系(連携大学院)・グローバル教育院(協働大学院)教授を歴任。2025年から、京都大学iPS細胞研究財団研究開発センターユニット長として、iPS細胞の再生医療の研究開発に携わる。
【講演内容】
ヒトiPS細胞を用いた再生医療と創薬が進展する中、私はこれまで一貫してiPS細胞の研究開発と産業化に従事してきた。今回の講演では、前職と現職における研究用と再生医療用のiPS細胞の整備状況と私自身が行ったiPS細胞を用いた病態モデル研究や再生医療に向けた大量培養開発について紹介する。
【講演者プロフィール】
2004年、東京大学教養学部生命・認知科学科卒業。2009年まで東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻の浅島誠研究室にて哺乳類多能性幹細胞の研究を行い、博士課程を修了。2009年から2015年まで、Gladstone Institute of Cardiovascular Diseaseの山中伸弥研究室にてPostdoctoral FellowとしてiPS細胞の研究に従事。日本に帰国後は、筑波大学医学医療系助教、理化学研究所バイオリソース研究センター iPS細胞高次特性解析開発チームチームリーダー、筑波大学医学医療系(連携大学院)・グローバル教育院(協働大学院)教授を歴任。2025年から、京都大学iPS細胞研究財団研究開発センターユニット長として、iPS細胞の再生医療の研究開発に携わる。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
ヒトiPS細胞由来膵島細胞を用いた糖尿病治療に向けて

|
京都大学iPS細胞研究所 講師 豊田 太郎 |

|

【講演内容】
糖尿病は膵島組織中のβ細胞が分泌するインスリンの作用不足で発症する。膵β細胞の機能不全や欠乏に対しては細胞補充が有効であるが、ドナー不足が課題の一つである。我々は産学連携活動で、臨床応用に向けた大量生産可能な膵島細胞(iPIC)製造系を構築した。本発表では系構築への取り組みを中心に紹介する。
【講演者プロフィール】
2006年3月に京都大学大学院で学位取得(農学)。その後、米国ジョスリン糖尿病センターで、骨格筋糖代謝に関する研究に従事。2010年、京都大学iPS細胞研究所で特定拠点助教として、iPS細胞技術を用いた細胞治療および幹細胞に関する研究を開始。2015年同講師、現在に至る。
【講演内容】
糖尿病は膵島組織中のβ細胞が分泌するインスリンの作用不足で発症する。膵β細胞の機能不全や欠乏に対しては細胞補充が有効であるが、ドナー不足が課題の一つである。我々は産学連携活動で、臨床応用に向けた大量生産可能な膵島細胞(iPIC)製造系を構築した。本発表では系構築への取り組みを中心に紹介する。
【講演者プロフィール】
2006年3月に京都大学大学院で学位取得(農学)。その後、米国ジョスリン糖尿病センターで、骨格筋糖代謝に関する研究に従事。2010年、京都大学iPS細胞研究所で特定拠点助教として、iPS細胞技術を用いた細胞治療および幹細胞に関する研究を開始。2015年同講師、現在に至る。
iPS細胞由来膵島細胞の社会実装に向けて

|
オリヅルセラピューティクス(株) 代表取締役社長兼CEO 野中 健史 |

|

【講演内容】
当社はiPS細胞由来分化細胞による細胞治療事業及び分化培養技術を基盤とする研究支援事業を展開している。パイプラインの一つであるiPS由来膵島細胞シートは、京都大学において安全性確認のための治験開始が決定した。本講演ではiPS細胞技術の社会実装を目指す取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
1990年杏林大学医学部卒、医師免許取得。20年近く製薬企業で研究開発に携わり、直近ではヤンセンファーマ株式会社の取締役兼研究開発本部長に従事。製薬業界で担当した疾患領域は、悪性腫瘍(血液、前立腺癌)、自己免疫疾患、精神神経疾患(統合失調症、アルツハイマー病)、感染症(C型肝炎、HIV/RSV感染、結核)、循環器疾患、糖尿病等多岐にわたる。製薬以前は心臓血管外科医として12年臨床現場で勤務し、うち2年に及ぶアメリカでの人工心臓研究を含む。業界活動として2017年からPhRMA S&R leadership Forumの議長も務めた。2021年4月より現職。
【講演内容】
当社はiPS細胞由来分化細胞による細胞治療事業及び分化培養技術を基盤とする研究支援事業を展開している。パイプラインの一つであるiPS由来膵島細胞シートは、京都大学において安全性確認のための治験開始が決定した。本講演ではiPS細胞技術の社会実装を目指す取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
1990年杏林大学医学部卒、医師免許取得。20年近く製薬企業で研究開発に携わり、直近ではヤンセンファーマ株式会社の取締役兼研究開発本部長に従事。製薬業界で担当した疾患領域は、悪性腫瘍(血液、前立腺癌)、自己免疫疾患、精神神経疾患(統合失調症、アルツハイマー病)、感染症(C型肝炎、HIV/RSV感染、結核)、循環器疾患、糖尿病等多岐にわたる。製薬以前は心臓血管外科医として12年臨床現場で勤務し、うち2年に及ぶアメリカでの人工心臓研究を含む。業界活動として2017年からPhRMA S&R leadership Forumの議長も務めた。2021年4月より現職。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
慶應義塾大学 医学部 医学研究科 石井・石橋記念講座(拡張知能医学) 教授/ (国研)理化学研究所 生命医科学研究センター 予測医学特別プロジェクト プロジェクトディレクター 桜田 一洋 |
|
【講演内容】
医学へのAIの応用と並行して、患者デジタルツインに向けた技術開発が進展している。患者デジタルツインは汎用疾患モデルによって駆動される。汎用疾患モデルを利用した治療コンセプトの精緻化は、再生医療の有効性や安全性を高めることができる。このような観点から、現在の研究開発の概要を紹介する。
【講演者プロフィール】
1988年大阪大学大学院理学研究科修士課程修了。協和発酵(株)東京研究所研究員、京都大学医学部(中西重忠教授)研究生を務め、1993年理学博士(大阪大学)を授与。Salk研究所(Fred Gage教授)客員研究員、協和発酵(株)東京研究所の再生医療担当主任研究員を経て、ドイツSchering社により神戸に新設されたリサーチセンターのセンター長に着任。Bayer Schering Pharmaドイツ本社の日本研究部門統括、再生医療本部長、グローバル研究幹部会メンバーならびにバイエル薬品の執行役員リサーチセンター長を務めた後、米国でiZumi Bio社を立ち上げ、最高科学責任者としてバイエル薬品で開発したヒト細胞初期化技術を移管。2008年ソニーコンピューターサイエンス研究所上席研究員、2016年からは理化学研究所 医科学イノベーションハブ推進プログラム 副プログラムディレクターとして健康医療領域の予測の科学を開拓。2021年4月より理化学研究所 先端データサイエンス プロジェクトのプロジェクトリーダー。同年10月より現職。2023年10月から大阪大学WPI疾患メタバース研究拠点(PRIMe)特任教授。2025年4月より理化学研究所生命医科学研究センター予測医学特別プロジェクトのプロジェクトディレクター。著書に『亜種の起源 苦しみは波のように』幻冬舎 (2020年)
【講演内容】
医学へのAIの応用と並行して、患者デジタルツインに向けた技術開発が進展している。患者デジタルツインは汎用疾患モデルによって駆動される。汎用疾患モデルを利用した治療コンセプトの精緻化は、再生医療の有効性や安全性を高めることができる。このような観点から、現在の研究開発の概要を紹介する。
【講演者プロフィール】
1988年大阪大学大学院理学研究科修士課程修了。協和発酵(株)東京研究所研究員、京都大学医学部(中西重忠教授)研究生を務め、1993年理学博士(大阪大学)を授与。Salk研究所(Fred Gage教授)客員研究員、協和発酵(株)東京研究所の再生医療担当主任研究員を経て、ドイツSchering社により神戸に新設されたリサーチセンターのセンター長に着任。Bayer Schering Pharmaドイツ本社の日本研究部門統括、再生医療本部長、グローバル研究幹部会メンバーならびにバイエル薬品の執行役員リサーチセンター長を務めた後、米国でiZumi Bio社を立ち上げ、最高科学責任者としてバイエル薬品で開発したヒト細胞初期化技術を移管。2008年ソニーコンピューターサイエンス研究所上席研究員、2016年からは理化学研究所 医科学イノベーションハブ推進プログラム 副プログラムディレクターとして健康医療領域の予測の科学を開拓。2021年4月より理化学研究所 先端データサイエンス プロジェクトのプロジェクトリーダー。同年10月より現職。2023年10月から大阪大学WPI疾患メタバース研究拠点(PRIMe)特任教授。2025年4月より理化学研究所生命医科学研究センター予測医学特別プロジェクトのプロジェクトディレクター。著書に『亜種の起源 苦しみは波のように』幻冬舎 (2020年)
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
再生・細胞医療・遺伝子治療の社会実装に向けた産業化の取組み

|
経済産業省 生物化学産業課 総括課長補佐 小松 慶太 |
|
【講演内容】
再生・細胞医療、遺伝子治療については、今後、国内外での市場拡大が期待されている分野である。
経済産業省では、再生・細胞医療・遺伝子治療製品を円滑に製造できる能力を国内に確保するため、CDMO(受託開発・製造事業者)の国内受託製造拠点の整備や製造人材育成に対しての支援を行う事業を令和6年度の補正予算で措置し、取り組みを実施しているところ。
本講演では、経済産業省が進めている、再生医療・細胞医療・遺伝子治療の産業化促進に向けた取り組みや今後の方向性について説明する。
【講演者プロフィール】
2012年3月、東京大学理学部 生物情報科学科 卒業(BS)、2014年3月 東京大学大学院 情報生命科学専攻 修了(MSc)。
2014年4月に経済産業省入省。貿易管理部 安全保障貿易管理課 総括係長、貿易管理部 特殊関税等調査室 総括係長、貿易管理部 貿易管理課 課長補佐等を歴任。
2019年5月に内閣官房 健康・医療戦略室に出向、主査を勤める。
2022年8月に米国留学し、ハーバード大学公衆衛生大学院 修了、MPH(医療経済学)を取得。
2024年7月より現職。
【講演内容】
再生・細胞医療、遺伝子治療については、今後、国内外での市場拡大が期待されている分野である。
経済産業省では、再生・細胞医療・遺伝子治療製品を円滑に製造できる能力を国内に確保するため、CDMO(受託開発・製造事業者)の国内受託製造拠点の整備や製造人材育成に対しての支援を行う事業を令和6年度の補正予算で措置し、取り組みを実施しているところ。
本講演では、経済産業省が進めている、再生医療・細胞医療・遺伝子治療の産業化促進に向けた取り組みや今後の方向性について説明する。
【講演者プロフィール】
2012年3月、東京大学理学部 生物情報科学科 卒業(BS)、2014年3月 東京大学大学院 情報生命科学専攻 修了(MSc)。
2014年4月に経済産業省入省。貿易管理部 安全保障貿易管理課 総括係長、貿易管理部 特殊関税等調査室 総括係長、貿易管理部 貿易管理課 課長補佐等を歴任。
2019年5月に内閣官房 健康・医療戦略室に出向、主査を勤める。
2022年8月に米国留学し、ハーバード大学公衆衛生大学院 修了、MPH(医療経済学)を取得。
2024年7月より現職。
再生医療等製品開発におけるCDMOの重要性

|
(株)ジャパン・ティッシュエンジニアリング 相談役 畠 賢一郎 |

|

【講演内容】
演者らはこれまで5品目の再生医療等製品を上市してきた。生きた細胞を用いた再生医療等製品は、上市後はもとより、開発段階においても医薬品等と異なった対応が必要となる。本講演では、再生医療等製品開発や製造支援を担うCDMOの役割と意義について述べたい。
【講演者プロフィール】
1991年 広島大学歯学部卒業、1995年 名古屋大学大学院医学研究科博士課程修了。2002年名古屋大学医学部附属病院 遺伝子再生医療センター助教授として再生医療の基礎から応用研究のあり方を模索した。口腔外科医としては、顎変形症、口蓋裂の集学的治療を専門とし、多くの外科矯正手術を手がけた。2004年 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリングに入社。自家培養表皮ならびに自家培養軟骨等を上市するとともに、再生医療産業化に寄与する技術開発を行った。2017年より現職。現在、再生医療イノベーションフォーラム代表理事、日本再生医療学会理事等の活動を通じて、再生医療領域における産学官連携を積極的に推進する役割を担っている。
【講演内容】
演者らはこれまで5品目の再生医療等製品を上市してきた。生きた細胞を用いた再生医療等製品は、上市後はもとより、開発段階においても医薬品等と異なった対応が必要となる。本講演では、再生医療等製品開発や製造支援を担うCDMOの役割と意義について述べたい。
【講演者プロフィール】
1991年 広島大学歯学部卒業、1995年 名古屋大学大学院医学研究科博士課程修了。2002年名古屋大学医学部附属病院 遺伝子再生医療センター助教授として再生医療の基礎から応用研究のあり方を模索した。口腔外科医としては、顎変形症、口蓋裂の集学的治療を専門とし、多くの外科矯正手術を手がけた。2004年 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリングに入社。自家培養表皮ならびに自家培養軟骨等を上市するとともに、再生医療産業化に寄与する技術開発を行った。2017年より現職。現在、再生医療イノベーションフォーラム代表理事、日本再生医療学会理事等の活動を通じて、再生医療領域における産学官連携を積極的に推進する役割を担っている。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
セルリソーシズ(株) 代表取締役社長 有田 孝太郎 |

|

【講演内容】
アルフレッサグループとMinarisは、再生医療等製品の開発・製造・流通体制の強化を目的として、国内における協業を開始した。これにより、細胞治療製品に関する包括的な一気通貫サービスの提供が可能となった。本セミナーでは、本協業におけるアルフレッサグループおよびMinarisそれぞれの役割と、両社が有する技術的・運用的な強みを活かした顧客向けサービスの詳細を紹介する。
【講演者プロフィール】
2012年3月私大薬学部卒業。四国アルフレッサ株式会社に入社。2019年アルフレッサホールディングス株式会社出向。事業開発部に所属し、再生医療ベンチャー投資や新規事業開発に従事。2022年11月よりセルリソーシズ株式会社代表取締役に就任、現在に至る。
【講演内容】
アルフレッサグループとMinarisは、再生医療等製品の開発・製造・流通体制の強化を目的として、国内における協業を開始した。これにより、細胞治療製品に関する包括的な一気通貫サービスの提供が可能となった。本セミナーでは、本協業におけるアルフレッサグループおよびMinarisそれぞれの役割と、両社が有する技術的・運用的な強みを活かした顧客向けサービスの詳細を紹介する。
【講演者プロフィール】
2012年3月私大薬学部卒業。四国アルフレッサ株式会社に入社。2019年アルフレッサホールディングス株式会社出向。事業開発部に所属し、再生医療ベンチャー投資や新規事業開発に従事。2022年11月よりセルリソーシズ株式会社代表取締役に就任、現在に至る。

|
ミナリスアドバンストセラピーズ(株) 代表取締役社長 坂東 博人 |

|

【講演者プロフィール】
武田薬品工業株式会社の再生医療ユニット シニアディレクター、富士フイルム株式会社の医薬品事業部 シニアマネージャー、株式会社レゾナックの再生医療事業部 事業部長、Minaris Regenerative Medicineの日米欧3拠点のCEOを経て、2025年より日本拠点の代表取締役社長に就任し、現在に至る。
【講演者プロフィール】
武田薬品工業株式会社の再生医療ユニット シニアディレクター、富士フイルム株式会社の医薬品事業部 シニアマネージャー、株式会社レゾナックの再生医療事業部 事業部長、Minaris Regenerative Medicineの日米欧3拠点のCEOを経て、2025年より日本拠点の代表取締役社長に就任し、現在に至る。
坂東様におかれましては、会社名が変更になりました。(2025/6/3)
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
臨床試験における医療データ利活用の期待 ~ドラッグロス解消の一助として

|
メディカル・データ・ビジョン株式会社 EBM 本部 臨床試験事業部 ゼネラルマネージャー 小川 武則 |
|
【講演内容】
国内におけるドラッグロス/ラグの問題は周知のとおりであり、新しい薬/治療法が国内の患者へ届かない事態は絶対に避けなければならない。PMDAが主導する治験エコシステム推進事業で取り扱う課題として、治験の効率化・開始までの時間短縮に大きく寄与する課題、海外と比較し、国内治験の症例集積性の向上に大きく寄与する課題が挙げられており、ALL JAPAN での取り組みが急務となっている。本講演では、上記課題に対して医療データ利活用の可能性を探求し、具体的なデータ事例なども交えて、現状と期待をご紹介させて頂きます。
【講演内容】
国内におけるドラッグロス/ラグの問題は周知のとおりであり、新しい薬/治療法が国内の患者へ届かない事態は絶対に避けなければならない。PMDAが主導する治験エコシステム推進事業で取り扱う課題として、治験の効率化・開始までの時間短縮に大きく寄与する課題、海外と比較し、国内治験の症例集積性の向上に大きく寄与する課題が挙げられており、ALL JAPAN での取り組みが急務となっている。本講演では、上記課題に対して医療データ利活用の可能性を探求し、具体的なデータ事例なども交えて、現状と期待をご紹介させて頂きます。
AIで描くメディカルライティングの未来:資材審査の効率化と新たな可能性

|
株式会社 博報堂メディカル 薮 紘明 |
|
【講演内容】
独自に開発したメディカルライティング支援AIの概要を、製品デモを交えてご紹介します。このAIはブルーブックの全ルールとメディカルライターの暗黙知を学習し、医薬品プロモーション資料を自動でチェックします。これにより、メディカルチェック作業を効率化し、審査の迅速化とプロモーション資料の質の向上を実現します。本AIは特許申請済みで、人工知能学会に論文が採択されています。ぜひ、ご聴講ください。
【講演内容】
独自に開発したメディカルライティング支援AIの概要を、製品デモを交えてご紹介します。このAIはブルーブックの全ルールとメディカルライターの暗黙知を学習し、医薬品プロモーション資料を自動でチェックします。これにより、メディカルチェック作業を効率化し、審査の迅速化とプロモーション資料の質の向上を実現します。本AIは特許申請済みで、人工知能学会に論文が採択されています。ぜひ、ご聴講ください。
医療者の新薬コミュニケーションを支える!コミュニケーションDX

|
株式会社OPERe 代表取締役 /CEO 澤田 優香 |

|

【講演内容】
専門性が上がり続ける医療情報、多忙を極める医療現場。患者説明をDXするシステム「ポケさぽ」を活用し、製薬企業・医療機関・システムベンダーの三者が協働しコミュニケーションをDXした事例をご紹介します。
【講演内容】
専門性が上がり続ける医療情報、多忙を極める医療現場。患者説明をDXするシステム「ポケさぽ」を活用し、製薬企業・医療機関・システムベンダーの三者が協働しコミュニケーションをDXした事例をご紹介します。
"DXの壁"を突破するブレインパッドの内製化支援サービス

|
株式会社 ブレインパッド 執行役員 エンタープライズユニット 統括ディレクター 鵜飼 武志 |

|

【講演内容】
この数年間で多くの企業がDXに取り組み、小さな成果を出しつつあります。
一方で、持続的で大きな経営効果に繋げるには”DXの壁”が立ちはだかります。
ブレインパッドは200名を超えるデータサイエンティストを有し、データ分析・人材育成のノウハウを蓄積してきました。
当社のノウハウを軸に、DXに取り組む多くの企業の前に立ちはだかる壁の正体と、”DXの壁”を乗り越えた事例・成功の要諦をご紹介します。
また、セミナー後半ではペイシェントセントリシティが重視される中、ブレインパッドならではの手法で患者インサイトの収集・分析を行う新規サービスもご紹介します。
【講演者プロフィール】
外資系コンサルティングファームでキャリアをスタートし、2023年よりブレインパッドに参画。
データ/生成AI活用の構想策定・プランニングから、経営効果創出に至るまでの業務適用のユースケース作り、分析/データ活用組織の設計立ち上げを主に支援。
【講演内容】
この数年間で多くの企業がDXに取り組み、小さな成果を出しつつあります。
一方で、持続的で大きな経営効果に繋げるには”DXの壁”が立ちはだかります。
ブレインパッドは200名を超えるデータサイエンティストを有し、データ分析・人材育成のノウハウを蓄積してきました。
当社のノウハウを軸に、DXに取り組む多くの企業の前に立ちはだかる壁の正体と、”DXの壁”を乗り越えた事例・成功の要諦をご紹介します。
また、セミナー後半ではペイシェントセントリシティが重視される中、ブレインパッドならではの手法で患者インサイトの収集・分析を行う新規サービスもご紹介します。
【講演者プロフィール】
外資系コンサルティングファームでキャリアをスタートし、2023年よりブレインパッドに参画。
データ/生成AI活用の構想策定・プランニングから、経営効果創出に至るまでの業務適用のユースケース作り、分析/データ活用組織の設計立ち上げを主に支援。

|
株式会社 ブレインパッド セールス&マーケティングユニット マネージャー 小嶋 純平 |

|

【講演者プロフィール】
医療IT企業で製薬業界向けのマーケティング・営業支援に従事した後、2024年よりブレインパッドに参画。
現在はヘルスケア業界を中心にBtoB企業のデータ/AI活用支援に従事。
【講演者プロフィール】
医療IT企業で製薬業界向けのマーケティング・営業支援に従事した後、2024年よりブレインパッドに参画。
現在はヘルスケア業界を中心にBtoB企業のデータ/AI活用支援に従事。

|
株式会社 ブレインパッド アナリティクスコンサルティングユニット シニアコンサルタント 小暮 純子 |

|

【講演者プロフィール】
ブレインパッドにてキャリアをスタート。
データ分析組織立ち上げや内製化、データ活用構想策定・プランニングを主に支援。
【講演者プロフィール】
ブレインパッドにてキャリアをスタート。
データ分析組織立ち上げや内製化、データ活用構想策定・プランニングを主に支援。
製薬企業向け販促コンテンツ管理システム「PromoGate」のご紹介 〜マニュアルレス、高速・省力化、そしてAI活用による次世代コンテンツ管理へ〜

|
株式会社イットアップ XS部 セールスリーダー 前田 真吾 |

|

【講演内容】
製薬企業における販促コンテンツ管理には、常に法令遵守と業務効率化の両立が求められています。
本日は、この課題を解決するために開発された、申請・承認プロセスを高速かつ省力化する販促コンテンツ管理システム「PromoGate」をご紹介します。
直感的に使えるマニュアルレスのUI設計、無駄を省いた機能特化型サービス設計に加え、
今後実装を予定しているAIによるフィードバック機能やドキュメント提案機能のロードマップについても解説いたします。
「使いやすさ」「審査効率の向上」「コスト削減」を実現し、
さらにAIによるコンテンツ運用支援まで視野に入れた、次世代型資材管理の姿をお届けします。
【講演内容】
製薬企業における販促コンテンツ管理には、常に法令遵守と業務効率化の両立が求められています。
本日は、この課題を解決するために開発された、申請・承認プロセスを高速かつ省力化する販促コンテンツ管理システム「PromoGate」をご紹介します。
直感的に使えるマニュアルレスのUI設計、無駄を省いた機能特化型サービス設計に加え、
今後実装を予定しているAIによるフィードバック機能やドキュメント提案機能のロードマップについても解説いたします。
「使いやすさ」「審査効率の向上」「コスト削減」を実現し、
さらにAIによるコンテンツ運用支援まで視野に入れた、次世代型資材管理の姿をお届けします。
リアルワールドデータ×AI入力支援で変わる、未来の臨床研究

|
TXP Medical株式会社 医療データ事業部 マネージャー 山本 浩寿 |

|

【講演内容】
臨床研究の現場では、電子カルテ等のデータを転記する業務は医療従事者の大きな負担となっていました。弊社は、電子カルテデータの正規化、QRコードによるデータ連携、OCR機能の活用によりこれらの課題を解決してまいりました。さらに最近では、生成AIを用いた医療データの構造化技術の実用化を実現しており、これらのAI入力支援技術は臨床研究や治験のあり方を大きく変える可能性があります。臨床研究DXの最前線について、実際の導入事例を交えてご紹介いたします。
【講演内容】
臨床研究の現場では、電子カルテ等のデータを転記する業務は医療従事者の大きな負担となっていました。弊社は、電子カルテデータの正規化、QRコードによるデータ連携、OCR機能の活用によりこれらの課題を解決してまいりました。さらに最近では、生成AIを用いた医療データの構造化技術の実用化を実現しており、これらのAI入力支援技術は臨床研究や治験のあり方を大きく変える可能性があります。臨床研究DXの最前線について、実際の導入事例を交えてご紹介いたします。
臨床現場につながる医療データ利活用

|
株式会社Yuimedi 取締役・CFO/医療機関事業開発責任者 村岡 和彦 |

|

【講演内容】
リアルワールドデータ(RWD)が注目される中、Yuimediは異なるデータベース間のギャップを標準化によって解消し、利活用を簡素化する仕組みを構築しています。一方で、医療機関が保有する臨床データを直接活用し、データドリブンで患者動向を把握し、製薬企業のマーケティング施策の一助となるサービスを展開しています。
【講演内容】
リアルワールドデータ(RWD)が注目される中、Yuimediは異なるデータベース間のギャップを標準化によって解消し、利活用を簡素化する仕組みを構築しています。一方で、医療機関が保有する臨床データを直接活用し、データドリブンで患者動向を把握し、製薬企業のマーケティング施策の一助となるサービスを展開しています。
AIで描くメディカルライティングの未来:資材審査の効率化と新たな可能性

|
株式会社 博報堂メディカル 後藤 誠 |
|
【講演内容】
独自に開発したメディカルライティング支援AIの概要を、製品デモを交えてご紹介します。このAIはブルーブックの全ルールとメディカルライターの暗黙知を学習し、医薬品プロモーション資料を自動でチェックします。これにより、メディカルチェック作業を効率化し、審査の迅速化とプロモーション資料の質の向上を実現します。本AIは特許申請済みで、人工知能学会に論文が採択されています。ぜひ、ご聴講ください。
【講演内容】
独自に開発したメディカルライティング支援AIの概要を、製品デモを交えてご紹介します。このAIはブルーブックの全ルールとメディカルライターの暗黙知を学習し、医薬品プロモーション資料を自動でチェックします。これにより、メディカルチェック作業を効率化し、審査の迅速化とプロモーション資料の質の向上を実現します。本AIは特許申請済みで、人工知能学会に論文が採択されています。ぜひ、ご聴講ください。
DtoDマーケティングにおける新たな解としての”Medii Eコンサル”

|
株式会社 Medii 取締役 執行役員COO 筒井 亮介 |

|

【講演内容】
製薬企業における医師向けのマーケティング活動がオムニチャネル化する中で、Web講演会をはじめとしたDoctor to Doctor(DtoD)のチャネルは不可欠なアクティビティとなってきています。一方で、Web講演会の乱立や、医師の働き方改革等の影響で、DtoDアクティビティのあり方に変化が求められる潮目のタイミングでもあります。
Mediiは、主治医が専門医に相談出来るプラットフォーム「Medii Eコンサル」を通じて、主治医がこれまで診断出来ていなかった/最適な治療が導入出来ていなかった症例に対して、適切な解を提供し主治医が「行動変容」するためのサポートを行っています。このプラットフォームの活用によって、希少疾患のように診断が付きづらい疾患領域のみならず、重症喘息のように新たな治療法が出てきているものの主治医が適切に新薬を使いこなせていない領域も含めて、幅広い疾患領域で多数の製薬企業様をサポートしています。
当日の講演の中では、製薬企業のマーケティング活動を俯瞰した上で、Eコンサルの概要や他チャネルとのベストミックス、製薬企業様とのプロジェクトにおけるベストプラクティス等を解説します。
【講演者プロフィール】
慶應義塾大学法学部法律学科を卒業後、アクセンチュアの戦略コンサルティンググループに入社。
以後、約10年間に亘り、新規事業立案・実行支援を中心に、中期経営計画策定支援やR&D戦略立案、パートナリング戦略立案等の幅広いプロジェクト・テーマに従事。
2020年11月のMedii参画後は、ビジネスサイドの責任者として、製薬企業向け事業や外部企業とのアライアンス、新規事業の立ち上げ、
Eコンサルプラットフォームのグロース等に幅広くコミット。
【講演内容】
製薬企業における医師向けのマーケティング活動がオムニチャネル化する中で、Web講演会をはじめとしたDoctor to Doctor(DtoD)のチャネルは不可欠なアクティビティとなってきています。一方で、Web講演会の乱立や、医師の働き方改革等の影響で、DtoDアクティビティのあり方に変化が求められる潮目のタイミングでもあります。
Mediiは、主治医が専門医に相談出来るプラットフォーム「Medii Eコンサル」を通じて、主治医がこれまで診断出来ていなかった/最適な治療が導入出来ていなかった症例に対して、適切な解を提供し主治医が「行動変容」するためのサポートを行っています。このプラットフォームの活用によって、希少疾患のように診断が付きづらい疾患領域のみならず、重症喘息のように新たな治療法が出てきているものの主治医が適切に新薬を使いこなせていない領域も含めて、幅広い疾患領域で多数の製薬企業様をサポートしています。
当日の講演の中では、製薬企業のマーケティング活動を俯瞰した上で、Eコンサルの概要や他チャネルとのベストミックス、製薬企業様とのプロジェクトにおけるベストプラクティス等を解説します。
【講演者プロフィール】
慶應義塾大学法学部法律学科を卒業後、アクセンチュアの戦略コンサルティンググループに入社。
以後、約10年間に亘り、新規事業立案・実行支援を中心に、中期経営計画策定支援やR&D戦略立案、パートナリング戦略立案等の幅広いプロジェクト・テーマに従事。
2020年11月のMedii参画後は、ビジネスサイドの責任者として、製薬企業向け事業や外部企業とのアライアンス、新規事業の立ち上げ、
Eコンサルプラットフォームのグロース等に幅広くコミット。
データから読み解く、オムニチャネル戦略を成功に導く営業組織の人的資本

|
リープ 株式会社 荒木 恵 |

|

【講演内容】
医薬品業界のセールス&マーケティングは、今まさに転換期を迎えています。
本セミナーでは、
「オムニチャネル戦略を最大化させる営業組織の人的資本」をテーマに、
営業現場のスキルやパフォーマンスデータを、いかに""活きたリソース""として活用するかを深掘りします。
リアルとデジタルの境界が曖昧になり、顧客接点は「オムニチャネル」へと進化。
従来の常識や成功パターンが通用しなくなる中で、デジタルを含む戦略の立案と実行こそが、成果を左右する時代へと突入しました。
戦略は描くだけでは意味がありません。
それを実行に移すためには、「人」の力が不可欠です。
MRがデータをどう読み取り、複数チャネルとどのように連動して動いているのか。
また、マネジメントはどのタイミングで介入すべきか――
こうした要素が、企業の戦略遂行力を大きく左右しています。
セミナーでは、
戦略の理解から実行のプロセスにおける理解度・スキル・パフォーマンスの可視化に関する実践的な手法とデータをもとに、
戦略の成果を最大化する「人的資本マネジメント」について迫ります。
営業組織を未来に向けてどう設計していくか。
皆さまとともに考える機会となれば幸いです。
【講演者プロフィール】
ヘルスケア関連企業などを経て人材開発コンサルティング企業に従事。営業、MR、フィールドトレーナー、事業開発などを経験。熊本大学大学院教授システム学でインストラクショナルデザインを学び、教育評価を研究。修士(教授システム学)、RCiS連携研究員、認定アクションラーニングコーチ、日本評価学会認定評価士。
【講演内容】
医薬品業界のセールス&マーケティングは、今まさに転換期を迎えています。
本セミナーでは、
「オムニチャネル戦略を最大化させる営業組織の人的資本」をテーマに、
営業現場のスキルやパフォーマンスデータを、いかに""活きたリソース""として活用するかを深掘りします。
リアルとデジタルの境界が曖昧になり、顧客接点は「オムニチャネル」へと進化。
従来の常識や成功パターンが通用しなくなる中で、デジタルを含む戦略の立案と実行こそが、成果を左右する時代へと突入しました。
戦略は描くだけでは意味がありません。
それを実行に移すためには、「人」の力が不可欠です。
MRがデータをどう読み取り、複数チャネルとどのように連動して動いているのか。
また、マネジメントはどのタイミングで介入すべきか――
こうした要素が、企業の戦略遂行力を大きく左右しています。
セミナーでは、
戦略の理解から実行のプロセスにおける理解度・スキル・パフォーマンスの可視化に関する実践的な手法とデータをもとに、
戦略の成果を最大化する「人的資本マネジメント」について迫ります。
営業組織を未来に向けてどう設計していくか。
皆さまとともに考える機会となれば幸いです。
【講演者プロフィール】
ヘルスケア関連企業などを経て人材開発コンサルティング企業に従事。営業、MR、フィールドトレーナー、事業開発などを経験。熊本大学大学院教授システム学でインストラクショナルデザインを学び、教育評価を研究。修士(教授システム学)、RCiS連携研究員、認定アクションラーニングコーチ、日本評価学会認定評価士。
ヘルステック業界における疾患啓発の役割と「いしゃまち病院検索」事例紹介

|
株式会社 メディウィル 代表取締役 城間 波留人 |

|

【講演内容】
最新のヘルステック動向を踏まえた上で、患者中心時代における疾患啓発の役割と事例を紹介します。旭化成ファーマ社の骨粗鬆症の疾患啓発プロジェクト「骨検」、協和キリン社のFGF23関連の低リン血症性くる病・骨軟化症の疾患啓発プロジェクト「くるこつ広場」、株式会社ヴァンティブ社の疾患啓発プロジェクト「透析病院ドットコム」をはじめ、ペイシェントジャーニーに添った「いしゃまち病院検索サービス」を活用した豊富な経験から学んだ疾患啓発の役割を解説していきます。
【講演内容】
最新のヘルステック動向を踏まえた上で、患者中心時代における疾患啓発の役割と事例を紹介します。旭化成ファーマ社の骨粗鬆症の疾患啓発プロジェクト「骨検」、協和キリン社のFGF23関連の低リン血症性くる病・骨軟化症の疾患啓発プロジェクト「くるこつ広場」、株式会社ヴァンティブ社の疾患啓発プロジェクト「透析病院ドットコム」をはじめ、ペイシェントジャーニーに添った「いしゃまち病院検索サービス」を活用した豊富な経験から学んだ疾患啓発の役割を解説していきます。
電子契約をもっと活かすには?製薬業界におけるDocYou活用のススメ!

|
日鉄日立システムソリューションズ 株式会社 営業統括本部 諏訪 貴俊 |
|
【講演内容】
・DX推進、業務効率化を図り、電子契約や書類配信サービスを導入したが、
契約書や請求書の配信等の特定業務でのみ利用しているため、
もっと他の業務利用シーン等で有効活用できないものかと検討している。
・電子契約と書類配信等、複数のサービスを契約しており、
ランニングコストも積み重なり、サービスの統合化をしたい。
以上のような課題をお持ちの皆様へ、企業間取引プラットフォーム「DocYou(ドックユー)」のご紹介を交えた
電子取引、書類配信サービスの活用についてご紹介いたします。
【講演内容】
・DX推進、業務効率化を図り、電子契約や書類配信サービスを導入したが、
契約書や請求書の配信等の特定業務でのみ利用しているため、
もっと他の業務利用シーン等で有効活用できないものかと検討している。
・電子契約と書類配信等、複数のサービスを契約しており、
ランニングコストも積み重なり、サービスの統合化をしたい。
以上のような課題をお持ちの皆様へ、企業間取引プラットフォーム「DocYou(ドックユー)」のご紹介を交えた
電子取引、書類配信サービスの活用についてご紹介いたします。
製薬業界の“情報ロス”はこうして防ぐ〜他部門間の連携と監査対応を迅速化する契約情報基盤の重要性

|
株式会社Hubble 執行役員 COO 町田 健太 |
|
【講演内容】
製薬企業やメーカー企業では営業、法務、知財、開発、品質など複数部署が関わる契約業務において、情報の属人化や部署での情報の断絶、承認の停滞が業務効率や監査対応の大きな負担となります。本講演では、こうした情報ロスや二重管理を防ぎ、事業拡大のボトルネックを解消する契約情報の整理・共有基盤づくりやグループ間のナレッジ共有について、大手製薬企業様の事例を交えながら紹介します。
【講演者プロフィール】
大阪大学工学部卒業後、株式会社電通にて大手企業の統合マーケティング戦略の立案・実行に従事。Amazon Japanでは複数業界の大手法人に対し、EC 戦略の構築・推進を支援。2022年より株式会社Hubbleに参画し、マーケティングマネージャー、事業責任者を経て、現職。
【講演内容】
製薬企業やメーカー企業では営業、法務、知財、開発、品質など複数部署が関わる契約業務において、情報の属人化や部署での情報の断絶、承認の停滞が業務効率や監査対応の大きな負担となります。本講演では、こうした情報ロスや二重管理を防ぎ、事業拡大のボトルネックを解消する契約情報の整理・共有基盤づくりやグループ間のナレッジ共有について、大手製薬企業様の事例を交えながら紹介します。
【講演者プロフィール】
大阪大学工学部卒業後、株式会社電通にて大手企業の統合マーケティング戦略の立案・実行に従事。Amazon Japanでは複数業界の大手法人に対し、EC 戦略の構築・推進を支援。2022年より株式会社Hubbleに参画し、マーケティングマネージャー、事業責任者を経て、現職。
製薬業界におけるDX実践 ~経験と勘に頼らない営業・マーケティング改革~

|
株式会社 テクロス 代表取締役 橋本 悟 |

|

【講演内容】
DXを支援するInsighTCROSSは、AIを活用して営業・マーケの無駄を排除し、再現性ある活動でコスト削減を実現します。本講演では、医師が求める情報と企業が提供する情報の乖離に着目し、営業・マーケ活動に潜む無駄の原因を可視化・分析し、効率化へと導く実践的な手法をご紹介します。
【講演者プロフィール】
アメリカ、ベルビュー大学経営学部卒業(cum laude)後帰国、外資系ヘルスケアコンサルティング会社を経て、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コーディス事業部に入社。その後は一貫してカテーテルインターベンション領域で営業・マーケティングのキャリアを経て、2005年株式会社テクロスを設立。2019年グロービス経営大学院経営研究科入学、2021年同大学院経営研究科卒業 MBA(経営学修士: 成績優秀修了者)。2023年 中央大学大学院戦略経営研究科ビジネス科学専攻 博士後期課程。
【講演内容】
DXを支援するInsighTCROSSは、AIを活用して営業・マーケの無駄を排除し、再現性ある活動でコスト削減を実現します。本講演では、医師が求める情報と企業が提供する情報の乖離に着目し、営業・マーケ活動に潜む無駄の原因を可視化・分析し、効率化へと導く実践的な手法をご紹介します。
【講演者プロフィール】
アメリカ、ベルビュー大学経営学部卒業(cum laude)後帰国、外資系ヘルスケアコンサルティング会社を経て、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コーディス事業部に入社。その後は一貫してカテーテルインターベンション領域で営業・マーケティングのキャリアを経て、2005年株式会社テクロスを設立。2019年グロービス経営大学院経営研究科入学、2021年同大学院経営研究科卒業 MBA(経営学修士: 成績優秀修了者)。2023年 中央大学大学院戦略経営研究科ビジネス科学専攻 博士後期課程。

|
株式会社 テクロス デジタルマーケティング マネジャー/医師・医学博士 許沢 佳弘 |

|

【講演者プロフィール】
日本赤十字社医療センター、東京大学医学部附属病院で循環器内科医として勤務。東京大学大学院で分子生物学領域の基礎研究に従事。医療系ベンチャーミーカンパニー株式会社を経て、2019年より株式会社テクロスへ入社。現在も臨床医の傍ら、TCROSS NEWSでwebコンテンツの企画とMedical advisorを兼任。 循環器専門医、東京大学医学部卒業(MD)、 東京大学大学院医学系研究科博士課程修了(Ph.D.)。
【講演者プロフィール】
日本赤十字社医療センター、東京大学医学部附属病院で循環器内科医として勤務。東京大学大学院で分子生物学領域の基礎研究に従事。医療系ベンチャーミーカンパニー株式会社を経て、2019年より株式会社テクロスへ入社。現在も臨床医の傍ら、TCROSS NEWSでwebコンテンツの企画とMedical advisorを兼任。 循環器専門医、東京大学医学部卒業(MD)、 東京大学大学院医学系研究科博士課程修了(Ph.D.)。
営業DXは何からはじめるべきか

|
Sansan株式会社 Sansan事業部 SMB第1営業部 シニアマネジャー 能勢 翔 |

|

【講演内容】
近年、顧客の購買プロセスの変化や労働人口の減少により、営業プロセスの抜本的な見直しが必要となっています。営業DXの流れも加速しており、営業活動の各プロセスで、さまざまなデジタルツールが登場しています。しかし「営業DXを何からはじめるべきか?」については明確な解がなく、悩まれている企業も多いのではないでしょうか。本セッションでは、営業DXを実現させるためのポイントと、その成功事例をご紹介します。
【講演内容】
近年、顧客の購買プロセスの変化や労働人口の減少により、営業プロセスの抜本的な見直しが必要となっています。営業DXの流れも加速しており、営業活動の各プロセスで、さまざまなデジタルツールが登場しています。しかし「営業DXを何からはじめるべきか?」については明確な解がなく、悩まれている企業も多いのではないでしょうか。本セッションでは、営業DXを実現させるためのポイントと、その成功事例をご紹介します。
最新事例に学ぶDX変革と最新ツールの活用術
|
|
株式会社 デジタルフォルン デジタル改革・データアナリティクス1事業部 事業部長 石川 晴基 |
|
【講演内容】
本講演では、トップ企業がDXを実現するために取り入れている最新業務管理ツール・ノーコード開発ツールのご紹介とその効果的な活用方法を紹介します。前半は、業務管理で活用できる自動化機能などの主要機能を解説し、後半は、実際のビジネスシーンにおける活用事例を紹介し、このツールが業務効率化にどのように役立つかを示します。
製薬業界の事例として、生産設備のリプレイス管理、医薬品のQC管理等の生産現場での事例をご紹介します。また、既存システムを活用しながら海外の最新のツールと連携し活用するケースや、他業界での先進事例についてもご紹介します。
【講演内容】
本講演では、トップ企業がDXを実現するために取り入れている最新業務管理ツール・ノーコード開発ツールのご紹介とその効果的な活用方法を紹介します。前半は、業務管理で活用できる自動化機能などの主要機能を解説し、後半は、実際のビジネスシーンにおける活用事例を紹介し、このツールが業務効率化にどのように役立つかを示します。
製薬業界の事例として、生産設備のリプレイス管理、医薬品のQC管理等の生産現場での事例をご紹介します。また、既存システムを活用しながら海外の最新のツールと連携し活用するケースや、他業界での先進事例についてもご紹介します。
ヘルステック業界における疾患啓発の役割と「いしゃまち病院検索」事例紹介

|
株式会社 メディウィル デジタルマーケティングディレクター 菊地 栄斗 |

|

【講演内容】
最新のヘルステック動向を踏まえた上で、患者中心時代における疾患啓発の役割と事例を紹介します。旭化成ファーマ社の骨粗鬆症の疾患啓発プロジェクト「骨検」、協和キリン社のFGF23関連の低リン血症性くる病・骨軟化症の疾患啓発プロジェクト「くるこつ広場」、株式会社ヴァンティブ社の疾患啓発プロジェクト「透析病院ドットコム」をはじめ、ペイシェントジャーニーに添った「いしゃまち病院検索サービス」を活用した豊富な経験から学んだ疾患啓発の役割を解説していきます。
【講演内容】
最新のヘルステック動向を踏まえた上で、患者中心時代における疾患啓発の役割と事例を紹介します。旭化成ファーマ社の骨粗鬆症の疾患啓発プロジェクト「骨検」、協和キリン社のFGF23関連の低リン血症性くる病・骨軟化症の疾患啓発プロジェクト「くるこつ広場」、株式会社ヴァンティブ社の疾患啓発プロジェクト「透析病院ドットコム」をはじめ、ペイシェントジャーニーに添った「いしゃまち病院検索サービス」を活用した豊富な経験から学んだ疾患啓発の役割を解説していきます。
患者起点データによる製薬マーケティングの新たなアプローチ

|
Ubie株式会社 ファーマイノベーション事業本部 営業統括 榊原 健太 |
|
【講演内容】
従来のデータセットだけでは、「どのような患者さんが、どの医療機関を受診しているのか」を正確かつリアルタイムに把握することは困難でした。
しかし、ユビーが保有するPHR(Personal Health Record)データを活用することで、適切なターゲットに対し、最適なタイミングで情報提供を行うことが可能になります。
実際にこの仕組みを導入したスペシャリティ薬剤では、新規症例の約20%をユビー起点のデータに基づいて特定することに成功しています。また、希少疾患領域においては、データ利用前と比較して、症例発見に至るまでの医療機関訪問数を1/7に削減できた事例もでてきています。
本セミナーでは、マーケティング部門、コマーシャルエクセレンス部門、デジタル部門、データ分析部門の方々などを対象に、製薬企業が患者データをどのようにマーケティングや営業活動に活用できるのかユースケースを交えてご紹介します。
また、製薬企業がこれからの時代に目指すべきデータ活用の在り方についても深掘りしていきます。
【講演内容】
従来のデータセットだけでは、「どのような患者さんが、どの医療機関を受診しているのか」を正確かつリアルタイムに把握することは困難でした。
しかし、ユビーが保有するPHR(Personal Health Record)データを活用することで、適切なターゲットに対し、最適なタイミングで情報提供を行うことが可能になります。
実際にこの仕組みを導入したスペシャリティ薬剤では、新規症例の約20%をユビー起点のデータに基づいて特定することに成功しています。また、希少疾患領域においては、データ利用前と比較して、症例発見に至るまでの医療機関訪問数を1/7に削減できた事例もでてきています。
本セミナーでは、マーケティング部門、コマーシャルエクセレンス部門、デジタル部門、データ分析部門の方々などを対象に、製薬企業が患者データをどのようにマーケティングや営業活動に活用できるのかユースケースを交えてご紹介します。
また、製薬企業がこれからの時代に目指すべきデータ活用の在り方についても深掘りしていきます。
製薬業界のDXを加速する──“AIネイティブ”業務構築による現場変革のリアル

|
株式会社Kiei AIコンサルティング事業部 取締役 桜井 竜佳 |

|

【講演内容】
製薬業界におけるDXやAI活用は、多くの場合「規制の厳しさ」や「業務の複雑さ」によって足踏みしがちです。
特にAI活用においては、「導入が難しい」「成果が出にくい」という先入観が強く、実装フェーズまで進めないケースも少なくありません。
しかし、私たちが実践しているのは、その常識を覆すアプローチです。
業界理解を深めた業界特化のコンサルティングチームとR&Dをはじめ最新の技術を有するエンジニアチームが、表層的な“デジタル化”ではなく、業務そのものをAI起点で再設計する“AIネイティブ”な業務構築を推進しています。
また、個社ごとの業務フローや課題を現場で実体験することで、実情に即した完全カスタマイズ型の提案を実現し、セキュリティ要件や既存システムとの整合性を考慮しつつ、社内環境内でのAI実装も可能にしています。
本講演では、「泥臭く、しかしアジャイルに」──そんな姿勢で取り組んできた生成AI活用のリアルをご紹介します。
単なるツール導入にとどまらない、事業・業務の根幹を変革するためのAI活用戦略として、製薬業界に最適化されたDXの進め方を、実例とともにお伝えします。
【講演内容】
製薬業界におけるDXやAI活用は、多くの場合「規制の厳しさ」や「業務の複雑さ」によって足踏みしがちです。
特にAI活用においては、「導入が難しい」「成果が出にくい」という先入観が強く、実装フェーズまで進めないケースも少なくありません。
しかし、私たちが実践しているのは、その常識を覆すアプローチです。
業界理解を深めた業界特化のコンサルティングチームとR&Dをはじめ最新の技術を有するエンジニアチームが、表層的な“デジタル化”ではなく、業務そのものをAI起点で再設計する“AIネイティブ”な業務構築を推進しています。
また、個社ごとの業務フローや課題を現場で実体験することで、実情に即した完全カスタマイズ型の提案を実現し、セキュリティ要件や既存システムとの整合性を考慮しつつ、社内環境内でのAI実装も可能にしています。
本講演では、「泥臭く、しかしアジャイルに」──そんな姿勢で取り組んできた生成AI活用のリアルをご紹介します。
単なるツール導入にとどまらない、事業・業務の根幹を変革するためのAI活用戦略として、製薬業界に最適化されたDXの進め方を、実例とともにお伝えします。

培養期間を50%短縮!表皮モデルの早期成熟化 - 収縮抑制全層モデルも-

|
株式会社 高研 研究所 佐藤 雄三 |
|
【講演内容】
市販の表皮モデルや皮膚全層モデルの価格や納期、実験の柔軟性に課題を感じていらっしゃいませんか?ご自身でお持ちの角化細胞を使い、僅か7日間の気液界面培養でヒトの表皮200μmに近い厚さの表皮モデル作製が可能な「FibColl高透過性アテロコラーゲンインサート」をご提案いたします。
また、収縮を抑制した皮膚全層モデルや乾癬様炎症誘導モデル、アトピー性皮膚炎誘導モデルについても合わせてご紹介します。
【講演内容】
市販の表皮モデルや皮膚全層モデルの価格や納期、実験の柔軟性に課題を感じていらっしゃいませんか?ご自身でお持ちの角化細胞を使い、僅か7日間の気液界面培養でヒトの表皮200μmに近い厚さの表皮モデル作製が可能な「FibColl高透過性アテロコラーゲンインサート」をご提案いたします。
また、収縮を抑制した皮膚全層モデルや乾癬様炎症誘導モデル、アトピー性皮膚炎誘導モデルについても合わせてご紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

エクソソーム産生・MSCs大量培養向けfixed-bedバイオリアクターのご紹介

|
PHC 株式会社 吉田 茉由 |
|
【講演内容】
scale-X™シリーズは接着細胞・浮遊細胞が培養可能なfixed-bedバイオリアクターを搭載し、培養面積0.5m2から600m2までのスケーラブルなラインナップを提供します。近年、接着細胞である間葉系幹細胞を利用したエクソソームの製造需要が高まっており、エクソソーム生産における間葉系幹細胞大量培養系へのfixed-bedバイオリアクターの活用が期待されます。本講演ではscale-Xシリーズにおける間葉系幹細胞を用いた培養事例、エクソソーム生産事例をご紹介します。
【講演内容】
scale-X™シリーズは接着細胞・浮遊細胞が培養可能なfixed-bedバイオリアクターを搭載し、培養面積0.5m2から600m2までのスケーラブルなラインナップを提供します。近年、接着細胞である間葉系幹細胞を利用したエクソソームの製造需要が高まっており、エクソソーム生産における間葉系幹細胞大量培養系へのfixed-bedバイオリアクターの活用が期待されます。本講演ではscale-Xシリーズにおける間葉系幹細胞を用いた培養事例、エクソソーム生産事例をご紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

建築専門家による!医療品・化粧品業界のカーボンニュートラルに向けた施策

|
明豊ファシリティワークス 株式会社 CM事業創造本部 部長 江口 正剛 |
|
【講演内容】
カーボンニュートラルへの対応が急務となる中、医療品・化粧品業界でも脱炭素化への取り組みが加速しています。
本セミナーでは、医療品・化粧品工場や研究所の建設プロジェクトにおける支援事例が豊富な当社が、カーボンニュートラルに向けた取り組み事例や当社のサービスをご紹介します。
脱炭素の施策としては様々な手法があり、何から手を付けて良いか分からないことが多いと言われています。
当社はこれらの様々な手法を1つ1つ具体的に検討し、それらを発注者の立場でメリット・デメリット、さらにそれらに対するコストを整理することで、発注者が脱炭素に向けた第一歩を踏み出す支援をさせていただきます。
【講演内容】
カーボンニュートラルへの対応が急務となる中、医療品・化粧品業界でも脱炭素化への取り組みが加速しています。
本セミナーでは、医療品・化粧品工場や研究所の建設プロジェクトにおける支援事例が豊富な当社が、カーボンニュートラルに向けた取り組み事例や当社のサービスをご紹介します。
脱炭素の施策としては様々な手法があり、何から手を付けて良いか分からないことが多いと言われています。
当社はこれらの様々な手法を1つ1つ具体的に検討し、それらを発注者の立場でメリット・デメリット、さらにそれらに対するコストを整理することで、発注者が脱炭素に向けた第一歩を踏み出す支援をさせていただきます。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

医薬・化粧品製造におけるDX化を可能にする防爆モバイル機器

|
ジャパンマシナリー 株式会社 エンタープライズモビリティ部 テクニカルセールススペシャリスト 藏田 あや |
|
【講演内容】
医薬・化粧品製造の防爆エリアでも利用可能な防爆モバイル機器。
DX化を支える、防爆スマートフォン、防爆タブレットPCなど実際の事例を含めて紹介。
【講演内容】
医薬・化粧品製造の防爆エリアでも利用可能な防爆モバイル機器。
DX化を支える、防爆スマートフォン、防爆タブレットPCなど実際の事例を含めて紹介。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

エピジェネティクス技術が切り拓く次世代スキンケアOEMの可能性

|
株式会社 LIVIUS JAPAN 最高執行責任者 大谷 慶仁 |
|
【講演内容】
エピジェネティクス技術の進化は、スキンケア市場に新たな可能性をもたらしています。本講演では、LIVIUSが長年にわたり研究・開発してきたmiRNA誘導技術を応用したエピジェネティクス化粧品「LIVIUS EPIシリーズ」を題材に、従来のアンチエイジング製品とは一線を画す製品設計のポイントや科学的根拠、実証データをご紹介します。独自の低分子化合物による細胞リプログラミングやDNA修復技術、miRNA活性化による「細胞レベルの若返り現象」は、OEM製品としても大きな差別化要素となります。安全性と機能性を両立した特許技術、確かなエビデンス、具体的なOEM対応実績も交えながら、今後の化粧品市場に求められる「本物のエイジングケア」の開発パートナーシップ像を提案いたします。OEMを検討されている皆様にとって、最新技術による新規ビジネス展開のヒントとなれば幸いです。
【講演内容】
エピジェネティクス技術の進化は、スキンケア市場に新たな可能性をもたらしています。本講演では、LIVIUSが長年にわたり研究・開発してきたmiRNA誘導技術を応用したエピジェネティクス化粧品「LIVIUS EPIシリーズ」を題材に、従来のアンチエイジング製品とは一線を画す製品設計のポイントや科学的根拠、実証データをご紹介します。独自の低分子化合物による細胞リプログラミングやDNA修復技術、miRNA活性化による「細胞レベルの若返り現象」は、OEM製品としても大きな差別化要素となります。安全性と機能性を両立した特許技術、確かなエビデンス、具体的なOEM対応実績も交えながら、今後の化粧品市場に求められる「本物のエイジングケア」の開発パートナーシップ像を提案いたします。OEMを検討されている皆様にとって、最新技術による新規ビジネス展開のヒントとなれば幸いです。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

「こんな手袋欲しかった」製造現場で役立つ作業手袋のご紹介

|
ウインセス 株式会社 営業部 部長代理 石黒 強 |
|
【講演内容】
製造現場における「異物混入対策」として、使い捨てゴム製手袋(ニトリル・ラテックスなど)は多くの企業で採用されています。しかしながら、これらの手袋は手荒れや蒸れ、手の圧迫感といった作業者の不満を招きやすく、長時間の作業にストレスを与えています。特に、熟練の作業者が手荒れなどを理由に離職してしまうのは、企業にとって大きな損失です。
本プレゼンテーションでは、作業者にとって快適でありながら、異物混入リスクや怪我の防止といった製造現場の要請にも応える、さまざまな高機能手袋をご紹介します。
例えば、無孔質の透湿フィルムを使用することで、ゴム手袋のような密閉性がありながら蒸れにくい防塵手袋。さらに、作業をしながらタブレット操作が可能なタッチパネル対応手袋や、スーパー繊維を使用した極薄耐切創インナー手袋もラインアップ。加えて、眼鏡拭き素材を掌に配したマイクロファイバー製ワイピング手袋など、現場の「こんなの欲しかった」を形にした製品群をお見せします。
従業員の定着率向上や作業効率アップ、環境への配慮(洗浄して繰り返し使える手袋によるゴミの削減)など、多方面のメリットが得られる製品を、実物を交えながらご紹介いたします。
【講演内容】
製造現場における「異物混入対策」として、使い捨てゴム製手袋(ニトリル・ラテックスなど)は多くの企業で採用されています。しかしながら、これらの手袋は手荒れや蒸れ、手の圧迫感といった作業者の不満を招きやすく、長時間の作業にストレスを与えています。特に、熟練の作業者が手荒れなどを理由に離職してしまうのは、企業にとって大きな損失です。
本プレゼンテーションでは、作業者にとって快適でありながら、異物混入リスクや怪我の防止といった製造現場の要請にも応える、さまざまな高機能手袋をご紹介します。
例えば、無孔質の透湿フィルムを使用することで、ゴム手袋のような密閉性がありながら蒸れにくい防塵手袋。さらに、作業をしながらタブレット操作が可能なタッチパネル対応手袋や、スーパー繊維を使用した極薄耐切創インナー手袋もラインアップ。加えて、眼鏡拭き素材を掌に配したマイクロファイバー製ワイピング手袋など、現場の「こんなの欲しかった」を形にした製品群をお見せします。
従業員の定着率向上や作業効率アップ、環境への配慮(洗浄して繰り返し使える手袋によるゴミの削減)など、多方面のメリットが得られる製品を、実物を交えながらご紹介いたします。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

ラマン検査装置の概念を覆す、圧倒的なコスト・生成AIによる簡単操作を実現

|
メタセンシング株式会社 CTO 森村 皓之 |
|
【講演内容】
ラマン検査装置導入の3大課題:(価格が高い・ザイズが大きい・操作性が複雑)に対するメタセンシングからの提案をお聞きください
高価で大型なラマン検査装置に代わりお持ちの顕微鏡に僅か1分で簡単装着。
世界最小・従来品の1/10の価格・タブレットやスマートフオンを用いて簡単操作
【講演内容】
ラマン検査装置導入の3大課題:(価格が高い・ザイズが大きい・操作性が複雑)に対するメタセンシングからの提案をお聞きください
高価で大型なラマン検査装置に代わりお持ちの顕微鏡に僅か1分で簡単装着。
世界最小・従来品の1/10の価格・タブレットやスマートフオンを用いて簡単操作
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

界面活性剤不使用・アレルゲンフリー機能性化粧品ODM

|
株式会社ファーストラボ 平野 富夫 |
|
【講演内容】
界面活性剤不使用処方の未来を切り拓く集束型超音波技術
高均一親水性リポソームで吸収率を10倍以上に改善
高機能・高安定処方を実現する次世代化粧品製造装置
【講演内容】
界面活性剤不使用処方の未来を切り拓く集束型超音波技術
高均一親水性リポソームで吸収率を10倍以上に改善
高機能・高安定処方を実現する次世代化粧品製造装置
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

–化粧品原材料の品質向上– 全数検査できる粉体検査装置について

|
池上通信機 株式会社 営業・マーケティング本部 インスペクションソリューション営業部 主任 柴垣 聡太 |
|
【講演内容】
各種検査装置の製造・販売について50年以上の実績を持つ池上通信機と申します。本セミナーでは粉体原料向け検査装置POIE-8000CA(TYPE-i)についてご紹介させていただきます。
粉体原料の需要増に伴い、品質についての要求レベルも上がり、目視やふるいでは対応しきれない。というお悩みはございませんでしょうか?そのお悩み、弊社の検査装置により解決いたします。
本粉体検査装置は検査、異物除去、良品の回収までを行うオールインワンタイプの装置です。装置に投入された粉体は高性能カメラにて、混入される細かい毛髪や微細異物を検出。50µm相当までの異物除去が可能で、良品のみを回収いたします。
異物除去はスポット吸引によりピンポイントで行われるため、歩留まりへの影響を限りなく抑え、生産性向上に寄与します。品種や異物は先に登録しますので、タッチパネルで簡単に運用開始が可能です。現状の検査精度のバラつき、不効率といったお悩みを解決すると共に、高品質な製品をクライアントに納めることができるため、本装置の導入は御社のセールストークとしても効果的です。化粧品原料など粉体の検査は是非、池上通信機の粉体検査装置にお任せください。ご紹介する装置はブースに実機を展示しておりますので、セミナーと合わせてぜひ実物をご覧いただければ幸いです。
【講演内容】
各種検査装置の製造・販売について50年以上の実績を持つ池上通信機と申します。本セミナーでは粉体原料向け検査装置POIE-8000CA(TYPE-i)についてご紹介させていただきます。
粉体原料の需要増に伴い、品質についての要求レベルも上がり、目視やふるいでは対応しきれない。というお悩みはございませんでしょうか?そのお悩み、弊社の検査装置により解決いたします。
本粉体検査装置は検査、異物除去、良品の回収までを行うオールインワンタイプの装置です。装置に投入された粉体は高性能カメラにて、混入される細かい毛髪や微細異物を検出。50µm相当までの異物除去が可能で、良品のみを回収いたします。
異物除去はスポット吸引によりピンポイントで行われるため、歩留まりへの影響を限りなく抑え、生産性向上に寄与します。品種や異物は先に登録しますので、タッチパネルで簡単に運用開始が可能です。現状の検査精度のバラつき、不効率といったお悩みを解決すると共に、高品質な製品をクライアントに納めることができるため、本装置の導入は御社のセールストークとしても効果的です。化粧品原料など粉体の検査は是非、池上通信機の粉体検査装置にお任せください。ご紹介する装置はブースに実機を展示しておりますので、セミナーと合わせてぜひ実物をご覧いただければ幸いです。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

汚染管理戦略の新提案!微生物迅速検査装置PixeeMo-nX

|
株式会社 SCREENホールディングス ライフサイエンス事業室 主任 田中 創 |
|
【講演内容】
PixeeMo-nX(ピクシーモ-エヌエックス)は、フローサイトメトリーと固相サイトメトリーを組み合わせて確立した微生物迅速検査装置です。独自開発のマイクロ流体デバイス(エレスタプレート)上で、試料中の「生きている微生物」を誘電泳動力によって捕捉、微生物数を自動カウントします。
2023年8月に有効化されたPIC/S GMP Annex 1によって、医薬品や再生医療等製品に微生物迅速検査を活用した汚染管理戦略が求められています。
本項では、汚染管理戦略の新たなソリューションとしてPixeeMo-nXについて詳しくご紹介します。
【講演内容】
PixeeMo-nX(ピクシーモ-エヌエックス)は、フローサイトメトリーと固相サイトメトリーを組み合わせて確立した微生物迅速検査装置です。独自開発のマイクロ流体デバイス(エレスタプレート)上で、試料中の「生きている微生物」を誘電泳動力によって捕捉、微生物数を自動カウントします。
2023年8月に有効化されたPIC/S GMP Annex 1によって、医薬品や再生医療等製品に微生物迅速検査を活用した汚染管理戦略が求められています。
本項では、汚染管理戦略の新たなソリューションとしてPixeeMo-nXについて詳しくご紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

ヒト脂肪由来幹細胞セクレトームエキスへの期待

|
株式会社 テレバイオ 吉村 浩太郎 |
|
【講演内容】
ヒト脂肪由来幹細胞セクレトームエキスにはさまざまな期待がされています。
リポソーム化されたセクレトームエキス®Nanoを新発売しています。
【講演内容】
ヒト脂肪由来幹細胞セクレトームエキスにはさまざまな期待がされています。
リポソーム化されたセクレトームエキス®Nanoを新発売しています。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

プラスチックパッケージの環境対応における課題解決-新しいパルプ成形品-

|
NISSHA 株式会社 産業資材事業部 事業戦略部 サステナブル成形推進グループ グループ長 今井 宏樹 |
|
【講演内容】
化粧品・医薬品のパッケージ設計や輸送・搬送に関わる担当者様を対象に、環境負荷軽減と機能性向上を両立させた最新のサステナブルパッケージ技術とその事例をご紹介します。
当社はプラスチック成形のスペシャリストとして培った経験を活かし、パルプを主原料とした成形品の提供をしています。本セミナーでご紹介するのは、多様なパルプ成形工法ラインアップのうち、パルプモールドと異なるユニークな特長をもつPaperFoam®(ペーパーフォーム)、Pulp-Injection(パルプインジェクション)と、新工法のFiber-Forming(ファイバーフォーミング)の3種類になります。
PaperFoam®はでんぷんとパルプを主原料とした発泡成形品で、衝撃から製品を保護する高いクッション性があります。
Pulp-Injectionは、複雑な形状の成形が可能であり、粉塵の発生を抑え、プラスチックに近い形状再現ができるため既存包装システムにも対応可能です。
新工法であるFiber-Formingの特長もご紹介します。
参加者の皆様には、最新のサステナブルパッケージ技術についての知識を深めていただき、実際の業務に役立てていただけることを目指しています。ぜひご参加いただき、共に持続可能な未来を築いていきましょう。
【講演内容】
化粧品・医薬品のパッケージ設計や輸送・搬送に関わる担当者様を対象に、環境負荷軽減と機能性向上を両立させた最新のサステナブルパッケージ技術とその事例をご紹介します。
当社はプラスチック成形のスペシャリストとして培った経験を活かし、パルプを主原料とした成形品の提供をしています。本セミナーでご紹介するのは、多様なパルプ成形工法ラインアップのうち、パルプモールドと異なるユニークな特長をもつPaperFoam®(ペーパーフォーム)、Pulp-Injection(パルプインジェクション)と、新工法のFiber-Forming(ファイバーフォーミング)の3種類になります。
PaperFoam®はでんぷんとパルプを主原料とした発泡成形品で、衝撃から製品を保護する高いクッション性があります。
Pulp-Injectionは、複雑な形状の成形が可能であり、粉塵の発生を抑え、プラスチックに近い形状再現ができるため既存包装システムにも対応可能です。
新工法であるFiber-Formingの特長もご紹介します。
参加者の皆様には、最新のサステナブルパッケージ技術についての知識を深めていただき、実際の業務に役立てていただけることを目指しています。ぜひご参加いただき、共に持続可能な未来を築いていきましょう。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

水と油、エマルションを膜分離 【Zaiput社液液/気液セパレーターのご紹介】

|
株式会社 日本サイエンスコア 林 修平 |
|
【講演内容】
Zaiput Flow Technologies社の液-液/液-ガス セパレーターは最新の膜分離技術を用いて、水相と油相(有機相)の分離を迅速に、且つ容易にスケールアップが可能です。
水/油抽出液の連続分離、溶媒と副生成物の分離、水相・有機相の効率的切り出し、二層製品の製造・管理など今直面している課題をZaiput社のセパ―レーターで解決いたします。
Zaiput社のセパレーターはスケールアップが可能です。ラボスケールのSEP-10(10ml/min)、パイロットスケールのSEP-200(200ml/min)、生産スケールのSEP-3000(3000ml/min), SEP-40K(40,000ml/min)まで対応可能です。
本セミナーではZaiput社セパレーターの構成や分離の仕組み、使用されている膜についてやその膜の選定方法などについてご紹介いたします。
弊社ブースでは実機も展示しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。
【講演内容】
Zaiput Flow Technologies社の液-液/液-ガス セパレーターは最新の膜分離技術を用いて、水相と油相(有機相)の分離を迅速に、且つ容易にスケールアップが可能です。
水/油抽出液の連続分離、溶媒と副生成物の分離、水相・有機相の効率的切り出し、二層製品の製造・管理など今直面している課題をZaiput社のセパ―レーターで解決いたします。
Zaiput社のセパレーターはスケールアップが可能です。ラボスケールのSEP-10(10ml/min)、パイロットスケールのSEP-200(200ml/min)、生産スケールのSEP-3000(3000ml/min), SEP-40K(40,000ml/min)まで対応可能です。
本セミナーではZaiput社セパレーターの構成や分離の仕組み、使用されている膜についてやその膜の選定方法などについてご紹介いたします。
弊社ブースでは実機も展示しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

Leveraging ExoMX™ for Scalable Production of MSC-derived Exosomes

|
Mycenax Biotech Inc. Pharmaceutical Development Senior Manager Peggy Tseng, Ph.D. |
|
【講演内容】
Exosomes, a subtype of small extracellular vesicles (EVs) derived from mesenchymal stem cells (MSCs), retain the regenerative potential of their parental MSCs and have been widely explored for both cosmetic and therapeutic clinical applications. However, the clinical translation of EV production from lab-scale to large-scale remains challenging due to their nanoscale size, heterogeneity, complex isolation procedures with low recovery yields, and limited stability. In this presentation, we will introduce how the Mycenax ExoMX™ platform can be leveraged to overcome these manufacturing hurdles and industrialize large-scale production of MSC-derived EVs to meet growing market demands.
【講演内容】
Exosomes, a subtype of small extracellular vesicles (EVs) derived from mesenchymal stem cells (MSCs), retain the regenerative potential of their parental MSCs and have been widely explored for both cosmetic and therapeutic clinical applications. However, the clinical translation of EV production from lab-scale to large-scale remains challenging due to their nanoscale size, heterogeneity, complex isolation procedures with low recovery yields, and limited stability. In this presentation, we will introduce how the Mycenax ExoMX™ platform can be leveraged to overcome these manufacturing hurdles and industrialize large-scale production of MSC-derived EVs to meet growing market demands.
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

ガンマ線照射による滅菌・殺菌 -化粧品への応用-

|
株式会社 コーガアイソトープ 仲谷まほろ |
|
【講演内容】
ガンマ線を用いた滅菌・殺菌技術は、医療機器や衛生用品、包装資材など、さまざまな業界で幅広く利用されており、その範囲はますます拡大しています。
化粧品業界においても、ガンマ線滅菌・殺菌の導入や切り替えが進んでおり、微生物汚染による回収リスクの低減や、滅菌・殺菌工程における破袋等のロス削減、防腐剤フリーを実現しております。
ガンマ線は高い透過力を持つため、重量のある化粧品原料も滅菌・殺菌が可能であり、光と同じ性質を持つことから、残留物のリスクもございません。
本セミナーでは、ガンマ線滅菌・殺菌の基本原理、ガス滅菌など他の滅菌技術との比較だけでなく、化粧品分野に特化した具体的な応用事例などをご紹介いたします。
【講演内容】
ガンマ線を用いた滅菌・殺菌技術は、医療機器や衛生用品、包装資材など、さまざまな業界で幅広く利用されており、その範囲はますます拡大しています。
化粧品業界においても、ガンマ線滅菌・殺菌の導入や切り替えが進んでおり、微生物汚染による回収リスクの低減や、滅菌・殺菌工程における破袋等のロス削減、防腐剤フリーを実現しております。
ガンマ線は高い透過力を持つため、重量のある化粧品原料も滅菌・殺菌が可能であり、光と同じ性質を持つことから、残留物のリスクもございません。
本セミナーでは、ガンマ線滅菌・殺菌の基本原理、ガス滅菌など他の滅菌技術との比較だけでなく、化粧品分野に特化した具体的な応用事例などをご紹介いたします。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

「動物実験から細胞実験へ」加速する化粧品開発研究

|
プロメガ 株式会社 営業部 ABCプロジェクト アプライドプロジェクト スペシャリスト 鈴木 康哲 |
|
【講演内容】
化粧品やその他の製品は、その有用性のみならず、安全性が最も重要な要素であり、長年動物実験が安全性評価に使用されてきた。しかし、EUでは2013年に化粧品開発における動物実験が全面禁止され、その後アメリカや日本でも動物実験を自主規制する動きが広まった。
動物実験を行わずに安全性を担保する方法が「動物実験代替法」として細胞実験の導入である。特に皮膚炎などの安全性評価を行う際には、動物実験は倫理的な問題や高コスト、実験の習熟度が必要であるなどの課題がある。一方で、細胞実験は動物を犠牲にすることなく、均一で低コストなデータを得ることが可能となる。
細胞実験の例として、レポーターを活用した[KeratinoSens]や3D皮膚モデルを使用した[EpiSensA]をについて、安全性評価への有用性を紹介する。また、動物実験代替法に関する課題とその解決方法にも触れ、今後の化粧品開発における新しいアプローチについても考察する。
【講演内容】
化粧品やその他の製品は、その有用性のみならず、安全性が最も重要な要素であり、長年動物実験が安全性評価に使用されてきた。しかし、EUでは2013年に化粧品開発における動物実験が全面禁止され、その後アメリカや日本でも動物実験を自主規制する動きが広まった。
動物実験を行わずに安全性を担保する方法が「動物実験代替法」として細胞実験の導入である。特に皮膚炎などの安全性評価を行う際には、動物実験は倫理的な問題や高コスト、実験の習熟度が必要であるなどの課題がある。一方で、細胞実験は動物を犠牲にすることなく、均一で低コストなデータを得ることが可能となる。
細胞実験の例として、レポーターを活用した[KeratinoSens]や3D皮膚モデルを使用した[EpiSensA]をについて、安全性評価への有用性を紹介する。また、動物実験代替法に関する課題とその解決方法にも触れ、今後の化粧品開発における新しいアプローチについても考察する。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

化粧品製造における高速攪拌機の活用

|
プライミクス 株式会社 細川 達暉 |
|
【講演内容】
攪拌機は、化粧品、医薬品、食品、電子デバイス、電池、樹脂、セラミックスなど、多様な製造プロセスで活用され、製品の付加価値向上や生産効率の改善に貢献しています。
特に、弊社の高速攪拌機は処理流体に強力なせん断を与え、分散や乳化といった高度な処理に適しています。
化粧品製造にはさまざまな工程があり、それぞれの工程において攪拌目的も多種多様です。
また乳化や分散を行う攪拌機にもさまざまな種類があり、それぞれに特長があります。
そのため、各製造工程を考慮し、最適な攪拌機を選定することが重要になります。
本講演では、スタンダードな機種として化粧品製造に活用いただいているプライミクスの攪拌機のご紹介とともに、化粧品および医薬品に使用される酸化チタンを様々な攪拌機で処理したデータを基に攪拌機の特徴をご紹介します。
【講演内容】
攪拌機は、化粧品、医薬品、食品、電子デバイス、電池、樹脂、セラミックスなど、多様な製造プロセスで活用され、製品の付加価値向上や生産効率の改善に貢献しています。
特に、弊社の高速攪拌機は処理流体に強力なせん断を与え、分散や乳化といった高度な処理に適しています。
化粧品製造にはさまざまな工程があり、それぞれの工程において攪拌目的も多種多様です。
また乳化や分散を行う攪拌機にもさまざまな種類があり、それぞれに特長があります。
そのため、各製造工程を考慮し、最適な攪拌機を選定することが重要になります。
本講演では、スタンダードな機種として化粧品製造に活用いただいているプライミクスの攪拌機のご紹介とともに、化粧品および医薬品に使用される酸化チタンを様々な攪拌機で処理したデータを基に攪拌機の特徴をご紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

マテチャ葉の濃縮パワーで、肌覚醒。瞬時にエネルギッシュな肌へ導く。

|
東洋サイエンス 株式会社 立花 英寛 |
|
【講演内容】
スイスRAHN社が開発したスキンケア用化粧品原料、YERBALUXE-PEARL(イェルバラクス パール)は、マテ茶葉の濃縮パワーで、肌を覚醒。瞬時にエネルギッシュな肌へ導くきます。肌のエネルギーを呼び覚まし、見た目を瞬時に、そして、レベルアップします。
その秘密は、マテ茶製造の過程で生まれる、貴重なアップサイクル素材「マテの副産物」。豊富なカフェインとパワフルな抗酸化成分が、あなたの肌を内側から輝かせます。
現代社会のストレスや環境ダメージは、肌の活力を奪い、くすみや疲労感の原因に。YERBALUXE-PEARL(イェルバラクス パール)は、マテ茶の力で、肌の酸素レベルを格段に向上させ、血流を促進します。一般的なマテ茶と比較して、ポリフェノール13倍、カフェイン2倍、ルチン8倍という圧倒的なパワーで、肌をバイオハック。若々しく、エネルギッシュな美しさを呼び覚まします。使うたびに、肌は輝きを増し、ハリと弾力を取り戻し、年齢を感じさせない、自信に満ちた肌へ。
臨床試験では、YERBALUXE-PEARL(イェルバラクス パール)が血流を促進し、酸素レベルを高めることで肌を活性化することが証明されています。さらに、肌の赤みを軽減する効果も確認されています。YERBALUXE-PEARL(イェルバラクス パール)は、肌のバリア機能を素早く強化し、潤いを与え、内側から輝くような自然なツヤをもたらします。使い続けることで、肌のハリと弾力が向上し、気になる目じりのシワも目立たなくなります。白人だけでなく、アフリカ系被験者を含む試験で長期的な効果を、中国人被験者による試験で即効性と短期的な効果を確認済みです。In-vitro試験では、ミトコンドリアを保護し、セラミドの生成を促進することで、肌のバリア機能を高める効果が確認されています。
本セミナーでは、スイスRAHN社の最新化粧品原料、YERBALUXE-PEARL(イェルバラクス パール)の効果を紹介させていただきます。
【講演内容】
スイスRAHN社が開発したスキンケア用化粧品原料、YERBALUXE-PEARL(イェルバラクス パール)は、マテ茶葉の濃縮パワーで、肌を覚醒。瞬時にエネルギッシュな肌へ導くきます。肌のエネルギーを呼び覚まし、見た目を瞬時に、そして、レベルアップします。
その秘密は、マテ茶製造の過程で生まれる、貴重なアップサイクル素材「マテの副産物」。豊富なカフェインとパワフルな抗酸化成分が、あなたの肌を内側から輝かせます。
現代社会のストレスや環境ダメージは、肌の活力を奪い、くすみや疲労感の原因に。YERBALUXE-PEARL(イェルバラクス パール)は、マテ茶の力で、肌の酸素レベルを格段に向上させ、血流を促進します。一般的なマテ茶と比較して、ポリフェノール13倍、カフェイン2倍、ルチン8倍という圧倒的なパワーで、肌をバイオハック。若々しく、エネルギッシュな美しさを呼び覚まします。使うたびに、肌は輝きを増し、ハリと弾力を取り戻し、年齢を感じさせない、自信に満ちた肌へ。
臨床試験では、YERBALUXE-PEARL(イェルバラクス パール)が血流を促進し、酸素レベルを高めることで肌を活性化することが証明されています。さらに、肌の赤みを軽減する効果も確認されています。YERBALUXE-PEARL(イェルバラクス パール)は、肌のバリア機能を素早く強化し、潤いを与え、内側から輝くような自然なツヤをもたらします。使い続けることで、肌のハリと弾力が向上し、気になる目じりのシワも目立たなくなります。白人だけでなく、アフリカ系被験者を含む試験で長期的な効果を、中国人被験者による試験で即効性と短期的な効果を確認済みです。In-vitro試験では、ミトコンドリアを保護し、セラミドの生成を促進することで、肌のバリア機能を高める効果が確認されています。
本セミナーでは、スイスRAHN社の最新化粧品原料、YERBALUXE-PEARL(イェルバラクス パール)の効果を紹介させていただきます。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

ChemTunes・ToxGPSを活用した次世代型リスク評価(NGRA)の実践

|
株式会社 モルシス ライフサイエンス部 東田 欣也 |
|
【講演内容】
近年、化学物質の安全性評価において、動物実験に依存しない次世代型リスク評価(Next Generation Risk Assessment: NGRA)が注目されています。本プレゼンテーションでは、各国の規制当局など様々なデータソースからの毒性・安全性試験データを統合し、化学物質のリスク評価のための多様な解析機能を備えたプラットフォームChemTunes・ToxGPSについて紹介します。
ChemTunes・ToxGPSのデータベースには、急性・慢性毒性試験、変異原性試験、皮膚感作性試験、反復投与毒性試験の結果などが含まれます。また、以下の先進的な解析機能を実装しています。
1. リードアクロス(Read-Across)解析: 類似構造を持つ既存化合物のデータを活用し、新規化合物の毒性を推定。
2. QSAR(Quantitative Structure-Activity Relationship)モデル: 機械学習を活用し、化学構造から毒性を予測。
3. TTC(Threshold of Toxicological Concern)解析: 化学構造に基づき許容摂取量を推定し、低暴露レベルのリスクを迅速に評価。
4. NOAEL(無毒性量)・EC3値(皮膚感作性の指標)推算: 公開データや数理モデルを用いた推算機能により、試験データがない化合物の安全性評価を補完。
ChemTunes・ToxGPS により、毒性試験データの不足を補い、より迅速かつ倫理的なリスク評価が可能となります。本システムは、企業の安全性評価部門、規制機関、研究機関など幅広いユーザーにとって有用なツールとなることが期待されます。NGRAの実現に向けた本システムの有効性を、具体的な活用例とともに紹介します。
【講演内容】
近年、化学物質の安全性評価において、動物実験に依存しない次世代型リスク評価(Next Generation Risk Assessment: NGRA)が注目されています。本プレゼンテーションでは、各国の規制当局など様々なデータソースからの毒性・安全性試験データを統合し、化学物質のリスク評価のための多様な解析機能を備えたプラットフォームChemTunes・ToxGPSについて紹介します。
ChemTunes・ToxGPSのデータベースには、急性・慢性毒性試験、変異原性試験、皮膚感作性試験、反復投与毒性試験の結果などが含まれます。また、以下の先進的な解析機能を実装しています。
1. リードアクロス(Read-Across)解析: 類似構造を持つ既存化合物のデータを活用し、新規化合物の毒性を推定。
2. QSAR(Quantitative Structure-Activity Relationship)モデル: 機械学習を活用し、化学構造から毒性を予測。
3. TTC(Threshold of Toxicological Concern)解析: 化学構造に基づき許容摂取量を推定し、低暴露レベルのリスクを迅速に評価。
4. NOAEL(無毒性量)・EC3値(皮膚感作性の指標)推算: 公開データや数理モデルを用いた推算機能により、試験データがない化合物の安全性評価を補完。
ChemTunes・ToxGPS により、毒性試験データの不足を補い、より迅速かつ倫理的なリスク評価が可能となります。本システムは、企業の安全性評価部門、規制機関、研究機関など幅広いユーザーにとって有用なツールとなることが期待されます。NGRAの実現に向けた本システムの有効性を、具体的な活用例とともに紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

化粧品、医薬品メーカー向け 包装工程 自動化・省人化事例

|
グローリー 株式会社 中川 浩太 |
|
【講演内容】
昨今の働き手不足により化粧品、医薬品製造工程において自動化・省人化のニーズが高まってきております。
当社ではこれまで培ってきたロボティクス技術により各種自動化のご提案を行っています。
その一例をご紹介させていただきます。
・省スペース型 ケーサー・パレタイザー 一体型システム
・カートナーへの資材自動供給システム(工場内自動搬送+協働ロボットによるデパレタイジング)
・各種箱詰め自動化
・バケット式 小型自動倉庫
【講演内容】
昨今の働き手不足により化粧品、医薬品製造工程において自動化・省人化のニーズが高まってきております。
当社ではこれまで培ってきたロボティクス技術により各種自動化のご提案を行っています。
その一例をご紹介させていただきます。
・省スペース型 ケーサー・パレタイザー 一体型システム
・カートナーへの資材自動供給システム(工場内自動搬送+協働ロボットによるデパレタイジング)
・各種箱詰め自動化
・バケット式 小型自動倉庫
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

ヒト型ロボットNEXTAGEで実現する製造革新 ~人手不足時代のアプローチ~

|
カワダロボティクス 株式会社 営業部 営業課 主任 川端 健太郎 |
|
【講演内容】
「人と一緒に働く」というコンセプトのもと、人手不足を解消すべく開発されたヒト型ロボットNEXTAGE。
NEXTAGEは、周囲の環境を認識しながら作業する汎用性の高さを活かし、様々な人手工程にフレキシブルに対応してきました。
本講演では、 人手不足時代において、機械業界だけではなく、三品業界へも展開しつつあるNEXTAGEの自動化アプローチについてご紹介します。
【講演内容】
「人と一緒に働く」というコンセプトのもと、人手不足を解消すべく開発されたヒト型ロボットNEXTAGE。
NEXTAGEは、周囲の環境を認識しながら作業する汎用性の高さを活かし、様々な人手工程にフレキシブルに対応してきました。
本講演では、 人手不足時代において、機械業界だけではなく、三品業界へも展開しつつあるNEXTAGEの自動化アプローチについてご紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

化粧品・サプリメントを製造する機械装置の移設・搬入据付・撤去

|
徳三運輸倉庫株式会社 特殊輸送部 部長 鎌田 友寛 |
|
【講演内容】
クリーンルームで製造される化粧品、サプリメント。
それらを製造するために使用される機械・装置は、精密機械であり、重量は100キロ~数トンに及びます。
これらの機械装置のレイアウト変更や新規導入の設置には、専門知識と専用機材を要します。
徳三運輸倉庫は、半導体製造装置の物流で培ったノウハウ・経験を活かし、貴社の大切な機械・装置を安全に、丁寧に運搬設置いたします。
一般建設業(とび・土工工事業)、ISO9001を持ち、コンプライアンス、安全作業に徹底して取り組んでおります。
本プレゼンテーションでは、弊社のご紹介、及び化粧品やサプリメント分野において弊社が出来ることを中心に説明をさせて頂きます。
【講演内容】
クリーンルームで製造される化粧品、サプリメント。
それらを製造するために使用される機械・装置は、精密機械であり、重量は100キロ~数トンに及びます。
これらの機械装置のレイアウト変更や新規導入の設置には、専門知識と専用機材を要します。
徳三運輸倉庫は、半導体製造装置の物流で培ったノウハウ・経験を活かし、貴社の大切な機械・装置を安全に、丁寧に運搬設置いたします。
一般建設業(とび・土工工事業)、ISO9001を持ち、コンプライアンス、安全作業に徹底して取り組んでおります。
本プレゼンテーションでは、弊社のご紹介、及び化粧品やサプリメント分野において弊社が出来ることを中心に説明をさせて頂きます。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

日本で一番使用されているかも?フランスの老舗充填機メーカーの紹介

|
株式会社 マツボー 大阪営業二部 部長 福島 庄一郎 |
|
【講演内容】
国内1号機納入は今から50年以上前
国内納入実績60台以上のフランスの老舗充填機メーカーCitus Kalix社の最新技術のご紹介
【講演内容】
国内1号機納入は今から50年以上前
国内納入実績60台以上のフランスの老舗充填機メーカーCitus Kalix社の最新技術のご紹介
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

均一な乳化粒子・ナノ粒子合成技術-強制薄膜式リアクター「ULREA」

|
エム・テクニック (株) 吉住 真衣 |
|
【講演内容】
強制薄膜式リアクター「ULREA」は液膜を反応場として連続的に各種合成を行うことができる全く新しいフローリアクターです。化学反応や晶析による微粒子合成や均一な乳化粒子の作製技術により、UVカット材料や難溶性化合物の微粒子、マイクロスフェアなどの化粧品・医薬品原料の生産における課題を解決できる装置をご紹介します。
【講演内容】
強制薄膜式リアクター「ULREA」は液膜を反応場として連続的に各種合成を行うことができる全く新しいフローリアクターです。化学反応や晶析による微粒子合成や均一な乳化粒子の作製技術により、UVカット材料や難溶性化合物の微粒子、マイクロスフェアなどの化粧品・医薬品原料の生産における課題を解決できる装置をご紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

製薬用水の品質を担保しながら製造プロセスを効率化する方法とは?

|
セントラル科学 株式会社 業務推進部 主任 梅谷 光祐 |
|
【講演内容】
プロセス分析技術(PAT)とはリアルタイムの測定データを活用して、プロセスの設計、分析、管理を行い、製品の品質を保証するプロセスです。製薬用水設備のプロセスを最適化する場合、製薬用水のTOC試験にPATを導入することが効果的です。製薬用水のTOCをオンライン監視することで、堅牢なプロセス理解と制御が可能になり、品質と生産性が向上します。リアルタイムデータにより、従来のラボ分析に関連するサンプリングエラー・リソース・ラボエラー・サンプリングコスト・データ遅延を大幅に削減できます。プロセス理解が向上することで、リアルタイムで根本原因解析・リスク特定・リスク緩和・トレンド分析・OOSやOOTの検出が可能になります。
一方で、PATを最大限に活用するには、薬局方とICHの要件に従った分析法バリデーションが必要です。分析法がバリデーションされていなければ、リアルタイムデータの価値は失われます。さらに、PATを実装するためにはオンラインTOC計がデータインテグリティ要件を満たしていることも要求されます。また、分析法をラボからオンラインに移管する場合は、リアルタイムテストのプロセスバリデーションも必要です。
プロセスバリデーションには3つのステップ(分析法移管、分析法同等性検証、ユースポイント検証)があります。弊社取扱のSievers オンラインTOC計を用いた製薬用水設備の最適化とプロセスバリデーションについてご紹介します。
【講演内容】
プロセス分析技術(PAT)とはリアルタイムの測定データを活用して、プロセスの設計、分析、管理を行い、製品の品質を保証するプロセスです。製薬用水設備のプロセスを最適化する場合、製薬用水のTOC試験にPATを導入することが効果的です。製薬用水のTOCをオンライン監視することで、堅牢なプロセス理解と制御が可能になり、品質と生産性が向上します。リアルタイムデータにより、従来のラボ分析に関連するサンプリングエラー・リソース・ラボエラー・サンプリングコスト・データ遅延を大幅に削減できます。プロセス理解が向上することで、リアルタイムで根本原因解析・リスク特定・リスク緩和・トレンド分析・OOSやOOTの検出が可能になります。
一方で、PATを最大限に活用するには、薬局方とICHの要件に従った分析法バリデーションが必要です。分析法がバリデーションされていなければ、リアルタイムデータの価値は失われます。さらに、PATを実装するためにはオンラインTOC計がデータインテグリティ要件を満たしていることも要求されます。また、分析法をラボからオンラインに移管する場合は、リアルタイムテストのプロセスバリデーションも必要です。
プロセスバリデーションには3つのステップ(分析法移管、分析法同等性検証、ユースポイント検証)があります。弊社取扱のSievers オンラインTOC計を用いた製薬用水設備の最適化とプロセスバリデーションについてご紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

培養細胞を用いたオーダーメイド型の化粧品開発支援

|
株式会社エーセル 長尾 勇佑 |
|
【講演内容】
当社では、2011年の設立以来、化粧品、食品、製薬などの様々な分野において、培養細胞の使用を中心とした受託研究・支援サービスを展開しております。特に、ユーザーの試験目的に合わせたオーダーメイド型の試験に力を入れており、各種サンプルの有効性評価に対して幅広く対応しております。化粧品開発においては、2013年のEUにおける化粧品に対する動物実験の全面禁止から世界的にも動物実験を控える取り組みが強化され、培養細胞を用いたin vitro評価系の活用が求められております。本講演では、近年問合せの増えてきた老化に関する細胞試験や、そのほか初代培養ヒト細胞を用いた化粧品の有効性評価試験について紹介します。
【講演内容】
当社では、2011年の設立以来、化粧品、食品、製薬などの様々な分野において、培養細胞の使用を中心とした受託研究・支援サービスを展開しております。特に、ユーザーの試験目的に合わせたオーダーメイド型の試験に力を入れており、各種サンプルの有効性評価に対して幅広く対応しております。化粧品開発においては、2013年のEUにおける化粧品に対する動物実験の全面禁止から世界的にも動物実験を控える取り組みが強化され、培養細胞を用いたin vitro評価系の活用が求められております。本講演では、近年問合せの増えてきた老化に関する細胞試験や、そのほか初代培養ヒト細胞を用いた化粧品の有効性評価試験について紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

レオトライボテスタによる塗布剤の摩擦・粘弾性の総合評価

|
株式会社 レスカ 技術部門 古橋 翼 |
|
【講演内容】
塗布剤における肌触りの評価について、少なくともその流動性や摩擦抵抗を定量的に捉える必要がありますが、これまではレオロジー及びトライボロジーに特化した別々の装置を用いて個別に測定する必要があり、実用における摩擦や粘弾性の複雑な絡み合いを理解するのに課題がありました。
そこで弊社は、レオロジーとトライボロジーの評価を1台で可能とするレオトライボテスタを開発しました。弊社がこれまでぬれ性試験機で培った電磁平衡式センサと新開発のボイスコイルモーター式加振ステージを搭載することで実現しました。
本機は特に、薄い試料の測定に強みがあり、実際、粘着シートにおける厚み数µmの粘弾性の評価を製品状態そのままで測定できる唯一無二の装置となっています。従来の試験方法では肌に塗る厚みとは全くことなる量で物性を評価する必要がありましたが、レオトライボテスタは実態に近い量や厚みによる材料物性の評価結果を提供します。
本演題では実際に塗布剤を用いた測定事例を紹介しますので、ご興味のある方は是非ご公聴いただけますと幸いです。
【講演内容】
塗布剤における肌触りの評価について、少なくともその流動性や摩擦抵抗を定量的に捉える必要がありますが、これまではレオロジー及びトライボロジーに特化した別々の装置を用いて個別に測定する必要があり、実用における摩擦や粘弾性の複雑な絡み合いを理解するのに課題がありました。
そこで弊社は、レオロジーとトライボロジーの評価を1台で可能とするレオトライボテスタを開発しました。弊社がこれまでぬれ性試験機で培った電磁平衡式センサと新開発のボイスコイルモーター式加振ステージを搭載することで実現しました。
本機は特に、薄い試料の測定に強みがあり、実際、粘着シートにおける厚み数µmの粘弾性の評価を製品状態そのままで測定できる唯一無二の装置となっています。従来の試験方法では肌に塗る厚みとは全くことなる量で物性を評価する必要がありましたが、レオトライボテスタは実態に近い量や厚みによる材料物性の評価結果を提供します。
本演題では実際に塗布剤を用いた測定事例を紹介しますので、ご興味のある方は是非ご公聴いただけますと幸いです。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

製造業における技術継承の解決策!動画を活用した技術継承の在り方とは?

|
株式会社 オープンエイト 成田 立樹 |
|
【講演内容】
2036年までに労働人口の約3割にあたる1,300万人のベテラン社員が退職するといわれるなか、高い技術力を持つ企業であっても、その技術を十分に継承できているのは全体のわずか5%程度に過ぎません。貴社でも「今の技術や業務ノウハウを、5年後・10年後もきちんと引き継げるのか」と不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
特に、言葉では伝えにくい“貴社ならでは”の業務手順やノウハウの継承に課題を感じている企業も多く見受けられます。そこでおすすめしたいのが、AIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」です。どなたでも簡単に作業手順動画やマニュアル動画を作成できるこのクラウドサービスは「AI×情報流通」をコンセプトに、技術継承と業務効率化を同時に実現します。
本セミナーでは、人手不足の解消や生産性向上につながる“動画活用術”と、その成功事例をご紹介いたします。
【講演内容】
2036年までに労働人口の約3割にあたる1,300万人のベテラン社員が退職するといわれるなか、高い技術力を持つ企業であっても、その技術を十分に継承できているのは全体のわずか5%程度に過ぎません。貴社でも「今の技術や業務ノウハウを、5年後・10年後もきちんと引き継げるのか」と不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
特に、言葉では伝えにくい“貴社ならでは”の業務手順やノウハウの継承に課題を感じている企業も多く見受けられます。そこでおすすめしたいのが、AIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」です。どなたでも簡単に作業手順動画やマニュアル動画を作成できるこのクラウドサービスは「AI×情報流通」をコンセプトに、技術継承と業務効率化を同時に実現します。
本セミナーでは、人手不足の解消や生産性向上につながる“動画活用術”と、その成功事例をご紹介いたします。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

リアルタイムで"生きたまま"モニタリング 細胞生存性・毒性・アポトーシス

|
プロメガ(株) 営業部 ABCプロジェクト アプライドプロジェクト スペシャリスト 鈴木 康哲 |
|
【講演内容】
がん研究において、細胞の生存性、毒性、アポトーシスの評価は重要な研究項目であるが、従来の多くの細胞アッセイ試薬はエンドポイントで評価を行うため、得られるデータはスナップショットに過ぎず、重要な動的情報を見逃す恐れがある。一方で、リアルタイムで生存性を細胞接着を指標にして測定する手法なども存在するが、高価な機器やデバイスが必要となる。また、アポトーシスの評価はフローサイトメーターを使用することが一般的であるが、操作が煩雑なうえ、時系列データ取得のためには複数回の実験を行わなければならないのに加え、機器のコストも課題となっている。
そこで弊社では、細胞培地に添加するだけで、細胞の生育に影響を与えることなく、細胞生存性、毒性、アポトーシスをリアルタイムで測定できる試薬を開発した。これらの試薬は、プレートリーダーさえあれば、好きなタイミングで何度でも簡単に測定が可能である。
動的なデータを経時的にモニタリングし、簡便に正確な結果を得ることができる本ツールを活用することで、がん研究の進展を加速させる新しいアプローチを提供する。
【講演内容】
がん研究において、細胞の生存性、毒性、アポトーシスの評価は重要な研究項目であるが、従来の多くの細胞アッセイ試薬はエンドポイントで評価を行うため、得られるデータはスナップショットに過ぎず、重要な動的情報を見逃す恐れがある。一方で、リアルタイムで生存性を細胞接着を指標にして測定する手法なども存在するが、高価な機器やデバイスが必要となる。また、アポトーシスの評価はフローサイトメーターを使用することが一般的であるが、操作が煩雑なうえ、時系列データ取得のためには複数回の実験を行わなければならないのに加え、機器のコストも課題となっている。
そこで弊社では、細胞培地に添加するだけで、細胞の生育に影響を与えることなく、細胞生存性、毒性、アポトーシスをリアルタイムで測定できる試薬を開発した。これらの試薬は、プレートリーダーさえあれば、好きなタイミングで何度でも簡単に測定が可能である。
動的なデータを経時的にモニタリングし、簡便に正確な結果を得ることができる本ツールを活用することで、がん研究の進展を加速させる新しいアプローチを提供する。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

がん研究のためのフローサイトメトリー ~EV解析と好酸球ノンラベル検出~

|
ベックマン・コールター株式会社 ライフサイエンス フローサイトメトリー事業本部 事業本部長/博士 伊藤 俊行 |
|
【講演内容】
本セミナーでは、フローサイトメトリー技術に焦点をあて、がん研究分野で注目を集めている細胞から分泌される細胞外小胞(EV)のポピュレーション解析についてナノフローサイトメトリーの観点から紹介し、
次に近年腫瘍免疫研究において論文数が増加している好酸球についてのスペクトルフローサイトメトリーを用いたノンラベル検出の例を紹介します。
がん研究においてフローサイトメトリーは個々の細胞(粒子)を解析できる使い慣れた手法でありながら、最適な機器がなく、それ故に新しい改良が期待されてきました。
近年、EV研究においては、単一EVの表面マーカーを蛍光標識してポピュレーション解析をするために、より小さい粒子の検出を目指してナノフローサイトメトリーが開発されています。
これにより、これまでヘテロな集団のEVをバルクとして解析していましたが、個々のEVとして見ることが可能となりました。
また、細胞解析においては、より多くのマーカーの容易な解析と自家蛍光の除去などを目指してスペクトルフローサイトメトリーが開発され、コンベンショナルからスペクトルへ容易にアップグレードできるシステムへと進化しています。
さらに、スペクトラルフローサイトメーターは、マルチカラー化だけではなく、複数のレーザー光からの各側方散乱光(side scatter: SSC)の検出器を追加することで、新たな活用が可能となってきています。
本セミナーでは、単一細胞外小胞(EV)のポピュレーション解析についてナノフローサイトメトリーの観点からナノフローサイトメーターCytoFLEX nanoを用いた例を紹介し、
次に近年論文数が増加している好酸球についてスペクトルフローサイトメトリーCytoFLEX mosaicによるIRレーザーのSSCを用いたノンラベル検出の例を紹介します。
▼より詳しい製品説明をご希望の方は、以下のURLにアクセスください。
ナノフローサイトメーター CytoFLEX nano: https://www.beckman.jp/flow-cytometry/research-flow-cytometers/cytoflex-nano
スペクトルフローサイトメーターCytoFLEX mosaic:https://www.beckman.jp/flow-cytometry/research-flow-cytometers/cytoflex-mosaic
【講演内容】
本セミナーでは、フローサイトメトリー技術に焦点をあて、がん研究分野で注目を集めている細胞から分泌される細胞外小胞(EV)のポピュレーション解析についてナノフローサイトメトリーの観点から紹介し、
次に近年腫瘍免疫研究において論文数が増加している好酸球についてのスペクトルフローサイトメトリーを用いたノンラベル検出の例を紹介します。
がん研究においてフローサイトメトリーは個々の細胞(粒子)を解析できる使い慣れた手法でありながら、最適な機器がなく、それ故に新しい改良が期待されてきました。
近年、EV研究においては、単一EVの表面マーカーを蛍光標識してポピュレーション解析をするために、より小さい粒子の検出を目指してナノフローサイトメトリーが開発されています。
これにより、これまでヘテロな集団のEVをバルクとして解析していましたが、個々のEVとして見ることが可能となりました。
また、細胞解析においては、より多くのマーカーの容易な解析と自家蛍光の除去などを目指してスペクトルフローサイトメトリーが開発され、コンベンショナルからスペクトルへ容易にアップグレードできるシステムへと進化しています。
さらに、スペクトラルフローサイトメーターは、マルチカラー化だけではなく、複数のレーザー光からの各側方散乱光(side scatter: SSC)の検出器を追加することで、新たな活用が可能となってきています。
本セミナーでは、単一細胞外小胞(EV)のポピュレーション解析についてナノフローサイトメトリーの観点からナノフローサイトメーターCytoFLEX nanoを用いた例を紹介し、
次に近年論文数が増加している好酸球についてスペクトルフローサイトメトリーCytoFLEX mosaicによるIRレーザーのSSCを用いたノンラベル検出の例を紹介します。
▼より詳しい製品説明をご希望の方は、以下のURLにアクセスください。
ナノフローサイトメーター CytoFLEX nano: https://www.beckman.jp/flow-cytometry/research-flow-cytometers/cytoflex-nano
スペクトルフローサイトメーターCytoFLEX mosaic:https://www.beckman.jp/flow-cytometry/research-flow-cytometers/cytoflex-mosaic
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

MOEを活用したTPD分子のin silico設計支援

|
(株)モルシス ライフサイエンス部 神谷 謙太朗 |
|
【講演内容】
TPD(Targeted Protein Degradation)技術は、細胞内のタンパク質分解機構を利用してがんを含む各種疾患の原因タンパク質を選択的に分解する新たな創薬モダリティです。特に、従来の低分子医薬では標的化が困難であった転写因子や足場タンパク質など、“アンドラッガブル”とされてきたがん関連タンパク質をも標的とできることから、がん治療への応用が強く期待されています。
代表的なTPD分子として知られているPROTAC(PROteolysis TArgeting Chimera)や分子糊は、標的タンパク質とE3ユビキチンリガーゼを接近させることで、三元複合体を形成し、標的タンパク質のユビキチン化とプロテアソーム分解を誘導します。TPD分子の薬効発現には三元複合体の形成が必須であるため、この三元複合体の形成様式やその安定性を理解することは、合理的なTPD分子設計の鍵となります。
MOE(Molecular Operating Environment)は、分子モデリング、ドッキング計算、相互作用解析など、創薬研究に必要な一連のin silico手法を提供する統合計算化学システムです。本発表では、MOEを用いた三元複合体モデリング手法の概要とその適用事例を紹介します。
【講演内容】
TPD(Targeted Protein Degradation)技術は、細胞内のタンパク質分解機構を利用してがんを含む各種疾患の原因タンパク質を選択的に分解する新たな創薬モダリティです。特に、従来の低分子医薬では標的化が困難であった転写因子や足場タンパク質など、“アンドラッガブル”とされてきたがん関連タンパク質をも標的とできることから、がん治療への応用が強く期待されています。
代表的なTPD分子として知られているPROTAC(PROteolysis TArgeting Chimera)や分子糊は、標的タンパク質とE3ユビキチンリガーゼを接近させることで、三元複合体を形成し、標的タンパク質のユビキチン化とプロテアソーム分解を誘導します。TPD分子の薬効発現には三元複合体の形成が必須であるため、この三元複合体の形成様式やその安定性を理解することは、合理的なTPD分子設計の鍵となります。
MOE(Molecular Operating Environment)は、分子モデリング、ドッキング計算、相互作用解析など、創薬研究に必要な一連のin silico手法を提供する統合計算化学システムです。本発表では、MOEを用いた三元複合体モデリング手法の概要とその適用事例を紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

完全ヒト治療ADC抗体を60日で作成するプラットフォームテクノロジー

|
プレシジョン アンティボディー 林 順 |
|
【講演内容】
トランスジェニックマウスを免疫することにより、正常なヒトB細胞のコドン使用頻度とIgG可変領域のアミノ酸レパートリーを模倣した完全ヒト抗体を開発することで、モノクローナル抗体のキメラ化・ヒト化、およびヒト抗体ファージディスプレイライブラリーの使用に代わる新たな手法が生まれました。
Precision Antibody(PA)は、高親和性でエピトープリッチな完全ヒトモノクローナル抗体を60日間で多数のクローンを生産する独自の方法を開発しました。これにより、所望の特性を持つ抗体を100%の成功率で作製できます。開発期間を大幅に短縮しながら、機能性治療用抗体候補を多数開発することは、重要でかつ非常に望ましい技術です。PAの技術では、生製されたハイブリドーマクローンの約20%が抗原を認識します。PAは、中和抗体、内在化抗体、アゴニスト抗体など、多くの機能性抗体を単離することができました。
ここでは、Precision Antibody 社の完全ヒト抗体開発テクノロジーの特徴について、内在化抗体の選択と、固有の癌標的に対する抗体薬物複合体の開発のケーススタディとともに紹介します。
【講演内容】
トランスジェニックマウスを免疫することにより、正常なヒトB細胞のコドン使用頻度とIgG可変領域のアミノ酸レパートリーを模倣した完全ヒト抗体を開発することで、モノクローナル抗体のキメラ化・ヒト化、およびヒト抗体ファージディスプレイライブラリーの使用に代わる新たな手法が生まれました。
Precision Antibody(PA)は、高親和性でエピトープリッチな完全ヒトモノクローナル抗体を60日間で多数のクローンを生産する独自の方法を開発しました。これにより、所望の特性を持つ抗体を100%の成功率で作製できます。開発期間を大幅に短縮しながら、機能性治療用抗体候補を多数開発することは、重要でかつ非常に望ましい技術です。PAの技術では、生製されたハイブリドーマクローンの約20%が抗原を認識します。PAは、中和抗体、内在化抗体、アゴニスト抗体など、多くの機能性抗体を単離することができました。
ここでは、Precision Antibody 社の完全ヒト抗体開発テクノロジーの特徴について、内在化抗体の選択と、固有の癌標的に対する抗体薬物複合体の開発のケーススタディとともに紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

がん研究におけるラベルフリー細胞分離・解析の新たなソリューション提案

|
株式会社 SCREENホールディングス ライフサイエンス事業室 主任 伊藤 啓太 |
|
【講演内容】
ELESTA CROSSORTERは、革新的フィルター技術AMATAR(アマタ)を搭載したラベルフリー細胞分析分離システムです。マイクロ流路によるサイズ分離と、誘電泳動力を利用した電気特性分離を組み合わせた独自のCROSSORTERチップにより細胞を特異マーカーなしにラベルフリー分離をします。
Cell3iMager NXは培養プレート全体の顕微鏡観察と人工知能による解析が可能なイメージングシステムです。高速スキャンと優れた明視野撮像技術、DeepLearningによる画像解析により、非侵襲でハイスループットなラベルフリー解析を実現します。
がん研究における新たなソリューションとして、これら製品の活用例をご紹介いたします。
【講演内容】
ELESTA CROSSORTERは、革新的フィルター技術AMATAR(アマタ)を搭載したラベルフリー細胞分析分離システムです。マイクロ流路によるサイズ分離と、誘電泳動力を利用した電気特性分離を組み合わせた独自のCROSSORTERチップにより細胞を特異マーカーなしにラベルフリー分離をします。
Cell3iMager NXは培養プレート全体の顕微鏡観察と人工知能による解析が可能なイメージングシステムです。高速スキャンと優れた明視野撮像技術、DeepLearningによる画像解析により、非侵襲でハイスループットなラベルフリー解析を実現します。
がん研究における新たなソリューションとして、これら製品の活用例をご紹介いたします。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

未来のためのオートメーションロボット

|
フナコシ(株) 機器部 スペシャリスト 酒井 大吉 |
|
【講演内容】
イノベーションの可能性が無限大なオートメーションシステムです。
ハードウエアとソフトウエアの特徴を余すことなくご紹介させていただきます。
ソフトウエアにおける動作のプログラミング大きな特徴の一つで、初心者からプログラミングに精通したプロフェッショナルまでそれぞれに応じたプログラミングの手法を準備しています。
NGS, プロテオミクス、チェリーピッキング、核酸抽出、PCRなど様々なワークフローをイメージ通りに自動化できる未来のオートメーションシステムとなります。
【講演内容】
イノベーションの可能性が無限大なオートメーションシステムです。
ハードウエアとソフトウエアの特徴を余すことなくご紹介させていただきます。
ソフトウエアにおける動作のプログラミング大きな特徴の一つで、初心者からプログラミングに精通したプロフェッショナルまでそれぞれに応じたプログラミングの手法を準備しています。
NGS, プロテオミクス、チェリーピッキング、核酸抽出、PCRなど様々なワークフローをイメージ通りに自動化できる未来のオートメーションシステムとなります。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

バイオ・ラッドが提供するモダリティ横断的最先端がん研究ツールとその応用

|
バイオ・ラッドラボラトリーズ(株) シニアアプリケーションスペシャリスト 廣中 克典 |
|
【講演内容】
現在の創薬モダリティを取り巻く環境について概説しつつ、最先端がん研究におけるドロップレットデジタルPCR、微小粒子解析対応セルアナライザー、CTC解析システムといった、バイオ・ラッドが提供するモダリティ研究ツールや関連試薬について、興味深い実際の論文を交えつつ、様々なアプリケーション、ブレイクスルーやその可能性について具体例をご紹介します。
分子細胞生物学の発展により得られてきた、様々な生命現象や疾患、病態メカニズムの分子レベルでの膨大な知見に基づいて、現在では疾患や病態の発生機序に関与する分子を直接ターゲットとした分子標的薬の構想・開発が進んでいます。その中で、従来の低分子化合物を中心とする「結果的な効能のみに基づいた創薬」から、より「分子的な作用機序に基づいた創薬」への転換が進んできました。そのような流れの中で、がん治療の創薬モダリティは低分子化合物に加え、ペプチドを含む中分子医薬、抗体医薬といった新たなモダリティ開発の時代に突入し、抗体医薬品を中心とする分子標的薬の目覚ましい発展が進んでいます。
昨今では核酸医薬、遺伝子・細胞治療、再生医療、免疫細胞医薬、マイクロバイオーム医療など、これまでとは異なる観点から、多種多様な新規モダリティ開発が活発に行われています。さらに、モダリティ組合せなどの複雑化、低分子医薬品・中分子医薬品への再脚光化、AIの活用、in Silicoデザイン技術の応用など、高度な創薬研究トレンドへと日々進化しており、必要とされる研究ツールやその使用方法も高度化しています。
本セミナーでは、このような創薬モダリティ開発の中で重要な役割を担っている、バイオ・ラッドの研究ツールと関連試薬、最先端アプリケーションについてご紹介します。
【講演内容】
現在の創薬モダリティを取り巻く環境について概説しつつ、最先端がん研究におけるドロップレットデジタルPCR、微小粒子解析対応セルアナライザー、CTC解析システムといった、バイオ・ラッドが提供するモダリティ研究ツールや関連試薬について、興味深い実際の論文を交えつつ、様々なアプリケーション、ブレイクスルーやその可能性について具体例をご紹介します。
分子細胞生物学の発展により得られてきた、様々な生命現象や疾患、病態メカニズムの分子レベルでの膨大な知見に基づいて、現在では疾患や病態の発生機序に関与する分子を直接ターゲットとした分子標的薬の構想・開発が進んでいます。その中で、従来の低分子化合物を中心とする「結果的な効能のみに基づいた創薬」から、より「分子的な作用機序に基づいた創薬」への転換が進んできました。そのような流れの中で、がん治療の創薬モダリティは低分子化合物に加え、ペプチドを含む中分子医薬、抗体医薬といった新たなモダリティ開発の時代に突入し、抗体医薬品を中心とする分子標的薬の目覚ましい発展が進んでいます。
昨今では核酸医薬、遺伝子・細胞治療、再生医療、免疫細胞医薬、マイクロバイオーム医療など、これまでとは異なる観点から、多種多様な新規モダリティ開発が活発に行われています。さらに、モダリティ組合せなどの複雑化、低分子医薬品・中分子医薬品への再脚光化、AIの活用、in Silicoデザイン技術の応用など、高度な創薬研究トレンドへと日々進化しており、必要とされる研究ツールやその使用方法も高度化しています。
本セミナーでは、このような創薬モダリティ開発の中で重要な役割を担っている、バイオ・ラッドの研究ツールと関連試薬、最先端アプリケーションについてご紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

がん研究を推進するWuXi AppTecのプラットフォームのご紹介

|
株式会社 WuXi AppTec Japan 高崎真理 |
|
【講演内容】
WuXi AppTecは世界中で6000を超えるお客様の創薬研究を推進し、画期的な治療法を患者にいち早く提供できるように、創薬研究開発から商業製造まで幅広いサービスを提供しています。 当社の統合された創薬プラットフォームは、お客様のあらゆるニーズに応える最先端の技術と設備を有しており、高い費用対効果と効率的な課題解決能力によって、お客様の新薬創製の生産性向上に貢献します。
WuXi AppTecはお客様のオンコロジー分野での研究をサポートする専属のプラットフォームを有しております。弊社のサービス内容や実績についてご紹介差し上げます。
【講演内容】
WuXi AppTecは世界中で6000を超えるお客様の創薬研究を推進し、画期的な治療法を患者にいち早く提供できるように、創薬研究開発から商業製造まで幅広いサービスを提供しています。 当社の統合された創薬プラットフォームは、お客様のあらゆるニーズに応える最先端の技術と設備を有しており、高い費用対効果と効率的な課題解決能力によって、お客様の新薬創製の生産性向上に貢献します。
WuXi AppTecはお客様のオンコロジー分野での研究をサポートする専属のプラットフォームを有しております。弊社のサービス内容や実績についてご紹介差し上げます。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

がん研究を加速する組織分散自動化

|
Cytiva D&Gフィールドアプリケーションサイエンティスト 瀬古 ⼤暉 |
|
【講演内容】
本セミナーでは、Omics bundle – VIA Extractorを用い、限られたがん臨床検体を対象に最適な組織分散条件を確立する手法を紹介します。効率的かつ再現性の高い分散プロトコルにより、下流のオミクス解析精度向上を実現し、先端がん研究の発展を支援します。
【講演内容】
本セミナーでは、Omics bundle – VIA Extractorを用い、限られたがん臨床検体を対象に最適な組織分散条件を確立する手法を紹介します。効率的かつ再現性の高い分散プロトコルにより、下流のオミクス解析精度向上を実現し、先端がん研究の発展を支援します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

自動化によるリキッドバイオプシー研究生産性向上と規模化の可能性について

|
テカンジャパン(株) 営業企画部長 城戸 康政 |
|
【講演内容】
がん研究に関わる基礎研究や、その創薬に関わる理化学機器の技術進歩は目覚ましく、血液や血清などの生体試料をサンプルとしたゲノム解析や、高感度質量分析(MS)によるプロテオミクス解析を通して新たな知見が得られるようになってきました。このような中、分析の規模化や研究生産性向上のために、より多くの検体をいかに正確かつ同時に扱えるか?がキーとなってきています。一方で、生体試料をもとにした生化学実験のオートメーションには難所があり、サンプルの物性や個体差に基づいた様々な工夫が求められます。本プレゼンテーションでは、これまで経験した多数のプロジェクトから得た自動化の要点と、現在どのような作業が自動化できるようになっているのか?について、動画を中心に紹介いたします。
【講演内容】
がん研究に関わる基礎研究や、その創薬に関わる理化学機器の技術進歩は目覚ましく、血液や血清などの生体試料をサンプルとしたゲノム解析や、高感度質量分析(MS)によるプロテオミクス解析を通して新たな知見が得られるようになってきました。このような中、分析の規模化や研究生産性向上のために、より多くの検体をいかに正確かつ同時に扱えるか?がキーとなってきています。一方で、生体試料をもとにした生化学実験のオートメーションには難所があり、サンプルの物性や個体差に基づいた様々な工夫が求められます。本プレゼンテーションでは、これまで経験した多数のプロジェクトから得た自動化の要点と、現在どのような作業が自動化できるようになっているのか?について、動画を中心に紹介いたします。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

Beacon®がもたらすシングルセル機能解析によるがん治療創薬革命

|
ブルカージャパン株式会社 Bruker Cellular Analysis Sales Manager 太田 慶祐 |
|
【講演内容】
現代のがん治療開発は、個々のがん細胞の多様性(ヘテロジェニアリティ)を理解し、それに応じた精密な治療戦略を立てることが求められています。本講演では、この課題に応える革新的な技術として、ブルカー社が提供するBeaconオプトフルイディックシステムに着目し、本システムが現代のがん創薬研究、特に免疫療法の開発にどのように貢献しているかを詳説します。
Beaconシステムは、独自の光誘導技術と微細加工流路(ナノペンチャンバー)を組み合わせることで、数千から数万個の単一細胞を分離・培養し、それぞれの細胞が持つ機能(サイトカイン分泌、細胞殺傷能、抗体産生など)をリアルタイムかつハイスループットに解析することを可能にします。これにより、従来は見過ごされてきた希少な高機能細胞の同定や、薬剤に対する個々の細胞応答の精密な評価が実現します。
本講演ではまず、Beaconシステムの基本原理と、それがもたらすシングルセルレベルでの機能解析の優位性について解説します。次に、この技術ががん創薬研究において具体的にどのように活用されているか、以下の3つの主要な貢献ポイントに焦点を当てて説明します。
ーがん免疫療法の加速: 患者さん自身の免疫細胞(T細胞やB細胞)の中から、がん細胞を効果的に攻撃する能力を持つ細胞や、治療用抗体を産生する細胞を、その機能に基づいて迅速に選抜・単離する事例を紹介します。これにより、CAR-T細胞療法、TCR-T細胞療法、抗体医薬などの開発期間が大幅に短縮され、個別化医療の実現が近づきます。
ー機能と遺伝子情報の統合による新規ターゲット探索: Beaconシステムでは、機能解析を行った個々の細胞を回収し、その遺伝子情報を解析することが可能です。この「機能ゲノミクス」アプローチにより、特定の治療効果と関連する遺伝子シグネチャーを同定し、新たな創薬ターゲットやバイオマーカーの発見を促進します。
ーBeaconシステムがもたらすがん創薬のパラダイムシフトと今後の展望について議論し、シングルセル機能解析技術が切り拓くがん治療の未来像を提示します。本講演が、がん研究に携わる皆様の新たな視点や研究開発の一助となれば幸いです。
【講演内容】
現代のがん治療開発は、個々のがん細胞の多様性(ヘテロジェニアリティ)を理解し、それに応じた精密な治療戦略を立てることが求められています。本講演では、この課題に応える革新的な技術として、ブルカー社が提供するBeaconオプトフルイディックシステムに着目し、本システムが現代のがん創薬研究、特に免疫療法の開発にどのように貢献しているかを詳説します。
Beaconシステムは、独自の光誘導技術と微細加工流路(ナノペンチャンバー)を組み合わせることで、数千から数万個の単一細胞を分離・培養し、それぞれの細胞が持つ機能(サイトカイン分泌、細胞殺傷能、抗体産生など)をリアルタイムかつハイスループットに解析することを可能にします。これにより、従来は見過ごされてきた希少な高機能細胞の同定や、薬剤に対する個々の細胞応答の精密な評価が実現します。
本講演ではまず、Beaconシステムの基本原理と、それがもたらすシングルセルレベルでの機能解析の優位性について解説します。次に、この技術ががん創薬研究において具体的にどのように活用されているか、以下の3つの主要な貢献ポイントに焦点を当てて説明します。
ーがん免疫療法の加速: 患者さん自身の免疫細胞(T細胞やB細胞)の中から、がん細胞を効果的に攻撃する能力を持つ細胞や、治療用抗体を産生する細胞を、その機能に基づいて迅速に選抜・単離する事例を紹介します。これにより、CAR-T細胞療法、TCR-T細胞療法、抗体医薬などの開発期間が大幅に短縮され、個別化医療の実現が近づきます。
ー機能と遺伝子情報の統合による新規ターゲット探索: Beaconシステムでは、機能解析を行った個々の細胞を回収し、その遺伝子情報を解析することが可能です。この「機能ゲノミクス」アプローチにより、特定の治療効果と関連する遺伝子シグネチャーを同定し、新たな創薬ターゲットやバイオマーカーの発見を促進します。
ーBeaconシステムがもたらすがん創薬のパラダイムシフトと今後の展望について議論し、シングルセル機能解析技術が切り拓くがん治療の未来像を提示します。本講演が、がん研究に携わる皆様の新たな視点や研究開発の一助となれば幸いです。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

最新のがん研究に役立つ遺伝子解析技術と抗体作製サービス

|
ツイストバイオサイエンス 須藤 倫子 |
|
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

革新的空間解析 Curio Trekker ~true single-cell spatial omics~ のご紹介

|
タカラバイオ(株) 浅井 雄一郎 |
|
【講演内容】
がんのヘテロジェナイティやがん微小環境の解析において注目されている空間オミックス解析の新しいテクノロジーCurio Trekkerについてご紹介します。従来の空間トランスクリプトーム解析技術はシングルセルRNA-Seqデータと比べると、細胞当たりの検出遺伝子数が少ない、ATAC-Seqやレパトアと組み合わせて解析できない、セルセグメンテーションに頼らざるを得ない、など、シングルセルRNA-Seqとのギャップを感じることはないでしょうか?シングルセルデータをそのまま空間情報にコンバートする技術Curio Trekkerについてご紹介します。本セミナーでは基本原理や解析例などについてご紹介させて頂きます。
【講演内容】
がんのヘテロジェナイティやがん微小環境の解析において注目されている空間オミックス解析の新しいテクノロジーCurio Trekkerについてご紹介します。従来の空間トランスクリプトーム解析技術はシングルセルRNA-Seqデータと比べると、細胞当たりの検出遺伝子数が少ない、ATAC-Seqやレパトアと組み合わせて解析できない、セルセグメンテーションに頼らざるを得ない、など、シングルセルRNA-Seqとのギャップを感じることはないでしょうか?シングルセルデータをそのまま空間情報にコンバートする技術Curio Trekkerについてご紹介します。本セミナーでは基本原理や解析例などについてご紹介させて頂きます。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

再生医療等製品の製造所における、電子記録の導入と将来展望
|
|
帝人リジェネット(株) CMO事業グループ シニアマネージャー 望月 勢司 |
|
【講演内容】
遺伝子細胞治療(Cell & Gene Therapy:C>)は、近年著しい進展を遂げている最先端の治療法であり、がんをはじめとした難治性疾患に対して、患者ごとに最適化された治療手段として大きな注目を集めている。特に自己由来のC>製品においては、採取から加工・培養を経て体内へ再投与する一連の工程において高度な製造技術、クリーンな設備環境、厳密な品質保証が求められるとともに、製品が患者ごとに製造される。このため、全工程にわたるデータインテグリティとトレーサビリティの担保が不可欠となる。
一方で、C>は依然として発展途上の分野であり従来のバイオ医薬品に比べて標準化や規制枠組みが十分に整備されておらず、製造体制と同様に規制対応についても柔軟かつ継続的な見直しが求められている。
本発表では、再生医療等製品に特化したCDMOである帝人リジェネット株式会社と、製造実行システム(PAS-X MES)を提供するケルバー・ジャパン株式会社による協働のもとCAR-T細胞製品の製造における電子記録導入の取り組みと将来展望について紹介する。具体的には、製造工程の標準化、ヒューマンエラーの低減、厳格な品質管理の実現に向けた課題と解決策 を取り上げる。
CAR-T細胞製品の製造の課題として、バッチごとの工程ばらつき、同等性・同質性の評価、OOS(規格外試験結果)バッチの取り扱い、患者にとっての利益とリスクの判断材料となる製造時の重要工程パラメータの信頼性確保、CoI・CoC管理と患者プライバシーに関するデータ管理、多品種変量生産への対応、PIC/S GMP Annex-1に示されるCCS(汚染管理戦略)への対応などがある。
また、CDMOとしては、顧客の製品のプロセスや特徴に応じて、臨機応変にマスターバッチレコード(MBR)をデザインしていく必要がある。
上記の要件にあった製造実行システムであるPAS-X MESの特長を解説するとともに、帝人リジェネットにおける導入開始~運用開始までの検討事項、導入を進めるにあたっての留意事項について、導入を進めている経験を踏まえて解説する。
【講演内容】
遺伝子細胞治療(Cell & Gene Therapy:C>)は、近年著しい進展を遂げている最先端の治療法であり、がんをはじめとした難治性疾患に対して、患者ごとに最適化された治療手段として大きな注目を集めている。特に自己由来のC>製品においては、採取から加工・培養を経て体内へ再投与する一連の工程において高度な製造技術、クリーンな設備環境、厳密な品質保証が求められるとともに、製品が患者ごとに製造される。このため、全工程にわたるデータインテグリティとトレーサビリティの担保が不可欠となる。
一方で、C>は依然として発展途上の分野であり従来のバイオ医薬品に比べて標準化や規制枠組みが十分に整備されておらず、製造体制と同様に規制対応についても柔軟かつ継続的な見直しが求められている。
本発表では、再生医療等製品に特化したCDMOである帝人リジェネット株式会社と、製造実行システム(PAS-X MES)を提供するケルバー・ジャパン株式会社による協働のもとCAR-T細胞製品の製造における電子記録導入の取り組みと将来展望について紹介する。具体的には、製造工程の標準化、ヒューマンエラーの低減、厳格な品質管理の実現に向けた課題と解決策 を取り上げる。
CAR-T細胞製品の製造の課題として、バッチごとの工程ばらつき、同等性・同質性の評価、OOS(規格外試験結果)バッチの取り扱い、患者にとっての利益とリスクの判断材料となる製造時の重要工程パラメータの信頼性確保、CoI・CoC管理と患者プライバシーに関するデータ管理、多品種変量生産への対応、PIC/S GMP Annex-1に示されるCCS(汚染管理戦略)への対応などがある。
また、CDMOとしては、顧客の製品のプロセスや特徴に応じて、臨機応変にマスターバッチレコード(MBR)をデザインしていく必要がある。
上記の要件にあった製造実行システムであるPAS-X MESの特長を解説するとともに、帝人リジェネットにおける導入開始~運用開始までの検討事項、導入を進めるにあたっての留意事項について、導入を進めている経験を踏まえて解説する。

|
ケルバージャパン(株) Pharma Software コンサルタント 谷口 奈々美 |
|
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。
受講券の発行方法をお選びください。












