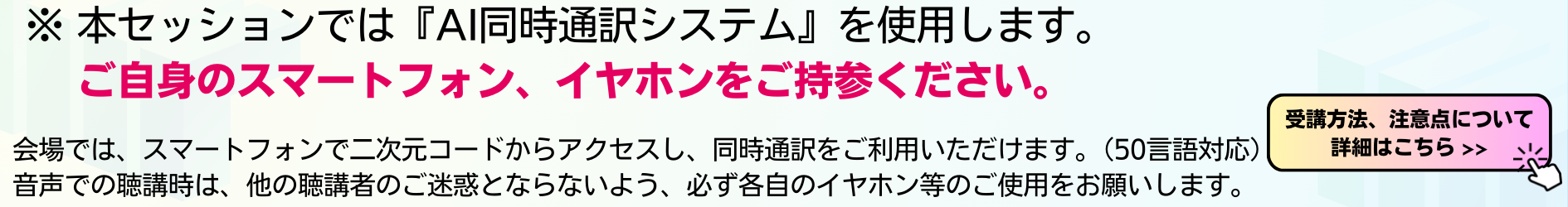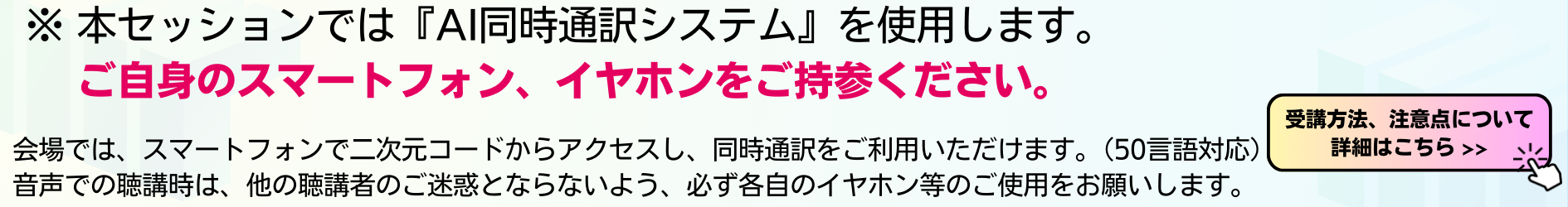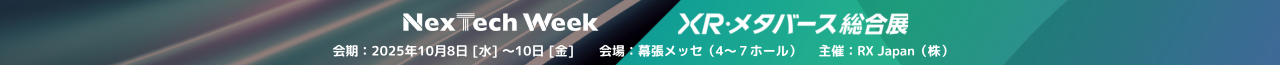
概要
★講演会場決定!来場前にこちらからご確認ください>>
今更聞けない生成AIを導入するコツ

|
(株)ヘッドウォータース 代表取締役 篠田 庸介 |

|


|
(株)エクサウィザーズ AIプラットフォーム事業本部 本部長 グループ執行役員 羽間 康至 |

|


|
(一社)AICX協会 代表理事 小澤 健祐 |
|
<講演概要>
生成AIを導入したいのに、「上司をどう説得する?」「セキュリティって大丈夫?」「どのモデルを選ぶ?」「何から始めれば?」と足踏みしていませんか? 本セッションでは、日本を代表する導入実績を誇る2社が登壇。事前に皆様から寄せられた質問にその場で答えるライブQ&A形式で、実際にどう導入を推進してきたのかをご紹介!今さら聞けないと思っている皆様に、生成AI導入を一歩踏み出す背中を押すセッションです。
<プロフィール>
●篠田 庸介
1989年にベンチャー企業の立ち上げに参画し、1999年にはEラーニング企業を設立。
2005年にヘッドウォータースを設立し、AIソリューション事業を展開。
2020年に東証マザーズ(現、東証グロース市場)上場を実現し、2024年にはマイクロソフト社の「AIイノベーション パートナー オブ ザ イヤー」を獲得。
AIエージェントなど先端技術の事業活用に注力し、エンタープライズ領域でのAI導入を先導している。
●羽間 康至
京都大学工学部物理工学科、情報学研究科修士卒。AIを活用した企業の実データ解析の研究に従事。A.T.カーニーに新卒入社し、事業戦略策定・事業開発支援、マーケティング戦略策定、業務改革、コスト削減、事業再生など幅広く経験。2018年にエクサウィザーズへ参画、医療ヘルスケア領域の事業責任者として事業を立ち上げ。2021年より執行役員、現在はグループ執行役員として多様な産業におけるAIプラットフォーム事業本部長を務める。健康・医療に特化した100%子会社のExaMD代表取締役社長。経済産業省 認知症イノベーションアライアンスWG委員、山口大学医学系研究科客員准教授
●小澤 健祐
「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。ディップが運営するAI専門メディア AINOW編集長を務める。
書籍「生成AI導入の教科書」。1000本以上のAI関連記事を執筆。一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員。
その他、AI領域で幅広く活動。生成AI教育事業を展開するCynthialyの顧問、日本最大のAI活用コミュニティ「SHIFT AI」のモデレーター&パートナーインフルエンサー、ディップの生成AI活用推進プロジェクト「dip AI Force」の推進、生成AIとエンターテイメントの融合を進めるAI Booster顧問、東大発AIスタートアップ Lightblue顧問、AIベンチャー Carnotの事業戦略なども務める。AIに関するトークセッションのモデレーターや登壇も多数。
<講演概要>
生成AIを導入したいのに、「上司をどう説得する?」「セキュリティって大丈夫?」「どのモデルを選ぶ?」「何から始めれば?」と足踏みしていませんか? 本セッションでは、日本を代表する導入実績を誇る2社が登壇。事前に皆様から寄せられた質問にその場で答えるライブQ&A形式で、実際にどう導入を推進してきたのかをご紹介!今さら聞けないと思っている皆様に、生成AI導入を一歩踏み出す背中を押すセッションです。
<プロフィール>
●篠田 庸介
1989年にベンチャー企業の立ち上げに参画し、1999年にはEラーニング企業を設立。
2005年にヘッドウォータースを設立し、AIソリューション事業を展開。
2020年に東証マザーズ(現、東証グロース市場)上場を実現し、2024年にはマイクロソフト社の「AIイノベーション パートナー オブ ザ イヤー」を獲得。
AIエージェントなど先端技術の事業活用に注力し、エンタープライズ領域でのAI導入を先導している。
●羽間 康至
京都大学工学部物理工学科、情報学研究科修士卒。AIを活用した企業の実データ解析の研究に従事。A.T.カーニーに新卒入社し、事業戦略策定・事業開発支援、マーケティング戦略策定、業務改革、コスト削減、事業再生など幅広く経験。2018年にエクサウィザーズへ参画、医療ヘルスケア領域の事業責任者として事業を立ち上げ。2021年より執行役員、現在はグループ執行役員として多様な産業におけるAIプラットフォーム事業本部長を務める。健康・医療に特化した100%子会社のExaMD代表取締役社長。経済産業省 認知症イノベーションアライアンスWG委員、山口大学医学系研究科客員准教授
●小澤 健祐
「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。ディップが運営するAI専門メディア AINOW編集長を務める。
書籍「生成AI導入の教科書」。1000本以上のAI関連記事を執筆。一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員。
その他、AI領域で幅広く活動。生成AI教育事業を展開するCynthialyの顧問、日本最大のAI活用コミュニティ「SHIFT AI」のモデレーター&パートナーインフルエンサー、ディップの生成AI活用推進プロジェクト「dip AI Force」の推進、生成AIとエンターテイメントの融合を進めるAI Booster顧問、東大発AIスタートアップ Lightblue顧問、AIベンチャー Carnotの事業戦略なども務める。AIに関するトークセッションのモデレーターや登壇も多数。
AI役員が経営会議に出席する時代 〜現場発の挑戦と組織カルチャーが実現した「AI×経営」〜

|
キリンホールディングス(株) 経営企画部 木村 弥由 |
|

|
キリンホールディングス(株) デジタルICT戦略部 主務 真弓 裕貴 |
|

|
(一社)AICX協会 代表理事 小澤 健祐 |
|
<講演概要>
「AI役員」が経営会議に参加!? Kirinが挑む意思決定の変革「CoreMate(コアメイト)」は、10年分の議事録や社内資料を分析し、人格化されたAIが議論を支援。現場の起案者と開発者が、経営層を動かした舞台裏をデモンストレーションと共にご紹介します。
<プロフィール>
●木村 弥由
2019年4月、キリンホールディングス株式会社に入社。
キリンビバレッジ株式会社にて、中四国エリアの自動販売機営業および量販営業を担当した後、営業企画にてエリアCSV戦略の立案・推進および広報業務に従事。
2023年4月より、キリンホールディングス株式会社 経営企画部にてガバナンス領域を担当。AI役員(CoreMate)を起案する。
●真弓 裕貴
2020年3月 キリンホールディングス株式会社 ブランド戦略部に中途入社。データサイエンティストとして営業部門と連携し、データドリブンな意思決定を推進。
2022年4月 株式会社ファンケル 通販営業本部へ出向。デジタルマーケティングを担当し、顧客データを活用した定期購入の解約防止モデルを開発。
2024年10月 キリンホールディングス株式会社 デジタルICT戦略部に帰任。データ・AI活用戦略を策定・実行し、今回AI役員「CoreMate」を開発。現在に至る。
●小澤 健祐
「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。ディップが運営するAI専門メディア AINOW編集長を務める。
書籍「生成AI導入の教科書」。1000本以上のAI関連記事を執筆。一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員。
その他、AI領域で幅広く活動。生成AI教育事業を展開するCynthialyの顧問、日本最大のAI活用コミュニティ「SHIFT AI」のモデレーター&パートナーインフルエンサー、ディップの生成AI活用推進プロジェクト「dip AI Force」の推進、生成AIとエンターテイメントの融合を進めるAI Booster顧問、東大発AIスタートアップ Lightblue顧問、AIベンチャー Carnotの事業戦略なども務める。AIに関するトークセッションのモデレーターや登壇も多数。
<講演概要>
「AI役員」が経営会議に参加!? Kirinが挑む意思決定の変革「CoreMate(コアメイト)」は、10年分の議事録や社内資料を分析し、人格化されたAIが議論を支援。現場の起案者と開発者が、経営層を動かした舞台裏をデモンストレーションと共にご紹介します。
<プロフィール>
●木村 弥由
2019年4月、キリンホールディングス株式会社に入社。
キリンビバレッジ株式会社にて、中四国エリアの自動販売機営業および量販営業を担当した後、営業企画にてエリアCSV戦略の立案・推進および広報業務に従事。
2023年4月より、キリンホールディングス株式会社 経営企画部にてガバナンス領域を担当。AI役員(CoreMate)を起案する。
●真弓 裕貴
2020年3月 キリンホールディングス株式会社 ブランド戦略部に中途入社。データサイエンティストとして営業部門と連携し、データドリブンな意思決定を推進。
2022年4月 株式会社ファンケル 通販営業本部へ出向。デジタルマーケティングを担当し、顧客データを活用した定期購入の解約防止モデルを開発。
2024年10月 キリンホールディングス株式会社 デジタルICT戦略部に帰任。データ・AI活用戦略を策定・実行し、今回AI役員「CoreMate」を開発。現在に至る。
●小澤 健祐
「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。ディップが運営するAI専門メディア AINOW編集長を務める。
書籍「生成AI導入の教科書」。1000本以上のAI関連記事を執筆。一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員。
その他、AI領域で幅広く活動。生成AI教育事業を展開するCynthialyの顧問、日本最大のAI活用コミュニティ「SHIFT AI」のモデレーター&パートナーインフルエンサー、ディップの生成AI活用推進プロジェクト「dip AI Force」の推進、生成AIとエンターテイメントの融合を進めるAI Booster顧問、東大発AIスタートアップ Lightblue顧問、AIベンチャー Carnotの事業戦略なども務める。AIに関するトークセッションのモデレーターや登壇も多数。
生成AI × 空間知能が導く未来のビジネスコミュニケーション

|
AVATAi Sdn Bhd CHAIRMAN/CEO Magomet (Maga) Malsagov |

|

<講演概要>
マレーシア発スタートアップAVATAiが提案する、最新の「生成AI」と革新的な「空間知能(Spatial Intelligence)」を融合した3Dアバター。わずか1枚の写真から瞬時にアバターやヒューマノイドを生成し、AIアシスタントや没入型プレゼンテーションを実現します。 ビジネスコミュニケーションを飛躍的に進化させる次世代技術。その可能性を、リアルタイム講演と参加者とのインタラクティブな質疑応答デモを通じて体感するセッションです。
<プロフィール>
食品・飲料(F&B)およびIT分野で20年以上の経験を持つ起業家・経営者です。ステビア原料のグローバル企業PureCircle Ltd.を創業し、持続可能な収益モデルを構築。同社はその後、フォーチューン500に選出される大手企業に買収されました。
現在は、3D生成AIを活用した技術開発を行うAVATAi Sdn Bhdを立ち上げ、革新的な取り組みに挑戦しています。
ハーバード・ビジネス・スクールを卒業し、複数の特許を取得。事業開発や戦略立案、業務改革に携わりながら、スイスを拠点に国内外の企業で取締役も務めています。
<講演概要>
マレーシア発スタートアップAVATAiが提案する、最新の「生成AI」と革新的な「空間知能(Spatial Intelligence)」を融合した3Dアバター。わずか1枚の写真から瞬時にアバターやヒューマノイドを生成し、AIアシスタントや没入型プレゼンテーションを実現します。 ビジネスコミュニケーションを飛躍的に進化させる次世代技術。その可能性を、リアルタイム講演と参加者とのインタラクティブな質疑応答デモを通じて体感するセッションです。
<プロフィール>
食品・飲料(F&B)およびIT分野で20年以上の経験を持つ起業家・経営者です。ステビア原料のグローバル企業PureCircle Ltd.を創業し、持続可能な収益モデルを構築。同社はその後、フォーチューン500に選出される大手企業に買収されました。
現在は、3D生成AIを活用した技術開発を行うAVATAi Sdn Bhdを立ち上げ、革新的な取り組みに挑戦しています。
ハーバード・ビジネス・スクールを卒業し、複数の特許を取得。事業開発や戦略立案、業務改革に携わりながら、スイスを拠点に国内外の企業で取締役も務めています。
Physical AIが拓く新しい未来

|
(一社)AIロボット協会 理事長 尾形 哲也 |
|
<講演概要>
近年、AIが環境や身体性を通じて自律的に知能を創発する“Physical AI”という新たなアプローチが、社会実装のフェーズへと近づいています。本講演では、このPhysical AIの社会実装をテーマに、ムーンショットでの研究成果やAIロボット協会(AIRoA)の活動をご紹介します。
<プロフィール>
1993年早稲田大学理工学部機械工学科卒業、1997年日本学術振興会特別研究員(DC2)、1999年早稲田大学理工学部助手、2001年理化学研究所脳科学総合研究センター研究員、2003年京都大学大学院情報学研究科講師、2005年同准教授を経て、2012年より早稲田大学理工学術院基幹理工学部表現工学科教授。博士(工学)。2009年-2015年JSTさきがけ領域研究員。また2017年より産業総合技術研究所人工知能研究センター特定フェロー。2013年から2014年日本ロボット学会理事。2016年から2018年人工知能学会理事などを歴任。2017年より日本ディープラーニング協会理事。2020年より早稲田大学次世代ロボット研究機構AIロボット研究所所長。2024年より国立情報学研究所大規模言語モデル研究開発センター客員教授。2025年よりAIロボット協会理事長。2025年よりJST CREST領域研究総括。深層学習、生成AIに代表される神経回路モデルとロボットシステムを用いた,認知ロボティクス研究,特に予測学習,模倣学習,マルチモーダル統合,言語学習,コミュニケーションなどの研究に従事.2021年IEEE ICRA2021 Best Paper Award In Cognitive Science、2023年文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)などを受賞。
<講演概要>
近年、AIが環境や身体性を通じて自律的に知能を創発する“Physical AI”という新たなアプローチが、社会実装のフェーズへと近づいています。本講演では、このPhysical AIの社会実装をテーマに、ムーンショットでの研究成果やAIロボット協会(AIRoA)の活動をご紹介します。
<プロフィール>
1993年早稲田大学理工学部機械工学科卒業、1997年日本学術振興会特別研究員(DC2)、1999年早稲田大学理工学部助手、2001年理化学研究所脳科学総合研究センター研究員、2003年京都大学大学院情報学研究科講師、2005年同准教授を経て、2012年より早稲田大学理工学術院基幹理工学部表現工学科教授。博士(工学)。2009年-2015年JSTさきがけ領域研究員。また2017年より産業総合技術研究所人工知能研究センター特定フェロー。2013年から2014年日本ロボット学会理事。2016年から2018年人工知能学会理事などを歴任。2017年より日本ディープラーニング協会理事。2020年より早稲田大学次世代ロボット研究機構AIロボット研究所所長。2024年より国立情報学研究所大規模言語モデル研究開発センター客員教授。2025年よりAIロボット協会理事長。2025年よりJST CREST領域研究総括。深層学習、生成AIに代表される神経回路モデルとロボットシステムを用いた,認知ロボティクス研究,特に予測学習,模倣学習,マルチモーダル統合,言語学習,コミュニケーションなどの研究に従事.2021年IEEE ICRA2021 Best Paper Award In Cognitive Science、2023年文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)などを受賞。
全社的な生成AI活用の効果と今後の戦略:パナソニック コネクトが切り拓く業務の未来

|
パナソニック コネクト(株) 執行役員 VP CIO 兼 IT・デジタル推進本部マネージングダイレクター 河野 昭彦 |

|

<講演概要>
2023年2月、パナソニック コネクトはChatGPTをベースとした自社向けAIアシスタントサービス「ConnectAI」を全社展開しました。日本の大企業の中でも、なぜいち早く導入を決断し、生成AIの企業内利用の先駆者となれたのか。そして、テクノロジーのみならず、組織として従業員を巻き込み、生成AIを活用する文化を醸成してきた実践的な取り組みと進化する戦略をご紹介します。
<プロフィール>
1992年松下電器産業に入社。空調事業の情報システム部門に社内SEとしてシステム開発に従事。その後、コーポレートIT部門へ異動し、グローバルSCM推進、全社データ標準化推進、データ分析部門の立ち上げ、事業部門のIT責任者を経験。2022年4月より、パナソニック コネクトのCIOを務める。同社、IT・デジタル推進本部 マネージングダイレクターを兼務。
<講演概要>
2023年2月、パナソニック コネクトはChatGPTをベースとした自社向けAIアシスタントサービス「ConnectAI」を全社展開しました。日本の大企業の中でも、なぜいち早く導入を決断し、生成AIの企業内利用の先駆者となれたのか。そして、テクノロジーのみならず、組織として従業員を巻き込み、生成AIを活用する文化を醸成してきた実践的な取り組みと進化する戦略をご紹介します。
<プロフィール>
1992年松下電器産業に入社。空調事業の情報システム部門に社内SEとしてシステム開発に従事。その後、コーポレートIT部門へ異動し、グローバルSCM推進、全社データ標準化推進、データ分析部門の立ち上げ、事業部門のIT責任者を経験。2022年4月より、パナソニック コネクトのCIOを務める。同社、IT・デジタル推進本部 マネージングダイレクターを兼務。
AI活用の“格差”に終止符を ~富士フイルムビジネスイノベーションのAI戦略~

|
富士フイルムビジネスイノベーション(株) 取締役・常務執行役員 チーフ・ テクニカル・オフィサー(CTO) 鍋田 敏之 |

|

<講演概要>
生産性向上の切り札として企業への導入が期待されているAI。しかし、現実には企業内に蓄積されるデータの約9割が、AIによる活用のハードルが高い「非構造化データ」です。この”企業の知”を生かす鍵こそ、データの構造化にあります。本講演では、データの現状と課題、そしてAIが最大の効果を発揮するための技術プロセスや事業成長への具体的アプローチについて解説します。
<プロフィール>
1994年に富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム)に入社。足柄研究所での写真フィルム感材の開発を経て、2006年からはデジタルX線機器の開発に従事。2017年、医療ITソリューション部長として医療AI技術ブランド「REiLI」を立ち上げ、2018年にはメディカルシステム開発センター長を兼任し、医療IT・AIを核とした高付加価値の医療機器・サービス開発を牽引。2019年にはICT戦略推進室副室長を兼任し、全事業における製品DX戦略の加速を推進。2022年に執行役員に就任。2024年より富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の取締役・常務執行役員 CTOとして技術・開発全般を管掌。医療領域で培った経験を基盤にAIによる成長戦略を主導する。
<講演概要>
生産性向上の切り札として企業への導入が期待されているAI。しかし、現実には企業内に蓄積されるデータの約9割が、AIによる活用のハードルが高い「非構造化データ」です。この”企業の知”を生かす鍵こそ、データの構造化にあります。本講演では、データの現状と課題、そしてAIが最大の効果を発揮するための技術プロセスや事業成長への具体的アプローチについて解説します。
<プロフィール>
1994年に富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム)に入社。足柄研究所での写真フィルム感材の開発を経て、2006年からはデジタルX線機器の開発に従事。2017年、医療ITソリューション部長として医療AI技術ブランド「REiLI」を立ち上げ、2018年にはメディカルシステム開発センター長を兼任し、医療IT・AIを核とした高付加価値の医療機器・サービス開発を牽引。2019年にはICT戦略推進室副室長を兼任し、全事業における製品DX戦略の加速を推進。2022年に執行役員に就任。2024年より富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の取締役・常務執行役員 CTOとして技術・開発全般を管掌。医療領域で培った経験を基盤にAIによる成長戦略を主導する。
深津式プロンプト × 弁護士の視点 ─AI活用の最前線に潜む法的リスク

|
(一社)日本ディープラーニング協会 有識者会員・GR統括 阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー弁護士 柴山 吉報 |

|


|
(一社)日本ディープラーニング協会 理事 富士ソフト(株) 常務執行役員 技術管理、セキュリティ担当 八木 聡之 |

|


|
(株)THE GUILD 代表取締役 深津 貴之 |
|
<講演概要>
生成AIの活用が広がる一方で、企業には法的リスクやガバナンスの課題が立ちはだかります。本セッションでは「深津式プロンプト」で知られる深津氏のAI活用術について、弁護士が実務の視点からその利点と落とし穴を検証。企業が安心してAIを活用するための実践的ヒントを探ります。
<プロフィール>
●柴山 吉報
弁護士・機械学習エンジニア(JDLA・E資格)。
生成AI利用時のリスク対応、AI開発の契約及び紛争対応、AIを活用した新規事業の立ち上げ、ルールメイキング等を中心に扱う。
総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン」検討会委員(2024年~)、AI法研究会政策提言部会 部会長。
著書に「Q&A AIの法務と倫理」(共著・中央経済社)、「ディープラーニングG検定(ジェネラリスト) 法律・倫理テキスト」(共著・技術評論社)等。
●八木 聡之
2000年、新卒で富士ソフト株式会社に入社。
入社以降、メインフレーム、オープン系、クラウドコンピューティングとIT業界の歴史を辿るように様々な技術での開発プロジェクトに ITアーキテクトとして従事。
2017年以降は主にAIを主戦場とし、日本のAI活用促進に関わる活動に注力している。
近年はCTO兼DX担当役員という肩書を活かし、生成AIに負けない人間になろう。をキーワードとした、『Generative AI Native人材』の育成に力を入れて、 様々な場所で講演活動などを実施している。
●深津 貴之
サービスデザイナー。ユーザーの行動設計や体験設計を主軸に、新規事業の企画やグロース、新技術の導入などの伴走を行う。2009年 株式会社Art&Mobile、2013年 クリエイティブファームTHE GUILDを設立。現在はnote株式会社や弁護士ドットコム株式会社のCXOを務めるほか、横須賀市のAI戦略アドバイザーなど、領域を超えた事業アドバイザリーを行う。執筆、講演などでも精力的に活動。
<講演概要>
生成AIの活用が広がる一方で、企業には法的リスクやガバナンスの課題が立ちはだかります。本セッションでは「深津式プロンプト」で知られる深津氏のAI活用術について、弁護士が実務の視点からその利点と落とし穴を検証。企業が安心してAIを活用するための実践的ヒントを探ります。
<プロフィール>
●柴山 吉報
弁護士・機械学習エンジニア(JDLA・E資格)。
生成AI利用時のリスク対応、AI開発の契約及び紛争対応、AIを活用した新規事業の立ち上げ、ルールメイキング等を中心に扱う。
総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン」検討会委員(2024年~)、AI法研究会政策提言部会 部会長。
著書に「Q&A AIの法務と倫理」(共著・中央経済社)、「ディープラーニングG検定(ジェネラリスト) 法律・倫理テキスト」(共著・技術評論社)等。
●八木 聡之
2000年、新卒で富士ソフト株式会社に入社。
入社以降、メインフレーム、オープン系、クラウドコンピューティングとIT業界の歴史を辿るように様々な技術での開発プロジェクトに ITアーキテクトとして従事。
2017年以降は主にAIを主戦場とし、日本のAI活用促進に関わる活動に注力している。
近年はCTO兼DX担当役員という肩書を活かし、生成AIに負けない人間になろう。をキーワードとした、『Generative AI Native人材』の育成に力を入れて、 様々な場所で講演活動などを実施している。
●深津 貴之
サービスデザイナー。ユーザーの行動設計や体験設計を主軸に、新規事業の企画やグロース、新技術の導入などの伴走を行う。2009年 株式会社Art&Mobile、2013年 クリエイティブファームTHE GUILDを設立。現在はnote株式会社や弁護士ドットコム株式会社のCXOを務めるほか、横須賀市のAI戦略アドバイザーなど、領域を超えた事業アドバイザリーを行う。執筆、講演などでも精力的に活動。
失敗しないAI導入 ─ FDE (Forward Deployed Engineer)、Vibe Coding、そしてLLM活用へ

|
(株)I.Y.P Consulting 代表取締役CEO 崔 晉豪 |

|


|
(株)I.Y.P Consulting 執行役員CTO 大澤 昇平 |

|

<講演概要>
生成AIの急速な普及により、多くの企業が業務改善・競争力強化を目的にAI導入を進めています。しかし、ノウハウ獲得に時間を要し運用に至らず、成果が出にくいケースも少なくありません。本講演では、技術と現場を繋ぐ存在として、AIを単なる「実証実験」に終わらせず、組織に根付く成果へ導くAI人材であるFDEを取り上げ、プロジェクトを成功に導くマネジメント法を解説します。※本講演は、同社独自LLM/SLMの初公表を含みます。
<プロフィール>
●崔 晉豪
韓国・高麗大学経営情報学科卒業。新卒で日本IBMに入社し、金融機関向けシステム開発に従事。その後、アクセンチュア、デロイトトーマツコンサルティングにて、Salesforceを活用した業務改革やDX推進プロジェクトを多数リード。戦略立案から業務設計、システム導入、定着化支援まで一貫したプロジェクト推進を強みとする。2023年に株式会社I.Y.P Consultingを創業し、「End-to-End伴走型支援」を掲げ、設立から約2年で複数業界・業種にわたる案件を展開。若手人材が早期に裁量を持ち成長できる組織文化を重視し、先端技術と人材育成の両立を目指す。
●大澤 昇平
東京大学大学院工学系研究科博士課程修了(工学博士)。生成AI・マルチエージェントシステム・ブロックチェーン分野における研究開発で国内外に実績を持つ。IBM東京基礎研究所にてブロックチェーン基盤の研究開発に従事し社長賞を受賞。東京大学大学院情報学環准教授として「AI2.0」概念を提唱し教育に従事。AIベンチャー創業や大規模プロジェクトの技術統括を歴任し、商社系上場企業の執行役員CTO・経営企画本部長を経て現職。
<講演概要>
生成AIの急速な普及により、多くの企業が業務改善・競争力強化を目的にAI導入を進めています。しかし、ノウハウ獲得に時間を要し運用に至らず、成果が出にくいケースも少なくありません。本講演では、技術と現場を繋ぐ存在として、AIを単なる「実証実験」に終わらせず、組織に根付く成果へ導くAI人材であるFDEを取り上げ、プロジェクトを成功に導くマネジメント法を解説します。※本講演は、同社独自LLM/SLMの初公表を含みます。
<プロフィール>
●崔 晉豪
韓国・高麗大学経営情報学科卒業。新卒で日本IBMに入社し、金融機関向けシステム開発に従事。その後、アクセンチュア、デロイトトーマツコンサルティングにて、Salesforceを活用した業務改革やDX推進プロジェクトを多数リード。戦略立案から業務設計、システム導入、定着化支援まで一貫したプロジェクト推進を強みとする。2023年に株式会社I.Y.P Consultingを創業し、「End-to-End伴走型支援」を掲げ、設立から約2年で複数業界・業種にわたる案件を展開。若手人材が早期に裁量を持ち成長できる組織文化を重視し、先端技術と人材育成の両立を目指す。
●大澤 昇平
東京大学大学院工学系研究科博士課程修了(工学博士)。生成AI・マルチエージェントシステム・ブロックチェーン分野における研究開発で国内外に実績を持つ。IBM東京基礎研究所にてブロックチェーン基盤の研究開発に従事し社長賞を受賞。東京大学大学院情報学環准教授として「AI2.0」概念を提唱し教育に従事。AIベンチャー創業や大規模プロジェクトの技術統括を歴任し、商社系上場企業の執行役員CTO・経営企画本部長を経て現職。
人とAIが共生する社会へ。AI時代に問われる人間らしさとは

|
Tools for Humanity 日本代表 牧野 友衛 |

|


|
(一社)生成AI活用普及協会 理事/ 東京学芸大学 大学院 教育学研究科 教授 小宮山 利恵子 |
|

|
(一社)生成AI活用普及協会(GUGA) 業務執行理事 兼 事務局長 小村 亮 |
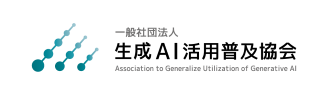
|
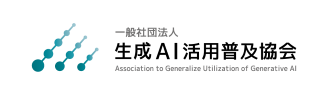
<講演概要>
生成AIを起点に、AIエージェント、フィジカルAIへと期待が高まる昨今。AIの普及が進んだ先に、どのような未来が訪れるのでしょうか。今回は、サム・アルトマン氏が共同創設したプロジェクト「World」を推進するTools for Humanity 日本代表の牧野氏と、生成AI活用普及協会 理事の小宮山氏が徹底議論。AIの可能性とリスク、人間らしさの重要性など、人とAIの共生に向けた示唆を探ります。
<プロフィール>
●牧野 友衛
2024年9月より現職。Worldプロジェクトを支援するテクノロジー企業であるTools For Humanityの日本の事業を統括する。
Tools for Humanity入社以前は、GoogleやYouTube、Twitterの事業責任者や、トリップアドバイザー、Activision Blizzard Japanの代表職を歴任。
米国テクノロジー企業で20年以上の勤務経験でイノベーション、事業戦略、リーダーシップの実績から、政府や自治体の有識者や専門委員も務める。
●小宮山 利恵子
1977年東京都生まれ。早稲田大学大学院修了後、衆議院にて国会議員秘書。その後、株式会社ベネッセコーポレーションにて会長秘書等を経て、2015年よりリクルート教育研究所所長。東京学芸大学大学院教授を兼務。教育とテクノロジー、アントレプレナーシップ(起業家精神)領域を探究。AI時代における「人間にしかできない力」をテーマに、現場体験や五感、身体知を重視した教育実践を推進。「鮨 銀座おのでら」で修行、「鮨 銀座おのでら 鮨アカデミー」寿司職人コース修了。狩猟免許も取得し、栃木県や鹿児島県等で活動中。近著に『好奇心を学びに変える「なぜ?どうして?」の伸ばし方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2025年)。
●小村 亮
2017年、株式会社オプトに新卒入社。PRを主軸にコミュニケーションデザインやブランドクリエイティブなどブランディング領域のプランナーとして従事。株式会社デジタルホールディングスへの出向を経て、フリーランスとして独立し、複数社の経営に携わる。
生成AIの台頭を受け、あらゆる産業や職業におけるゲームチェンジの可能性を実感するとともに、AIとの健全な付き合い方を普及する必要性を実感し、生成AI活用普及協会の立ち上げに参画。広報責任者、事務局次長を経て現職。
<講演概要>
生成AIを起点に、AIエージェント、フィジカルAIへと期待が高まる昨今。AIの普及が進んだ先に、どのような未来が訪れるのでしょうか。今回は、サム・アルトマン氏が共同創設したプロジェクト「World」を推進するTools for Humanity 日本代表の牧野氏と、生成AI活用普及協会 理事の小宮山氏が徹底議論。AIの可能性とリスク、人間らしさの重要性など、人とAIの共生に向けた示唆を探ります。
<プロフィール>
●牧野 友衛
2024年9月より現職。Worldプロジェクトを支援するテクノロジー企業であるTools For Humanityの日本の事業を統括する。
Tools for Humanity入社以前は、GoogleやYouTube、Twitterの事業責任者や、トリップアドバイザー、Activision Blizzard Japanの代表職を歴任。
米国テクノロジー企業で20年以上の勤務経験でイノベーション、事業戦略、リーダーシップの実績から、政府や自治体の有識者や専門委員も務める。
●小宮山 利恵子
1977年東京都生まれ。早稲田大学大学院修了後、衆議院にて国会議員秘書。その後、株式会社ベネッセコーポレーションにて会長秘書等を経て、2015年よりリクルート教育研究所所長。東京学芸大学大学院教授を兼務。教育とテクノロジー、アントレプレナーシップ(起業家精神)領域を探究。AI時代における「人間にしかできない力」をテーマに、現場体験や五感、身体知を重視した教育実践を推進。「鮨 銀座おのでら」で修行、「鮨 銀座おのでら 鮨アカデミー」寿司職人コース修了。狩猟免許も取得し、栃木県や鹿児島県等で活動中。近著に『好奇心を学びに変える「なぜ?どうして?」の伸ばし方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2025年)。
●小村 亮
2017年、株式会社オプトに新卒入社。PRを主軸にコミュニケーションデザインやブランドクリエイティブなどブランディング領域のプランナーとして従事。株式会社デジタルホールディングスへの出向を経て、フリーランスとして独立し、複数社の経営に携わる。
生成AIの台頭を受け、あらゆる産業や職業におけるゲームチェンジの可能性を実感するとともに、AIとの健全な付き合い方を普及する必要性を実感し、生成AI活用普及協会の立ち上げに参画。広報責任者、事務局次長を経て現職。
未来型エンタープライズへの進化 ―AIポストトレーニング活用で実現する現場改革

|
LB AI ジャパン(株) 代表取締役 橋場 芊 |

|


|
LBAI Technology Company 工学博士 シニアアドバイザー 王 謙 |
|
<講演概要>
AIによる企業変革の最前線とは?本講演では、LBAIが提案する最新AIソリューションの全貌と、KONEエレベーターで実証された「設計期間短縮・部品調達の最適化・ナレッジ変革」を同時に叶える3つのAIソリューションを紹介します。現場改善からコスト削減、そして新たな事業創出まで、企業競争力を高める最新事例を詳しく解説します。https://blog.lbai.ai/archives/LBAI%20confirms%20attendance%20at%20nextech-week
<プロフィール>
●橋場 芊
中央大学法学研究科博士前期課程卒業。知的財産権・企業秘密の国際私法を研究後、日立グループで13年間グローバル事業企画や海外拠点立上げを歴任し、LBAI日本法人を設立。LBAI事業ではAI大規模モデルのカスタマイズ・プライベート化を推進し、AIエージェントによる業務自動化・データ主権確保・GDPR/CCPA準拠の実績を持つ。製造・医療・金融など各業界で導入企業の生産性向上や運用コスト削減を牽引し、企業DX・AI化の最前線を熟知。展示会では、豊富な事例・最新デモを交え、AI原生ビジネスモデルの要点と成果を圧倒的な専門知見で解説します。
●王 謙
工学博士。LBAIテクノロジーカンパニーにてシニアアドバイザーを務めておられ、北米市場責任者および投資責任者も兼任されております。筑波大学にて工学博士号をご取得後、東京工業大学の客員研究員、日本工業技術院電子技術総合研究所(ETL)の特別研究員として、先端技術の研究に従事されました。 その後、NEC(中国)において事業企画部部長および移動通信本部部長を歴任され、事業推進とイノベーションの最前線でご活躍。さらに、ベンチャーキャピタル会社Transpac Capitalの中国地区総代表として、幅広い投資活動を展開され、多岐にわたる投資および経営のご経験をお持ちです。
<講演概要>
AIによる企業変革の最前線とは?本講演では、LBAIが提案する最新AIソリューションの全貌と、KONEエレベーターで実証された「設計期間短縮・部品調達の最適化・ナレッジ変革」を同時に叶える3つのAIソリューションを紹介します。現場改善からコスト削減、そして新たな事業創出まで、企業競争力を高める最新事例を詳しく解説します。https://blog.lbai.ai/archives/LBAI%20confirms%20attendance%20at%20nextech-week
<プロフィール>
●橋場 芊
中央大学法学研究科博士前期課程卒業。知的財産権・企業秘密の国際私法を研究後、日立グループで13年間グローバル事業企画や海外拠点立上げを歴任し、LBAI日本法人を設立。LBAI事業ではAI大規模モデルのカスタマイズ・プライベート化を推進し、AIエージェントによる業務自動化・データ主権確保・GDPR/CCPA準拠の実績を持つ。製造・医療・金融など各業界で導入企業の生産性向上や運用コスト削減を牽引し、企業DX・AI化の最前線を熟知。展示会では、豊富な事例・最新デモを交え、AI原生ビジネスモデルの要点と成果を圧倒的な専門知見で解説します。
●王 謙
工学博士。LBAIテクノロジーカンパニーにてシニアアドバイザーを務めておられ、北米市場責任者および投資責任者も兼任されております。筑波大学にて工学博士号をご取得後、東京工業大学の客員研究員、日本工業技術院電子技術総合研究所(ETL)の特別研究員として、先端技術の研究に従事されました。 その後、NEC(中国)において事業企画部部長および移動通信本部部長を歴任され、事業推進とイノベーションの最前線でご活躍。さらに、ベンチャーキャピタル会社Transpac Capitalの中国地区総代表として、幅広い投資活動を展開され、多岐にわたる投資および経営のご経験をお持ちです。
生成AI経営戦略論|管理職の意識改革を進める生成AI導入とは

|
日清食品ホールディングス(株) 執行役員 CIO グループ情報責任者 成田 敏博 |

|


|
日本航空(株) システムマネジメント部 部長 福島 雅哉 |
|

|
(一社)AICX協会 代表理事 小澤 健祐 |
|
<講演概要>
AIエージェント・生成AIはもはや業務効率化の道具にとどまらず、経営戦略・人事戦略・デジタル戦略を横断して企業経営そのものに影響を及ぼしています。
いま問われているのは技術導入ではなく、経営層・管理職がどう意識を変え、組織を導いていくかです。
本セッションでは先進企業の実践と未来構想をもとに、生成AI時代に求められるリーダーシップと経営のあり方を議論します。
<プロフィール>
●成田 敏博
1999年、新卒でアクセンチュアに入社。 公共サービス本部にて業務プロセス改革、基幹業務システム構築などに従事。
2012年、ディー・エヌ・エー入社。グローバル基幹業務システム構築プロジェクトに参画後、IT戦略部長として全社システム企画・構築・運用全般を統括。
その後、メルカリ IT戦略室長を経て、2019年12月に日清食品ホールディングスに入社。2022年4月より現職。
●福島 雅哉
1991年に日本航空に入社し情報システム部門において、インターネットの発展や企業システムのクラウド化など変遷を経験してきました。2018年以降は情報セキュリティを担当し、2023年以降は社内の生成AI活用推進も担当しています。
●小澤 健祐
「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。ディップが運営するAI専門メディア AINOW編集長を務める。
書籍「生成AI導入の教科書」。1000本以上のAI関連記事を執筆。一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員。
その他、AI領域で幅広く活動。生成AI教育事業を展開するCynthialyの顧問、日本最大のAI活用コミュニティ「SHIFT AI」のモデレーター&パートナーインフルエンサー、ディップの生成AI活用推進プロジェクト「dip AI Force」の推進、生成AIとエンターテイメントの融合を進めるAI Booster顧問、東大発AIスタートアップ Lightblue顧問、AIベンチャー Carnotの事業戦略なども務める。AIに関するトークセッションのモデレーターや登壇も多数。
<講演概要>
AIエージェント・生成AIはもはや業務効率化の道具にとどまらず、経営戦略・人事戦略・デジタル戦略を横断して企業経営そのものに影響を及ぼしています。
いま問われているのは技術導入ではなく、経営層・管理職がどう意識を変え、組織を導いていくかです。
本セッションでは先進企業の実践と未来構想をもとに、生成AI時代に求められるリーダーシップと経営のあり方を議論します。
<プロフィール>
●成田 敏博
1999年、新卒でアクセンチュアに入社。 公共サービス本部にて業務プロセス改革、基幹業務システム構築などに従事。
2012年、ディー・エヌ・エー入社。グローバル基幹業務システム構築プロジェクトに参画後、IT戦略部長として全社システム企画・構築・運用全般を統括。
その後、メルカリ IT戦略室長を経て、2019年12月に日清食品ホールディングスに入社。2022年4月より現職。
●福島 雅哉
1991年に日本航空に入社し情報システム部門において、インターネットの発展や企業システムのクラウド化など変遷を経験してきました。2018年以降は情報セキュリティを担当し、2023年以降は社内の生成AI活用推進も担当しています。
●小澤 健祐
「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。ディップが運営するAI専門メディア AINOW編集長を務める。
書籍「生成AI導入の教科書」。1000本以上のAI関連記事を執筆。一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員。
その他、AI領域で幅広く活動。生成AI教育事業を展開するCynthialyの顧問、日本最大のAI活用コミュニティ「SHIFT AI」のモデレーター&パートナーインフルエンサー、ディップの生成AI活用推進プロジェクト「dip AI Force」の推進、生成AIとエンターテイメントの融合を進めるAI Booster顧問、東大発AIスタートアップ Lightblue顧問、AIベンチャー Carnotの事業戦略なども務める。AIに関するトークセッションのモデレーターや登壇も多数。
Quantum Economy ~量子で実現する未来社会~

|
IonQ Managing Director Noam Zakay |
|

|
IonQ VP of WW Sales Mark Solomon |
|
<講演概要>
「量子経済」とは、量子コンピュータや量子通信、量子センサーといった技術を使って生まれる新しい産業や仕事、投資、制度などをまとめて表す言葉です。官民学における取り組みをはじめ研究開発から社会実装までバリューチェーン全体が含まれます。本セッションでは、量子経済発展の可能性と、金融やサイバーセキュリティ、製造、医療、物流、教育など、私たちの生活や社会や産業へのインパクトについて語ります。
<プロフィール>
●Noam Zakay
IonQの欧州・中東・アフリカおよび日本事業を統括。豊富な専門知識を活かし、IonQの最先端量子技術の商業化と革新的なパートナーシップの構築を主導している。30年にわたるキャリアの中で、同氏は複数のリーディング企業で要職を務め、新たなビジネス機会の創出、戦略的ミッションの策定、革新的な戦略の実行に尽力してきた。卓越した交渉力と実績が評価され、INSEADより「Master Deal Maker(マスターディールメーカー)」の認定を受けている。南フロリダ大学タンパ校にて優等で工業工学の学士号を取得。
●Mark Solomon
電気工学を専門とし、深い技術的知見に基づきキャリアを築く。長年にわたりHPC分野に従事し、過去14年間は量子コンピューティングの営業および事業開発に注力。現在はIonQのグローバルセールス担当副社長として、14億ドル超の戦略的顧客関係・パートナーシップを構築するなど、顕著な成果を上げている。先端技術の市場戦略策定に精通し、複雑な技術を企業・行政・経営層に実用的な価値として伝えることに長けている。
<講演概要>
「量子経済」とは、量子コンピュータや量子通信、量子センサーといった技術を使って生まれる新しい産業や仕事、投資、制度などをまとめて表す言葉です。官民学における取り組みをはじめ研究開発から社会実装までバリューチェーン全体が含まれます。本セッションでは、量子経済発展の可能性と、金融やサイバーセキュリティ、製造、医療、物流、教育など、私たちの生活や社会や産業へのインパクトについて語ります。
<プロフィール>
●Noam Zakay
IonQの欧州・中東・アフリカおよび日本事業を統括。豊富な専門知識を活かし、IonQの最先端量子技術の商業化と革新的なパートナーシップの構築を主導している。30年にわたるキャリアの中で、同氏は複数のリーディング企業で要職を務め、新たなビジネス機会の創出、戦略的ミッションの策定、革新的な戦略の実行に尽力してきた。卓越した交渉力と実績が評価され、INSEADより「Master Deal Maker(マスターディールメーカー)」の認定を受けている。南フロリダ大学タンパ校にて優等で工業工学の学士号を取得。
●Mark Solomon
電気工学を専門とし、深い技術的知見に基づきキャリアを築く。長年にわたりHPC分野に従事し、過去14年間は量子コンピューティングの営業および事業開発に注力。現在はIonQのグローバルセールス担当副社長として、14億ドル超の戦略的顧客関係・パートナーシップを構築するなど、顕著な成果を上げている。先端技術の市場戦略策定に精通し、複雑な技術を企業・行政・経営層に実用的な価値として伝えることに長けている。
量子コンピューティング基礎講座 ―アカデミアと産業の対話からみるビジネス活用の現在地と可能性

|
大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授 藤井 啓祐 |
|

|
QuEra Computing President 北川 拓也 |
|
<講演概要>
量子力学の原理に基づく量子コンピュータは、現在の計算技術を根本から変える可能性を秘めている。本対談では、量子コンピューティングの基礎から始め、ビジネスにおける現実的な応用例と今後の可能性について、分野の第一人者である大阪大学 藤井教授と実際に量子コンピューターを作っているQuEra社 北川氏の対話を通じて、解説する。技術的な課題や期待値を冷静に見極めつつ、今なぜ量子に注目が集まるのかを共有する。
<プロフィール>
●藤井 啓祐
2011年、京都大学大学院工学研究科博士課程修了。2019年より現職。大阪大学量子情報・量子生命研究センター副センター長、理化学研究所量子コンピュータ研究センターチームリーダー、情報処理推進機構(IPA)未踏ターゲット事業プログラムマネージャーを兼任。株式会社 QunaSys 最高技術顧問。
●北川 拓也
冷却原子を基にした量子コンピューターの開発、製造を行うQuEra computingのPresident兼取締役。
株式会社メルカリ社外取締役。元楽天常務執行役員、CDO(チーフデータオフィサー)兼楽天技術研究所グローバル所長。グループ全体のAI・データ戦略・研究の実行を担い、日本を含む、アメリカやインド、フランス、シンガポールを含む海外5拠点の組織を統括した。Well-being for planet earth、雲孫財団共同創業者。ハーバード大学数学・物理学専攻、同大学院物理学科博士課程修了。
<講演概要>
量子力学の原理に基づく量子コンピュータは、現在の計算技術を根本から変える可能性を秘めている。本対談では、量子コンピューティングの基礎から始め、ビジネスにおける現実的な応用例と今後の可能性について、分野の第一人者である大阪大学 藤井教授と実際に量子コンピューターを作っているQuEra社 北川氏の対話を通じて、解説する。技術的な課題や期待値を冷静に見極めつつ、今なぜ量子に注目が集まるのかを共有する。
<プロフィール>
●藤井 啓祐
2011年、京都大学大学院工学研究科博士課程修了。2019年より現職。大阪大学量子情報・量子生命研究センター副センター長、理化学研究所量子コンピュータ研究センターチームリーダー、情報処理推進機構(IPA)未踏ターゲット事業プログラムマネージャーを兼任。株式会社 QunaSys 最高技術顧問。
●北川 拓也
冷却原子を基にした量子コンピューターの開発、製造を行うQuEra computingのPresident兼取締役。
株式会社メルカリ社外取締役。元楽天常務執行役員、CDO(チーフデータオフィサー)兼楽天技術研究所グローバル所長。グループ全体のAI・データ戦略・研究の実行を担い、日本を含む、アメリカやインド、フランス、シンガポールを含む海外5拠点の組織を統括した。Well-being for planet earth、雲孫財団共同創業者。ハーバード大学数学・物理学専攻、同大学院物理学科博士課程修了。
量子産業化元年 ―大規模量子コンピュータとAIの融合の必要性

|
(国研)産業技術総合研究所 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター 副センター長 堀部 雅弘 |

|

<講演概要>
今年は、量子産業化元年。今後、量子コンピュータの産業界には大規模化と現在の計算基盤との融合さらには、AI技術との相互補完的な利用が不可欠となる。このような中、引き続きの基礎研究に加え、エンジニアリング技術やAI技術の活用がカギを握る。このような多岐にわたる取り組みを支える拠点・テストベッドとしてG-QuATの整備と活動を行っている。取り組みの概要と今後の展開(ロードマップ)について説明する。
<プロフィール>
名古屋大学で量子工学博士号取得後、富士通に入社。2021年に産総研に入所し、高周波・マイクロ波計測を専門とする物理計測標準研究部門電磁気計測研究グループ長を歴任。2021年より経済産業省に出向し、研究開発調整官として政策調整に従事。さらに内閣府では企画官として量子技術に関する国家戦略やイノベーション政策の立案にも関わった経験を持つ。2023年7月からは、量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G‑QuAT)副センター長に就任し、量子コンピューティングとAIの融合を通じた産業応用やビジネスエコシステム構築を推進している。
<講演概要>
今年は、量子産業化元年。今後、量子コンピュータの産業界には大規模化と現在の計算基盤との融合さらには、AI技術との相互補完的な利用が不可欠となる。このような中、引き続きの基礎研究に加え、エンジニアリング技術やAI技術の活用がカギを握る。このような多岐にわたる取り組みを支える拠点・テストベッドとしてG-QuATの整備と活動を行っている。取り組みの概要と今後の展開(ロードマップ)について説明する。
<プロフィール>
名古屋大学で量子工学博士号取得後、富士通に入社。2021年に産総研に入所し、高周波・マイクロ波計測を専門とする物理計測標準研究部門電磁気計測研究グループ長を歴任。2021年より経済産業省に出向し、研究開発調整官として政策調整に従事。さらに内閣府では企画官として量子技術に関する国家戦略やイノベーション政策の立案にも関わった経験を持つ。2023年7月からは、量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G‑QuAT)副センター長に就任し、量子コンピューティングとAIの融合を通じた産業応用やビジネスエコシステム構築を推進している。
量子技術のグローバルなエコシステム創出と社会実装に向けて

|
(一社)量子技術による新産業創出協議会(Q-STAR) 代表理事 /(株) 東芝 代表取締役 社長執行役員 CEO 島田 太郎 |
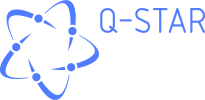
|
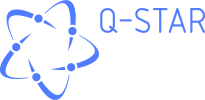
<講演概要>
量子コンピューティングがもたらす産業構造の転換を展望しながら、Q-STARが推進する産業界主導のエコシステム構築、標準化、政策提言、国際的な連携など、産業界のリーダーとして具体的な取り組みを紹介する。さらに、グローバルな量子技術開発の競争の中で、オープンなエコシステム創出に向けたグローバル協業の重要性についても提言する。
<プロフィール>
新明和工業株式会社、シーメンス株式会社などを経て、2018年10月にコーポレートデジタル事業責任者(CSO)として株式会社東芝に入社。2019年4月より執行役常務 最高デジタル責任者(CDO)、2020年執行役上席常務CDO、2022年3月より代表執行役役社長CEO、2023年12月より代表取締役 社長執行役員 CEO。一般社団法人量子技術による新産業創出協議会(Q-STAR)代表理事を務める。
<講演概要>
量子コンピューティングがもたらす産業構造の転換を展望しながら、Q-STARが推進する産業界主導のエコシステム構築、標準化、政策提言、国際的な連携など、産業界のリーダーとして具体的な取り組みを紹介する。さらに、グローバルな量子技術開発の競争の中で、オープンなエコシステム創出に向けたグローバル協業の重要性についても提言する。
<プロフィール>
新明和工業株式会社、シーメンス株式会社などを経て、2018年10月にコーポレートデジタル事業責任者(CSO)として株式会社東芝に入社。2019年4月より執行役常務 最高デジタル責任者(CDO)、2020年執行役上席常務CDO、2022年3月より代表執行役役社長CEO、2023年12月より代表取締役 社長執行役員 CEO。一般社団法人量子技術による新産業創出協議会(Q-STAR)代表理事を務める。
三井物産の量子取組と量子・古典ハイブリッドプラットフォーム「QIDO」

|
三井物産(株) コーポレートディベロップメント本部 総合力推進部 量子イノベーション室 技術戦略・事業化マネージャー 濱野 倫弥 |

|

<講演概要>
三井物産は、量子技術を活用した新たな産業創出と社会実装を目指し、国内外のパートナーとともにエコシステム構築、技術検証、事業化を推進しています。本講演では、当社の量子分野におけるこれまでの取り組みと戦略を紹介するとともに、量子コンピュータと古典コンピュータを統合したハイブリッドプラットフォーム「QIDO」の概要と、その導入を通じた三井物産の狙いを解説します。
<プロフィール>
2019年に三井物産入社後、社内唯一の量子技術担当として事業基盤を構築。2022年に専任組織「量子イノベーション室」立ち上げに参画し、全社戦略を策定・推進。Quantinuumなど国内外の主要プレイヤーとの関係構築を開拓し協業を主導。量子・古典ハイブリッドプラットフォーム「QIDO」の企画・事業化や、量子通信による次世代暗号「Quantum Tokens」の機能拡張・用途開発など、量子技術の検証・開発・事業化を多様な産業分野で推進している。
<講演概要>
三井物産は、量子技術を活用した新たな産業創出と社会実装を目指し、国内外のパートナーとともにエコシステム構築、技術検証、事業化を推進しています。本講演では、当社の量子分野におけるこれまでの取り組みと戦略を紹介するとともに、量子コンピュータと古典コンピュータを統合したハイブリッドプラットフォーム「QIDO」の概要と、その導入を通じた三井物産の狙いを解説します。
<プロフィール>
2019年に三井物産入社後、社内唯一の量子技術担当として事業基盤を構築。2022年に専任組織「量子イノベーション室」立ち上げに参画し、全社戦略を策定・推進。Quantinuumなど国内外の主要プレイヤーとの関係構築を開拓し協業を主導。量子・古典ハイブリッドプラットフォーム「QIDO」の企画・事業化や、量子通信による次世代暗号「Quantum Tokens」の機能拡張・用途開発など、量子技術の検証・開発・事業化を多様な産業分野で推進している。
AI時代の人材戦略 ~AI導入によって変わる人材マネジメント~

|
デロイトトーマツコンサルティング(同) 執行役員 Organization & Workforce Transformation Unit Leader 古澤 哲也 |
|

|
デロイトトーマツコンサルティング(同) 執行役員 AI & Data Unit Leader 下川 憲一 |
|
<講演概要>
AIの普及により、経営と人材戦略の連動がこれまで以上に重要になっています。
本講演では「AIを前提とした経営戦略」と、その実現に不可欠な組織変革や企業構造の再設計について解説します。
さらに、AIと共存し価値を発揮できる人材を活用・育成するための指針や、スキル強化のアプローチを提案します。
<プロフィール>
●古澤 哲也
事業会社、外資系コンサルティング会社を経て現職。
組織・人材コンサルティング歴20年以上。国内外の企業の様々な経営課題を組織・人事面から解決する業務に従事。
経営・事業戦略を推進するための人材マネジメント構想、戦略の立案、施策の設計に従事。
変革局面における意識・行動改革とデジタル変革局面におけるChange Managementサービスをリード。
●下川 憲一
事業会社、外資系コンサルティング会社を経て現職。
中期経営計画、全社構造改革などを多数経験。また近年は、最新技術を活用した様々な業務・ビジネストランスフォーメーションの支援に強みを持つ。
最新のDigital技術(LLM・ML、AI-OCR、RPAなど)を活用した「業務全体の刷新、改革の構想策定から実行」までを支援。特に近年は生成AIが登場し、「各部門の業務特化型、E2Eのプロセス横断型のAI活用プロセスの構築や事業部門のビジネスにおけるAI活用の支援」を行う。
AI&D Offeringをリードしている。
<講演概要>
AIの普及により、経営と人材戦略の連動がこれまで以上に重要になっています。
本講演では「AIを前提とした経営戦略」と、その実現に不可欠な組織変革や企業構造の再設計について解説します。
さらに、AIと共存し価値を発揮できる人材を活用・育成するための指針や、スキル強化のアプローチを提案します。
<プロフィール>
●古澤 哲也
事業会社、外資系コンサルティング会社を経て現職。
組織・人材コンサルティング歴20年以上。国内外の企業の様々な経営課題を組織・人事面から解決する業務に従事。
経営・事業戦略を推進するための人材マネジメント構想、戦略の立案、施策の設計に従事。
変革局面における意識・行動改革とデジタル変革局面におけるChange Managementサービスをリード。
●下川 憲一
事業会社、外資系コンサルティング会社を経て現職。
中期経営計画、全社構造改革などを多数経験。また近年は、最新技術を活用した様々な業務・ビジネストランスフォーメーションの支援に強みを持つ。
最新のDigital技術(LLM・ML、AI-OCR、RPAなど)を活用した「業務全体の刷新、改革の構想策定から実行」までを支援。特に近年は生成AIが登場し、「各部門の業務特化型、E2Eのプロセス横断型のAI活用プロセスの構築や事業部門のビジネスにおけるAI活用の支援」を行う。
AI&D Offeringをリードしている。
100名のAIエージェント開発者育成で加速するライオンのDX

|
ライオン(株) 執行役員 全社デジタル戦略担当 中林 紀彦 |

|

<講演概要>
130年以上の歴史を誇るライオンは、経営ビジョンの実現に向けてデジタル戦略を刷新し、研究開発からサプライチェーン、顧客接点までをデータで結ぶ“データドリブン経営”へと大きく舵を切っています。さらに生成AIなど最先端テクノロジーを活用し、オペレーショナル・エクセレンスの高度化にも注力しています。本講演では、100名規模の現場開発者を育成し、オペレーショナル・エクセレンスを深化させるプロセスと、その中核となるハイブリッド人材の育成に焦点を当て、具体的に解説します。
<プロフィール>
日本アイ・ビー・エム株式会社においてデータサイエンティストとして企業の様々な課題を解決。その後、株式会社オプトホールディング データサイエンスラボ副所長、SOMPOホールディングス株式会社チーフ・データサイエンティスト、ヤマトホールディングス株式会社の執行役員を歴任し、2024年4月にライオン株式会社の執行役員に就任。全社デジタル戦略担当としてグループ全体のIT・デジタル・データに関する戦略立案と実行を担う。
<講演概要>
130年以上の歴史を誇るライオンは、経営ビジョンの実現に向けてデジタル戦略を刷新し、研究開発からサプライチェーン、顧客接点までをデータで結ぶ“データドリブン経営”へと大きく舵を切っています。さらに生成AIなど最先端テクノロジーを活用し、オペレーショナル・エクセレンスの高度化にも注力しています。本講演では、100名規模の現場開発者を育成し、オペレーショナル・エクセレンスを深化させるプロセスと、その中核となるハイブリッド人材の育成に焦点を当て、具体的に解説します。
<プロフィール>
日本アイ・ビー・エム株式会社においてデータサイエンティストとして企業の様々な課題を解決。その後、株式会社オプトホールディング データサイエンスラボ副所長、SOMPOホールディングス株式会社チーフ・データサイエンティスト、ヤマトホールディングス株式会社の執行役員を歴任し、2024年4月にライオン株式会社の執行役員に就任。全社デジタル戦略担当としてグループ全体のIT・デジタル・データに関する戦略立案と実行を担う。
組織と個人の成長を実現するリスキリング ~先進企業の成果、課題と展望~

|
(一社)ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事 後藤 宗明 |

|


|
ダイキン工業(株) DX戦略推進室 担当部長 廣瀬 忠史 |
|

|
ダイハツ工業(株) DX推進室 デジタル変革グループ長 (兼) 東京LABOシニアデータサイエンティスト (兼) DX戦略担当 太古 無限 |

|

<講演概要>
先進的にリスキリングとDXを進めてきた企業は、どのような成果を上げ、どんな新たな課題に直面しているのか。DX推進の現場責任者が、企業にとって必要な姿勢や取り組みを共有し、今後の展望を深掘りするセッションです。
<プロフィール>
●後藤 宗明
みずほ銀⾏入⾏後、米国フィンテック企業、アクセンチュアにて人事領域のDX、AIスタートアップにてAI研修の企画運営を担当。2021年より現職、政府、自治体向け政策提言、企業向けのリスキリング導入支援を行う。2022年、スキルベース組織への変革を支援するSkyHive日本代表に就任。広島県、山梨県、山形県、茨城県にてリスキリング推進に向けた協議会委員、経済産業省「スキル標準化調査委員会」委員等を歴任。著書『自分のスキルをアップデートし続ける「リスキリング」』は読者が選ぶビジネス書グランプリ部門賞受賞。2025年9月に新著『リスキリング【人材戦略編】』を上梓。
●廣瀬 忠史
1996年 ダイキン工業入社。CAEセンターで3DCAD関連システムの企画、海外拠点導入を担当。 2007年に本社IT部門に異動。グローバルでのコード統一や経営情報可視化の企画等を経て、2015年より先進テクノロジーを活用した業務改革推進を担当。2021年12月より現職で全社のDX戦略を担う。
●太古 無限
2007年ダイハツ工業入社後は開発部にて小型車用エンジンの制御開発を担当。2020年から東京LABOデータサイエンスグループ長、2021年からDX推進室データサイエンスグループ長(兼務)を得て、DX推進室デジタル変革グループ長(兼)東京LABOシニアデータサイエンティストとして、全社のDX推進する業務に従事。その他に、滋賀大学データサイエンス部インダストリーアドバイザーとして、社外におけるAI活用の普及活動にも努める。経営学修士。「Forbes JAPAN CIO Award 2024-25」にて、次世代のテクノロジーリーダーのひとりとして「チェンジレガシー賞」を受賞。
<講演概要>
先進的にリスキリングとDXを進めてきた企業は、どのような成果を上げ、どんな新たな課題に直面しているのか。DX推進の現場責任者が、企業にとって必要な姿勢や取り組みを共有し、今後の展望を深掘りするセッションです。
<プロフィール>
●後藤 宗明
みずほ銀⾏入⾏後、米国フィンテック企業、アクセンチュアにて人事領域のDX、AIスタートアップにてAI研修の企画運営を担当。2021年より現職、政府、自治体向け政策提言、企業向けのリスキリング導入支援を行う。2022年、スキルベース組織への変革を支援するSkyHive日本代表に就任。広島県、山梨県、山形県、茨城県にてリスキリング推進に向けた協議会委員、経済産業省「スキル標準化調査委員会」委員等を歴任。著書『自分のスキルをアップデートし続ける「リスキリング」』は読者が選ぶビジネス書グランプリ部門賞受賞。2025年9月に新著『リスキリング【人材戦略編】』を上梓。
●廣瀬 忠史
1996年 ダイキン工業入社。CAEセンターで3DCAD関連システムの企画、海外拠点導入を担当。 2007年に本社IT部門に異動。グローバルでのコード統一や経営情報可視化の企画等を経て、2015年より先進テクノロジーを活用した業務改革推進を担当。2021年12月より現職で全社のDX戦略を担う。
●太古 無限
2007年ダイハツ工業入社後は開発部にて小型車用エンジンの制御開発を担当。2020年から東京LABOデータサイエンスグループ長、2021年からDX推進室データサイエンスグループ長(兼務)を得て、DX推進室デジタル変革グループ長(兼)東京LABOシニアデータサイエンティストとして、全社のDX推進する業務に従事。その他に、滋賀大学データサイエンス部インダストリーアドバイザーとして、社外におけるAI活用の普及活動にも努める。経営学修士。「Forbes JAPAN CIO Award 2024-25」にて、次世代のテクノロジーリーダーのひとりとして「チェンジレガシー賞」を受賞。
ステーブルコインと共に加速する金融・RWA・エンタメ領域のブロックチェーン事業

|
SBINFT(株) 取締役 SBIホールディングス(株) Web3事業推進部長 高 長徳 |

|


|
JPYC(株) 代表取締役 岡部 典孝 |
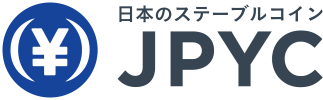
|
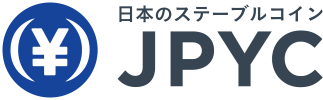

|
Oasys Pte. Ltd. Director 満足 亮 |

|

<講演概要>
日本初の円建てステーブルコインを展開するJPYC、エンタメ領域などで現実資産のトークン化を進めるブロックチェーン・Oasys、SBIグループでNFT事業を展開するSBINFTの3社対談。話題沸騰のステーブルコイン、RWAやIPのトークン化、SBIグループの「ネオメディア構想」など、ホットなテーマの最新動向に触れながら、幅広い業種・業界で活用可能な技術やアイデアをご紹介。
<プロフィール>
●高 長徳
IT系コンサル会社を経た後、GMOメディア株式会社、ヤフー株式会社(現:LINEヤフー株式会社)、株式会社ドリコムや株式会社モブキャストホールディングスでゲームプラットフォームのブロデューサーを歴任。2018年よりブロックチェーン領域でプラットフォーム事業を立ち上げる。2021年4月、NFTマーケットプレイス「nanakusa」をリリース、同年9月にSBIグループにジョインし、SBINFT株式会社代表取締役に就任。2023年8月、一般社団法人ブロックチェーン推進協会理事に就任。現在は、SBIホールディングス株式会社Web3事業推進部長 兼 SBINFT株式会社取締役として、Web3全領域においてSBIグループと国内外の事業者との連携を推進中。
●岡部 典孝
2001年に一橋大学在学中に一社目を創業し、以降、代表取締役や取締役CTOとして数々のプロジェクトをリード。2019年に日本暗号資産市場株式会社(現JPYC株式会社)を立ち上げ、代表取締役として2021年より日本円建プリペイド型トークン「JPYC Prepaid」の発行を開始。2023年7月からはBCCC「ステーブルコイン普及推進部会」の部会長に就任し、ブロックチェーン技術の普及と発展に貢献しています。さらに、一般社団法人ブロックチェーン推進協会(BCCC)副代表理事、一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)理事を務めるなど、業界発展にも注力。
●満足 亮
コンピューターサイエンスの修士号取得後、モバイルゲーム会社等でSRE統括等を経験。
2018年にブロックチェーンゲーム開発のdouble jump.tokyo株式会社に入社し、インフラ設計運用、サーバーサイド開発、SmartContract開発、ブロックチェーン技術調査を担当。
2020年に同社取締役CTO、2022年に代表取締役CTOに就任。2024年4月よりゲーム特化型ブロックチェーンプロジェクトOasysにDirector in Techとして参画し、2025年2月正式にOasys Pte. Ltd. Directorに就任。
<講演概要>
日本初の円建てステーブルコインを展開するJPYC、エンタメ領域などで現実資産のトークン化を進めるブロックチェーン・Oasys、SBIグループでNFT事業を展開するSBINFTの3社対談。話題沸騰のステーブルコイン、RWAやIPのトークン化、SBIグループの「ネオメディア構想」など、ホットなテーマの最新動向に触れながら、幅広い業種・業界で活用可能な技術やアイデアをご紹介。
<プロフィール>
●高 長徳
IT系コンサル会社を経た後、GMOメディア株式会社、ヤフー株式会社(現:LINEヤフー株式会社)、株式会社ドリコムや株式会社モブキャストホールディングスでゲームプラットフォームのブロデューサーを歴任。2018年よりブロックチェーン領域でプラットフォーム事業を立ち上げる。2021年4月、NFTマーケットプレイス「nanakusa」をリリース、同年9月にSBIグループにジョインし、SBINFT株式会社代表取締役に就任。2023年8月、一般社団法人ブロックチェーン推進協会理事に就任。現在は、SBIホールディングス株式会社Web3事業推進部長 兼 SBINFT株式会社取締役として、Web3全領域においてSBIグループと国内外の事業者との連携を推進中。
●岡部 典孝
2001年に一橋大学在学中に一社目を創業し、以降、代表取締役や取締役CTOとして数々のプロジェクトをリード。2019年に日本暗号資産市場株式会社(現JPYC株式会社)を立ち上げ、代表取締役として2021年より日本円建プリペイド型トークン「JPYC Prepaid」の発行を開始。2023年7月からはBCCC「ステーブルコイン普及推進部会」の部会長に就任し、ブロックチェーン技術の普及と発展に貢献しています。さらに、一般社団法人ブロックチェーン推進協会(BCCC)副代表理事、一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)理事を務めるなど、業界発展にも注力。
●満足 亮
コンピューターサイエンスの修士号取得後、モバイルゲーム会社等でSRE統括等を経験。
2018年にブロックチェーンゲーム開発のdouble jump.tokyo株式会社に入社し、インフラ設計運用、サーバーサイド開発、SmartContract開発、ブロックチェーン技術調査を担当。
2020年に同社取締役CTO、2022年に代表取締役CTOに就任。2024年4月よりゲーム特化型ブロックチェーンプロジェクトOasysにDirector in Techとして参画し、2025年2月正式にOasys Pte. Ltd. Directorに就任。
【新規事業】Web3を活用したコンテンツづくりの裏側と可能性

|
キリフダ(株) 代表取締役社長 赤川 英之 |
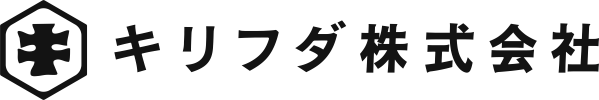
|
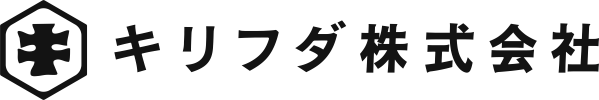

|
キリフダ(株) 開発部 CTO 髙井 比文 |
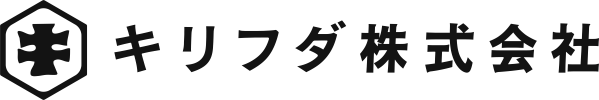
|
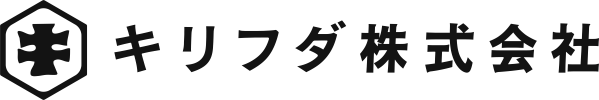

|
(株)スクウェア・エニックス インキュベーションディビジョン プロデューサー 伊藤 一紀 |

|


|
(株)スクウェア・エニックス インキュベーションディビジョン プロデューサー 渡辺 優 |

|

<講演概要>
本講演では多くの名作ゲームを生み出してきた株式会社スクウェア・エニックスと、Web3特化のコンサルティング会社であるキリフダ社が、コンテンツ開発におけるブロックチェーンがもたらす新たな体験価値や単なる技術導入に留まらない本質的な可能性について深ぼっていきます。
<プロフィール>
●赤川 英之
1997年台湾台北市生まれ。東京大学大学院にて屋内測位および聴覚的空間体験の研究に従事し2022年に修士号を取得。同年3月にシンシズモ株式会社(現キリフダ株式会社)を創業。NFTの賃貸借をスムーズに実現する世界初のプロダクトを開発し、ETHGlobal主催の国際的なハッカソンにて1st-Prizeを獲得。現在は、web3特化の総合コンサルティング事業を展開し、東急不動産や大阪ガスを含む国内エンタープライズ向けに新規事業開発の支援やシステム開発を展開している。
●髙井 比文
北海道大学大学院にて金属流体の数値解析手法を研究後、新日鐵住金(現日本製鉄)に新卒入社。設備投資プロジェクトのPMとして製鉄プラント最適化に従事。
その後、ITインフラ領域に転身し、エンジニアリングマネージャーとして製造業向けBtoB SaaS開発組織を統括。
2022年、Web3領域の可能性に着目してキリフダにブロックチェーンエンジニアとして参画。同年CTOに就任。現在はソリューション開発から受託開発まで技術開発全般を統括し、LINEエコシステムとブロックチェーン技術を融合した事業を技術面から牽引。フルスタック開発能力を活かし、インフラ設計からフロントエンド開発まで一貫して担当。
●伊藤 一紀
2009年、株式会社スクウェア・エニックス入社。PC向けオンラインゲーム「戦国IXA」の立ち上げや運営などに携わった後、新規事業開発のプロデューサーとして体験型アトラクションやイベント開発に従事。当時の新VR技術を活用したアトラクション「バハムートディスコ」、デジタルアトラクションを駆使した体験型展示会「PLAY! スペースインベーダー展」、ゲームやアニメの世界観を五感で楽しめる街歩き型イベント「FIELD WALK RPG」などを手掛ける。2023年よりブロックチェーン事業に参画。
●渡辺 優
2015年、株式会社スクウェア・エニックスに入社し、スマートフォン向けゲームの運営に携わる。
その後、新規事業開発部門の立ち上げから参加し、ゲームセンターやテーマパークなど施設向けエンタテインメント事業の企画を担当。10人が同時に対戦できるアーケードゲーム「SPACE INVADERS GIGAMAX」や「FIELD WALK RPG」などでプロデューサーを務める。2022年からはブロックチェーン事業の部署に異動し、「資産性ミリオンアーサー」の運営担当coプロデューサーを務める。
<講演概要>
本講演では多くの名作ゲームを生み出してきた株式会社スクウェア・エニックスと、Web3特化のコンサルティング会社であるキリフダ社が、コンテンツ開発におけるブロックチェーンがもたらす新たな体験価値や単なる技術導入に留まらない本質的な可能性について深ぼっていきます。
<プロフィール>
●赤川 英之
1997年台湾台北市生まれ。東京大学大学院にて屋内測位および聴覚的空間体験の研究に従事し2022年に修士号を取得。同年3月にシンシズモ株式会社(現キリフダ株式会社)を創業。NFTの賃貸借をスムーズに実現する世界初のプロダクトを開発し、ETHGlobal主催の国際的なハッカソンにて1st-Prizeを獲得。現在は、web3特化の総合コンサルティング事業を展開し、東急不動産や大阪ガスを含む国内エンタープライズ向けに新規事業開発の支援やシステム開発を展開している。
●髙井 比文
北海道大学大学院にて金属流体の数値解析手法を研究後、新日鐵住金(現日本製鉄)に新卒入社。設備投資プロジェクトのPMとして製鉄プラント最適化に従事。
その後、ITインフラ領域に転身し、エンジニアリングマネージャーとして製造業向けBtoB SaaS開発組織を統括。
2022年、Web3領域の可能性に着目してキリフダにブロックチェーンエンジニアとして参画。同年CTOに就任。現在はソリューション開発から受託開発まで技術開発全般を統括し、LINEエコシステムとブロックチェーン技術を融合した事業を技術面から牽引。フルスタック開発能力を活かし、インフラ設計からフロントエンド開発まで一貫して担当。
●伊藤 一紀
2009年、株式会社スクウェア・エニックス入社。PC向けオンラインゲーム「戦国IXA」の立ち上げや運営などに携わった後、新規事業開発のプロデューサーとして体験型アトラクションやイベント開発に従事。当時の新VR技術を活用したアトラクション「バハムートディスコ」、デジタルアトラクションを駆使した体験型展示会「PLAY! スペースインベーダー展」、ゲームやアニメの世界観を五感で楽しめる街歩き型イベント「FIELD WALK RPG」などを手掛ける。2023年よりブロックチェーン事業に参画。
●渡辺 優
2015年、株式会社スクウェア・エニックスに入社し、スマートフォン向けゲームの運営に携わる。
その後、新規事業開発部門の立ち上げから参加し、ゲームセンターやテーマパークなど施設向けエンタテインメント事業の企画を担当。10人が同時に対戦できるアーケードゲーム「SPACE INVADERS GIGAMAX」や「FIELD WALK RPG」などでプロデューサーを務める。2022年からはブロックチェーン事業の部署に異動し、「資産性ミリオンアーサー」の運営担当coプロデューサーを務める。
JPYC社会実装の第一歩 ーリアル店舗とノーコード連携がつなぐ新しい金融インフラ

|
JPYC(株) 代表取締役 岡部 典孝 |
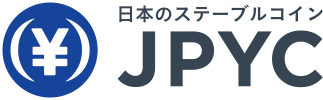
|
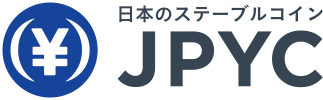

|
アステリア(株) 代表取締役社長/CEO 平野 洋一郎 |

|


|
(株)電算システム ビジネスデザイン企画推進本部 上席執行役員 鎌田 啓之 |

|


|
(株)finoject 代表取締役 三根 公博 |

|

<講演概要>
JPYCが電算システムの店舗決済網とアステリアのノーコード基幹連携をつなぎ、リテールから企業利用まで広がる活用事例を紹介します。
<プロフィール>
●岡部 典孝
2001年に一橋大学在学中に一社目を創業し、以降、代表取締役や取締役CTOとして数々のプロジェクトをリード。2019年に日本暗号資産市場株式会社(現JPYC株式会社)を立ち上げ、代表取締役として2021年より日本円建プリペイド型トークン「JPYC Prepaid」の発行を開始。2023年7月からはBCCC「ステーブルコイン普及推進部会」の部会長に就任し、ブロックチェーン技術の普及と発展に貢献しています。さらに、一般社団法人ブロックチェーン推進協会(BCCC)副代表理事、一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)理事を務めるなど、業界発展にも注力。
●平野 洋一郎
熊本大学工学部在学中にソフトウェア開発ベンチャー設立に参画するなど早くからエンジニアとして活躍。1998年にインフォテリア(現アステリア)株式会社を創業し、19年連続市場シェア1位のデータ連携ツール「ASTERIA Warp」をはじめ、”つなぐ”をテーマにしたソフトウェアを提供している。現在は一般社団法人ブロックチェーン推進協会代表理事として、ブロックチェーンの社会実装に向けた普及啓発活動にも尽力している。
●鎌田 啓之
1994年、現三井住友銀行入行、本店営業部、三井物産メディア事業部出向、ネットビジネス企画部、EC業務部、等歴任。2007年4月、楽天株式会社入社、楽天トラベル株式会社常務執行役員事業戦略部長。2014年3月楽天退社後、Globe-Trotter CIO、融資型クラウドファンディング事業会社副社長執行役員等を経て、2024年1月より株式会社電算システムにてブロックチェーン、ステーブルコイン等の新規事業開発を推進中。
●三根 公博
一橋大学法学部卒業後、日本興業銀行(現・みずほ銀行)に入行。
その後、松井証券などで役員を歴任し、金融業界における豊富な経営経験を積む。
株式会社bitFlyerの代表取締役社長および日本暗号資産取引業協会会長に就任し、国内の暗号資産業界の発展に寄与。
現在は株式会社finoject代表取締役として、「DXコンサルティング」や「ブロックチェーンコンサルティング」などを中心に、企業のデジタル変革・新技術導入支援を展開している
<講演概要>
JPYCが電算システムの店舗決済網とアステリアのノーコード基幹連携をつなぎ、リテールから企業利用まで広がる活用事例を紹介します。
<プロフィール>
●岡部 典孝
2001年に一橋大学在学中に一社目を創業し、以降、代表取締役や取締役CTOとして数々のプロジェクトをリード。2019年に日本暗号資産市場株式会社(現JPYC株式会社)を立ち上げ、代表取締役として2021年より日本円建プリペイド型トークン「JPYC Prepaid」の発行を開始。2023年7月からはBCCC「ステーブルコイン普及推進部会」の部会長に就任し、ブロックチェーン技術の普及と発展に貢献しています。さらに、一般社団法人ブロックチェーン推進協会(BCCC)副代表理事、一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)理事を務めるなど、業界発展にも注力。
●平野 洋一郎
熊本大学工学部在学中にソフトウェア開発ベンチャー設立に参画するなど早くからエンジニアとして活躍。1998年にインフォテリア(現アステリア)株式会社を創業し、19年連続市場シェア1位のデータ連携ツール「ASTERIA Warp」をはじめ、”つなぐ”をテーマにしたソフトウェアを提供している。現在は一般社団法人ブロックチェーン推進協会代表理事として、ブロックチェーンの社会実装に向けた普及啓発活動にも尽力している。
●鎌田 啓之
1994年、現三井住友銀行入行、本店営業部、三井物産メディア事業部出向、ネットビジネス企画部、EC業務部、等歴任。2007年4月、楽天株式会社入社、楽天トラベル株式会社常務執行役員事業戦略部長。2014年3月楽天退社後、Globe-Trotter CIO、融資型クラウドファンディング事業会社副社長執行役員等を経て、2024年1月より株式会社電算システムにてブロックチェーン、ステーブルコイン等の新規事業開発を推進中。
●三根 公博
一橋大学法学部卒業後、日本興業銀行(現・みずほ銀行)に入行。
その後、松井証券などで役員を歴任し、金融業界における豊富な経営経験を積む。
株式会社bitFlyerの代表取締役社長および日本暗号資産取引業協会会長に就任し、国内の暗号資産業界の発展に寄与。
現在は株式会社finoject代表取締役として、「DXコンサルティング」や「ブロックチェーンコンサルティング」などを中心に、企業のデジタル変革・新技術導入支援を展開している
全ての企業がWeb3/NFTを活用する時代へ 〜最新事例ご紹介〜

|
(株)クリプトリエ 代表取締役 CEO 手塚 康夫 |

|


|
(株)QTnet 経営戦略本部 YOKAプロ部 上堀内 一貴 |

|

<講演概要>
Web3/NFT技術のビジネス活用は顧客向けのデジタルマーケティングから社内向けのエンゲージメント向上施策まで幅広い領域で注目を集めています。
本講演では、クリプトリエによるNFTのビジネス活用の最新事例のご紹介に加えて、具体事例として九州電力グループで通信事業を展開するQTnetのWeb3/NFT の取り組みをご紹介。企業におけるリアルなWeb3/NFT活用の最新動向を対談形式でお届けします。
<プロフィール>
,●手塚 康夫
2006年に株式会社ジェナを設立、2021年の株式会社マネーフォワードによるM&A後に同社を退任。現在は2023年に設立した法人向けにWeb3ビジネスを展開する株式会社クリプトリエの代表取締役を務める。株式会社クリプトリエでは、NFTのビジネス活用を簡単かつ迅速に実現するプロダクト「MintMonster」を提供し、企業におけるWeb3活用の普及を目指す。
●上堀内 一貴
大卒後、食品の営業を経て、現職。新規顧客開拓営業(10年)→営業推進(2年)→新規事業開発(7年)のキャリア。
<これまでにかかわってきたもの>
・IoT農業(センサーネットワークの構築)の実証実験
・eスポーツ事業立ち上げ、チーム買収
・放送局内のYoutubeチャンネル向けインフラ構築
・スタートアップのソーシング/出資
・デジタルツインを通じたプラットフォームビジネスの実証実験
・カジュアルゲームの広告化に関する実証実験
・まちづくりDXに関する実証実験
・Web3インフラに関する実証実験
・NFT配布を通じた事業化の実証実験
<講演概要>
Web3/NFT技術のビジネス活用は顧客向けのデジタルマーケティングから社内向けのエンゲージメント向上施策まで幅広い領域で注目を集めています。
本講演では、クリプトリエによるNFTのビジネス活用の最新事例のご紹介に加えて、具体事例として九州電力グループで通信事業を展開するQTnetのWeb3/NFT の取り組みをご紹介。企業におけるリアルなWeb3/NFT活用の最新動向を対談形式でお届けします。
<プロフィール>
,●手塚 康夫
2006年に株式会社ジェナを設立、2021年の株式会社マネーフォワードによるM&A後に同社を退任。現在は2023年に設立した法人向けにWeb3ビジネスを展開する株式会社クリプトリエの代表取締役を務める。株式会社クリプトリエでは、NFTのビジネス活用を簡単かつ迅速に実現するプロダクト「MintMonster」を提供し、企業におけるWeb3活用の普及を目指す。
●上堀内 一貴
大卒後、食品の営業を経て、現職。新規顧客開拓営業(10年)→営業推進(2年)→新規事業開発(7年)のキャリア。
<これまでにかかわってきたもの>
・IoT農業(センサーネットワークの構築)の実証実験
・eスポーツ事業立ち上げ、チーム買収
・放送局内のYoutubeチャンネル向けインフラ構築
・スタートアップのソーシング/出資
・デジタルツインを通じたプラットフォームビジネスの実証実験
・カジュアルゲームの広告化に関する実証実験
・まちづくりDXに関する実証実験
・Web3インフラに関する実証実験
・NFT配布を通じた事業化の実証実験
ATMからのNFT発行によるコミュニケーションデザイン

|
(株)セブン銀行 セブン・ラボ 調査役 山方 大輝 |

|


|
SUSHI TOP MARKETING(株) 代表取締役CEO 徳永 大輔 |

|

<講演概要>
ATMからNFTを発行するという世界初の試みにより、セブン銀行が提供する非金融型体験価値の可能性に迫る。
NFTを通じた新たな顧客接点の創出や、生活導線上におけるデジタル販促の新たなあり方について提案する。
これらの取り組みについては、SUSHITOPMARKETINGとの協業事例を中心に紹介する。
<プロフィール>
●山方 大輝
2014年にSMBC日興証券に入社し、リテールセールスに従事。その後、投資情報部にて個人投資家向けの金融市場のリサーチ業務を担当後、2020年9月からセブン銀行にジョイン。
●徳永 大輔
立命館大学卒業、新卒で「山と渓谷社」に入社。SEOメディアで起業し事業売却を経験。
トークングラフマーケティングの文化創造をミッションに掲げるSUSHITOPMARKETING株式会社を2021年に創業し、現在に至る。
<講演概要>
ATMからNFTを発行するという世界初の試みにより、セブン銀行が提供する非金融型体験価値の可能性に迫る。
NFTを通じた新たな顧客接点の創出や、生活導線上におけるデジタル販促の新たなあり方について提案する。
これらの取り組みについては、SUSHITOPMARKETINGとの協業事例を中心に紹介する。
<プロフィール>
●山方 大輝
2014年にSMBC日興証券に入社し、リテールセールスに従事。その後、投資情報部にて個人投資家向けの金融市場のリサーチ業務を担当後、2020年9月からセブン銀行にジョイン。
●徳永 大輔
立命館大学卒業、新卒で「山と渓谷社」に入社。SEOメディアで起業し事業売却を経験。
トークングラフマーケティングの文化創造をミッションに掲げるSUSHITOPMARKETING株式会社を2021年に創業し、現在に至る。
災害時に広がる“情報の二次災害”を防げ!放送×ブロックチェーンが挑む偽・誤情報対策

|
関西テレビソフトウェア(株) デジタルデザイングループ チーフエキスパート 横島 裕明 |

|


|
(株)Opening Line ブロックチェーンイノベーション事業部 ジェネラルマネージャー 岡田 和也 |
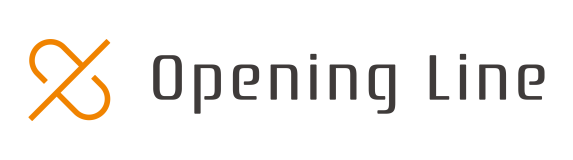
|
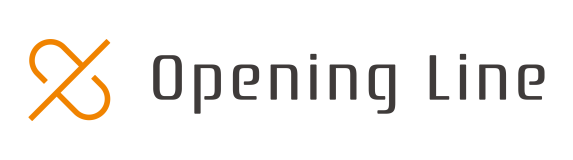

|
(株)ベリサーブ サイバーセキュリティ事業部 エンジニア 原 隆 |
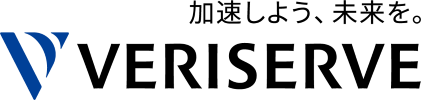
|
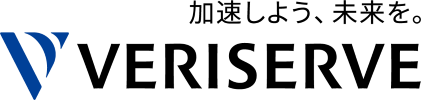
<講演概要>
SNSなどで広がる偽・誤情報は、災害現場の対応に混乱をもたらす“情報の二次災害”を引き起こす。
本セッションでは、地上デジタル放送波(IPDC)とブロックチェーンを活用し、通信インフラに依存せずに判断と行動を支援する手法と、その社会実装の展望を紹介し、セキュリティの専門家の視点も交えて議論する。
<プロフィール>
●横島 裕明
2004年、関西テレビソフトウェア株式会社に入社。放送と連動したITシステム開発に従事。
2015年より、生放送番組での投票システムにブロックチェーンを活用した実証を行うなど、非金融分野での社会実装について研究開発を続ける。
●岡田 和也
2018年Opening Lineに入社。主にSymbolブロックチェーンを活用したシステム・サービスの企画・開発に従事。これまでに半導体製造装置メーカー向けの物流トレーサビリティや静岡県のデジタル人材育成プログラムの修了証NFT導入などトレーサビリティやNFTの利活用の面で企業におけるブロックチェーンの活用・社会実装に携わってきた。自社サービスにおいても、ファイル共有サービスJ「Juggle」やNFTスタンプラリーサービス「ピースコレクション」、トレーサビリティプラットフォームの企画・開発を行い、より多くのブロックチェーン活用を目指している。
●原 隆
2014年に株式会社ベリサーブへ入社し、サイバーセキュリティ事業部にてセキュリティ評価サービス業務に従事。脆弱性診断やリスクアセスメントなど多様な案件への対応を担当。2023年には、同社がJCMVP(暗号モジュール試験および認証制度)の暗号モジュール試験機関としての認定を取得する際、プロセス全体の推進と社内外調整・審査対応などを担当。現在も同事業部で、お客様の製品・サービスのセキュリティ確保に関する業務に従事している。
<講演概要>
SNSなどで広がる偽・誤情報は、災害現場の対応に混乱をもたらす“情報の二次災害”を引き起こす。
本セッションでは、地上デジタル放送波(IPDC)とブロックチェーンを活用し、通信インフラに依存せずに判断と行動を支援する手法と、その社会実装の展望を紹介し、セキュリティの専門家の視点も交えて議論する。
<プロフィール>
●横島 裕明
2004年、関西テレビソフトウェア株式会社に入社。放送と連動したITシステム開発に従事。
2015年より、生放送番組での投票システムにブロックチェーンを活用した実証を行うなど、非金融分野での社会実装について研究開発を続ける。
●岡田 和也
2018年Opening Lineに入社。主にSymbolブロックチェーンを活用したシステム・サービスの企画・開発に従事。これまでに半導体製造装置メーカー向けの物流トレーサビリティや静岡県のデジタル人材育成プログラムの修了証NFT導入などトレーサビリティやNFTの利活用の面で企業におけるブロックチェーンの活用・社会実装に携わってきた。自社サービスにおいても、ファイル共有サービスJ「Juggle」やNFTスタンプラリーサービス「ピースコレクション」、トレーサビリティプラットフォームの企画・開発を行い、より多くのブロックチェーン活用を目指している。
●原 隆
2014年に株式会社ベリサーブへ入社し、サイバーセキュリティ事業部にてセキュリティ評価サービス業務に従事。脆弱性診断やリスクアセスメントなど多様な案件への対応を担当。2023年には、同社がJCMVP(暗号モジュール試験および認証制度)の暗号モジュール試験機関としての認定を取得する際、プロセス全体の推進と社内外調整・審査対応などを担当。現在も同事業部で、お客様の製品・サービスのセキュリティ確保に関する業務に従事している。
ローカルコンテンツ × NFT/web3で実現する地域創生

|
Marbull X(株) 代表取締役 CEO 小川 翔太郎 |
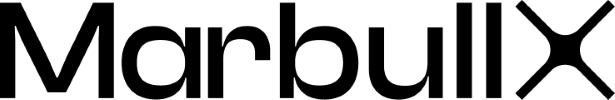
|
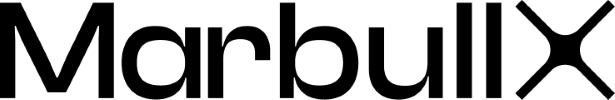

|
大井川鐵道(株) 鉄道部計画課 兼 経営企画室 副長 山田 直哉 |

|

<講演概要>
静岡県の地方鉄道、大井川鐵道は、SLの動態保存や奥大井湖上駅で多くの鉄道ファンを魅了しています。同社は今年からLINEとNFTを活用したCRM施策を開始しました。企画を支援するweb3コンサルティング企業、Marbull Xとともに、地域のコンテンツとNFTを組み合わせた地方創生の可能性について、議論します。
<プロフィール>
●小川 翔太郎
京都大学工学部卒/同大学院修了。
新卒で昭和シェル石油(現出光興産)に入社した後、アクセンチュアに参画。戦略コンサルタントとして、通信業界を中心に、新規事業立案や組織改革、大企業のweb3領域参入支援等に従事。
2024年、Marbull X株式会社を共同設立。NFT×LINEを活用したマーケティングツール「Marbullコネクト」を開発し、様々な業界の企業、および地方自治体向けにサービスを提供中。
日本を代表する企業様の事業戦略策定に従事してきた実務経験をもとに、新規事業領域を中心としたコンサルティングサービスも提供する。
● 山田 直哉
現場経験をへて経営企画室に参画。動態保存を行うSL蒸気機関車などの観光資源を活かし、新たな事業開発を手がける。SL夜行列車の運行や食堂車の企画など、これまでにない挑戦によって、創立100周年を経た伝統ある会社の新たな価値と魅力の発信をする事業
<講演概要>
静岡県の地方鉄道、大井川鐵道は、SLの動態保存や奥大井湖上駅で多くの鉄道ファンを魅了しています。同社は今年からLINEとNFTを活用したCRM施策を開始しました。企画を支援するweb3コンサルティング企業、Marbull Xとともに、地域のコンテンツとNFTを組み合わせた地方創生の可能性について、議論します。
<プロフィール>
●小川 翔太郎
京都大学工学部卒/同大学院修了。
新卒で昭和シェル石油(現出光興産)に入社した後、アクセンチュアに参画。戦略コンサルタントとして、通信業界を中心に、新規事業立案や組織改革、大企業のweb3領域参入支援等に従事。
2024年、Marbull X株式会社を共同設立。NFT×LINEを活用したマーケティングツール「Marbullコネクト」を開発し、様々な業界の企業、および地方自治体向けにサービスを提供中。
日本を代表する企業様の事業戦略策定に従事してきた実務経験をもとに、新規事業領域を中心としたコンサルティングサービスも提供する。
● 山田 直哉
現場経験をへて経営企画室に参画。動態保存を行うSL蒸気機関車などの観光資源を活かし、新たな事業開発を手がける。SL夜行列車の運行や食堂車の企画など、これまでにない挑戦によって、創立100周年を経た伝統ある会社の新たな価値と魅力の発信をする事業
KDDIとCASIO、Web3挑戦の裏側と両社が描く未来

|
(株)Pacific Meta Executive Officer, Business Development 松本 頌平 |
|

|
カシオ計算機(株) 時計統轄部 デジタルマーケティング部 D2C戦略室 室長 大林 大祐 |

|


|
KDDI(株) オープンイノベーション推進本部 ビジネス共創推進室 3G グループリーダー 笠井 道彦 |

|

<講演概要>
CASIOとKDDIがパネル形式でWeb3挑戦のリアルを共有し、事業化の背景、直面した課題と学び、Web3が事業にもたらした価値を提示。さらに2025年以降のWeb3事業構想を展望する。モデレーターはPacific Metaが担当する。
<プロフィール>
●松本 頌平
トークン・ファイナンスコンサルタント。事業開発コンサルタント。Web3スタートアップでオンチェーンの分析ツール開発に携わった後、Web3に特化したファンドを持つSkyland Venturesでキャピタリストとして投資を行う。現在はPacific Metaにて新規事業開発を行う。
●大林 大祐
新卒で広告代理店に勤務後、カシオのハウスエージェンシー・宣伝部にてマスメディアからデジタルメディアまでメディアコミュニケーションデザイン・バイイングを担当。2015年より、米国駐在にて北米エリアのマーケティングに従事し、帰任後デジタルマーケティングを中心に業務を進めながら、2022年より通常業務とは別で、VIRTUAL G-SHOCKプロジェクトを推進。
●笠井 道彦
KDDIに入社後、EC、金融等の新規事業開発、上海拠点への駐在を含む国内外ベンチャーへの投資活動等を経てWeb3領域の企画推進を担当し、現在に至る。
<講演概要>
CASIOとKDDIがパネル形式でWeb3挑戦のリアルを共有し、事業化の背景、直面した課題と学び、Web3が事業にもたらした価値を提示。さらに2025年以降のWeb3事業構想を展望する。モデレーターはPacific Metaが担当する。
<プロフィール>
●松本 頌平
トークン・ファイナンスコンサルタント。事業開発コンサルタント。Web3スタートアップでオンチェーンの分析ツール開発に携わった後、Web3に特化したファンドを持つSkyland Venturesでキャピタリストとして投資を行う。現在はPacific Metaにて新規事業開発を行う。
●大林 大祐
新卒で広告代理店に勤務後、カシオのハウスエージェンシー・宣伝部にてマスメディアからデジタルメディアまでメディアコミュニケーションデザイン・バイイングを担当。2015年より、米国駐在にて北米エリアのマーケティングに従事し、帰任後デジタルマーケティングを中心に業務を進めながら、2022年より通常業務とは別で、VIRTUAL G-SHOCKプロジェクトを推進。
●笠井 道彦
KDDIに入社後、EC、金融等の新規事業開発、上海拠点への駐在を含む国内外ベンチャーへの投資活動等を経てWeb3領域の企画推進を担当し、現在に至る。
「持続的な収益を生み出すビジネス」を大企業がWeb3領域で行うには

|
(株)Recept 取締役COO 大島 拓也 |

|


|
トレードログ(株) 代表取締役 藤田 誠広 |
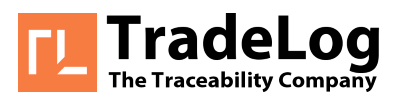
|
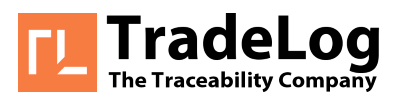

|
(株)QTnet YOKAプロ部 新規事業創出担当 伊波 亮 |

|

<講演概要>
過剰な期待が寄せられ、一過性のブームだったともいわれるWeb3。
本来、ビジネスを構築する際に先に技術の特性が語られることは避けるべきであるが、Web3ではそのNGパターンが繰り返されてきたとも言える。
本講演では、持続的なビジネスにつながるWeb3技術の活用を実際のケースを用いて考察する。
<プロフィール>
●大島 拓也
2021年3月に横浜国立大学を卒業。株式会社セブン銀行に入社し、同行史上最年少のプロジェクトリーダーとしてWeb3関連の新規事業を起ち上げる。
同社在籍中に、大学同期でエンジニアとしてキャリアを積んでいた共同創業者CEOの中瀬と(株)Receptを創業。事業戦略の立案・投資家対応などを担当し、大手ベンダーや教育機関へのプロダクト導入、複数投資家や銀行からの資金調達を行う。
●藤田 誠広
上智大学法学部卒業後、バックパッカー、ニート、非正規労働者等を経てデータビジネス業界へ。メーカー、小売、D2Cなどの大手企業の広告宣伝部門・マーケティング部門向けに法人営業、サービス開発、DX支援などに従事。多くの大手企業がデータのサイロ化、曖昧なデータなどに悩まされているために、新しいブランドマネジメントの構築に苦しんでいることを実感。ブランド、生活者、社会の3者の関係を再構築できる具体的な方途を模索する中で、ブロックチェーン技術に可能性を見出し、2018年トレードログ株式会社を設立。消費財/耐久財、動脈/静脈、モノ/電力など、様々なトレーサビリティプロジェクトに参画。
●伊波 亮
2018年3月、鹿児島大学法文学部卒業。株式会社QTnetへ入社し、コンシューマ営業を3年経験後、サービス開発部署にてコンシューマサービス開発に従事。2024年からYOKAプロ部(新規事業開発)へ異動しスタートアップとのオープンイノベーション事業を担当。
<講演概要>
過剰な期待が寄せられ、一過性のブームだったともいわれるWeb3。
本来、ビジネスを構築する際に先に技術の特性が語られることは避けるべきであるが、Web3ではそのNGパターンが繰り返されてきたとも言える。
本講演では、持続的なビジネスにつながるWeb3技術の活用を実際のケースを用いて考察する。
<プロフィール>
●大島 拓也
2021年3月に横浜国立大学を卒業。株式会社セブン銀行に入社し、同行史上最年少のプロジェクトリーダーとしてWeb3関連の新規事業を起ち上げる。
同社在籍中に、大学同期でエンジニアとしてキャリアを積んでいた共同創業者CEOの中瀬と(株)Receptを創業。事業戦略の立案・投資家対応などを担当し、大手ベンダーや教育機関へのプロダクト導入、複数投資家や銀行からの資金調達を行う。
●藤田 誠広
上智大学法学部卒業後、バックパッカー、ニート、非正規労働者等を経てデータビジネス業界へ。メーカー、小売、D2Cなどの大手企業の広告宣伝部門・マーケティング部門向けに法人営業、サービス開発、DX支援などに従事。多くの大手企業がデータのサイロ化、曖昧なデータなどに悩まされているために、新しいブランドマネジメントの構築に苦しんでいることを実感。ブランド、生活者、社会の3者の関係を再構築できる具体的な方途を模索する中で、ブロックチェーン技術に可能性を見出し、2018年トレードログ株式会社を設立。消費財/耐久財、動脈/静脈、モノ/電力など、様々なトレーサビリティプロジェクトに参画。
●伊波 亮
2018年3月、鹿児島大学法文学部卒業。株式会社QTnetへ入社し、コンシューマ営業を3年経験後、サービス開発部署にてコンシューマサービス開発に従事。2024年からYOKAプロ部(新規事業開発)へ異動しスタートアップとのオープンイノベーション事業を担当。
ブロックチェーン活用事例3選 〜フードNFT、BDAとDAO、トレーサビリティの現場から〜

|
Atomos-Seed(同) 代表/ フードNFTコンソーシアム 共同代表 / NPO法人NEMTUS 理事長 後藤 博之 |

|


|
岐阜大学 大学院医学系研究科 再生機能医学分野准教授/ (株)しずい細胞研究所 代表取締役 手塚 建一(オンライン) |
|

|
(株)サイアムレイワインターナショナル 副社長 茅原 拓人(オンライン) |
|

|
東京藝術大学 芸術情報センター 准教授 嘉村 哲郎 |
|

|
(株)NFTDrive 代表取締役 中島 理男(オンライン) |
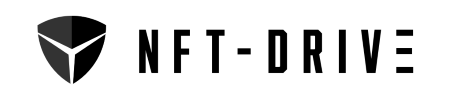
|
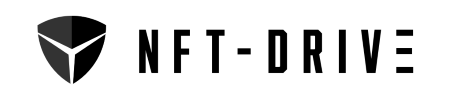
<講演概要>
本セッションでは、ブロックチェーン技術が実際にどのように活用・運用されているのか、各分野の専門家や第一線のディレクター、開発者を交え、実事例を通して紹介する。『フードNFTの実用と今後』、 『ブロックチェーンデジタルアーカイブとDAOの実践』 、『[農業] [医療] ×トレーサビリティ』の3つのジャンルについて、最新の動向を取り上げながら、使い所や課題、未来像を多角的に探る。
<プロフィール>
●後藤 博之
2009年ビットコイン誕生後、ブロックチェーン研究を開始、関連事業のサポート業務に従事。
2017年10月から2019年9月まで、テックビューロ株式会社にてZaif・mijin・COMSAの全事業に従事し、コンテンツ、マーケティング、経営企画を担当。
2020年春にNEMブロックチェーンの普及推進を図るNPO法人起ち上げを呼びかけ、同年8月にNPO法人NEM技術普及推進会NEMTUSを設立し理事長に就任。
2022年1月、Atomos-Seed合同会社を設立。2022年4月、フードNFTコンソーシアムを設立し共同代表を務める。
●手塚 建一
1987年3月, 京都大学卒業。ヘキストジャパン株式会社に入社。明海大学で博士号を取得後、米国メルク社でポスドク研究員。1997年に帰国後は、東京理科大学講師、岐阜大学准教授として、骨代謝研究をおこなう。骨の形態シミュレーションをきっかけにITを使った研究にも従事。科学技術振興機構さきがけ研究員を兼任。親知らずから単離した歯髄細胞からiPS細胞を誘導して、京都大学山中教授とともに米国・国際歯学会論文賞受賞。現在は株式会社しずい細胞研究所代表取締役を兼任。ブロックチェーンを使った歯髄細胞トレーサビリティシステム「ShizuiNet」を構築し、現在に至る。
●茅原 拓人
大学卒業後、大手住宅メーカーにて建築設計職としてキャリアをスタート。
その後、東南アジアを中心に海外建設プロジェクトのプロジェクトマネージャーとして、
日系企業の海外工場建設およびODA・JICA支援の国際インフラプロジェクトに多数従事した。
近年は、ブロックチェーン技術を活用した一次産業のデジタル化に注力。
日本では過去3年間、自然薯およびお米を対象とした農産物のトレーサビリティ(生産履歴管理)を導入し、生産から出荷までの流通情報を可視化することで、安全性・信頼性の向上と農家支援を実現。その実績をもとに、グループ会社のあるタイ王国では、医療用植物に対するブロックチェーン型トレーサビリティの実証運用を進行中。合法かつ透明な管理体制構築を目指す、アジア発の先進事例として注目されている。
●嘉村 哲郎
東京藝術大学 芸術情報センター 准教授。NPO法人Linked Open Data Initiative理事。
専門は博物館情報の組織化、芸術作品・資料等のデジタル化およびアーカイブ。主な著書・論文に『デジタルアーカイブ・ベーシックス デジタルデータの長期保存・活用』 (責任編集、勉誠出版、2025年)、「博物館・図書館・文書館から見たアーカイブ史 」 (『デジタル時代のアーカイブ系譜学』みすず書房、2022年)、「デジタルアーカイブにおける分散型情報技術を用いたコンテンツ管理と流通」 (『デジタルアーカイブ学会誌』6 (s3)、2022年)、「著名な日本人洋画家の属性分析に基づく特徴抽出の試み」 (共同執筆、『人工知能学会全国大会論文集』2020年)などがある。
●中島 理男
株式会社NFTDriveの代表取締役である中島理男氏は、ブロックチェーン技術の専門家です。同社は、2022年12月に自身が発行したフルオンチェーンNFTを返礼品とするクラウドファンディングを実施し、目標額を上回る支援金を集めて2023年3月に設立されました。デジタルアーカイブ学会のイベントで登壇し、ファクトチェックにおけるブロックチェーンの活用について解説したほか、同会の研究大会では共同研究発表も行っています。2023年には、日本ブロックチェーン協会から「BlockChain Award 05 person of the year JAPAN」を受賞しました。NFTDriveの開発者として、ブロックチェーン技術の社会実装を推進しています。
<講演概要>
本セッションでは、ブロックチェーン技術が実際にどのように活用・運用されているのか、各分野の専門家や第一線のディレクター、開発者を交え、実事例を通して紹介する。『フードNFTの実用と今後』、 『ブロックチェーンデジタルアーカイブとDAOの実践』 、『[農業] [医療] ×トレーサビリティ』の3つのジャンルについて、最新の動向を取り上げながら、使い所や課題、未来像を多角的に探る。
<プロフィール>
●後藤 博之
2009年ビットコイン誕生後、ブロックチェーン研究を開始、関連事業のサポート業務に従事。
2017年10月から2019年9月まで、テックビューロ株式会社にてZaif・mijin・COMSAの全事業に従事し、コンテンツ、マーケティング、経営企画を担当。
2020年春にNEMブロックチェーンの普及推進を図るNPO法人起ち上げを呼びかけ、同年8月にNPO法人NEM技術普及推進会NEMTUSを設立し理事長に就任。
2022年1月、Atomos-Seed合同会社を設立。2022年4月、フードNFTコンソーシアムを設立し共同代表を務める。
●手塚 建一
1987年3月, 京都大学卒業。ヘキストジャパン株式会社に入社。明海大学で博士号を取得後、米国メルク社でポスドク研究員。1997年に帰国後は、東京理科大学講師、岐阜大学准教授として、骨代謝研究をおこなう。骨の形態シミュレーションをきっかけにITを使った研究にも従事。科学技術振興機構さきがけ研究員を兼任。親知らずから単離した歯髄細胞からiPS細胞を誘導して、京都大学山中教授とともに米国・国際歯学会論文賞受賞。現在は株式会社しずい細胞研究所代表取締役を兼任。ブロックチェーンを使った歯髄細胞トレーサビリティシステム「ShizuiNet」を構築し、現在に至る。
●茅原 拓人
大学卒業後、大手住宅メーカーにて建築設計職としてキャリアをスタート。
その後、東南アジアを中心に海外建設プロジェクトのプロジェクトマネージャーとして、
日系企業の海外工場建設およびODA・JICA支援の国際インフラプロジェクトに多数従事した。
近年は、ブロックチェーン技術を活用した一次産業のデジタル化に注力。
日本では過去3年間、自然薯およびお米を対象とした農産物のトレーサビリティ(生産履歴管理)を導入し、生産から出荷までの流通情報を可視化することで、安全性・信頼性の向上と農家支援を実現。その実績をもとに、グループ会社のあるタイ王国では、医療用植物に対するブロックチェーン型トレーサビリティの実証運用を進行中。合法かつ透明な管理体制構築を目指す、アジア発の先進事例として注目されている。
●嘉村 哲郎
東京藝術大学 芸術情報センター 准教授。NPO法人Linked Open Data Initiative理事。
専門は博物館情報の組織化、芸術作品・資料等のデジタル化およびアーカイブ。主な著書・論文に『デジタルアーカイブ・ベーシックス デジタルデータの長期保存・活用』 (責任編集、勉誠出版、2025年)、「博物館・図書館・文書館から見たアーカイブ史 」 (『デジタル時代のアーカイブ系譜学』みすず書房、2022年)、「デジタルアーカイブにおける分散型情報技術を用いたコンテンツ管理と流通」 (『デジタルアーカイブ学会誌』6 (s3)、2022年)、「著名な日本人洋画家の属性分析に基づく特徴抽出の試み」 (共同執筆、『人工知能学会全国大会論文集』2020年)などがある。
●中島 理男
株式会社NFTDriveの代表取締役である中島理男氏は、ブロックチェーン技術の専門家です。同社は、2022年12月に自身が発行したフルオンチェーンNFTを返礼品とするクラウドファンディングを実施し、目標額を上回る支援金を集めて2023年3月に設立されました。デジタルアーカイブ学会のイベントで登壇し、ファクトチェックにおけるブロックチェーンの活用について解説したほか、同会の研究大会では共同研究発表も行っています。2023年には、日本ブロックチェーン協会から「BlockChain Award 05 person of the year JAPAN」を受賞しました。NFTDriveの開発者として、ブロックチェーン技術の社会実装を推進しています。
みんなのあしあと2.0 デジタル販促でのNFT活用のポテンシャル

|
SUSHI TOP MARKETING(株) 代表取締役CEO 徳永 大輔 |

|


|
(株)電通 電通 MCx室BX業務推進1部 部長 伊藤 弘和 |
|
<講演概要>
全国のテレビ局と展開する「みんなのあしあと2.0」において、NFTを活用したデジタル販促の実証事例を紹介する。本取り組みでは番組視聴や商品購入とNFTを連動させることにより、“体験の可視化”や“関係性のトークングラフ化”を実現する。これにより、Web3時代における広告の新たな可能性に迫る。
<プロフィール>
●徳永 大輔
立命館大学卒業、新卒で「山と渓谷社」に入社。SEOメディアで起業し事業売却を経験。
トークングラフマーケティングの文化創造をミッションに掲げるSUSHITOPMARKETING株式会社を2021年に創業し、現在に至る。
●伊藤 弘和
2019年に佐久間氏と共に「あちこちオードリー」の放送と、日本最大規模になった配信LIVEの立ち上げを主導。既成概念にとらわれないコンテンツビジネス開発に従事、戦略から事業成長のための協業までをオーガナイズ。複数の高校生イベント立ち上げやIP事業開発に従事。生活者に対して、コンテンツ体験価値の最大化を推進している。
<講演概要>
全国のテレビ局と展開する「みんなのあしあと2.0」において、NFTを活用したデジタル販促の実証事例を紹介する。本取り組みでは番組視聴や商品購入とNFTを連動させることにより、“体験の可視化”や“関係性のトークングラフ化”を実現する。これにより、Web3時代における広告の新たな可能性に迫る。
<プロフィール>
●徳永 大輔
立命館大学卒業、新卒で「山と渓谷社」に入社。SEOメディアで起業し事業売却を経験。
トークングラフマーケティングの文化創造をミッションに掲げるSUSHITOPMARKETING株式会社を2021年に創業し、現在に至る。
●伊藤 弘和
2019年に佐久間氏と共に「あちこちオードリー」の放送と、日本最大規模になった配信LIVEの立ち上げを主導。既成概念にとらわれないコンテンツビジネス開発に従事、戦略から事業成長のための協業までをオーガナイズ。複数の高校生イベント立ち上げやIP事業開発に従事。生活者に対して、コンテンツ体験価値の最大化を推進している。
XREALが描くARグラスの未来 ~次世代の体験と社会実装~

|
XREAL(株) プロダクトマネージャー 高 天夫 |
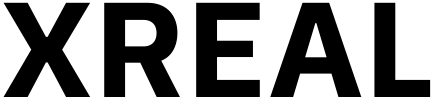
|
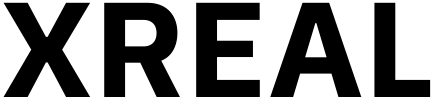
<講演概要>
XREALのARグラスが提供する「どこでも大画面」という新しい視聴体験。その一次世代体験を起点に、エンタメから産業利用まで広がる社会実装の今と、空間コンピューティングが実現する未来のライフスタイルを展望します。
<プロフィール>
大学卒業後、Apple、IKEAのセールス担当として高い販売実績を記録。その後、Huawei Japanに入社し、PC・タブレット事業のGTM(Go-to-Market)担当として、製品プロモーションや販売戦略の企画立案を経験。2022年10月よりXREAL(旧Nreal)に参画。プロダクトマネージャーとして日本市場に適したAR技術の普及戦略や製品定義を策定。現在はプロダクトや企画案担当として、メディアやKOL、パートナー企業との連携を強化し、ARグラスの更なる可能性を広めるべく活動している。
<講演概要>
XREALのARグラスが提供する「どこでも大画面」という新しい視聴体験。その一次世代体験を起点に、エンタメから産業利用まで広がる社会実装の今と、空間コンピューティングが実現する未来のライフスタイルを展望します。
<プロフィール>
大学卒業後、Apple、IKEAのセールス担当として高い販売実績を記録。その後、Huawei Japanに入社し、PC・タブレット事業のGTM(Go-to-Market)担当として、製品プロモーションや販売戦略の企画立案を経験。2022年10月よりXREAL(旧Nreal)に参画。プロダクトマネージャーとして日本市場に適したAR技術の普及戦略や製品定義を策定。現在はプロダクトや企画案担当として、メディアやKOL、パートナー企業との連携を強化し、ARグラスの更なる可能性を広めるべく活動している。
Beyond Reality:AI × XRが描く未来

|
カーネギーメロン大学 創始者記念全学教授 Metaverse Japan Lab名誉顧問 金出 武雄 |
|

|
(株)みずほフィナンシャルグループ 執行役員 CBDO (一社)Metaverse Japan 理事 中馬 和彦 |
|

|
麗澤大学 工学部 教授 東京大学大学院情報学環 特任准教授/ (株)HYPER CUBE 取締役CTO/ (一社)Metaverse Japan アドバイザー 小塩 篤史 |
|

|
(一社)Metaverse Japan 代表理事/ Xinobi AI(株) 共同CEO/ (一社)Generative AI Japan 代表理事/ JDLA 有識者会員 馬渕 邦美 |

|

<講演概要>
AIとXR(拡張現実)の融合は、私たちの生活や産業構造に大きな変革をもたらしています。生成AIによる空間創造、自然な対話を実現するインターフェース、5G/6Gインフラによる超低遅延の体験環境。これらの進化は、教育・医療・働き方・都市デザインなどあらゆる領域に広がりつつあります。本セッションでは、研究・文化・通信インフラの専門家が集い、「Beyond Reality=現実を超えた体験」が社会にどう浸透し、次世代の社会基盤となっていくのかを議論します。
<プロフィール>
●金出 武雄
知能ロボット・コンピュータビジョン研究者。顔画像認識、自動運転、「アイビジョン」多数カメラ画像技術などの開発。現在、カーネギーメロン大学創始者記念全学教授、京都大学高等研究院招聘特別教授。京都賞、米国フランクリン財団メダル・バウアー賞、IEEE創始者記念メダル、米国人工知能学会アレン・ニューウェル賞、スペインBBVA財団知識のフロンティア賞など受賞。文化功労者、米国工学アカデミー特別会員、日本学士院会員。
●中馬 和彦
みずほフィナンシャルグループにおいてオープンイノベーションによる新規事業を統括。「新しい資本主義実現会議」スタートアップ育成分科会委員、経済産業省 J-Startup推薦委員、経団連スタートアップエコシステム変革TF委員、東京大学大学院工学系研究科非常勤講師、一般社団法人日本オープンイノベーション研究会理事、他多数。
一般社団法人Metaverse Japan 理事/みずほフィナンシャルグループ 執行役員 CBDO
●小塩 篤史
データサイエンス・人工知能領域の研究を背景に、研究者・起業家としてAIやメタバースなどのデジタル技術による人間の可能性の拡張をすすめる。特に、医療・教育などの人間と密接に関わる領域でのITやAIの研究開発を行い、生成AIをベースにひとに寄り添う「やさしいAI・メタバース」の社会実装を行う。東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院客員研究員、東京大学空間情報科学研究センター等を経て、現職。
●馬渕 邦美
•2009年:世界No2広告代理店グループのオムニコムのデジタル・エージェンシー
Tribal DDB Tokyo ジェネラル・マネージャーに就任
•2012年:WPPグループである世界No1広告代理店オグルヴィ・ワン・ジャパン株
式会社、ネオ・アット・オグルヴィ株式会社の代表取締役に就任。2016年:オム
ニコム・グループのNo1PRエージェンシーであるフライシュマン・ヒラード
SVP&Partner。
•2017年:PwCコンサルティング合同会社のエグゼクティブ・アドバイザー就任。
•2018年:Facebook Japan Director (META) 役員に就任
インスタグラムの日本における3500万MAU、世界第2位の達成、APACにおける
No1のJapan Revenue Growthを成功させた
•2020年:PwCコンサルティング合同会社 パートナー 執行役員
•2024年:デロイトトーマツコンサルティング合同会社 パートナー 執行役員
<講演概要>
AIとXR(拡張現実)の融合は、私たちの生活や産業構造に大きな変革をもたらしています。生成AIによる空間創造、自然な対話を実現するインターフェース、5G/6Gインフラによる超低遅延の体験環境。これらの進化は、教育・医療・働き方・都市デザインなどあらゆる領域に広がりつつあります。本セッションでは、研究・文化・通信インフラの専門家が集い、「Beyond Reality=現実を超えた体験」が社会にどう浸透し、次世代の社会基盤となっていくのかを議論します。
<プロフィール>
●金出 武雄
知能ロボット・コンピュータビジョン研究者。顔画像認識、自動運転、「アイビジョン」多数カメラ画像技術などの開発。現在、カーネギーメロン大学創始者記念全学教授、京都大学高等研究院招聘特別教授。京都賞、米国フランクリン財団メダル・バウアー賞、IEEE創始者記念メダル、米国人工知能学会アレン・ニューウェル賞、スペインBBVA財団知識のフロンティア賞など受賞。文化功労者、米国工学アカデミー特別会員、日本学士院会員。
●中馬 和彦
みずほフィナンシャルグループにおいてオープンイノベーションによる新規事業を統括。「新しい資本主義実現会議」スタートアップ育成分科会委員、経済産業省 J-Startup推薦委員、経団連スタートアップエコシステム変革TF委員、東京大学大学院工学系研究科非常勤講師、一般社団法人日本オープンイノベーション研究会理事、他多数。
一般社団法人Metaverse Japan 理事/みずほフィナンシャルグループ 執行役員 CBDO
●小塩 篤史
データサイエンス・人工知能領域の研究を背景に、研究者・起業家としてAIやメタバースなどのデジタル技術による人間の可能性の拡張をすすめる。特に、医療・教育などの人間と密接に関わる領域でのITやAIの研究開発を行い、生成AIをベースにひとに寄り添う「やさしいAI・メタバース」の社会実装を行う。東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院客員研究員、東京大学空間情報科学研究センター等を経て、現職。
●馬渕 邦美
•2009年:世界No2広告代理店グループのオムニコムのデジタル・エージェンシー
Tribal DDB Tokyo ジェネラル・マネージャーに就任
•2012年:WPPグループである世界No1広告代理店オグルヴィ・ワン・ジャパン株
式会社、ネオ・アット・オグルヴィ株式会社の代表取締役に就任。2016年:オム
ニコム・グループのNo1PRエージェンシーであるフライシュマン・ヒラード
SVP&Partner。
•2017年:PwCコンサルティング合同会社のエグゼクティブ・アドバイザー就任。
•2018年:Facebook Japan Director (META) 役員に就任
インスタグラムの日本における3500万MAU、世界第2位の達成、APACにおける
No1のJapan Revenue Growthを成功させた
•2020年:PwCコンサルティング合同会社 パートナー 執行役員
•2024年:デロイトトーマツコンサルティング合同会社 パートナー 執行役員
IP×XRで描く次世代エンターテインメントの未来
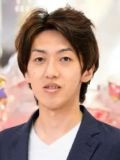
|
(株)サンリオ デジタル事業開発部 ゼネラルマネージャー 町田 雄史 |

|


|
(株)Gugenka 代表取締役 CEO 三上 昌史 |

|

<講演概要>
サンリオは長期ビジョンとして“グローバルIPプラットフォーマー”を掲げている。本講演では、その中核を担うデジタル事業の戦略と、IPを活用したXR領域における体験設計やGugenkaとの共創の取り組み、実証から事業化までの道筋を紹介する。
<プロフィール>
●町田 雄史
2008年株式会社サンリオ入社。デジタルライセンス事業、新規IP事業、エンタメ事業に従事し、2012年に音楽をテーマとした新キャラクタープロジェクト「SHOW BY ROCK!!」を立ち上げ、2022年に10周年を迎える。
新たなエンターテインメントの追求を続け、2021年にはVR上の音楽フェス「SANRIO Virtual Fes in Sanrio Puroland」を立ち上げた。
現在はデジタルコンテンツを中心に新規事業を担当し、世界中のファンに驚きやワクワクを提供するため挑戦を続けている。
●三上 昌史
2003年に独立し、2005年に株式会社シーエスレポーターズを創業。2021年に株式会社Gugenkaへ社名変更し、代表取締役CEOとしてXRやメタバースを活用したIPビジネスを推進。国内外でキャラクターやエンターテインメントを軸に新たな体験を創出している。
<講演概要>
サンリオは長期ビジョンとして“グローバルIPプラットフォーマー”を掲げている。本講演では、その中核を担うデジタル事業の戦略と、IPを活用したXR領域における体験設計やGugenkaとの共創の取り組み、実証から事業化までの道筋を紹介する。
<プロフィール>
●町田 雄史
2008年株式会社サンリオ入社。デジタルライセンス事業、新規IP事業、エンタメ事業に従事し、2012年に音楽をテーマとした新キャラクタープロジェクト「SHOW BY ROCK!!」を立ち上げ、2022年に10周年を迎える。
新たなエンターテインメントの追求を続け、2021年にはVR上の音楽フェス「SANRIO Virtual Fes in Sanrio Puroland」を立ち上げた。
現在はデジタルコンテンツを中心に新規事業を担当し、世界中のファンに驚きやワクワクを提供するため挑戦を続けている。
●三上 昌史
2003年に独立し、2005年に株式会社シーエスレポーターズを創業。2021年に株式会社Gugenkaへ社名変更し、代表取締役CEOとしてXRやメタバースを活用したIPビジネスを推進。国内外でキャラクターやエンターテインメントを軸に新たな体験を創出している。
フィジカルAIとデジタルツインが変革する産業デジタル化

|
NVIDIA(同) エンタープライズマーケティング シニアマネージャ 田中 秀明 |

|

<講演概要>
Omniverseによるデジタルツイン構築とCosmosの連携が可能にする産業でのフィジカルAI活用、そして工場デジタルツインのMega BlueprintやCAEリアルタイム化など産業デジタル化に向けたNVIDIAの取り組みをご紹介します。
<プロフィール>
外資系コンピューター企業にて、UNIXシステム、CADワークステーションのサポートを経て、1995年からプロダクトマーケティングとしてネットワーク、デスクトップPC、ワークステーション、エンタープライズサーバー製品を担当する。2016年にNVIDIAに入社、現在プロフェッショナルビジュアライゼーションのマーケティング担当に従事している。
<講演概要>
Omniverseによるデジタルツイン構築とCosmosの連携が可能にする産業でのフィジカルAI活用、そして工場デジタルツインのMega BlueprintやCAEリアルタイム化など産業デジタル化に向けたNVIDIAの取り組みをご紹介します。
<プロフィール>
外資系コンピューター企業にて、UNIXシステム、CADワークステーションのサポートを経て、1995年からプロダクトマーケティングとしてネットワーク、デスクトップPC、ワークステーション、エンタープライズサーバー製品を担当する。2016年にNVIDIAに入社、現在プロフェッショナルビジュアライゼーションのマーケティング担当に従事している。
XR × レジリエンス:防災と地域社会の新時代

|
香川大学 四国危機管理教育・研究・推進機構 特任教授 副機構長 学長特別補佐 金田 義行 |
|

|
(株)MetaEarthHeroes 代表取締役 木村 麻子 |
|

|
(株)Meta Osaka 代表取締役 毛利 英昭 |

|


|
(一社)Metaverse Japan 代表理事/ Xinobi AI(株) 共同CEO/ (一社)Generative AI Japan 代表理事/ JDLA 有識者会員 馬渕 邦美 |

|

<講演概要>
自然災害や人口減少といった課題に直面する地域社会において、XRやデジタルツインは新たな解決の手段となりつつあります。災害時の避難訓練を仮想空間で体験することで“もしも”への備えを強化し、地域資源をメタバースで発信することで新しい人流や産業を呼び込む。国の政策、自治体の実践、学術研究を横断する議論を通じて、XRがいかに防災と地方創生を結びつけ、より強靭で持続可能な社会をつくるのかを探ります。
<プロフィール>
●金田 義行
1953年東京生まれ。東京大学理学部研究科大学院地球物理専攻修士課程修了(理学博士)し、
専門は地震学、減災科学研究である、現在は香川大学 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構副機構、地域強靭化研究センター長、特任教授として減災科学研究を推進している。
現在、JICA-JST地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)トルコ防災課題統括責任者や
情報開発機構:データ利活用等のデジタル化の推進による社会課題・地域課題解決のための実証型研究開発課題の研究代表者として研究を行っている。
これまで、文部科学省委託研究「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト」総括責任者。情報科学技術委員会ほか多数を歴任し、著書:『先端巨大科学で探る地球』(東京大学出版会)など多数がある。
●木村 麻子
香川県出身
令和5年度日本商工会議所青年部女性初の会長就任。SDGs推進円卓会議構成委員、2025大阪・関西万博具現化検 討会有識者、持続可能な地方創生、日本版SDGs推進のまちづくりのブランディング企画、女性や若者に選ばれる新しい組織づくり講演やリーダー育成、アドバイザーとしても活躍。
●毛利 英昭
大阪で25年以上不動産業を営み、地域に根ざした事業を展開してきた毛利は、デジタルの力で大阪独自の文化やアイデンティティを守り発展させたいという想いから、2023年9月に株式会社Meta Osakaを設立。「大阪を世界一おもろい都市に」をミッションとし、メタバース技術を用いた地域課題解決に取り組む。大阪城や道頓堀を精巧に再現したFortniteマップの制作、柏原市との包括連携協定など、デジタル空間を活用した地域活性化を推進している。今年5月にはEXPO2025大阪・関西万博の会場で「メタバース・XR・AIアワード」を開催し、2日間で約15,000人を動員した。全国で累計5万人を動員した「こども万博」を主催し、10月にも万博会場での開催が決定している。
●馬渕 邦美
•2009年:世界No2広告代理店グループのオムニコムのデジタル・エージェンシー
Tribal DDB Tokyo ジェネラル・マネージャーに就任
•2012年:WPPグループである世界No1広告代理店オグルヴィ・ワン・ジャパン株
式会社、ネオ・アット・オグルヴィ株式会社の代表取締役に就任。2016年:オム
ニコム・グループのNo1PRエージェンシーであるフライシュマン・ヒラード
SVP&Partner。
•2017年:PwCコンサルティング合同会社のエグゼクティブ・アドバイザー就任。
•2018年:Facebook Japan Director (META) 役員に就任
インスタグラムの日本における3500万MAU、世界第2位の達成、APACにおける
No1のJapan Revenue Growthを成功させた
•2020年:PwCコンサルティング合同会社 パートナー 執行役員
•2024年:デロイトトーマツコンサルティング合同会社 パートナー 執行役員
<講演概要>
自然災害や人口減少といった課題に直面する地域社会において、XRやデジタルツインは新たな解決の手段となりつつあります。災害時の避難訓練を仮想空間で体験することで“もしも”への備えを強化し、地域資源をメタバースで発信することで新しい人流や産業を呼び込む。国の政策、自治体の実践、学術研究を横断する議論を通じて、XRがいかに防災と地方創生を結びつけ、より強靭で持続可能な社会をつくるのかを探ります。
<プロフィール>
●金田 義行
1953年東京生まれ。東京大学理学部研究科大学院地球物理専攻修士課程修了(理学博士)し、
専門は地震学、減災科学研究である、現在は香川大学 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構副機構、地域強靭化研究センター長、特任教授として減災科学研究を推進している。
現在、JICA-JST地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)トルコ防災課題統括責任者や
情報開発機構:データ利活用等のデジタル化の推進による社会課題・地域課題解決のための実証型研究開発課題の研究代表者として研究を行っている。
これまで、文部科学省委託研究「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト」総括責任者。情報科学技術委員会ほか多数を歴任し、著書:『先端巨大科学で探る地球』(東京大学出版会)など多数がある。
●木村 麻子
香川県出身
令和5年度日本商工会議所青年部女性初の会長就任。SDGs推進円卓会議構成委員、2025大阪・関西万博具現化検 討会有識者、持続可能な地方創生、日本版SDGs推進のまちづくりのブランディング企画、女性や若者に選ばれる新しい組織づくり講演やリーダー育成、アドバイザーとしても活躍。
●毛利 英昭
大阪で25年以上不動産業を営み、地域に根ざした事業を展開してきた毛利は、デジタルの力で大阪独自の文化やアイデンティティを守り発展させたいという想いから、2023年9月に株式会社Meta Osakaを設立。「大阪を世界一おもろい都市に」をミッションとし、メタバース技術を用いた地域課題解決に取り組む。大阪城や道頓堀を精巧に再現したFortniteマップの制作、柏原市との包括連携協定など、デジタル空間を活用した地域活性化を推進している。今年5月にはEXPO2025大阪・関西万博の会場で「メタバース・XR・AIアワード」を開催し、2日間で約15,000人を動員した。全国で累計5万人を動員した「こども万博」を主催し、10月にも万博会場での開催が決定している。
●馬渕 邦美
•2009年:世界No2広告代理店グループのオムニコムのデジタル・エージェンシー
Tribal DDB Tokyo ジェネラル・マネージャーに就任
•2012年:WPPグループである世界No1広告代理店オグルヴィ・ワン・ジャパン株
式会社、ネオ・アット・オグルヴィ株式会社の代表取締役に就任。2016年:オム
ニコム・グループのNo1PRエージェンシーであるフライシュマン・ヒラード
SVP&Partner。
•2017年:PwCコンサルティング合同会社のエグゼクティブ・アドバイザー就任。
•2018年:Facebook Japan Director (META) 役員に就任
インスタグラムの日本における3500万MAU、世界第2位の達成、APACにおける
No1のJapan Revenue Growthを成功させた
•2020年:PwCコンサルティング合同会社 パートナー 執行役員
•2024年:デロイトトーマツコンサルティング合同会社 パートナー 執行役員
AI時代必見!大集客を実現したXR体験最前線

|
(株)HIKKY CEO 舟越 靖 |

|

<講演概要>
AIと融合したXR活用は、企業や自治体のマーケティング手法を劇的に進化させている。本講演では、最新の業界動向を踏まえ、リアルでの大規模集客を実現したXRイベント「Vket Real」の成功事例を解説。リアルとバーチャルをつなぐ共創型メタバース体験が生み出す価値と、ビジネスへの応用ポイントをわかりやすく紹介する。
<プロフィール>
大手通信会社退職後、⾃身の夢だったクリエイティブ分野へ進出。2008年からクリエイターの潜在力を既存市場以外で活かす挑戦を試みる。あらゆるシーンで成果を得て、ハードウェアからゲーム・アニメ・映画など様々なコンテンツ制作・広告サービス、サービス開発を手掛ける法人を複数社立ち上げた。2018年メタバース事業に特化した「株式会社HIKKY」を設立、ギネス世界記録™を樹立した130万人以上が来場する「バーチャルマーケット」を主催。業界最多である企業のメタバース事業化の実績を元に、市場参入コンサルティング、VR空間コンテンツ制作、リアル連動型サービス開発などのメタバースソリューションを提供するほか、WEBブラウザ上で動く、完全オリジナルのメタバース開発サービス「Vket Cloud」を提供。
<講演概要>
AIと融合したXR活用は、企業や自治体のマーケティング手法を劇的に進化させている。本講演では、最新の業界動向を踏まえ、リアルでの大規模集客を実現したXRイベント「Vket Real」の成功事例を解説。リアルとバーチャルをつなぐ共創型メタバース体験が生み出す価値と、ビジネスへの応用ポイントをわかりやすく紹介する。
<プロフィール>
大手通信会社退職後、⾃身の夢だったクリエイティブ分野へ進出。2008年からクリエイターの潜在力を既存市場以外で活かす挑戦を試みる。あらゆるシーンで成果を得て、ハードウェアからゲーム・アニメ・映画など様々なコンテンツ制作・広告サービス、サービス開発を手掛ける法人を複数社立ち上げた。2018年メタバース事業に特化した「株式会社HIKKY」を設立、ギネス世界記録™を樹立した130万人以上が来場する「バーチャルマーケット」を主催。業界最多である企業のメタバース事業化の実績を元に、市場参入コンサルティング、VR空間コンテンツ制作、リアル連動型サービス開発などのメタバースソリューションを提供するほか、WEBブラウザ上で動く、完全オリジナルのメタバース開発サービス「Vket Cloud」を提供。
世界をつなぐ体験デザイン ― グローバル世代に響く学びとブランド体験

|
Roblox マーケティング本部 本部長 梅林 桜子 |
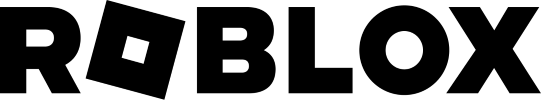
|
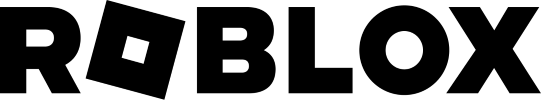

|
トランスコスモス(株) CX事業統括 CX事業推進本部 メタバース推進部 部長 メタバースストラテジスト 光田 刃 |

|


|
(一社)Metaverse Japan 代表理事/ (一社)渋谷未来デザイン 理事・事務局長 長田 新子 |

|

<講演概要>
メタバースという概念は、かつての特別なものから日常へと進化し、α世代からZ世代まで幅広い層に浸透しています。UGC(User Generated Content)の発展により、誰もが参加し創造できるグローバルなエコシステムが形成され、教育やブランド体験、文化発信など多様な領域で新しい価値が生まれています。
本セッションでは、世界で爆発的に広がるRobloxから日本のマーケティング責任者と、トランスコスモスのメタバース事業責任者を迎え、メタバースにおける日本発コンテンツのグローバル展開や、世代を超えて響く体験デザインの可能性について語ります。
<プロフィール>
●梅林 桜子
Google米国本社にてARおよびAI製品のマーケティングを担当した後、Roblox米国本社に入社。現在は日本を含むアジア太平洋地域のマーケティング本部長として、市場開拓やブランド戦略を推進している。3児の母としての視点も活かし、子どもたちが安心して楽しみ、学べる次世代デジタル体験の普及に取り組んでいる。
●光田 刃
2009年トランスコスモス株式会社入社。
コンタクトセンター事業のサービス設計・運営、企画、営業を経験後、責任者としてマーケティング部門を立ち上げ。
2022年よりWeb3やメタバース関連の新規事業を立ち上げ、
2023年2月にメタバース推進部を新設。
メタバースを活用した若年層/グローバルマーケティング支援を展開。
2024年より「Roblox」や「Fortnite」を活用した若年層・グローバル市場向けのマーケティング施策を推進し、松井証券、渋谷未来デザイン、HIS、バンダイ(たまごっち)、アサヒ飲料など多様な企業との取り組みを展開。
メタバースを通じた企業とユーザーの接点を進化させるべく、最適な活用方法を日々探求中。
●長田 新子
AT&T、ノキアにて通信・企業システム営業、マーケティング及び広報責任者を経て2007年にレッドブル・ジャパンに入社。コミュニケーション統括責任者及びマーケティング本部長(CMO)として10年半、エナジードリンクのカテゴリー確立及びブランド・製品を市場に浸透させるべく従事し2017年に退社。2018年から渋谷区にて設立された(一社)渋谷未来デザイン理事・事務局長として、都市の多様な可能性をデザインするプロジェクト活動を推進。
2018年にNEW KIDS(株)を立ち上げ、ブランド、コミュニティ・アスリート・イベント関連のアドバイザーや講演活動等を行いながら、Metaverse Japan代表理事、日本ダンススポーツ連盟理事、マーケターキャリア協会理事、シブヤ・スマートシティ推進機構理事、(株)SAKUSEN TOKYO 社外取締役、コミューン(株)顧問等の活動も行なっている。
著書に「アスリート×ブランド感動と興奮を分かち合うスポーツシーンのつくり方」(宣伝会議)、渋谷未来デザイン編・著書として「変わり続ける︕ シブヤ系まちづくり」(工作舎)を出版。
受賞歴:
バーチャルハロウィン企画:第7回JACEイベントアワード 最優秀賞「経済産業大臣賞」(2020年)
日本アドバタイザーズ協会デジタルマーケティング研究機構の第11回Webグランプリ「Web人賞」(2023年)
AIR RACE X:スポーツ庁主催SPORTS INNOVATION STUDIOコンテスト 「パイオニア賞」(2023年)
<講演概要>
メタバースという概念は、かつての特別なものから日常へと進化し、α世代からZ世代まで幅広い層に浸透しています。UGC(User Generated Content)の発展により、誰もが参加し創造できるグローバルなエコシステムが形成され、教育やブランド体験、文化発信など多様な領域で新しい価値が生まれています。
本セッションでは、世界で爆発的に広がるRobloxから日本のマーケティング責任者と、トランスコスモスのメタバース事業責任者を迎え、メタバースにおける日本発コンテンツのグローバル展開や、世代を超えて響く体験デザインの可能性について語ります。
<プロフィール>
●梅林 桜子
Google米国本社にてARおよびAI製品のマーケティングを担当した後、Roblox米国本社に入社。現在は日本を含むアジア太平洋地域のマーケティング本部長として、市場開拓やブランド戦略を推進している。3児の母としての視点も活かし、子どもたちが安心して楽しみ、学べる次世代デジタル体験の普及に取り組んでいる。
●光田 刃
2009年トランスコスモス株式会社入社。
コンタクトセンター事業のサービス設計・運営、企画、営業を経験後、責任者としてマーケティング部門を立ち上げ。
2022年よりWeb3やメタバース関連の新規事業を立ち上げ、
2023年2月にメタバース推進部を新設。
メタバースを活用した若年層/グローバルマーケティング支援を展開。
2024年より「Roblox」や「Fortnite」を活用した若年層・グローバル市場向けのマーケティング施策を推進し、松井証券、渋谷未来デザイン、HIS、バンダイ(たまごっち)、アサヒ飲料など多様な企業との取り組みを展開。
メタバースを通じた企業とユーザーの接点を進化させるべく、最適な活用方法を日々探求中。
●長田 新子
AT&T、ノキアにて通信・企業システム営業、マーケティング及び広報責任者を経て2007年にレッドブル・ジャパンに入社。コミュニケーション統括責任者及びマーケティング本部長(CMO)として10年半、エナジードリンクのカテゴリー確立及びブランド・製品を市場に浸透させるべく従事し2017年に退社。2018年から渋谷区にて設立された(一社)渋谷未来デザイン理事・事務局長として、都市の多様な可能性をデザインするプロジェクト活動を推進。
2018年にNEW KIDS(株)を立ち上げ、ブランド、コミュニティ・アスリート・イベント関連のアドバイザーや講演活動等を行いながら、Metaverse Japan代表理事、日本ダンススポーツ連盟理事、マーケターキャリア協会理事、シブヤ・スマートシティ推進機構理事、(株)SAKUSEN TOKYO 社外取締役、コミューン(株)顧問等の活動も行なっている。
著書に「アスリート×ブランド感動と興奮を分かち合うスポーツシーンのつくり方」(宣伝会議)、渋谷未来デザイン編・著書として「変わり続ける︕ シブヤ系まちづくり」(工作舎)を出版。
受賞歴:
バーチャルハロウィン企画:第7回JACEイベントアワード 最優秀賞「経済産業大臣賞」(2020年)
日本アドバタイザーズ協会デジタルマーケティング研究機構の第11回Webグランプリ「Web人賞」(2023年)
AIR RACE X:スポーツ庁主催SPORTS INNOVATION STUDIOコンテスト 「パイオニア賞」(2023年)
リアルとバーチャルをつなぐ“駅”空間 ─JR西日本グループが描くUGCとファン熱量を生むXR戦略

|
西日本旅客鉄道(株) ビジネスデザイン部 XR推進室 係長 (バーチャル大阪駅/バーチャル広島駅 当務駅長) 長沼 悠介 |

|

<講演概要>
「大阪駅」をバーチャル上に再現・拡張した「バーチャル大阪駅」を展開する中で、「リアルでの活躍の場を渇望するバーチャルニーズ」、「ユーザーが自律的にコンテンツを生み出すUGC」に可能性を見出し、”駅”を中心としたリアルアセット活用を主軸にユーザー巻き込み型の施策を行う、JR西日本グループの取り組みをご紹介いたします。
<プロフィール>
2013年に西日本旅客鉄道株式会社に入社。鉄道現業機関従事を経て、支社の輸送課にてダイヤの作成および車両・乗務員の運用を担当。2020年より本社の技術部門にて保安装置の運転ルールや取り扱いをまとめる業務に従事。2022年に、業務時間の20%を本業以外の活動に活用可能な制度を使い、有志メンバーでNFTを用いた事業を検討。2023年に社内ポスト公募制度を利用してビジネスデザイン部へ異動、「バーチャル大阪駅/広島駅」を中心としたXRとWeb3の新規事業の企画、運営を担当。
<講演概要>
「大阪駅」をバーチャル上に再現・拡張した「バーチャル大阪駅」を展開する中で、「リアルでの活躍の場を渇望するバーチャルニーズ」、「ユーザーが自律的にコンテンツを生み出すUGC」に可能性を見出し、”駅”を中心としたリアルアセット活用を主軸にユーザー巻き込み型の施策を行う、JR西日本グループの取り組みをご紹介いたします。
<プロフィール>
2013年に西日本旅客鉄道株式会社に入社。鉄道現業機関従事を経て、支社の輸送課にてダイヤの作成および車両・乗務員の運用を担当。2020年より本社の技術部門にて保安装置の運転ルールや取り扱いをまとめる業務に従事。2022年に、業務時間の20%を本業以外の活動に活用可能な制度を使い、有志メンバーでNFTを用いた事業を検討。2023年に社内ポスト公募制度を利用してビジネスデザイン部へ異動、「バーチャル大阪駅/広島駅」を中心としたXRとWeb3の新規事業の企画、運営を担当。


|
ベストプロトタイプ賞二次選考(ピッチ) 大きな可能性を秘めたプロトタイプ・アイデアを持つ ファイナリストによるピッチを開催! |

|

未来のメタバース・XRの姿を切り拓く、新進気鋭のプロジェクトが挑むベストプロトタイプ賞ファイナルピッチ(エントリー締切:9月11日)。開発途上ながらも大きな可能性を秘めたプロトタイプや斬新なアイデアを持つファイナリストたちが、自らの構想と挑戦を熱く語ります。革新的サービスや技術の誕生を間近で体感でき、審査員や観客からの反応が次なる飛躍の原動力となる瞬間に立ち会える絶好の機会。未来のビジネスパートナーや投資先との出会いも期待できます。
https://mvjaward.com/
未来のメタバース・XRの姿を切り拓く、新進気鋭のプロジェクトが挑むベストプロトタイプ賞ファイナルピッチ(エントリー締切:9月11日)。開発途上ながらも大きな可能性を秘めたプロトタイプや斬新なアイデアを持つファイナリストたちが、自らの構想と挑戦を熱く語ります。革新的サービスや技術の誕生を間近で体感でき、審査員や観客からの反応が次なる飛躍の原動力となる瞬間に立ち会える絶好の機会。未来のビジネスパートナーや投資先との出会いも期待できます。
https://mvjaward.com/


|
JAPAN Metaverse Awards 2025 表彰式 6部門の受賞者によるプレゼンテーション&表彰式 参加者同士による交流会も行います(飲食付き) |

|

国内外のメタバース・XR分野で革新をもたらしたプロジェクトを讃えるJAPAN Metaverse Awards 2025(エントリー締切:9月11日)。事前に選出された6部門の受賞者が集結し、それぞれの成果と未来へのビジョンをプレゼンテーションします。そして、この場で年間を通じた最高峰の栄誉・Best Performance Award(最優秀賞)が決定。第一線で活躍するクリエイターや企業の情熱に触れ、業界の潮流と次なる可能性を体感できる特別なステージです。https://mvjaward.com/
参加者の皆様にはドリンク、軽食をご用意しています。
国内外のメタバース・XR分野で革新をもたらしたプロジェクトを讃えるJAPAN Metaverse Awards 2025(エントリー締切:9月11日)。事前に選出された6部門の受賞者が集結し、それぞれの成果と未来へのビジョンをプレゼンテーションします。そして、この場で年間を通じた最高峰の栄誉・Best Performance Award(最優秀賞)が決定。第一線で活躍するクリエイターや企業の情熱に触れ、業界の潮流と次なる可能性を体感できる特別なステージです。https://mvjaward.com/
参加者の皆様にはドリンク、軽食をご用意しています。
受講券の発行方法をお選びください。