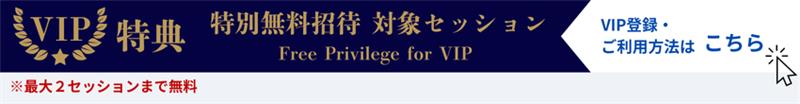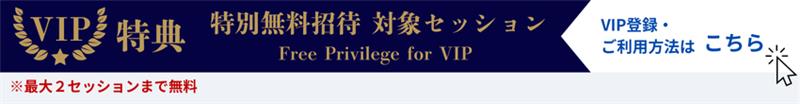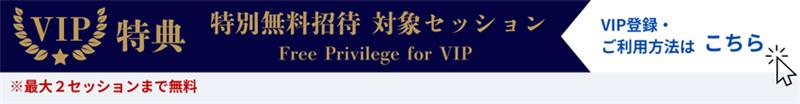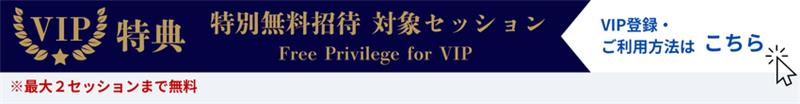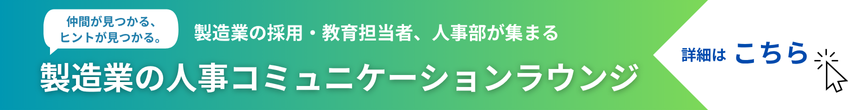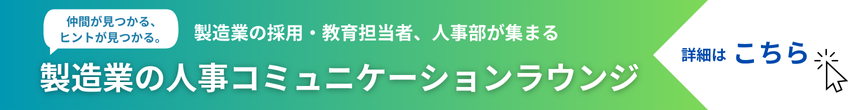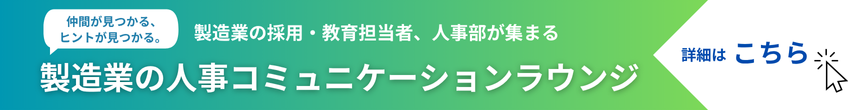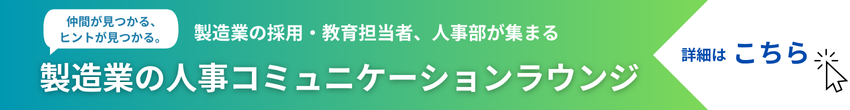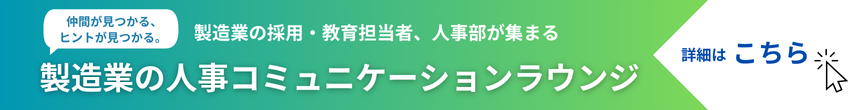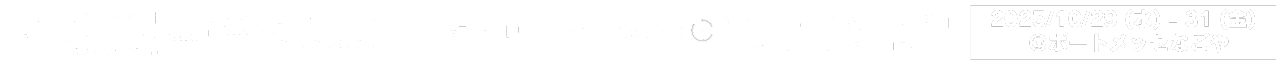
概要
【前回プログラム】本セミナーの開催は終了いたしました。
ご来場誠にありがとうございました。
次回は、2026年11月25日(水) ~27日(金) Aichi Sky Expoにて開催いたします。
<モデレーター>

|
トヨタ自動車(株) トヨタソフトウェアアカデミー 主査 チーフエバンジェリスト/ 岐阜大学 客員教授 成迫 剛志 |
|
講演内容
自動車業界、100年に一度の大変革期と言われ始めて早9年。そして、いよいよ本格的な SDV時代が到来しようとしている。 この Software Defined と言われる通り、クルマづくり、モビリティ社会づくりにとって、以前にも増してソフトウェアが重要となり、それを担うAI/ソフトウェア人財強化が求められている。 本講演では、この大きな潮流に対応するためにスタートしたトヨタソフトウェアアカデミーの取り組みについてご紹介する。
講演者プロフィール
米IBM、独SAP、中国方正集団、伊藤忠商事、ビットアイル・エクイニクスなどを経て2016年よりデンソーにて Out-Car ソフトウェア部隊の立ち上げを行う。2024年よりトヨタ自動車にてトヨタソフトウエアアカデミーの立ち上げに参画。2025年5月よりチーフ・エバンジェリスト。
講演内容
自動車業界、100年に一度の大変革期と言われ始めて早9年。そして、いよいよ本格的な SDV時代が到来しようとしている。 この Software Defined と言われる通り、クルマづくり、モビリティ社会づくりにとって、以前にも増してソフトウェアが重要となり、それを担うAI/ソフトウェア人財強化が求められている。 本講演では、この大きな潮流に対応するためにスタートしたトヨタソフトウェアアカデミーの取り組みについてご紹介する。
講演者プロフィール
米IBM、独SAP、中国方正集団、伊藤忠商事、ビットアイル・エクイニクスなどを経て2016年よりデンソーにて Out-Car ソフトウェア部隊の立ち上げを行う。2024年よりトヨタ自動車にてトヨタソフトウエアアカデミーの立ち上げに参画。2025年5月よりチーフ・エバンジェリスト。
<パネリスト>

|
(株)アイシン 製品開発センター 電子開発本部 理事 岩田 一行 |

|

講演者プロフィール
1997年アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 (現:株式会社アイシン)入社。
1999年AW Technical Center U.S.A., Inc.(現:AISIN World Corp. of America)オフィスの立上げ、2015年よりAW Technical Center Europe S.A. (現:AISIN EUROPE S.A.)にて海外OEM向け製品立上げを指揮。
2024年より製品開発センター 電子開発本部 グループソフトウェア強化担当 理事としてアイシングループのソフトウェア戦略を推進し、現在に至る。
講演者プロフィール
1997年アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 (現:株式会社アイシン)入社。
1999年AW Technical Center U.S.A., Inc.(現:AISIN World Corp. of America)オフィスの立上げ、2015年よりAW Technical Center Europe S.A. (現:AISIN EUROPE S.A.)にて海外OEM向け製品立上げを指揮。
2024年より製品開発センター 電子開発本部 グループソフトウェア強化担当 理事としてアイシングループのソフトウェア戦略を推進し、現在に至る。

|
ウーブン・バイ・トヨタ(株) Dojo ダイレクター 人材戦略部 ニコラス スミス |

|

講演者プロフィール
2020年 Woven by Toyota (当時TRI-AD株式会社)入社。
人材育成と戦略を主に担当。
現在、トヨタグループ内における人材の円滑な流動を実現するために、MS1という人材管理プラットフォームの開発を担当。
講演者プロフィール
2020年 Woven by Toyota (当時TRI-AD株式会社)入社。
人材育成と戦略を主に担当。
現在、トヨタグループ内における人材の円滑な流動を実現するために、MS1という人材管理プラットフォームの開発を担当。

|
(株)デンソー ソフトウェア統括部 ソフトキャリア支援室 課長 増子 敬 |

|

講演者プロフィール
1999年3月、明治大学卒業。株式会社デンソーに入社。デンソー工業技術短期大学校(現デンソー工業学園)に所属し若年エンジニア育成に従事。2014年からデンソーグループのソフトウェア人材開発を管轄する部門に異動し、教育や育成制度の企画・構築を担当、現在に至る。
講演者プロフィール
1999年3月、明治大学卒業。株式会社デンソーに入社。デンソー工業技術短期大学校(現デンソー工業学園)に所属し若年エンジニア育成に従事。2014年からデンソーグループのソフトウェア人材開発を管轄する部門に異動し、教育や育成制度の企画・構築を担当、現在に至る。

|
トヨタ自動車(株) トヨタソフトウェアアカデミー 主査 大西 悠季生 |

|

講演者プロフィール
2003年 大阪大学大学院卒、トヨタ自動車株式会社入社。
FCEVの制御ソフト・ハードの内製開発を皮切りに、Prius・AQUA向けインバータ、電池、HEV制御コントローラなどのパワートレイン開発を担当。近年はエンジン・HEV・BEV向けソフトの内製化やアジャイル開発を推進し、2023年には実車を活用した「ソフトウェアブートキャンプ」を立ち上げ、次世代エンジニア育成にも尽力。
また、先進的なユーザー体験の実現に向けた3D HMIの先行・量産開発も担当、現在に至る。
講演者プロフィール
2003年 大阪大学大学院卒、トヨタ自動車株式会社入社。
FCEVの制御ソフト・ハードの内製開発を皮切りに、Prius・AQUA向けインバータ、電池、HEV制御コントローラなどのパワートレイン開発を担当。近年はエンジン・HEV・BEV向けソフトの内製化やアジャイル開発を推進し、2023年には実車を活用した「ソフトウェアブートキャンプ」を立ち上げ、次世代エンジニア育成にも尽力。
また、先進的なユーザー体験の実現に向けた3D HMIの先行・量産開発も担当、現在に至る。

|
豊田通商(株) SDV事業部ソフトウェア事業グループ グループリーダー 松山 喜典 |

|

講演者プロフィール
2003年3月、早稲田大学卒業。豊田通商株式会社に入社。情報電子部(現・デジタルソリューション本部)に所属し、半導体/電子部品販売事業に従事。2008年、ネクスティエレクトロニクスへ出向し、車載組み込みソフトウェア開発事業に従事。2019年、コネクティッドサービスの事業開発を推進し、2021年、中東にて現地コネクティッドサービス事業の立ち上げに参画。2024年より、ソフトウェアに関する新規事業開発を担当し、現在に至る。
講演者プロフィール
2003年3月、早稲田大学卒業。豊田通商株式会社に入社。情報電子部(現・デジタルソリューション本部)に所属し、半導体/電子部品販売事業に従事。2008年、ネクスティエレクトロニクスへ出向し、車載組み込みソフトウェア開発事業に従事。2019年、コネクティッドサービスの事業開発を推進し、2021年、中東にて現地コネクティッドサービス事業の立ち上げに参画。2024年より、ソフトウェアに関する新規事業開発を担当し、現在に至る。
【交流会】SDV Networking Party 11:30~12:30

|
講演終了後11:30~ 交流会を開催いたします。(参加無料) 飲み物、軽食をご用意しております。 参加対象者:講師、基調講演聴講者、招待者、出展社 |
|
【講演】
本セッションでは、トヨタソフトウェアアカデミーの取り組みをご紹介した後、参画企業であるトヨタ自動車、デンソー、アイシン、Woven by Toyota、豊田通商の方々をお迎えし、パネルディスカッション形式にて、SDV時代のソフトウェア人財戦略を語っていただきます。
【交流会】
セミナーの終了後、「SDV Netwoking Party」と題して、講師・受講者・出展社による交流会を開催いたします。
セミナー受講者はどなたでもご参加いただけますので、ぜひ講演終了後はパーティ会場にお越しください。
時間:基調講演終了後 11:30~12:30
場所:基調講演会場そば 第一展示館内 VIPラウンジ
※交流会のみのご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
本講演をお申込みいただいた方は9:30より展示会場にご入場いただけます。
10:00前にご入場いただく際は、展示会入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
自動車をとりまく国内外の情勢と自動車政策の方向性

|
経済産業省 製造産業局 自動車課 自動車戦略企画室 課長補佐 岡林 俊起 |

|

講演内容
我が国は、自動車分野でのカーボンニュートラルの実現に向けて、EVのみならず、PHEVを含めた電動車、水素、合成燃料などの「多様な選択肢」の追求を基本方針としている。自動車産業をとりまく国内外の情勢と、自動車政策の方向性について紹介する。
講演者プロフィール
2012年 入省
2020年 製造産業局 生活製品課 課長補佐
2022年 電力・ガス取引監視等委員会事務局ネットワーク事業監視課 課長補佐
2024年 製造産業局 自動車課 課長補佐(現職)
講演内容
我が国は、自動車分野でのカーボンニュートラルの実現に向けて、EVのみならず、PHEVを含めた電動車、水素、合成燃料などの「多様な選択肢」の追求を基本方針としている。自動車産業をとりまく国内外の情勢と、自動車政策の方向性について紹介する。
講演者プロフィール
2012年 入省
2020年 製造産業局 生活製品課 課長補佐
2022年 電力・ガス取引監視等委員会事務局ネットワーク事業監視課 課長補佐
2024年 製造産業局 自動車課 課長補佐(現職)
ものづくり革新2.0で実現するマルチソリューション戦略

|
マツダ(株) 執行役員 パワートレイン開発・技術研究所担当 中井 英二 |

|

講演内容
カーボンニュートラル社会実現に向け実装してきたマルチソリューション戦略とそれを実現するものづくり革新2.0の取り組みについて述べる。
講演者プロフィール
1985年3月マツダ株式会社入社。技術研究所で内燃機関の新技術開発を担当。その後、開発本部にてモータースポーツエンジンの設計、開発、ディーゼルエンジンの本体、性能設計、制御設計、性能実験研究に従事し、SKYACTIV-G/D開発をリードする。2017年よりパワートレイン開発本部長、2019年 執行役員、2020年にはパワートレイン開発・統合制御システム開発担当、2023年からはパワートレイン開発・技術研究所担当に就任し、現在に至る。
講演内容
カーボンニュートラル社会実現に向け実装してきたマルチソリューション戦略とそれを実現するものづくり革新2.0の取り組みについて述べる。
講演者プロフィール
1985年3月マツダ株式会社入社。技術研究所で内燃機関の新技術開発を担当。その後、開発本部にてモータースポーツエンジンの設計、開発、ディーゼルエンジンの本体、性能設計、制御設計、性能実験研究に従事し、SKYACTIV-G/D開発をリードする。2017年よりパワートレイン開発本部長、2019年 執行役員、2020年にはパワートレイン開発・統合制御システム開発担当、2023年からはパワートレイン開発・技術研究所担当に就任し、現在に至る。
経済産業省については、講師が変更になりました。(10/15時点)
マツダ(株)については、講師が変更になりました。(10/6時点)

|
S&P Global Mobility ダイレクター 西本 真敏 |

|

講演内容
2025年1月米国で第二期トランプ政権が発足した。米国は「米国第一主義」を掲げ、米国の製造業を復活させるべく、完成車や部品関税の引き上げを強引に進めている。果たしてその野望は実現するのか?また2030年に向けて、自動車産業の主要各国や自動車メーカーはどんな影響を受けるのか?分析してみたい。
講演者プロフィール
日本鉄鋼メーカーの自動車部門で購買、営業、企画部門に携わる。2008年、米国ベンチャー企業であるCSM Worldwideへ入社、IHS Markitを経て、現在はS&P Global Mobilityにて日本/韓国生産予測の責任者を務める。日本と韓国の自動車生産や自動車メーカーの開発・生産戦略などの予測・分析を行う。
講演内容
2025年1月米国で第二期トランプ政権が発足した。米国は「米国第一主義」を掲げ、米国の製造業を復活させるべく、完成車や部品関税の引き上げを強引に進めている。果たしてその野望は実現するのか?また2030年に向けて、自動車産業の主要各国や自動車メーカーはどんな影響を受けるのか?分析してみたい。
講演者プロフィール
日本鉄鋼メーカーの自動車部門で購買、営業、企画部門に携わる。2008年、米国ベンチャー企業であるCSM Worldwideへ入社、IHS Markitを経て、現在はS&P Global Mobilityにて日本/韓国生産予測の責任者を務める。日本と韓国の自動車生産や自動車メーカーの開発・生産戦略などの予測・分析を行う。
●質疑応答あり
本講演をお申込みいただいた方は9:30より展示会場にご入場いただけます。
10:00前にご入場いただく際は、展示会入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

|
スズキ(株) 取締役副社長 技術統括 加藤 勝弘 |

|

講演内容
スズキは、お客様の生活に寄り添ったインフラモビリティを目指すため、カーボンニュートラル社会の実現やこれからのクルマの在り方などの社会解決に向けた技術戦略を立て、エネルギー極少化と本質価値の提供を技術哲学とした、ちょうどいいクルマづくりを目指す。
講演者プロフィール
1986年スズキ入社。四輪エンジン設計部門で約30年にわたり設計・実験など開発業務に携わる。その後、四輪技術・商品企画の分野における業務経験を経て、2020年から品質保証部門のトップとしてスズキのQCD基盤を再構築した。2023年からは広く四輪技術部門を管掌し、翌2024年からは技術統括として技術組織の抜本的な再編、技術戦略の策定、技術全般の横断的な指揮・監督を行う。本年4月の取締役副社長就任後も、クルマを取りまくさまざまな社会課題の解決に向けたスズキの技術戦略を実行するため、チームスズキの技術の陣頭指揮を執る。
講演内容
スズキは、お客様の生活に寄り添ったインフラモビリティを目指すため、カーボンニュートラル社会の実現やこれからのクルマの在り方などの社会解決に向けた技術戦略を立て、エネルギー極少化と本質価値の提供を技術哲学とした、ちょうどいいクルマづくりを目指す。
講演者プロフィール
1986年スズキ入社。四輪エンジン設計部門で約30年にわたり設計・実験など開発業務に携わる。その後、四輪技術・商品企画の分野における業務経験を経て、2020年から品質保証部門のトップとしてスズキのQCD基盤を再構築した。2023年からは広く四輪技術部門を管掌し、翌2024年からは技術統括として技術組織の抜本的な再編、技術戦略の策定、技術全般の横断的な指揮・監督を行う。本年4月の取締役副社長就任後も、クルマを取りまくさまざまな社会課題の解決に向けたスズキの技術戦略を実行するため、チームスズキの技術の陣頭指揮を執る。

|
パナソニック オートモーティブシステムズ(株) 代表取締役 副社長執行役員 CTO CISO 知的財産担当 水山 正重 |

|

講演内容
SDVは自動車の価値や競争に一大変化をもたらす「ゲームチェンジャー」である。当社の取組みと共に、その変化の本質、駆動要因、そして開発手法の抜本的革新である「ソフトウェアファースト」が目指すものやエコシステムの重要性を紹介する。
講演者プロフィール
パナソニック オートモーティブシステムズ(株)の代表取締役 副社長執行役員 チーフ・テクノロジー・オフィサー(CTO)およびチーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)を務め、知的財産分野も担当。1988年に松下電器産業(株)に入社し、オペレーティングシステム(OS)技術開発や携帯電話・スマートフォンの商品・要素技術開発などを幅広く経験。その後、オートモーティブ事業部門でのインフォテインメント事業技術責任者や先行技術開発責任者を経て、現在の役職に至る。卓越した技術力とリーダーシップが業界内外で高い評価を受けており、常に新たなイノベーションを追求している。
講演内容
SDVは自動車の価値や競争に一大変化をもたらす「ゲームチェンジャー」である。当社の取組みと共に、その変化の本質、駆動要因、そして開発手法の抜本的革新である「ソフトウェアファースト」が目指すものやエコシステムの重要性を紹介する。
講演者プロフィール
パナソニック オートモーティブシステムズ(株)の代表取締役 副社長執行役員 チーフ・テクノロジー・オフィサー(CTO)およびチーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)を務め、知的財産分野も担当。1988年に松下電器産業(株)に入社し、オペレーティングシステム(OS)技術開発や携帯電話・スマートフォンの商品・要素技術開発などを幅広く経験。その後、オートモーティブ事業部門でのインフォテインメント事業技術責任者や先行技術開発責任者を経て、現在の役職に至る。卓越した技術力とリーダーシップが業界内外で高い評価を受けており、常に新たなイノベーションを追求している。

|
プロジェクト・カーズ(同) 代表 水野 和敏 |
|
講演内容
イノベーションを発想したり実現するために必要な「発想の視点とエッセンスや、実現させるボイントと要件、人材の育成法と 組織の構成」などについて、メーカー選手権レース活動や、リバイバルプランでの高収益な5車型のヒット商品開発、そして通常の半分以下の開発資源(人、モノ、金、時間)で世界唯一のスーパーカー、日産GT-Rを開発した例題等も交えてお伝えする。
講演者プロフィール
・1972年日産自動車に入社後、乗用車の開発責任者やプロジェクト責任者を歴任し、多くの世界的ヒット車を創りだすと共に、監督兼チーフエンジニアとして⽇産のワークスレースに参戦し、全てのチャンピオンを獲得し続けた。 世界からは「Mr.GT-R」と 称される。
・2013年日産自動車を退職
・2014年より台湾、裕隆グループ、LUXGENブランド車の開発担当副社長と日本支社長を歴任した。
・2020年からは、プロジェクト‧カーズ合同会社を設⽴して「先見思考による創造力育成」の講演や研修、出版やコミュニティ運営、雑誌やメディア出演等で活動中。
1952年長野県生まれ
講演内容
イノベーションを発想したり実現するために必要な「発想の視点とエッセンスや、実現させるボイントと要件、人材の育成法と 組織の構成」などについて、メーカー選手権レース活動や、リバイバルプランでの高収益な5車型のヒット商品開発、そして通常の半分以下の開発資源(人、モノ、金、時間)で世界唯一のスーパーカー、日産GT-Rを開発した例題等も交えてお伝えする。
講演者プロフィール
・1972年日産自動車に入社後、乗用車の開発責任者やプロジェクト責任者を歴任し、多くの世界的ヒット車を創りだすと共に、監督兼チーフエンジニアとして⽇産のワークスレースに参戦し、全てのチャンピオンを獲得し続けた。 世界からは「Mr.GT-R」と 称される。
・2013年日産自動車を退職
・2014年より台湾、裕隆グループ、LUXGENブランド車の開発担当副社長と日本支社長を歴任した。
・2020年からは、プロジェクト‧カーズ合同会社を設⽴して「先見思考による創造力育成」の講演や研修、出版やコミュニティ運営、雑誌やメディア出演等で活動中。
1952年長野県生まれ
●会場:第一展示館 VIPラウンジ内特設会場
●質疑応答あり
AUTOMOTIVE INOVATORSは、
イノベーティブな発想と行動力で様々な壁を打ち破ってきたレジェンドたちによる、
固定概念を打ち破る新たな視点や発想を届ける、「発想転換のための特別授業」 です。

|
(同)Office F Vision 代表/ (株)ミクニ 取締役専務執行役員チーフイノベーションオフィサー 藤原 清志 |
|
講演内容
縦糸となる匠集団を全体構想・全体最適の考えの横糸で紡ぎ、「志」「熱意」により強いTeamを形成する。そのTeamがイノベーションを誘発するマネージメントの大切さを、SKYACTIV技術・鼓動デザインを有する新世代商品群の投入プロジェクト、大幅な利益成長プロジェクトなどのいくつかの事例とともに紹介する。小さなTeam活動から会社全体の経営まで参考になれば幸いです。
講演者プロフィール
元 マツダ株式会社 代表取締役 副社長執行役員 兼 COO
2012年以降のSKYACTIV技術・魂動デザインを有する新世代商品群の企画・開発をリード、4年に3度の日本カー・オブ・ザ・イヤー大賞受賞、そして大幅な利益成長によりブランド価値向上に貢献。
現在は、コンサルティング会社 Office F Vision を設立し、事業化、地域活性化の推進、アドバイザーとしての事業助言活動、 講演・講師などによる人材育成など「元気な日本へ」を志として活動中
同時に株式会社ミクニ取締役専務執行役員Chief Innovation Officerとして企業変革を実践中
講演内容
縦糸となる匠集団を全体構想・全体最適の考えの横糸で紡ぎ、「志」「熱意」により強いTeamを形成する。そのTeamがイノベーションを誘発するマネージメントの大切さを、SKYACTIV技術・鼓動デザインを有する新世代商品群の投入プロジェクト、大幅な利益成長プロジェクトなどのいくつかの事例とともに紹介する。小さなTeam活動から会社全体の経営まで参考になれば幸いです。
講演者プロフィール
元 マツダ株式会社 代表取締役 副社長執行役員 兼 COO
2012年以降のSKYACTIV技術・魂動デザインを有する新世代商品群の企画・開発をリード、4年に3度の日本カー・オブ・ザ・イヤー大賞受賞、そして大幅な利益成長によりブランド価値向上に貢献。
現在は、コンサルティング会社 Office F Vision を設立し、事業化、地域活性化の推進、アドバイザーとしての事業助言活動、 講演・講師などによる人材育成など「元気な日本へ」を志として活動中
同時に株式会社ミクニ取締役専務執行役員Chief Innovation Officerとして企業変革を実践中
●会場:第一展示館 VIPラウンジ内特設会場
●質疑応答あり
AUTOMOTIVE INOVATORSは、
イノベーティブな発想と行動力で様々な壁を打ち破ってきたレジェンドたちによる、
固定概念を打ち破る新たな視点や発想を届ける、「発想転換のための特別授業」 です。
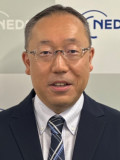
|
(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 プロジェクトマネージャー 東野 龍也 |

|

講演内容
2050年カーボンニュートラル実現に向け、グリーンイノベーション基金事業の1つである次世代蓄電池の開発に関する取り組みを株式会社GSユアサ、出光興産株式会社と共にご紹介する。両事業者がGI基金事業の中で進めて頂いている全固体電池・材料の開発進捗及び今後に向けた課題を紹介し、プロジェクトを進める上で必要と考えているスキーム等、ディスカッションを実施する。
講演者プロフィール
1999年日産自動車株式会社入社。
ハイブリッド・電気自動車向け電池設計開発を担当。
2023年4月よりNEDOに出向し、グリーンイノベーション基金事業「次世代蓄電池・次世代モーターの開発」のうち次世代蓄電池のプロジェクトマネージャーとして従事。
講演内容
2050年カーボンニュートラル実現に向け、グリーンイノベーション基金事業の1つである次世代蓄電池の開発に関する取り組みを株式会社GSユアサ、出光興産株式会社と共にご紹介する。両事業者がGI基金事業の中で進めて頂いている全固体電池・材料の開発進捗及び今後に向けた課題を紹介し、プロジェクトを進める上で必要と考えているスキーム等、ディスカッションを実施する。
講演者プロフィール
1999年日産自動車株式会社入社。
ハイブリッド・電気自動車向け電池設計開発を担当。
2023年4月よりNEDOに出向し、グリーンイノベーション基金事業「次世代蓄電池・次世代モーターの開発」のうち次世代蓄電池のプロジェクトマネージャーとして従事。

|
(株)GSユアサ 研究開発センター 先進固体電池開発部 部長 船引 厚志 |

|

講演者プロフィール
1999年3月京都大学大学院工学研究科卒業。博士(工学)を取得。旧日本電池株式会社に入社。
研究開発本部に所属し、次世代負極材料開発に従事。その後、リチウムイオン電池事業部に所属し、車載用LIB電極設計を担当。
2022年10月より研究開発センター先進固体電池開発部にて全固体電池開発を担当し、現在に至る。
講演者プロフィール
1999年3月京都大学大学院工学研究科卒業。博士(工学)を取得。旧日本電池株式会社に入社。
研究開発本部に所属し、次世代負極材料開発に従事。その後、リチウムイオン電池事業部に所属し、車載用LIB電極設計を担当。
2022年10月より研究開発センター先進固体電池開発部にて全固体電池開発を担当し、現在に至る。

|
出光興産(株) リチウム電池材料部 次長 草場 敏彰 |

|

講演者プロフィール
2003年3月、岡山大学大学院修了。出光興産株式会社に入社。生産技術センターに所属し、主に石油化学製品のプロセス開発に従事。その後、経営企画部、インドにある潤滑油の製造販売子会社、本社技術戦略部を経て、2022年7月より現職。
講演者プロフィール
2003年3月、岡山大学大学院修了。出光興産株式会社に入社。生産技術センターに所属し、主に石油化学製品のプロセス開発に従事。その後、経営企画部、インドにある潤滑油の製造販売子会社、本社技術戦略部を経て、2022年7月より現職。
ギガキャストの技術動向とダイカスト技術

|
リョービ(株) ダイカスト企画開発本部 研究開発部 部長 新田 真 |
|
講演内容
自動車の電動化が進む中、ダイカスト製品の適用内容も変化している。
従来は、エンジンブロックや変速器などのケース・カバー類が主な使用用途であったが、材料・金型・鋳造の技術の向上により、ボディシャシーへの適用も可能となり、その採用が増えてきている。
その中で、リアアンダーボディへの採用から始まった大型一体ダイカスト(ギガキャスト)の技術動向や技術課題、当社におけるギガキャスト機導入の取り組みを紹介する。
講演者プロフィール
1992年日本大学大学院卒業、リョービ株式会社に入社。研究部に配属され、1999年V6クローズドデッキタイプのシリンダーブロックを開発、2011年より中国に赴任し新工場の立ち上げに従事。2020年より研究開発部長を担当し、現在に至る。
講演内容
自動車の電動化が進む中、ダイカスト製品の適用内容も変化している。
従来は、エンジンブロックや変速器などのケース・カバー類が主な使用用途であったが、材料・金型・鋳造の技術の向上により、ボディシャシーへの適用も可能となり、その採用が増えてきている。
その中で、リアアンダーボディへの採用から始まった大型一体ダイカスト(ギガキャスト)の技術動向や技術課題、当社におけるギガキャスト機導入の取り組みを紹介する。
講演者プロフィール
1992年日本大学大学院卒業、リョービ株式会社に入社。研究部に配属され、1999年V6クローズドデッキタイプのシリンダーブロックを開発、2011年より中国に赴任し新工場の立ち上げに従事。2020年より研究開発部長を担当し、現在に至る。
軽量化・高機能化のための車体構造接着技術

|
マツダ(株) R&D戦略企画本部 開発戦略企画部 上席研究員 山本 研一 |

|

講演内容
電動化やソフトウェア化が進展しても、軽量化は「走る歓び」と燃費・電費の重要なファクターである。クルマの基本性能を司る車体において、構造接着は操縦安定性や静粛性と共に、軽量化に貢献できる。本講演では、マツダの車体構造接着の考え方と開発技術を紹介する。
講演者プロフィール
1992年、マツダ株式会社に入社。技術研究所に所属し、機能性材料・接合技術、材料分析技術の研究開発に従事。2023年よりR&D戦略企画本部に所属し、資源循環等の技術戦略策定に従事、現在に至る。車体構造接着技術に関し、2020年に第70回自動車技術会賞(技術開発賞)、2025年に第57回市村賞(市村産業賞 貢献賞)を受賞。博士(学術)、自動車技術会フェロー。
講演内容
電動化やソフトウェア化が進展しても、軽量化は「走る歓び」と燃費・電費の重要なファクターである。クルマの基本性能を司る車体において、構造接着は操縦安定性や静粛性と共に、軽量化に貢献できる。本講演では、マツダの車体構造接着の考え方と開発技術を紹介する。
講演者プロフィール
1992年、マツダ株式会社に入社。技術研究所に所属し、機能性材料・接合技術、材料分析技術の研究開発に従事。2023年よりR&D戦略企画本部に所属し、資源循環等の技術戦略策定に従事、現在に至る。車体構造接着技術に関し、2020年に第70回自動車技術会賞(技術開発賞)、2025年に第57回市村賞(市村産業賞 貢献賞)を受賞。博士(学術)、自動車技術会フェロー。
●質疑応答あり
プラスチックのサーキュラーエコノミーシステムの構築

|
東京大学 大学院新領域創成科学研究科 特別教授 伊藤 耕三 |
|
講演内容
本講演では、2023年度より始まった内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム「サーキュラーエコノミーシステムの構築」(SIP-CE)の取り組みについて紹介する。SIP-CEではELV規則案に対応するため、車以外からの再生材を用いて自動車部品製作の実証試験(X to Car)を行っている。
講演者プロフィール
1986年3月、東京大学大学院博士課程修了、工学博士。同年工業技術院繊維高分子材料研究所の研究員、主任研究官を経て、1991年より東京大学講師、助教授を経て2003年より教授、2024年より特別教授として現在に至る。2023年から物質・材料研究機構フェローおよびSIPプログラムディレクターを兼務。学生のころより現在に至るまで一貫して高分子の研究に従事し、2022-2023年には高分子学会会長を務める。
講演内容
本講演では、2023年度より始まった内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム「サーキュラーエコノミーシステムの構築」(SIP-CE)の取り組みについて紹介する。SIP-CEではELV規則案に対応するため、車以外からの再生材を用いて自動車部品製作の実証試験(X to Car)を行っている。
講演者プロフィール
1986年3月、東京大学大学院博士課程修了、工学博士。同年工業技術院繊維高分子材料研究所の研究員、主任研究官を経て、1991年より東京大学講師、助教授を経て2003年より教授、2024年より特別教授として現在に至る。2023年から物質・材料研究機構フェローおよびSIPプログラムディレクターを兼務。学生のころより現在に至るまで一貫して高分子の研究に従事し、2022-2023年には高分子学会会長を務める。
自動車産業におけるサーキュラーエコノミー実現に向けた最新動向 豊田合成の取組み

|
豊田合成(株) 第2材料技術部 主担当員 内田 均 |

|

講演内容
豊田合成は高分子技術を用いた自動車部品を提供するグローバルサプライヤーです。
2050年までのCO2排出ゼロを目指し、ゴム・樹脂の廃材や再生材の製品へのリサイクルを通じて、環境負荷低減にむけた取組みをご紹介する。
講演者プロフィール
1996年 群馬大学 材料工学 修了
2003年 豊田合成株式会社入社 材料技術部に所属し、自動車用樹脂・ゴム材料の開発に従事
現在は自動車用樹枝材料のリサイクルを担当
講演内容
豊田合成は高分子技術を用いた自動車部品を提供するグローバルサプライヤーです。
2050年までのCO2排出ゼロを目指し、ゴム・樹脂の廃材や再生材の製品へのリサイクルを通じて、環境負荷低減にむけた取組みをご紹介する。
講演者プロフィール
1996年 群馬大学 材料工学 修了
2003年 豊田合成株式会社入社 材料技術部に所属し、自動車用樹脂・ゴム材料の開発に従事
現在は自動車用樹枝材料のリサイクルを担当
●質疑応答あり
本講演をお申込みいただいた方は9:30より展示会場にご入場いただけます。
10:00前にご入場いただく際は、展示会入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。
Honda 0シリーズの統合ECUについて

|
本田技研工業(株) 四輪事業本部SDV事業開発統括部 配信ソフトウェア品質責任者、エグゼクティブチーフエンジニア 久木 隆 |

|

講演内容
SDV時代に向けたOTAによるソフトウェアのアップデートや、クロスドメインのアプリケーションを実現するために、Honda 0シリーズでは統合ECUを導入する。統合ECUのコンセプトと新技術について説明する。
講演者プロフィール
1990年3月 早稲田大学理工学部卒業 本田技術研究所に入社しエンジン制御ECUの開発に従事。
2022年4月より北米駐在から帰任し電子プラットフォーム開発を担当し、
2024年10月より配信SW品質責任者に従事。
講演内容
SDV時代に向けたOTAによるソフトウェアのアップデートや、クロスドメインのアプリケーションを実現するために、Honda 0シリーズでは統合ECUを導入する。統合ECUのコンセプトと新技術について説明する。
講演者プロフィール
1990年3月 早稲田大学理工学部卒業 本田技術研究所に入社しエンジン制御ECUの開発に従事。
2022年4月より北米駐在から帰任し電子プラットフォーム開発を担当し、
2024年10月より配信SW品質責任者に従事。
統合ECUソフト開発戦略

|
(株)デンソー 上席執行幹部 Chief Software Officer(CSwO)、 ソフトウェア改革統括室長 林田 篤 |
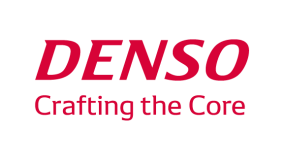
|
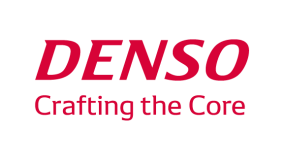
講演内容
統合ECUの開発において、SDV時代を見据えた当社のソフトウェア開発の進化の方向性、強み、取り組み事例を紹介する。
講演者プロフィール
1987年日本電装(株)(1996年に株式会社デンソーに社名変更)に入社し、携帯電話開発、ナビゲーションシステムなど、大規模ソフトウェア開発を中心に開発・設計を担当。2015年からコックピット関係の製品を開発。
現在は、2021年に発足した、デンソーの電子系ソフトウェア全般を担当するソフトウェア統括部。その後、2023年6月CSwOに就任。
CSwO直下組織であるソフトウェア改革統括室長として、デンソーグループ全体のソフトウェア改革活動も推進し、グローバルな開発力向上、技術者のスキル高度化、多様化を推進。
講演内容
統合ECUの開発において、SDV時代を見据えた当社のソフトウェア開発の進化の方向性、強み、取り組み事例を紹介する。
講演者プロフィール
1987年日本電装(株)(1996年に株式会社デンソーに社名変更)に入社し、携帯電話開発、ナビゲーションシステムなど、大規模ソフトウェア開発を中心に開発・設計を担当。2015年からコックピット関係の製品を開発。
現在は、2021年に発足した、デンソーの電子系ソフトウェア全般を担当するソフトウェア統括部。その後、2023年6月CSwOに就任。
CSwO直下組織であるソフトウェア改革統括室長として、デンソーグループ全体のソフトウェア改革活動も推進し、グローバルな開発力向上、技術者のスキル高度化、多様化を推進。
●質疑応答あり

|
トヨタ自動車(株) 主査, オープンソースプログラムグループ(TOYOTA OSPO)グループ長 遠藤 雅人 |

|

講演内容
自動車業界のソフトサプライチェーンは広大であり、適切なセキュリティ対応やライセンス管理のためには自社製品の中身を正確に把握する「Transparency」がSDVの進展と共により重要になっている。本セッションでは「オープンソース」や「SBOM」をキーワードに最新のトレンドを紹介する。
講演者プロフィール
トヨタ自動車株式会社においてバリューチェーンサービスに関する技術開発を進めると共に、社内のオープンソースソフトウエアの活用を推進するオープンソースプログラムグループ(TOYOTA OSPO)のマネージャーを務める。また、The Linux Foundationの初代Japan Evangelistの一人として日本国内のオープンソースコミュニティ活動の推進や、Open Chain Project Automotive Chairとしてグローバルな自動車業界におけるソフトウエアサプライチェーンマネジメントの標準化にも取り組んでいる。
講演内容
自動車業界のソフトサプライチェーンは広大であり、適切なセキュリティ対応やライセンス管理のためには自社製品の中身を正確に把握する「Transparency」がSDVの進展と共により重要になっている。本セッションでは「オープンソース」や「SBOM」をキーワードに最新のトレンドを紹介する。
講演者プロフィール
トヨタ自動車株式会社においてバリューチェーンサービスに関する技術開発を進めると共に、社内のオープンソースソフトウエアの活用を推進するオープンソースプログラムグループ(TOYOTA OSPO)のマネージャーを務める。また、The Linux Foundationの初代Japan Evangelistの一人として日本国内のオープンソースコミュニティ活動の推進や、Open Chain Project Automotive Chairとしてグローバルな自動車業界におけるソフトウエアサプライチェーンマネジメントの標準化にも取り組んでいる。
※講演終了時間が変更となりました。(9/25付)
●質疑応答あり
本講演をお申込みいただいた方は9:30より展示会場にご入場いただけます。
10:00前にご入場いただく際は、展示会入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。
半導体業界の「共創」担うレゾナックの新戦略

|
(株)レゾナック CTO(半導体材料)執行役員 エレクトロニクス事業本部 副本部長 阿部 秀則 |

|

講演内容
共創型化学企業を目指すレゾナックは、材料・基板・装置メーカーと共同で評価プラットフォーム「JOINT2」「JOINT3」を設置し、次世代2.5D/2.xDパッケージの技術開発を推進している。本講演では、共創がもたらす価値、材料イノベーション、そしてレゾナックの新しい「共創」戦略などを紹介する。
講演者プロフィール
東京工業大学 化学工学科 修士課程修了後、1998年に日立化成工業入社。封止材料開発部にて15年開発に従事。その間、Hitachi Chemical Co. America(現Resonac America)に駐在、OxfordにてEMBA取得。マーケティングを担当後、研磨材料ビジネスユニット長、パッケージングソリューションセンター長、開発センター長に就任、JOINT2・US-JOINT・JOINT3の立ち上げに従事。2024年、業務執行役およびエレクトロニクス事業本部副本部長を歴任し、2025年1月より現職に就任。
講演内容
共創型化学企業を目指すレゾナックは、材料・基板・装置メーカーと共同で評価プラットフォーム「JOINT2」「JOINT3」を設置し、次世代2.5D/2.xDパッケージの技術開発を推進している。本講演では、共創がもたらす価値、材料イノベーション、そしてレゾナックの新しい「共創」戦略などを紹介する。
講演者プロフィール
東京工業大学 化学工学科 修士課程修了後、1998年に日立化成工業入社。封止材料開発部にて15年開発に従事。その間、Hitachi Chemical Co. America(現Resonac America)に駐在、OxfordにてEMBA取得。マーケティングを担当後、研磨材料ビジネスユニット長、パッケージングソリューションセンター長、開発センター長に就任、JOINT2・US-JOINT・JOINT3の立ち上げに従事。2024年、業務執行役およびエレクトロニクス事業本部副本部長を歴任し、2025年1月より現職に就任。
未来を創る最先端半導体パッケージング技術

|
新光電気工業(株) 執行役員 開発統括部長 荒木 康 |

|

講演内容
最先端の半導体技術開発現場では、バックエンドプロセスの進化が不可欠であり、特に「先端半導体パッケージング技術」は、半導体の高性能、多機能化への要求に応え、高集積化を進めている。
本講演では、それら技術の進化と要求特性の両立を実現する基板製造技術と有機インターポーザー技術、ガラス基板技術、光電融合パッケージについて紹介する。
講演者プロフィール
1989年 名古屋大学応用化学専攻卒
1989年~2000年 富士通株式会社 ICアセンブリ技術に従事
2000年~2021年 新光電気工業株式会社 ICアセンブリ技術に従事
2021年~ 研究開発部門(開発統括部)にて研究開発業務に従事 現在に至る
講演内容
最先端の半導体技術開発現場では、バックエンドプロセスの進化が不可欠であり、特に「先端半導体パッケージング技術」は、半導体の高性能、多機能化への要求に応え、高集積化を進めている。
本講演では、それら技術の進化と要求特性の両立を実現する基板製造技術と有機インターポーザー技術、ガラス基板技術、光電融合パッケージについて紹介する。
講演者プロフィール
1989年 名古屋大学応用化学専攻卒
1989年~2000年 富士通株式会社 ICアセンブリ技術に従事
2000年~2021年 新光電気工業株式会社 ICアセンブリ技術に従事
2021年~ 研究開発部門(開発統括部)にて研究開発業務に従事 現在に至る
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
YAMAHA Roboticsが目指す自動化の未来

|
ヤマハ発動機(株) ロボティクス事業部営業統括部 営業統括部長 有本 一郎 |

|

講演内容
SMT業界の共通課題である “人材不足・人依存からの脱却”のために、"PERFECT FIT AUTOMATION”と題して、ヤマハが実現するSMTフロアの自動化並びにSMT後工程の自動化・省人化ソリューション提案の取り組みを紹介する。
講演者プロフィール
1997年4月ヤマハ発動機(株)に入社、IM事業部(現ロボティクス事業部)に所属し、表面実装(SMT)機器の営業に従事。東南アジア、欧州の営業責任者を経て2020年よりSMT営業部長、2022年より産業用小型ロボットも含むロボティクス事業部全商材の営業責任者として工場まるごと自動化提案を推進、現在に至る。
講演内容
SMT業界の共通課題である “人材不足・人依存からの脱却”のために、"PERFECT FIT AUTOMATION”と題して、ヤマハが実現するSMTフロアの自動化並びにSMT後工程の自動化・省人化ソリューション提案の取り組みを紹介する。
講演者プロフィール
1997年4月ヤマハ発動機(株)に入社、IM事業部(現ロボティクス事業部)に所属し、表面実装(SMT)機器の営業に従事。東南アジア、欧州の営業責任者を経て2020年よりSMT営業部長、2022年より産業用小型ロボットも含むロボティクス事業部全商材の営業責任者として工場まるごと自動化提案を推進、現在に至る。
高速X線CT技術と、生成AI活用とで目指す高スループット量産工場

|
オムロン(株) 検査システム事業本部 X線検査システム事業部 事業部長 村上 清 |

|

講演内容
省人化/ノウハウレス化の実現と、高度化/複雑化するデジタル化製品の高品質・高生産性との両立。 「X線CT自動検査」の最新技術およびSATASでの半導体後工程自動化取り組みを紹介。生成AIの活用によるモノづくり現場の革新を自動運転コントロール基板や、チップレット実装の事例で描く。
講演者プロフィール
2000年3月、中央大学院修士卒。同4月、オムロン株式会社に入社。 入社以来、現検査システム事業本部に所属し、開発、事業企画・商品企画に従事。 2023年より、X線検査システム事業部を担当し、現在に至る。
講演内容
省人化/ノウハウレス化の実現と、高度化/複雑化するデジタル化製品の高品質・高生産性との両立。 「X線CT自動検査」の最新技術およびSATASでの半導体後工程自動化取り組みを紹介。生成AIの活用によるモノづくり現場の革新を自動運転コントロール基板や、チップレット実装の事例で描く。
講演者プロフィール
2000年3月、中央大学院修士卒。同4月、オムロン株式会社に入社。 入社以来、現検査システム事業本部に所属し、開発、事業企画・商品企画に従事。 2023年より、X線検査システム事業部を担当し、現在に至る。
※ヤマハ発動機(株)有本様につきましては、講演スライドの配布はございません。
予めご了承の上、お申込みください。
本講演をお申込みいただいた方は9:30より展示会場にご入場いただけます。
10:00前にご入場いただく際は、展示会入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。
xEV向けインバータ開発におけるEMI技術

|
日産自動車(株) 総合研究所 EVシステム研究所 大久保 明範 |

|

講演内容
近年、パワーデバイスの進化により、高速・高周波でのスイッチング動作が可能となり、電力変換システムの高効率化や小型化が期待される一方で、EMI(電磁妨害)の増大は避けられない。ここでは、実際の第2世代e-POWER内製インバータの開発事例を交えて、キーとなるEMI設計技術を紹介する。
講演者プロフィール
2011年に日産自動車の研究所へ中途入社し、次世代インバータおよび車載充電器のパワーエレクトロニクス技術、ならびにEMI技術の研究に従事。その後、2017年に開発部門へ異動し、アリアやノートe-POWER等のxEV向け内製インバータのEMI設計および内蔵部品の回路設計を担当。 2019年に研究所に帰任し、V2Xシステム技術等の研究に従事し、現在に至る。また、電気学会「電力変換装置におけるEMC対策・設計の技術動向調査専門委員会」等の活動にも従事。
講演内容
近年、パワーデバイスの進化により、高速・高周波でのスイッチング動作が可能となり、電力変換システムの高効率化や小型化が期待される一方で、EMI(電磁妨害)の増大は避けられない。ここでは、実際の第2世代e-POWER内製インバータの開発事例を交えて、キーとなるEMI設計技術を紹介する。
講演者プロフィール
2011年に日産自動車の研究所へ中途入社し、次世代インバータおよび車載充電器のパワーエレクトロニクス技術、ならびにEMI技術の研究に従事。その後、2017年に開発部門へ異動し、アリアやノートe-POWER等のxEV向け内製インバータのEMI設計および内蔵部品の回路設計を担当。 2019年に研究所に帰任し、V2Xシステム技術等の研究に従事し、現在に至る。また、電気学会「電力変換装置におけるEMC対策・設計の技術動向調査専門委員会」等の活動にも従事。
xEV向け低損失、高生産性RC-IGBT の開発

|
(株)デンソー ウエハ製造部 室長 志賀 智英 |

|

講演内容
モビリティの電動化はカーボンニュートラル社会を実現するための重要な手段の一つである。
本講演では、xEVの「性能向上」と「本格普及」に貢献すべく、Siパワー半導体のRC-IGBTが抱える損失課題の克服と生産性の向上、300mmウェハでの量産を実現した取り組みを紹介する。
講演者プロフィール
2002年4月に株式会社デンソーに入社。電子機器開発部に所属し、車の電動化を支える車載パワー半導体(DMOS、IGBT)の開発に従事。
2015年からライフタイム制御レスRC-IGBTの開発に従事、その後300mmウェハでのRC-IGBT工程設計を担当し2023年に出荷を開始。2025年より、ウエハ製造部にて量産品、開発品の品質向上業務を担当し、現在に至る。
講演内容
モビリティの電動化はカーボンニュートラル社会を実現するための重要な手段の一つである。
本講演では、xEVの「性能向上」と「本格普及」に貢献すべく、Siパワー半導体のRC-IGBTが抱える損失課題の克服と生産性の向上、300mmウェハでの量産を実現した取り組みを紹介する。
講演者プロフィール
2002年4月に株式会社デンソーに入社。電子機器開発部に所属し、車の電動化を支える車載パワー半導体(DMOS、IGBT)の開発に従事。
2015年からライフタイム制御レスRC-IGBTの開発に従事、その後300mmウェハでのRC-IGBT工程設計を担当し2023年に出荷を開始。2025年より、ウエハ製造部にて量産品、開発品の品質向上業務を担当し、現在に至る。
AD/ADASにおける外界センシングとAstemoの取組み

|
Astemo(株) 技術開発統括本部 次世代モビリティ開発本部 ジェネラルマネージャー 村松 彰二 |

|

講演内容
AD/ADASでは、安全アセスメントや法整備化が進むと同時に、自動運転機能が急速に普及し始めている。機能進化を支える外界センシングについて、システム視点の開発と開発環境へのAstemoの取組みを述べる。
講演者プロフィール
1995年 日立製作所 日立研究所に入所。画像を主体としたセンシング技術開発に従事。2010年クラリオン(株)出向し、車載カメラセンシング開発を担当。2013年日立製作所 研究開発グループで研究マネージメントを経験。2017年より日立オートモティブシステムズ(現Astemo)にてAD/ADASの先行開発に従事。2023年4月より現職。博士(工学)。
講演内容
AD/ADASでは、安全アセスメントや法整備化が進むと同時に、自動運転機能が急速に普及し始めている。機能進化を支える外界センシングについて、システム視点の開発と開発環境へのAstemoの取組みを述べる。
講演者プロフィール
1995年 日立製作所 日立研究所に入所。画像を主体としたセンシング技術開発に従事。2010年クラリオン(株)出向し、車載カメラセンシング開発を担当。2013年日立製作所 研究開発グループで研究マネージメントを経験。2017年より日立オートモティブシステムズ(現Astemo)にてAD/ADASの先行開発に従事。2023年4月より現職。博士(工学)。
高解像度と高速性を同時実現する、ソニーの車載LiDAR向け積層型SPAD距離センサ―

|
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 車載事業部車載商品開発部2課 SPADセンサエキスパート 安福 正 |

|

講演内容
自動運転機能の高度化に向け、周辺環境の高精度な認識を可能にするLiDAR技術が注目されている。本講演では、高性能LiDARの実現に不可欠なSPAD距離センサーの高性能化に向けたソニーの取り組みと、開発したセンサーを用いたLiDAR実証試作機を紹介する。
講演者プロフィール
東京大学大学院工学系研究科にて後期博士課程を修了。博士(工学)。電機メーカーにて不揮発性半導体メモリの設計に従事した後、2018年にソニーへ入社。モバイル向けCMOSイメージセンサの画素設計を経て、現在は車載LiDAR向け積層型SPAD距離センサーの開発において中心的な役割を担っている。
講演内容
自動運転機能の高度化に向け、周辺環境の高精度な認識を可能にするLiDAR技術が注目されている。本講演では、高性能LiDARの実現に不可欠なSPAD距離センサーの高性能化に向けたソニーの取り組みと、開発したセンサーを用いたLiDAR実証試作機を紹介する。
講演者プロフィール
東京大学大学院工学系研究科にて後期博士課程を修了。博士(工学)。電機メーカーにて不揮発性半導体メモリの設計に従事した後、2018年にソニーへ入社。モバイル向けCMOSイメージセンサの画素設計を経て、現在は車載LiDAR向け積層型SPAD距離センサーの開発において中心的な役割を担っている。

|
名古屋大学 未来材料・システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授 山本 真義 |
|
講演内容
電気自動車のみならずハイブリッド車にも応用されるようになったSiCパワー半導体の応用事例とそこにおける技術的な課題について、材料、部品(センサ、受動素子等)、システム、車両全体の各階層における要求仕様を、テスラ・サイバートラックや小米・SU7の分解解析結果を交えながら図説する。
講演者プロフィール
2003年山口大学理工学研究科博士取得後、サンケン電気株式会社、島根大学総合理工学部講師を経て、2011年より島根大学総合理工学部准教授着任。2017年より名古屋大学未来材料・システム研究所教授着任。パワーエレクトロニクス全般 (磁気、制御、回路方式、半導体駆動)に関する研究に従事。博士 (工学)。IEEE、電気学会、電子情報通信学会会員。応用は航空機電動化、自動車電動化、ワイヤレス給電の三本柱。日本の大学研究室としては珍しく、共同研究企業は40社を超え、海外の完成車メーカーとも強いコネクションを持つ。産学連携活動を強力に推進しており、企業との共同特許出願数も多数。共同研究だけでなく、各企業の戦略コンサルタントも請け負い、技術顧問としての活動も幅広い。
講演内容
電気自動車のみならずハイブリッド車にも応用されるようになったSiCパワー半導体の応用事例とそこにおける技術的な課題について、材料、部品(センサ、受動素子等)、システム、車両全体の各階層における要求仕様を、テスラ・サイバートラックや小米・SU7の分解解析結果を交えながら図説する。
講演者プロフィール
2003年山口大学理工学研究科博士取得後、サンケン電気株式会社、島根大学総合理工学部講師を経て、2011年より島根大学総合理工学部准教授着任。2017年より名古屋大学未来材料・システム研究所教授着任。パワーエレクトロニクス全般 (磁気、制御、回路方式、半導体駆動)に関する研究に従事。博士 (工学)。IEEE、電気学会、電子情報通信学会会員。応用は航空機電動化、自動車電動化、ワイヤレス給電の三本柱。日本の大学研究室としては珍しく、共同研究企業は40社を超え、海外の完成車メーカーとも強いコネクションを持つ。産学連携活動を強力に推進しており、企業との共同特許出願数も多数。共同研究だけでなく、各企業の戦略コンサルタントも請け負い、技術顧問としての活動も幅広い。
●質疑応答あり
本講演をお申込みいただいた方は9:30より展示会場にご入場いただけます。
10:00前にご入場いただく際は、展示会入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

IPCがグローバルエレクトロニクスアソシエーションへと改名 その背景と展望を紹介

|
(株)ジャパンユニックス マーケティンググループ 執行役員 IPCユニット長 河野 友作 |

|

講演内容
2025年6月に70年の歴史を持つIPCがその組織名称をグローバルエレクトロニクスアソシエーション(GEA)へと改名しました。本講演では、その改名背景と今後の展望について紹介します。
講演者プロフィール
2006年Aston Business School(UK), MBA, Marketing Strategy卒業、2012年10月株式会社ジャパンユニックスに入社。マーケティング部およびIPCに関する新規事業の立ち上げを担当。2021年4月より、現グローバルエレクトロニクスアソシエーション(旧IPC)の日本代表に就任し、現在に至る。
講演内容
2025年6月に70年の歴史を持つIPCがその組織名称をグローバルエレクトロニクスアソシエーション(GEA)へと改名しました。本講演では、その改名背景と今後の展望について紹介します。
講演者プロフィール
2006年Aston Business School(UK), MBA, Marketing Strategy卒業、2012年10月株式会社ジャパンユニックスに入社。マーケティング部およびIPCに関する新規事業の立ち上げを担当。2021年4月より、現グローバルエレクトロニクスアソシエーション(旧IPC)の日本代表に就任し、現在に至る。
IPC導入事例と車載向け追加規格委員会(日本)の活動状況#4

|
(株)東海理化 生技開発部 接合生技室 室長 鈴木 貴人 |

|

講演内容
実質的な国際規格であるIPC採用とそのメリット、2022年に立ち上がったIPC-A-610/J-STD-001車載向け追加規格委員会(日本)活動、現在提案している内容とその評価方法を紹介。
24年10月名古屋ネプコン、25年1月ネプコンジャパン、25年5月ネプコン関西の更新版です。
講演者プロフィール
2000年 最大手プリント配線板メーカー入社。主にモバイル向けビルドアップ基板に従事
2002年 東海理化(現職)。鉛フリーはんだ付けの工法開発、量産立上げ、品質改善、
国内外サプライヤ(EMS, PWBメーカー)の選定、監査、技術指導に従事
2019年 JPCA(日本電子回路工業会)PWBコンサルタント登録
2022年 7-31BV:IPC J-STD-001/IPC-A-610 Automotive Addendum JP 委員長
2025年 JPCA PWBコンサルタントWG副委員長
講演内容
実質的な国際規格であるIPC採用とそのメリット、2022年に立ち上がったIPC-A-610/J-STD-001車載向け追加規格委員会(日本)活動、現在提案している内容とその評価方法を紹介。
24年10月名古屋ネプコン、25年1月ネプコンジャパン、25年5月ネプコン関西の更新版です。
講演者プロフィール
2000年 最大手プリント配線板メーカー入社。主にモバイル向けビルドアップ基板に従事
2002年 東海理化(現職)。鉛フリーはんだ付けの工法開発、量産立上げ、品質改善、
国内外サプライヤ(EMS, PWBメーカー)の選定、監査、技術指導に従事
2019年 JPCA(日本電子回路工業会)PWBコンサルタント登録
2022年 7-31BV:IPC J-STD-001/IPC-A-610 Automotive Addendum JP 委員長
2025年 JPCA PWBコンサルタントWG副委員長
国際標準を活用した品質と競争力の両立

|
トヨタ自動車(株) デジタルソフト開発センター 電子性能開発部 グループ長 西森 久雄 |
|
講演内容
車載電子部品には信頼性設計と高品質な生産維持が要求される。SDVを達成する商品力をある高機能な電子部品をタイムリーにグローバル調達するためは国際標準活用が効率的である。国際標準をトヨタ標準と組み合わせた品質と競争力の両立の取組みを紹介する。
講演者プロフィール
1997年早稲田大学大学院卒業後、電機メーカで車載ASIC設計に従事。2003年トヨタ自動車に中途入社。HEV用の内製パワーモジュール開発の回路・放熱・駆動用ICの設計・評価、はんだ接合の品質問題を担当。2013年に電子実験部に異動し、内製部品評価、車両環境評価、マルチメディア・ラジオ・電波応用システムの車両評価を担当。3年間のヨーロッパR&Dのマネージャ出向を経て2021年から現職。はんだ接合関係の社内テクニカルアドバイザ、部品評価とシミュレーション活用をグループ長として推進中。2022年にIPCに正式加入し、7-31BV-JPの日本タスクグループ副議長を兼務
講演内容
車載電子部品には信頼性設計と高品質な生産維持が要求される。SDVを達成する商品力をある高機能な電子部品をタイムリーにグローバル調達するためは国際標準活用が効率的である。国際標準をトヨタ標準と組み合わせた品質と競争力の両立の取組みを紹介する。
講演者プロフィール
1997年早稲田大学大学院卒業後、電機メーカで車載ASIC設計に従事。2003年トヨタ自動車に中途入社。HEV用の内製パワーモジュール開発の回路・放熱・駆動用ICの設計・評価、はんだ接合の品質問題を担当。2013年に電子実験部に異動し、内製部品評価、車両環境評価、マルチメディア・ラジオ・電波応用システムの車両評価を担当。3年間のヨーロッパR&Dのマネージャ出向を経て2021年から現職。はんだ接合関係の社内テクニカルアドバイザ、部品評価とシミュレーション活用をグループ長として推進中。2022年にIPCに正式加入し、7-31BV-JPの日本タスクグループ副議長を兼務
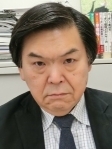
|
(株)産業タイムズ社 取締役会長/特別編集委員 泉谷 渉 |

|

講演内容
半導体、プリント基板、コンデンサー、コネクタ、さらには液晶・有機ELなどの電子デバイス産業は中長期的に高い成長を続けると思われる。その最大の引っ張り役はAIであり、これに関連するデバイスは大きなインパクトを受けるだろう。最新取材でリポートする。
講演者プロフィール
神奈川県横浜市出身。中央大学法学部政治学科卒業。40年以上にわたって第一線を走ってきた国内最古参の半導体記者であり、現在は産業タイムズ社 取締役 会長。著書には『自動車世界戦争』、『日・米・中IoT最終戦争』(以上、東洋経済新報社)、『伝説 ソニーの半導体』、『日本半導体産業 激動の21年史 2000年~2021年』、『君はニッポン100年企業の底力を見たか!!』(産業タイムズ社)など27冊がある。一般社団法人日本電子デバイス産業協会 理事 副会長。全国各地を講演と取材で飛びまわる毎日が続く。
講演内容
半導体、プリント基板、コンデンサー、コネクタ、さらには液晶・有機ELなどの電子デバイス産業は中長期的に高い成長を続けると思われる。その最大の引っ張り役はAIであり、これに関連するデバイスは大きなインパクトを受けるだろう。最新取材でリポートする。
講演者プロフィール
神奈川県横浜市出身。中央大学法学部政治学科卒業。40年以上にわたって第一線を走ってきた国内最古参の半導体記者であり、現在は産業タイムズ社 取締役 会長。著書には『自動車世界戦争』、『日・米・中IoT最終戦争』(以上、東洋経済新報社)、『伝説 ソニーの半導体』、『日本半導体産業 激動の21年史 2000年~2021年』、『君はニッポン100年企業の底力を見たか!!』(産業タイムズ社)など27冊がある。一般社団法人日本電子デバイス産業協会 理事 副会長。全国各地を講演と取材で飛びまわる毎日が続く。
製造現場での生成AI活用を競争力向上に活かす

|
デロイト トーマツ コンサルティング(同) 執行役員 芳賀 圭吾 |

|

講演内容
製造現場での生成AI活用は、文書検索・作成だけでなく、ノウハウ・ナレッジ継承、グローバル生産オペレーション体制の最適化など、競争力向上に大きな役割を果たす。その際に重要となるのは現場の事実情報である。
本講演では、現場の事実情報+生成AIによる、競争力向上に向けた事例を示し、成果を生める製造組織が備えるべき能力を提言する。
講演者プロフィール
重工業、産業機械 製造業を中心に、20年以上にわたって製造業向けコンサルティングに従事。
事業戦略、ビジネスモデル策定から、設計開発・営業・サプライチェーン・製造・サービスのオペレーション変革実行に至るまで幅広く支援している。
近年はデジタルを活用した事業構造変革に注力し、スマートファクトリーイニシアチブのリードも務める
講演内容
製造現場での生成AI活用は、文書検索・作成だけでなく、ノウハウ・ナレッジ継承、グローバル生産オペレーション体制の最適化など、競争力向上に大きな役割を果たす。その際に重要となるのは現場の事実情報である。
本講演では、現場の事実情報+生成AIによる、競争力向上に向けた事例を示し、成果を生める製造組織が備えるべき能力を提言する。
講演者プロフィール
重工業、産業機械 製造業を中心に、20年以上にわたって製造業向けコンサルティングに従事。
事業戦略、ビジネスモデル策定から、設計開発・営業・サプライチェーン・製造・サービスのオペレーション変革実行に至るまで幅広く支援している。
近年はデジタルを活用した事業構造変革に注力し、スマートファクトリーイニシアチブのリードも務める
ボッシュにおけるGenAIを活用した製造現場の業務改善事例

|
ボッシュ(株) デジタルソリューション&サービス部門 ビジネスデベロップメント アジアパシフィック部 マネージャー 赤堀 勝義 |

|

講演内容
弊社におけるAI関連活動に関して以下の3点を中心に紹介する。
・弊社概要及び全社を挙げてのAI活用推進体制
・ドイツ本国及び日本の製造現場における最新のGenAI活用事例
・製造現場における生成AI導入・活用をトップダウン、ボトムアップ双方から推進する取り組み
講演者プロフィール
1993年3月、早稲田大学卒業。 日揮株式会社に入社。 プラントエンジニアを経てERPコンサルタント(生産管理、品質管理)業務に従事。 2008年、ボッシュ株式会社に入社。 情報システム部門に所属し、社内のInd4.0/IoT関連プロジェクトのプロジェクトマネージャーを歴任。 2018年より情報システム部門の日本におけるIoT/Ind4.0活動(XR、AIを含む)の責任者を担当し、現在に至る。
講演内容
弊社におけるAI関連活動に関して以下の3点を中心に紹介する。
・弊社概要及び全社を挙げてのAI活用推進体制
・ドイツ本国及び日本の製造現場における最新のGenAI活用事例
・製造現場における生成AI導入・活用をトップダウン、ボトムアップ双方から推進する取り組み
講演者プロフィール
1993年3月、早稲田大学卒業。 日揮株式会社に入社。 プラントエンジニアを経てERPコンサルタント(生産管理、品質管理)業務に従事。 2008年、ボッシュ株式会社に入社。 情報システム部門に所属し、社内のInd4.0/IoT関連プロジェクトのプロジェクトマネージャーを歴任。 2018年より情報システム部門の日本におけるIoT/Ind4.0活動(XR、AIを含む)の責任者を担当し、現在に至る。
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details

|
三明機工(株) 代表取締役社長 久保田 和雄 |
|
講演内容
『もう人が足りないでは済まされない時代へ』
自動化へ舵を切った経営者たち。現状分析から見えてきたものとは何だったのか。
人材不足の先にある経営戦略──自動化がもたらす新しい現実
講演者プロフィール
• 1981年 三明機工入社
• 1981年 設計部設計課長就任
• 1986年 製造部製造部長就任
• 1991年 常務取締役就任
• 1997年 代表取締役社長就任 現在に至る
(一社)日本ロボット工業会副会長
(一社)日本ロボットシステムインテグレーター協会会長
日本鋳造協会理事役員
日本ダイカスト協会会員
講演内容
『もう人が足りないでは済まされない時代へ』
自動化へ舵を切った経営者たち。現状分析から見えてきたものとは何だったのか。
人材不足の先にある経営戦略──自動化がもたらす新しい現実
講演者プロフィール
• 1981年 三明機工入社
• 1981年 設計部設計課長就任
• 1986年 製造部製造部長就任
• 1991年 常務取締役就任
• 1997年 代表取締役社長就任 現在に至る
(一社)日本ロボット工業会副会長
(一社)日本ロボットシステムインテグレーター協会会長
日本鋳造協会理事役員
日本ダイカスト協会会員
自動化までのプロセスと費用対効果
|
|
(株)山清倉庫 包装事業部 統括部長 岡崎 好治 |
|
講演内容
ペットフード用スティック包装の袋詰めからパレタイズ工程までの自動化と費用対効果の検証
講演者プロフィール
1977年3月北海道立帯広農業高校酪農科卒業
1994年6月富士カプセル株式会社入社 工務部に配属となる。1999年に常務取締役管理本部長となるが工務部長も兼務してソフトカプセルの画像処理選別装置の導入に携わる。
2016年に株式会社山清倉庫に入社し包装事業部(健康食品及びペットフード)を統括し現在に至る。
講演内容
ペットフード用スティック包装の袋詰めからパレタイズ工程までの自動化と費用対効果の検証
講演者プロフィール
1977年3月北海道立帯広農業高校酪農科卒業
1994年6月富士カプセル株式会社入社 工務部に配属となる。1999年に常務取締役管理本部長となるが工務部長も兼務してソフトカプセルの画像処理選別装置の導入に携わる。
2016年に株式会社山清倉庫に入社し包装事業部(健康食品及びペットフード)を統括し現在に至る。
人手不足に生き残る鋳物工場

|
(株)アキオカ 取締役会長 秋岡 義典 |

|

講演内容
国内鋳物工場の経営規模と過去30年の業界推移、川上産業として無くては成らない鋳造品の価値、鋳物製造工程の自動化と省人化・省力化の紹介、IoT活用による生産状況の見える化の紹介
講演者プロフィール
1984年3月福岡工業大学卒業後、同年4月新東工業株式会社に入社約12年鋳造機械設備制御設計に所属1996年新東工業退社後、同年1月(株)アキオカに入社専務取締役を2005年まで務め同年代表取締役社長に就任、2020年取締役会長就任現在に至る。
講演内容
国内鋳物工場の経営規模と過去30年の業界推移、川上産業として無くては成らない鋳造品の価値、鋳物製造工程の自動化と省人化・省力化の紹介、IoT活用による生産状況の見える化の紹介
講演者プロフィール
1984年3月福岡工業大学卒業後、同年4月新東工業株式会社に入社約12年鋳造機械設備制御設計に所属1996年新東工業退社後、同年1月(株)アキオカに入社専務取締役を2005年まで務め同年代表取締役社長に就任、2020年取締役会長就任現在に至る。
本講演をお申込みいただいた方は9:30より展示会場にご入場いただけます。
10:00前にご入場いただく際は、展示会入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。
【脱炭素経営入門】市場競争力を高めるCO2見える化と削減の基本ー 中小企業の取り組み事例から学ぶ

|
アスエネ(株) アスエネ事業部 営業部 エンタープライズセールスG 兼 アスエネLCA G 兼 事業企画部 事業企画G マネージャー 岩渕 圭佑 |
|
講演内容
【中小企業経営者必見!】脱炭素経営の基本を学び、市場競争力を高めるためのCO2見える化と削減の方法を解説。中小企業の実践事例を通じて、具体的な取り組みのポイントを紹介する。サプライヤーを巻き込んで脱炭素を推進したい大手企業のご担当者様もぜひご参加ください。
講演者プロフィール
大手金融機関を中心にGHG算定支援・管理システム導入プロジェクトの統括経験を持ち、
現在はアスエネLCA事業責任者として製品別排出量の算定支援に注力し、メーカーやサプライヤー企業への導入支援を多数実施。
講演内容
【中小企業経営者必見!】脱炭素経営の基本を学び、市場競争力を高めるためのCO2見える化と削減の方法を解説。中小企業の実践事例を通じて、具体的な取り組みのポイントを紹介する。サプライヤーを巻き込んで脱炭素を推進したい大手企業のご担当者様もぜひご参加ください。
講演者プロフィール
大手金融機関を中心にGHG算定支援・管理システム導入プロジェクトの統括経験を持ち、
現在はアスエネLCA事業責任者として製品別排出量の算定支援に注力し、メーカーやサプライヤー企業への導入支援を多数実施。
2030年脱炭素企業への変革で企業価値を創造する

|
日崎工業(株) 代表取締役 セールスグループ マネージャー 三瓶 修 |
|
講演内容
日崎工業株式会社は、東日本大震災を契機に、省エネ・創エネを積極的に推進。LED照明や省エネ設備の導入により、電力消費を大幅に削減。さらに太陽光発電と蓄電池を活用し、BCP対策も強化。2030年までに完全脱炭素化を目指し、持続可能な社会の実現に貢献している。
講演者プロフィール
1983年3月、日本工業大学駒場高等学校を卒業。株式会社京浜精機製作所に入社し、品質管理課で商品開発やサプライヤーの品質管理を担当。1986年に退職後、3年間にわたり国内および北米を単独で旅し、自然環境やライフスタイルに関する知見を深める。1989年10月に日崎工業株式会社に入社し、製造業務を学びながら、受け身の営業スタイルを企画・設計・提案型のワンストップサービスに改革。2007年7月、代表取締役社長に就任。2011年の東日本大震災を契機に、エネルギー消費削減とエネルギーインフラに依存しない企業を目指し、近年はカーボンニュートラルを目指した製品開発を進めている。
講演内容
日崎工業株式会社は、東日本大震災を契機に、省エネ・創エネを積極的に推進。LED照明や省エネ設備の導入により、電力消費を大幅に削減。さらに太陽光発電と蓄電池を活用し、BCP対策も強化。2030年までに完全脱炭素化を目指し、持続可能な社会の実現に貢献している。
講演者プロフィール
1983年3月、日本工業大学駒場高等学校を卒業。株式会社京浜精機製作所に入社し、品質管理課で商品開発やサプライヤーの品質管理を担当。1986年に退職後、3年間にわたり国内および北米を単独で旅し、自然環境やライフスタイルに関する知見を深める。1989年10月に日崎工業株式会社に入社し、製造業務を学びながら、受け身の営業スタイルを企画・設計・提案型のワンストップサービスに改革。2007年7月、代表取締役社長に就任。2011年の東日本大震災を契機に、エネルギー消費削減とエネルギーインフラに依存しない企業を目指し、近年はカーボンニュートラルを目指した製品開発を進めている。

|
(株)Mujin CEO 兼 共同創業者 滝野 一征 |

|

講演内容
大変革期の真っ只中である製造業。工場/倉庫内物流自動化を今こそ推し進めて行く必要があります。本公演では、自動化を成功させるための鍵ともなる現場分析から仕様検討、更にデータ活用の方法を最新自動化事例と共に一挙解説します。
講演者プロフィール
米国大学卒業後、製造業の中でも世界最高の利益水準を誇る超硬切削工具メーカーの日本支社で、生産方法を提案する技術営業として活躍。営業成績1位となるなど輝かしい実績を残す。その後、ロボットの知能化により世界の生産性向上に貢献したいという想いを胸に、2011年にデアンコウ・ロセン博士とMujinを設立。
講演内容
大変革期の真っ只中である製造業。工場/倉庫内物流自動化を今こそ推し進めて行く必要があります。本公演では、自動化を成功させるための鍵ともなる現場分析から仕様検討、更にデータ活用の方法を最新自動化事例と共に一挙解説します。
講演者プロフィール
米国大学卒業後、製造業の中でも世界最高の利益水準を誇る超硬切削工具メーカーの日本支社で、生産方法を提案する技術営業として活躍。営業成績1位となるなど輝かしい実績を残す。その後、ロボットの知能化により世界の生産性向上に貢献したいという想いを胸に、2011年にデアンコウ・ロセン博士とMujinを設立。
トヨタに学ぶ“つながる管理”で現場を変える ~経営と現場をつなぐコミュニケーション~

|
(株)OJTソリューションズ エグゼクティブトレーナー 富安 輝美 |

|

講演内容
トヨタ式“つながる管理”の実践で現場改革ができる。経営方針から部署の方針へ、部署の方針から管理指標へ、さらに管理指標から日々の行動へとつなげる。そのつなぎ手は管理監督者である。しくみ化とつなぎ手の育成方法の実践値をトヨタの経験から解説。
講演者プロフィール
トヨタ学園を経て、1974年にトヨタ自動車株式会社に入社。主にプレス金型の製作業務に従事し、キャリア後半には管理監督者として100名以上の部下のマネジメントおよび人材育成に取り組む。アメリカやタイ、インドネシアなど、海外のトヨタ拠点においても多数の指導経験を有する。
2014年よりOJTソリューションズ株式会社に入社。トレーナーとして、食品、鉄鋼、化学、機械、ホテル業界など、幅広い業種において、現場に寄り添った伴走型の改善支援を行っている。
講演内容
トヨタ式“つながる管理”の実践で現場改革ができる。経営方針から部署の方針へ、部署の方針から管理指標へ、さらに管理指標から日々の行動へとつなげる。そのつなぎ手は管理監督者である。しくみ化とつなぎ手の育成方法の実践値をトヨタの経験から解説。
講演者プロフィール
トヨタ学園を経て、1974年にトヨタ自動車株式会社に入社。主にプレス金型の製作業務に従事し、キャリア後半には管理監督者として100名以上の部下のマネジメントおよび人材育成に取り組む。アメリカやタイ、インドネシアなど、海外のトヨタ拠点においても多数の指導経験を有する。
2014年よりOJTソリューションズ株式会社に入社。トレーナーとして、食品、鉄鋼、化学、機械、ホテル業界など、幅広い業種において、現場に寄り添った伴走型の改善支援を行っている。
実際と計画を連動させてDXの効果を出す工程管理の勘所

|
コンサルソーシング(株) 代表取締役 松井 順一 |

|

講演内容
製造現場の実際と計画を連動化させることで「生産計画の最適化ができない」「生産負荷が読めない」「工程の混乱が続く」「製造原価の精度が低い」といった課題を解決し、効果的な製造DXへと進化させる工程管理のポイントを実際の事例とともに紹介します。
講演者プロフィール
コンサルソーシング株式会社代表取締役。中小企業診断士、システムアナリスト、情報システム監査技術者。アイシン精機株式会社にてABS等の新製品開発に従事。微小洩れ測定法開発にて科学技術長官賞を受賞。その後、社団法人中部産業連盟、デロイトトーマツコンサルティング株式会社、現職にて、製造ライン構築・生産管理システムの構築・現場改善・製造DX化改善にコンサルティングに従事。【著書】「工場管理の改善手法がよ~くわかる本(秀和システム)」「トヨタ流 仕事の「見える化」大全」(アスコム)「ダンドリ倍速仕事術100の法則」(日本能率協会マネジメントセンター)「職場のかんばん方式」(日経BP社)他
講演内容
製造現場の実際と計画を連動化させることで「生産計画の最適化ができない」「生産負荷が読めない」「工程の混乱が続く」「製造原価の精度が低い」といった課題を解決し、効果的な製造DXへと進化させる工程管理のポイントを実際の事例とともに紹介します。
講演者プロフィール
コンサルソーシング株式会社代表取締役。中小企業診断士、システムアナリスト、情報システム監査技術者。アイシン精機株式会社にてABS等の新製品開発に従事。微小洩れ測定法開発にて科学技術長官賞を受賞。その後、社団法人中部産業連盟、デロイトトーマツコンサルティング株式会社、現職にて、製造ライン構築・生産管理システムの構築・現場改善・製造DX化改善にコンサルティングに従事。【著書】「工場管理の改善手法がよ~くわかる本(秀和システム)」「トヨタ流 仕事の「見える化」大全」(アスコム)「ダンドリ倍速仕事術100の法則」(日本能率協会マネジメントセンター)「職場のかんばん方式」(日経BP社)他
生成AIの登場から3年、テクノロジーの進化と製造業へのインパクト

|
日本マイクロソフト(株) 業務執行役員 エバンジェリスト 西脇 資哲 |

|

講演内容
急速に進化する生成AIは、文章や図面の生成に加え、膨大な生産データの整理・分析を行う能力も備えており、製造業での業務の負担を大きく軽減する。本講演では、その生成AIの最新動向を紹介しつつ、生成AIを使いこなすための考え方にふれ、さらに製造業を中心とした分野における設計、製造工程、品質管理、サポートなどでの取り組み方について紹介する。
講演者プロフィール
日本経済新聞でも紹介されたIT「伝道師」。IT業界の著名エバンジェリスト。エバンジェリストとはわかりやすく製品やサービス、技術を紹介する職種。現在はマイクロソフトにて多くの製品・サービスを伝え広めるエバンジェリスト。1990年代から企業システム、データベース、Java、インターネットのビジネスに関与し、1996年からオラクル社にてエバンジェリスト、2009年からはマイクロソフト社にてエバンジェリスト活動を継続。最新ITに係るプレゼンテーションやデモンストレーションに加え、ドローンやブロックチェーン・仮想通貨などのトレンドに関するプレゼンテーションも行っている。
講演内容
急速に進化する生成AIは、文章や図面の生成に加え、膨大な生産データの整理・分析を行う能力も備えており、製造業での業務の負担を大きく軽減する。本講演では、その生成AIの最新動向を紹介しつつ、生成AIを使いこなすための考え方にふれ、さらに製造業を中心とした分野における設計、製造工程、品質管理、サポートなどでの取り組み方について紹介する。
講演者プロフィール
日本経済新聞でも紹介されたIT「伝道師」。IT業界の著名エバンジェリスト。エバンジェリストとはわかりやすく製品やサービス、技術を紹介する職種。現在はマイクロソフトにて多くの製品・サービスを伝え広めるエバンジェリスト。1990年代から企業システム、データベース、Java、インターネットのビジネスに関与し、1996年からオラクル社にてエバンジェリスト、2009年からはマイクロソフト社にてエバンジェリスト活動を継続。最新ITに係るプレゼンテーションやデモンストレーションに加え、ドローンやブロックチェーン・仮想通貨などのトレンドに関するプレゼンテーションも行っている。
生成AIによる業務革新:導入から見えた課題と展望

|
三菱重工業(株) デジタルイノベーション本部DPI部モジュラーデザイングループ グループ長 後藤 大輔 |
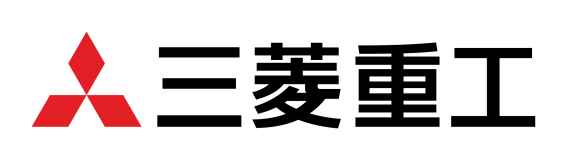
|
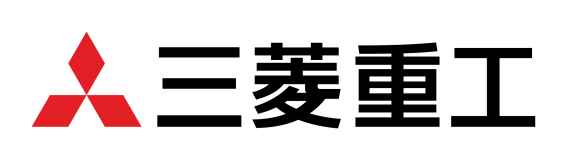
講演内容
三菱重工は2023年度に社内生成AIを導入し、グループ全体での活用を推進している。本講演では、生成AIを活用した人材不足や技術伝承への対応、具体的な事例、導入過程で顕在化した課題、さらには今後の展望と活用拡大に向けた取り組みについて紹介する。
講演者プロフィール
1998年に三菱重工業へ入社。製紙機械および社内業務システムの研究開発に従事。
2015年よりIoTプラットフォーム「TOMONI」プロジェクトに参画し、中心メンバーとして立ち上げから製品化までを牽引。
2023年には社内向け対話型生成AIアプリ「TOMONI TALK」を開発し、生成AIの社内導入を推進。
2024年にデジタルイノベーション本部へ異動。現在は生成AIプロジェクト責任者として、導入戦略の立案および業務改善への適用を推進中。
講演内容
三菱重工は2023年度に社内生成AIを導入し、グループ全体での活用を推進している。本講演では、生成AIを活用した人材不足や技術伝承への対応、具体的な事例、導入過程で顕在化した課題、さらには今後の展望と活用拡大に向けた取り組みについて紹介する。
講演者プロフィール
1998年に三菱重工業へ入社。製紙機械および社内業務システムの研究開発に従事。
2015年よりIoTプラットフォーム「TOMONI」プロジェクトに参画し、中心メンバーとして立ち上げから製品化までを牽引。
2023年には社内向け対話型生成AIアプリ「TOMONI TALK」を開発し、生成AIの社内導入を推進。
2024年にデジタルイノベーション本部へ異動。現在は生成AIプロジェクト責任者として、導入戦略の立案および業務改善への適用を推進中。
本講演をお申込みいただいた方は9:30より展示会場にご入場いただけます。
10:00前にご入場いただく際は、展示会入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。
中小企業における人材確保と省力化の取組

|
経済産業省 中小企業庁 事業環境部調査室 総括室長補佐 蓬田 桂一郎 |

|

講演内容
中小企業が直面する大きな供給制約である人手不足を乗り越えるための、人材確保・定着や省力化投資等の取組について、有効な取組事例を交えつつ紹介する。
講演者プロフィール
2018年経済産業省入省。2024年8月より中小企業庁調査室に所属し、中小企業の動向に関する調査・分析や、中小企業白書・小規模企業白書の執筆等に従事。
講演内容
中小企業が直面する大きな供給制約である人手不足を乗り越えるための、人材確保・定着や省力化投資等の取組について、有効な取組事例を交えつつ紹介する。
講演者プロフィール
2018年経済産業省入省。2024年8月より中小企業庁調査室に所属し、中小企業の動向に関する調査・分析や、中小企業白書・小規模企業白書の執筆等に従事。
人材こそ最大の資本!中小製造業の人的資本経営の成功事例

|
御津電子(株) 代表取締役 人見 雄一 |

|

講演内容
御津電子が考える人的資本経営とは、「人の可能性を引き出すこと」。人に寄り添い、強みを見出し、それを実践につなげることで、営業利益率を押し上げた。本講演では、その具体的な取り組みと現場の工夫を、実践事例を交えて紹介します。
講演者プロフィール
2007年から10年間、リクルートに在籍し「人を活かす経営」を学ぶ。2017年御津電子(株)へ入社。。リクルートでの経験を製造業に応用し、2年で工場をV字回復。2023年に代表に就任し、人の可能性を引き出すことを軸に、2年間で新たに2つの事業を展開。営業利益率と売上の双方を向上させ、持続的な成長を実現している。
講演内容
御津電子が考える人的資本経営とは、「人の可能性を引き出すこと」。人に寄り添い、強みを見出し、それを実践につなげることで、営業利益率を押し上げた。本講演では、その具体的な取り組みと現場の工夫を、実践事例を交えて紹介します。
講演者プロフィール
2007年から10年間、リクルートに在籍し「人を活かす経営」を学ぶ。2017年御津電子(株)へ入社。。リクルートでの経験を製造業に応用し、2年で工場をV字回復。2023年に代表に就任し、人の可能性を引き出すことを軸に、2年間で新たに2つの事業を展開。営業利益率と売上の双方を向上させ、持続的な成長を実現している。
【ご聴講者限定】
当日、本セッションをご聴講いただいた方は、中小企業庁様にご用意いただいた
補助金チラシ・パンフレット一覧をデータダウンロードいただけます。
製造業のGXに向けた愛知県の取組 ~水素社会実装施策を中心として~

|
愛知県経済産業局 水素社会実装推進課 水素・モビリティ推進監 都筑 秀典 |

|

講演内容
カーボンニュートラルと産業競争力強化の両立を目指し、愛知県が推進している水素・アンモニアのサプライチェーン構築や水素燃料工業炉の活用促進、燃料電池商用車の普及促進などの取組を紹介する。
講演者プロフィール
1995年4月に愛知県庁に入庁。繊維産業やロボット産業、科学技術などの振興業務に従事。2022年4月から新エネルギー産業振興を担当し、2023年12月に水素社会実装推進室長、2025年4月から現職。
講演内容
カーボンニュートラルと産業競争力強化の両立を目指し、愛知県が推進している水素・アンモニアのサプライチェーン構築や水素燃料工業炉の活用促進、燃料電池商用車の普及促進などの取組を紹介する。
講演者プロフィール
1995年4月に愛知県庁に入庁。繊維産業やロボット産業、科学技術などの振興業務に従事。2022年4月から新エネルギー産業振興を担当し、2023年12月に水素社会実装推進室長、2025年4月から現職。
GX実現に向けた投資戦略のあり方と具体的なアプローチについて

|
デロイト トーマツ コンサルティング(同) パブリックセクター パートナー 執行役員/Sustainability & Climate Initiative Lead 庵原 一水 |
|
講演内容
ネットゼロ実現に向けて、バリューチェーン軸(SCOPE3)と時間軸(短/中長期)の組み合わせによる具体的対策のロードマップの整備と実践が必要となる。資金調達、投資確保の観点から戦略の俯瞰的説明をした上で、補助金活用を含めた取り組みのあり方について解説する。
講演者プロフィール
建設コンサルタント、総合シンクタンクを経て現職。エネルギー・地球温暖化対策を中心とする環境分野のコンサルティングに25年以上従事。中央省庁の政策立案・実行支援から企業の戦略立案・R&D支援等を幅広く手掛けており、官民双方の立場からの政策実現に取り組む。特に、再エネ・省エネ技術に関する高度な専門的知見を有しており、国内外の最新のビジネス・政策動向を踏まえた政策/戦略立案、エネルギーシミュレーションに基づく政策/事業評価、官民連携によるR&Dや社会実証のコーディネートを得意とする。 大阪大学大学院工学研究科環境工学専攻修了(工学修士)、早稲田大学大学院環境エネルギー研究科博士後期課程単位取得後退学
講演内容
ネットゼロ実現に向けて、バリューチェーン軸(SCOPE3)と時間軸(短/中長期)の組み合わせによる具体的対策のロードマップの整備と実践が必要となる。資金調達、投資確保の観点から戦略の俯瞰的説明をした上で、補助金活用を含めた取り組みのあり方について解説する。
講演者プロフィール
建設コンサルタント、総合シンクタンクを経て現職。エネルギー・地球温暖化対策を中心とする環境分野のコンサルティングに25年以上従事。中央省庁の政策立案・実行支援から企業の戦略立案・R&D支援等を幅広く手掛けており、官民双方の立場からの政策実現に取り組む。特に、再エネ・省エネ技術に関する高度な専門的知見を有しており、国内外の最新のビジネス・政策動向を踏まえた政策/戦略立案、エネルギーシミュレーションに基づく政策/事業評価、官民連携によるR&Dや社会実証のコーディネートを得意とする。 大阪大学大学院工学研究科環境工学専攻修了(工学修士)、早稲田大学大学院環境エネルギー研究科博士後期課程単位取得後退学
バース予約・受付システムの開発・導入による物流最適化

|
福岡運輸(株) 業務推進部 次長 兼 システム課長 生津 瑠美 |

|

講演内容
人手不足が深刻化する中、当社は自社開発したバース予約・受付システムにより待機時間を削減し、作業効率と物流全体の最適化を実現した。本講演ではその取組みの経緯と概要、効果と共に今後の展望について紹介する。
講演者プロフィール
2000年に福岡運輸株式会社入社。
配車業務・営業を担当後、業務推進部にて新規センターの立ち上げ支援や監査、研修等の業務を担当。
2014年から同部内のシステム課にて社内向けシステム開発およびDX関連プロジェクトに従事。
講演内容
人手不足が深刻化する中、当社は自社開発したバース予約・受付システムにより待機時間を削減し、作業効率と物流全体の最適化を実現した。本講演ではその取組みの経緯と概要、効果と共に今後の展望について紹介する。
講演者プロフィール
2000年に福岡運輸株式会社入社。
配車業務・営業を担当後、業務推進部にて新規センターの立ち上げ支援や監査、研修等の業務を担当。
2014年から同部内のシステム課にて社内向けシステム開発およびDX関連プロジェクトに従事。
持続可能なサプライチェーンの構築

|
トランコム (株) Transportグループ 事業推進 マネージャー 西本 美央 |

|

講演内容
本講演では、持続可能なサプライチェーンを構築するためのアプローチとして求貨求車プラットフォームや自社ネットワークなど、様々な輸送モードを活用した業界別共同物流をご紹介する。
講演者プロフィール
2004年トランコム入社
営業企画として、3PL提案に向けた物流分析、現場改善分析の担当を経て、
拠点開発、物流センター設計業務に従事
講演内容
本講演では、持続可能なサプライチェーンを構築するためのアプローチとして求貨求車プラットフォームや自社ネットワークなど、様々な輸送モードを活用した業界別共同物流をご紹介する。
講演者プロフィール
2004年トランコム入社
営業企画として、3PL提案に向けた物流分析、現場改善分析の担当を経て、
拠点開発、物流センター設計業務に従事
*AI Translation System Available at This Session
Please bring your mobile phone & earphones to use the system.
>>>More Details
本講演をお申込みいただいた方は9:30より展示会場にご入場いただけます。
10:00前にご入場いただく際は、展示会入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。
トラック運送業の現状と人手不足対策 ~特定技能制度を中心に~
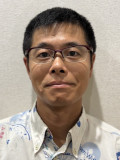
|
国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課 専門官 上中 理史 |

|

講演内容
物流2024年問題など、トラック運送業界を取り巻く現状と課題に加え、政府による物流革新に向けた施策、改正物流法の概要や特定技能制度について説明する。
講演者プロフィール
2006年国土交通省に入省。これまでトラック運送事業、倉庫業、利用運送事業等の物流事業所管部局において物流改善や補助事業などの業務に携わり、近年においてはスワップボディコンテナ車両のガイドラインや各荷種別物流改善のガイドライン策定などに従事。前部署においては首都高速道路(株)に出向。2025年4月から現職。トラック運送事業の人材確保や特定技能制度の担当として、「ホワイト物流」推進運動の展開や特定技能外国人の受入れ環境の整備等の各種政策を担当している。
講演内容
物流2024年問題など、トラック運送業界を取り巻く現状と課題に加え、政府による物流革新に向けた施策、改正物流法の概要や特定技能制度について説明する。
講演者プロフィール
2006年国土交通省に入省。これまでトラック運送事業、倉庫業、利用運送事業等の物流事業所管部局において物流改善や補助事業などの業務に携わり、近年においてはスワップボディコンテナ車両のガイドラインや各荷種別物流改善のガイドライン策定などに従事。前部署においては首都高速道路(株)に出向。2025年4月から現職。トラック運送事業の人材確保や特定技能制度の担当として、「ホワイト物流」推進運動の展開や特定技能外国人の受入れ環境の整備等の各種政策を担当している。
誰もが活躍できる職場づくり ~ロジスティクス変革期におけるハンナの健康経営とは~

|
(株)ハンナ 代表取締役 社長 下村 由加里 |

|

講演内容
2024年問題などに直面する今、運輸・物流業界は構造的な変革を求められており、
「人的資本の最大化」や「多様性」が業界の持続可能性を高める重要な戦略であると考える。
ハンナの「健康経営」を通じた社員の意識変革や企業文化の醸成など、
実践的な取り組み事例や課題、成果について現場・経営層の両視点から紹介する。
講演者プロフィール
1983年株式会社ハンナ(旧株式会社阪奈運輸)入社
1994年より専務取締役に就任
その後2006年に代表取締役社長に就任。
就任後グループ会社である、ライズ株式会社を設立。
ライズ株式会社は、その後GLOW株式会社に代わり、代表取締役を兼任。
公共活動として
奈良県防犯協会 理事
奈良商工会議所 議員
2014年4月から奈良国際文化観光都市建設審議会 審議委員委員
2016年4月から奈良県公共事業評価監視委員会 委員を現在も務めている。
また、公)日本ロジスティクスシステム協会では
ロジスティクス経営士 専門委員や関西支部 運営委員
関西大会 実行委員を務めている。
講演内容
2024年問題などに直面する今、運輸・物流業界は構造的な変革を求められており、
「人的資本の最大化」や「多様性」が業界の持続可能性を高める重要な戦略であると考える。
ハンナの「健康経営」を通じた社員の意識変革や企業文化の醸成など、
実践的な取り組み事例や課題、成果について現場・経営層の両視点から紹介する。
講演者プロフィール
1983年株式会社ハンナ(旧株式会社阪奈運輸)入社
1994年より専務取締役に就任
その後2006年に代表取締役社長に就任。
就任後グループ会社である、ライズ株式会社を設立。
ライズ株式会社は、その後GLOW株式会社に代わり、代表取締役を兼任。
公共活動として
奈良県防犯協会 理事
奈良商工会議所 議員
2014年4月から奈良国際文化観光都市建設審議会 審議委員委員
2016年4月から奈良県公共事業評価監視委員会 委員を現在も務めている。
また、公)日本ロジスティクスシステム協会では
ロジスティクス経営士 専門委員や関西支部 運営委員
関西大会 実行委員を務めている。
国土交通省については、講師が変更になりました。(10/17時点)
本講演をお申込みいただいた方は9:30より展示会場にご入場いただけます。
10:00前にご入場いただく際は、展示会入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。
運輸安全マネジメントにおけるリスク感受性向上とは

|
(一財)日本品質保証機構(JQA) マネジメントシステム部門 審査事業センター 品質審査部 運輸安全審査グループ グループ長 鋤柄 耕治 |
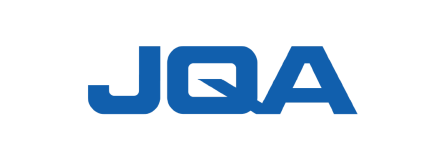
|
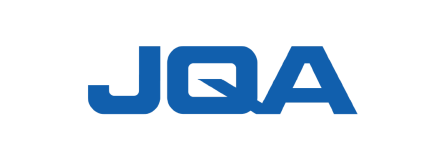
講演内容
運輸安全マネジメント(安マネ)では、「現場のリスクに気づく力(リスク感受性)」の向上が、事故の防止に効果的としている。本講演では、安マネ制度の概要とJQAの「リスク感受性向上セミナー」等を通じた運輸事業者の交通安全対策等について紹介する。
講演者プロフィール
国土交通省の運輸安全マネジメント認定セミナー講師研修を修了し、2020年からJQAで運輸安全マネジメント認定セミナー(ガイドライン、内部監査、運輸防災マネジメント)を担当。また、国土交通省の運輸安全マネジメント評価員研修を修了し、自動車モード(トラック・バス・タクシー)の運輸安全マネジメント主任評価員として、事業者の運輸安全マネジメント評価も担当。JQA認定ISO主任審査員(ISO9001、ISO14001、ISO39001)。
講演内容
運輸安全マネジメント(安マネ)では、「現場のリスクに気づく力(リスク感受性)」の向上が、事故の防止に効果的としている。本講演では、安マネ制度の概要とJQAの「リスク感受性向上セミナー」等を通じた運輸事業者の交通安全対策等について紹介する。
講演者プロフィール
国土交通省の運輸安全マネジメント認定セミナー講師研修を修了し、2020年からJQAで運輸安全マネジメント認定セミナー(ガイドライン、内部監査、運輸防災マネジメント)を担当。また、国土交通省の運輸安全マネジメント評価員研修を修了し、自動車モード(トラック・バス・タクシー)の運輸安全マネジメント主任評価員として、事業者の運輸安全マネジメント評価も担当。JQA認定ISO主任審査員(ISO9001、ISO14001、ISO39001)。
人材流出を防ぐカギは“事故ゼロ職場”

|
(株)ディ・クリエイト 代表取締役 上西 一美 |
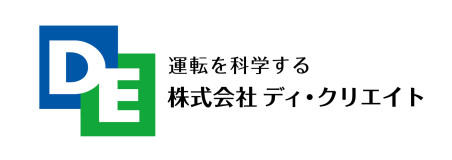
|
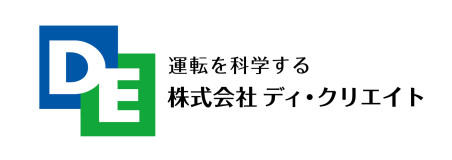
講演内容
人材不足と言われている時代、盲点になっているのは、その人材の流出である。その人材の流出につながる原因の1つが交通事故と言われている。交通事故防止の対策をしっかりと行い、人材が流出しない会社づくりのポイントを解説する。
講演者プロフィール
関西学院大学法学部法律学科卒
29歳で神戸市内タクシー会社社長就任
退職までの6年間で1,000人の乗務員を確保
運輸監査12回経験/交通事故前年比70%削減
35歳で交通事故防止コンサルタントとして起業
ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立
運輸業界(トラック・タクシー・バス)の労務管理・運輸監査対応にも精通
全国でコンサルティングを展開し、年間400件以上の研修を行っている
講演内容
人材不足と言われている時代、盲点になっているのは、その人材の流出である。その人材の流出につながる原因の1つが交通事故と言われている。交通事故防止の対策をしっかりと行い、人材が流出しない会社づくりのポイントを解説する。
講演者プロフィール
関西学院大学法学部法律学科卒
29歳で神戸市内タクシー会社社長就任
退職までの6年間で1,000人の乗務員を確保
運輸監査12回経験/交通事故前年比70%削減
35歳で交通事故防止コンサルタントとして起業
ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立
運輸業界(トラック・タクシー・バス)の労務管理・運輸監査対応にも精通
全国でコンサルティングを展開し、年間400件以上の研修を行っている
※(株)ディ・クリエイト 上西様につきましては、講演スライドの配布はございません。
予めご了承の上、お申込みください。
歩かない物流センターの実現 -エレコムの物流戦略を紐解く-

|
エレコム(株) 物流部 取締役 執行役員 町 一浩 |

|

講演内容
物流倉庫センターにおける人手不足対策・現場改善について解説する。
講演者プロフィール
1995年エレコム株式会社入社。営業部を経て2000年より物流部に従事。2021年取締役就任。物流技術管理士。
講演内容
物流倉庫センターにおける人手不足対策・現場改善について解説する。
講演者プロフィール
1995年エレコム株式会社入社。営業部を経て2000年より物流部に従事。2021年取締役就任。物流技術管理士。
【自動化は救世主か?】 物流×自動化の考察とSBSの挑戦

|
SBSホールディングス(株) LT企画部 部長 曲渕 章浩 |

|

講演内容
人手不足に歯止めがかからない物流現場において、自動化は本当に解決策となるのか。自動化の難しさや可能性を考察し、SBSグループによる打開への取り組み事例を通じて、物流現場の未来を探る。
講演者プロフィール
1997年3月、武蔵工業大学を卒業、リコーロジスティクス株式会社に入社。当初は情報システム部門にて社内システムの設計・開発・運用などに従事していたが、2003年に技術面から物流業務の効率化や高度化支援に取り組む「LT(ロジスティクス・テクノロジー)センター」に異動。2020年よりSBSホールディングス株式会社LT企画部に出向し、SBSグループ全体の物流技術戦略立案や物流業務の高度化に携わっている。
講演内容
人手不足に歯止めがかからない物流現場において、自動化は本当に解決策となるのか。自動化の難しさや可能性を考察し、SBSグループによる打開への取り組み事例を通じて、物流現場の未来を探る。
講演者プロフィール
1997年3月、武蔵工業大学を卒業、リコーロジスティクス株式会社に入社。当初は情報システム部門にて社内システムの設計・開発・運用などに従事していたが、2003年に技術面から物流業務の効率化や高度化支援に取り組む「LT(ロジスティクス・テクノロジー)センター」に異動。2020年よりSBSホールディングス株式会社LT企画部に出向し、SBSグループ全体の物流技術戦略立案や物流業務の高度化に携わっている。
本講演をお申込みいただいた方は9:30より展示会場にご入場いただけます。
10:00前にご入場いただく際は、展示会入口にてセミナー受講者である旨をお伝えのうえ、受講券をご提示ください。

|
トヨタ自動車(株) 車体製造技術部 プロセス革新2G グループ長 小笠原 知子 |
|
講演内容
女性活躍推進法が制定されてから10年。制度面では着実に前進し、男性育休制度なども整う中で、製造業も働きやすい職場に変わってきたと感じる。私自身、製造業で20年近く技術職として歩んできた。その中で経験したライフイベントとキャリアの両立、転職を経て感じたことを、当事者の視点でお話しする。さらに、より客観的な現状を把握するため、製造業で働く女性技術者90名以上にアンケートを実施し、ワークライフバランスなどに関する声を集めた。その結果を踏まえて、今の課題や今後に向けたヒントについて、皆さんと一緒に考えていきたいと思う。
講演者プロフィール
2008年、広島大学大学院工学研究科を修了後、三菱重工業 名古屋誘導推進システム製作所に入社し、航空宇宙製品の生産技術開発に従事。特に、航空宇宙製品への金属3Dプリンタのアプリケーション開発に注力した。2021年にトヨタ自動車へ転職し、現在は自動車の生産技術開発におけるマネジメント業務に従事。また、2021年よりグロービス経営大学院大学に通い、2023年に卒業。同年、理工系女性をつなぐコミュニティ「Wom-tech(ワムテック)」を設立し、SNSでの情報発信や定期的なイベント・交流会を開催している。プライベートでは小学3年生の子どもの子育て中。
講演内容
女性活躍推進法が制定されてから10年。制度面では着実に前進し、男性育休制度なども整う中で、製造業も働きやすい職場に変わってきたと感じる。私自身、製造業で20年近く技術職として歩んできた。その中で経験したライフイベントとキャリアの両立、転職を経て感じたことを、当事者の視点でお話しする。さらに、より客観的な現状を把握するため、製造業で働く女性技術者90名以上にアンケートを実施し、ワークライフバランスなどに関する声を集めた。その結果を踏まえて、今の課題や今後に向けたヒントについて、皆さんと一緒に考えていきたいと思う。
講演者プロフィール
2008年、広島大学大学院工学研究科を修了後、三菱重工業 名古屋誘導推進システム製作所に入社し、航空宇宙製品の生産技術開発に従事。特に、航空宇宙製品への金属3Dプリンタのアプリケーション開発に注力した。2021年にトヨタ自動車へ転職し、現在は自動車の生産技術開発におけるマネジメント業務に従事。また、2021年よりグロービス経営大学院大学に通い、2023年に卒業。同年、理工系女性をつなぐコミュニティ「Wom-tech(ワムテック)」を設立し、SNSでの情報発信や定期的なイベント・交流会を開催している。プライベートでは小学3年生の子どもの子育て中。
講演終了後、カジュアルな交流会を実施!

|
女性の技術者同士で、課題や悩みなど気軽にお話しください! |
|
本セミナーは、製造業で働く女性の技術者・研究者が対象です。
製造業で働く女性技術者が抱える特有の課題に対し、共感・共有・解決のきっかけの場となることを目的としています。
様々な業種の技術者と会社の垣根を越えて、気軽に交流いただける貴重な機会となります。
【参加メリット】
★同じ立場の技術者同士でリアルな課題や想いを共有
★他社の取り組みや工夫を知ることで新たな気づきやヒントを得られる
★今後のキャリア形成や職場改善へのきっかけづくり
【セッションの流れ】
■15:30~ 小笠原様による講演
■16:00~ 交流会
トークテーマ:セミナー内容、課題や本音(キャリア・働き方・プライベートとの両立など)、自分の身の回りでできること
※交流会は女性のみ参加いただけます。
トークテーマ:「新卒採用」の課題・悩みを採用担当者同士で話そう

|
製造業の人事コミュニケーションラウンジとは、採用/教育担当者、人事部のための交流イベントです |
|
本ラウンジでは、
トークテーマに沿って情報交換や、 企業の垣根を越えてコミュニティを作ることが可能です。
事前申し込み制となりますので、ぜひお申込みください。
※定員になり次第受付終了とさせていただきます。
※サービスや商品の売り込み、ヒアリングはご遠慮ください。参加をお断りさせていただきます。
トークテーマ:「中途/海外人材採用」の課題・悩みを採用担当者同士で話そう

|
製造業の人事コミュニケーションラウンジとは、採用/教育担当者、人事部のための交流イベントです |
|
本ラウンジでは、
トークテーマに沿って情報交換や、 企業の垣根を越えてコミュニティを作ることが可能です。
事前申し込み制となりますので、ぜひお申込みください。
※定員になり次第受付終了とさせていただきます。
※サービスや商品の売り込み、ヒアリングはご遠慮ください。参加をお断りさせていただきます。
トークテーマ:「研修/教育」の課題・悩みを教育担当者同士で話そう

|
製造業の人事コミュニケーションラウンジとは、採用/教育担当者、人事部のための交流イベントです |
|
本ラウンジでは、
トークテーマに沿って情報交換や、 企業の垣根を越えてコミュニティを作ることが可能です。
事前申し込み制となりますので、ぜひお申込みください。
※定員になり次第受付終了とさせていただきます。
※サービスや商品の売り込み、ヒアリングはご遠慮ください。参加をお断りさせていただきます。
トークテーマ:「新卒採用」の課題・悩みを採用担当者同士で話そう

|
製造業の人事コミュニケーションラウンジとは、採用/教育担当者、人事部のための交流イベントです |
|
本ラウンジでは、
トークテーマに沿って情報交換や、 企業の垣根を越えてコミュニティを作ることが可能です。
事前申し込み制となりますので、ぜひお申込みください。
※定員になり次第受付終了とさせていただきます。
※サービスや商品の売り込み、ヒアリングはご遠慮ください。参加をお断りさせていただきます。
トークテーマ:「中途/海外人材採用」の課題・悩みを採用担当者同士で話そう

|
製造業の人事コミュニケーションラウンジとは、採用/教育担当者、人事部のための交流イベントです |
|
本ラウンジでは、
トークテーマに沿って情報交換や、 企業の垣根を越えてコミュニティを作ることが可能です。
事前申し込み制となりますので、ぜひお申込みください。
※定員になり次第受付終了とさせていただきます。
※サービスや商品の売り込み、ヒアリングはご遠慮ください。参加をお断りさせていただきます。


|
(株)マークラインズソフト開発 代表取締役 片場 啓之 |

|

講演内容
本講演では、中国における車載インテリジェントソフトウェア市場の最新動向について、当社が協業する現地スマート製品プラットフォーム企業を通じて得た、市場ニーズ、技術的要件の変化などを交えてご紹介する。
講演者プロフィール
1992年4月、三信電気株式会社に入社。開発部に所属し、組み込みソフト開発に従事。
その後、車載や民生向けのSoC、MCUのFAEを経て、2025年1月、マークラインズ株式会社に入社。
2025年4月、マークラインズ株式会社(51%)と中国 華勤技術(49%)の合弁会社を設立し現在に至る。
講演内容
本講演では、中国における車載インテリジェントソフトウェア市場の最新動向について、当社が協業する現地スマート製品プラットフォーム企業を通じて得た、市場ニーズ、技術的要件の変化などを交えてご紹介する。
講演者プロフィール
1992年4月、三信電気株式会社に入社。開発部に所属し、組み込みソフト開発に従事。
その後、車載や民生向けのSoC、MCUのFAEを経て、2025年1月、マークラインズ株式会社に入社。
2025年4月、マークラインズ株式会社(51%)と中国 華勤技術(49%)の合弁会社を設立し現在に至る。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。


|
マークラインズ(株) コンサルティング事業部 チーフコンサルタント 齊藤 清一 |

|

講演内容
マークラインズでは、厚木に新設したベンチマークセンターで車両や車載部品の分解とベンチマーク調査を実施しています。 このセッションでは、SDVと関係の深いEEアーキテクチャーにフォーカスし、テスラ サイバートラックを中心に、モデルY、シャオミ SU7について解説する。
講演者プロフィール
1986年株式会社日立製作所に入社し、車載半導体の開発に従事。 2003年(株)ルネサステクノロジ転籍。2020年からマークラインズ㈱にて、車載エレクトロニクス関連の調査、コンサルティング業務を担当。
講演内容
マークラインズでは、厚木に新設したベンチマークセンターで車両や車載部品の分解とベンチマーク調査を実施しています。 このセッションでは、SDVと関係の深いEEアーキテクチャーにフォーカスし、テスラ サイバートラックを中心に、モデルY、シャオミ SU7について解説する。
講演者プロフィール
1986年株式会社日立製作所に入社し、車載半導体の開発に従事。 2003年(株)ルネサステクノロジ転籍。2020年からマークラインズ㈱にて、車載エレクトロニクス関連の調査、コンサルティング業務を担当。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。


|
マークラインズ(株) コンサルティング事業部 コスト分析チーム チーフコンサルタント 眞舩 建治 |

|

講演内容
本講演では、ECUベンチマークの取り組みについて、IVI-ECUベンチマークの事例を交えながら紹介する。具体的には、ECUベンチマークの手法と調査内容について説明すると同時に、IVI-ECUをベンチマークした結果、見えてきた事象について解説する。講演を通して、ECUベンチマークの活用方法と、重要性について理解を深めて頂ければ幸いである。
講演者プロフィール
1992年 NTTエレクトロニクステクノロジー株式会社入社
LSI事業部本部に所属し、半導体の故障解析・画像圧縮エンコーダLSI開発業務に従事
2004年 株式会社ヴァン・パートナーズ入社
半導体・電子基板の解析サービスに従事
2009年 株式会社豊通エレクトロニクスに入社
ECUベンチマーク、半導体・電子デバイス類の解析サービスに従事
2022年10月マークラインズ株式会社入社
コンサルティング事業部に所属し、ECUベンチマークサービスに従事
講演内容
本講演では、ECUベンチマークの取り組みについて、IVI-ECUベンチマークの事例を交えながら紹介する。具体的には、ECUベンチマークの手法と調査内容について説明すると同時に、IVI-ECUをベンチマークした結果、見えてきた事象について解説する。講演を通して、ECUベンチマークの活用方法と、重要性について理解を深めて頂ければ幸いである。
講演者プロフィール
1992年 NTTエレクトロニクステクノロジー株式会社入社
LSI事業部本部に所属し、半導体の故障解析・画像圧縮エンコーダLSI開発業務に従事
2004年 株式会社ヴァン・パートナーズ入社
半導体・電子基板の解析サービスに従事
2009年 株式会社豊通エレクトロニクスに入社
ECUベンチマーク、半導体・電子デバイス類の解析サービスに従事
2022年10月マークラインズ株式会社入社
コンサルティング事業部に所属し、ECUベンチマークサービスに従事
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

AI外観検査、失敗の先に見える「本当の成功」とは?

|
株式会社 Pros Cons 神谷 亮磨 |
|
【講演内容】
「デモでは成功するのに現場では使えない…」AI外観検査のよくある失敗の原因を、撮像・AI・装置の「3要素の統合」から解き明かします。
単なる欠陥検出に留まらず、工程改善や工場全体のDXまでを見据えた、真の成功に導くアプローチと事例をご紹介します。
【講演内容】
「デモでは成功するのに現場では使えない…」AI外観検査のよくある失敗の原因を、撮像・AI・装置の「3要素の統合」から解き明かします。
単なる欠陥検出に留まらず、工程改善や工場全体のDXまでを見据えた、真の成功に導くアプローチと事例をご紹介します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

SMT検査工程の省人化を実現する最新AI活用ソリューション

|
ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部技術統括部SMT第1開発部 部長 河合 秀幸 |

|

【講演内容】
SMT生産フロアにおける品質担保の砦としてAOIは欠かせませんが、最終的な基板良否判断は目視支援ソフトウェア等を活用した、人による目視検査によって行われるのが一般的です。
一方で、判定の難易度や個人差、不注意が品質のばらつきや見逃しリスクにつながっています。 さらに、検査員育成のコストやAOIチューニング不足による過検出で工数が増え、生産効率を低下させるといった課題にもなっています。
本セッションでは、こうした背景から開発を進めている「AI Judgement Station」をご紹介します。
お客様ごとに最適なAIモデルを簡単に生成できるツールと高精度なAI自動検査システムにより、効率的かつ高信頼性の検査を実現します。
【講演内容】
SMT生産フロアにおける品質担保の砦としてAOIは欠かせませんが、最終的な基板良否判断は目視支援ソフトウェア等を活用した、人による目視検査によって行われるのが一般的です。
一方で、判定の難易度や個人差、不注意が品質のばらつきや見逃しリスクにつながっています。 さらに、検査員育成のコストやAOIチューニング不足による過検出で工数が増え、生産効率を低下させるといった課題にもなっています。
本セッションでは、こうした背景から開発を進めている「AI Judgement Station」をご紹介します。
お客様ごとに最適なAIモデルを簡単に生成できるツールと高精度なAI自動検査システムにより、効率的かつ高信頼性の検査を実現します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

高速X線CT技術と、生成AI活用とで目指す高スループット量産工場

|
オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 検査システム事業本部 X線検査システム事業部 事業部長 村上 清 |

|

【講演内容】
省人化/ノウハウレス化の実現と、高度化/複雑化するデジタル化製品の高品質・高生産性との両立。 「X線CT自動検査」の最新技術およびSATASでの半導体後工程自動化取り組みを紹介。生成AIの活用によるモノづくり現場の革新を自動運転コントロール基板や、チップレット実装の事例で描く。
【講演内容】
省人化/ノウハウレス化の実現と、高度化/複雑化するデジタル化製品の高品質・高生産性との両立。 「X線CT自動検査」の最新技術およびSATASでの半導体後工程自動化取り組みを紹介。生成AIの活用によるモノづくり現場の革新を自動運転コントロール基板や、チップレット実装の事例で描く。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

AIスマートグラスソリューションで変わる現場DX

|
株式会社 ムクイル 代表取締役社長 入江 龍雅 |
|
【講演内容】
株式会社ムクイルは、IoTと画像認識AIに強みを持つスタートアップ企業として、製造・物流・建築をはじめとした多様な現場におけるDX推進をご支援しています。その中心的な取り組みが、現場での作業効率と品質を大きく変革するAIスマートグラスソリューションです。
本ソリューションは、骨格追跡や物体検知を用いた作業モニタリング機能を備え、リアルタイムで作業状況を把握し、ヒューマンエラーを未然に防止します。ARによる手順ガイド表示は、新人や非熟練者でも確実に作業を進められるよう支援し、教育効率を大幅に向上させます。また、IoT機器との連携により、点検履歴や設備データを自動的に記録し、品質の一貫性や安全管理の徹底を実現します。さらに、生成AIを活用したマニュアル検索や要点要約機能を組み込むことで、現場スタッフは必要な情報に瞬時にアクセスでき、記録業務も効率化されます。これにより、「情報を探す」「作業を実行する」「記録を残す」という一連の流れを、現場でハンズフリーに完結することが可能になります。
導入事例としては、製造現場における検査工程の効率化、段取り替えにおける手順ガイドの提示、物流業務での誤ピック防止、小売現場での在庫確認と補充依頼の自動化、建設現場での安全確認や進捗記録などが挙げられます。これらはすべて、知識の検索と記録を一体化する仕組みによって現場のナレッジが自然に蓄積され、標準化と品質向上に直結します。
本セミナーでは、このAIスマートグラスソリューションの主要機能紹介に加え、実際の導入事例のご紹介や、会場でのデモンストレーションを予定しています。参加者の皆様には、実際にどのように現場業務が変革されるのかを体感していただける内容となっております。
ムクイルは、AIとIoT、そして生成AIを含む多様な先端技術を組み合わせたソリューションを通じて、現場の品質向上・コスト削減・人材育成の加速に貢献し、企業の持続的な成長と競争力強化を後押ししてまいります。
【講演内容】
株式会社ムクイルは、IoTと画像認識AIに強みを持つスタートアップ企業として、製造・物流・建築をはじめとした多様な現場におけるDX推進をご支援しています。その中心的な取り組みが、現場での作業効率と品質を大きく変革するAIスマートグラスソリューションです。
本ソリューションは、骨格追跡や物体検知を用いた作業モニタリング機能を備え、リアルタイムで作業状況を把握し、ヒューマンエラーを未然に防止します。ARによる手順ガイド表示は、新人や非熟練者でも確実に作業を進められるよう支援し、教育効率を大幅に向上させます。また、IoT機器との連携により、点検履歴や設備データを自動的に記録し、品質の一貫性や安全管理の徹底を実現します。さらに、生成AIを活用したマニュアル検索や要点要約機能を組み込むことで、現場スタッフは必要な情報に瞬時にアクセスでき、記録業務も効率化されます。これにより、「情報を探す」「作業を実行する」「記録を残す」という一連の流れを、現場でハンズフリーに完結することが可能になります。
導入事例としては、製造現場における検査工程の効率化、段取り替えにおける手順ガイドの提示、物流業務での誤ピック防止、小売現場での在庫確認と補充依頼の自動化、建設現場での安全確認や進捗記録などが挙げられます。これらはすべて、知識の検索と記録を一体化する仕組みによって現場のナレッジが自然に蓄積され、標準化と品質向上に直結します。
本セミナーでは、このAIスマートグラスソリューションの主要機能紹介に加え、実際の導入事例のご紹介や、会場でのデモンストレーションを予定しています。参加者の皆様には、実際にどのように現場業務が変革されるのかを体感していただける内容となっております。
ムクイルは、AIとIoT、そして生成AIを含む多様な先端技術を組み合わせたソリューションを通じて、現場の品質向上・コスト削減・人材育成の加速に貢献し、企業の持続的な成長と競争力強化を後押ししてまいります。

|
株式会社 ムクイル 営業部 執行役員 最高営業責任者 酒井 一舞 |
|
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

そのAI画像認識、現場にあってますか? ― 選定迷子からの脱出法

|
PROTRUDE (株式会社BREXA Technology) 伊藤 幸弘 |

|

【講演内容】
AI画像認識の導入が進む一方で、「どの技術を選べばいいのか分からない」「導入したけど思ったほど効果が出ない」といった声が多く聞かれます。本セミナーでは、異なる特性を持つ3つの画像認識技術を紹介しながら、現場課題に応じた“選び方”と“組み合わせ方”の考え方を解説します。
単なる技術紹介ではなく、「なぜ選定に迷うのか?」「どうすれば現場にフィットする技術を選べるのか?」という本質的な問いに向き合い、選定迷子から脱出するためのヒントをお届けします。
【講演内容】
AI画像認識の導入が進む一方で、「どの技術を選べばいいのか分からない」「導入したけど思ったほど効果が出ない」といった声が多く聞かれます。本セミナーでは、異なる特性を持つ3つの画像認識技術を紹介しながら、現場課題に応じた“選び方”と“組み合わせ方”の考え方を解説します。
単なる技術紹介ではなく、「なぜ選定に迷うのか?」「どうすれば現場にフィットする技術を選べるのか?」という本質的な問いに向き合い、選定迷子から脱出するためのヒントをお届けします。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

AIを活用した目視検査のバラつき解決方法のご紹介

|
株式会社 Anamorphosis Networks 小澤 行央 |
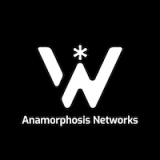
|
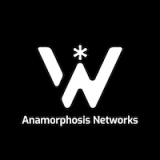
【講演内容】
本セミナーはこちらの4つの項目について順番にご説明させていただきます。
目視検査のばらつきに対する課題解決方法では、そもそも目視検査における課題とはどういったものが挙げられるのか。そして、それらの課題のうちどういったものがAIで解決可能かのかについて説明させていただきます。
次にAIによる自動検査についての基礎知識では、AIを用いて目視検査を自動化する上で重要なポイントを2点と、検査と一言で言っても多岐にわたる検査手法、検査対象がある中でAIが向いている検査とはどういう検査なのかについてご説明させていただきます。
そして目視検査自動化の流れと導入イメージでは実際に導入するまでの流れと検討して行くべきポイント、それらを踏まえた4つの導入パターンについてご説明させていただきます。
そして最後には4つの導入パターンそれぞれの実際に導入させていただいた事例をご紹介させていただきます。
【講演内容】
本セミナーはこちらの4つの項目について順番にご説明させていただきます。
目視検査のばらつきに対する課題解決方法では、そもそも目視検査における課題とはどういったものが挙げられるのか。そして、それらの課題のうちどういったものがAIで解決可能かのかについて説明させていただきます。
次にAIによる自動検査についての基礎知識では、AIを用いて目視検査を自動化する上で重要なポイントを2点と、検査と一言で言っても多岐にわたる検査手法、検査対象がある中でAIが向いている検査とはどういう検査なのかについてご説明させていただきます。
そして目視検査自動化の流れと導入イメージでは実際に導入するまでの流れと検討して行くべきポイント、それらを踏まえた4つの導入パターンについてご説明させていただきます。
そして最後には4つの導入パターンそれぞれの実際に導入させていただいた事例をご紹介させていただきます。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

AI外観検査ソリューション「HACARUS Check シリーズ」のご紹介

|
株式会社 HACARUS 事業開発本部 事業推進部 部長 池田 勤 |

|

【講演内容】
製造業の現場において、外観検査は製品の品質を担保する上で不可欠なプロセスです。しかしながら、目視検査においては、検査員の経験や体調に左右される不安定さ、熟練人材の不足といった課題が存在してきました。そうした背景のなか、AI技術を活用して検査工程を効率化・標準化するソリューションが求められています。
HACARUSが提供するAI外観検査ソリューション「HACARUS Check シリーズ」は、まさにその課題に応えるために開発されました。
ソリューションの中核を担う、外観検査AIソフトウェア「HACARUS Check ZERO」の最大の特長は、少量の学習データで高い精度を実現できる点にあります。これまでのディープラーニングベースの検査システムでは大量の不良品を収集する必要があり、現場導入の大きな障壁となっていました。一方、本ソリューションは独自のAIを採用しており、少量の良品画像から短期間で立ち上げができるため、現場での実用性が高いのが特長です。さらに、良品・不良品をアノテーションして追加学習するデュアルチューニング機能により、現場導入後も連続的な精度向上が可能です。
加えて、撮像するためのハードウェアも充実しています。複雑な形状のワークに対して、ロボットや多様な機構と組み合わせたラインナップを提案可能です。
本セミナーでは、HACARUS Checkシリーズの概要を解説するとともに、実際の適用事例をご紹介します。その上で、AI外観検査の導入を検討されている参加者の皆様に、具体的なメリットや導入プロセスのイメージを持っていただけるような内容をお届けします。
【講演内容】
製造業の現場において、外観検査は製品の品質を担保する上で不可欠なプロセスです。しかしながら、目視検査においては、検査員の経験や体調に左右される不安定さ、熟練人材の不足といった課題が存在してきました。そうした背景のなか、AI技術を活用して検査工程を効率化・標準化するソリューションが求められています。
HACARUSが提供するAI外観検査ソリューション「HACARUS Check シリーズ」は、まさにその課題に応えるために開発されました。
ソリューションの中核を担う、外観検査AIソフトウェア「HACARUS Check ZERO」の最大の特長は、少量の学習データで高い精度を実現できる点にあります。これまでのディープラーニングベースの検査システムでは大量の不良品を収集する必要があり、現場導入の大きな障壁となっていました。一方、本ソリューションは独自のAIを採用しており、少量の良品画像から短期間で立ち上げができるため、現場での実用性が高いのが特長です。さらに、良品・不良品をアノテーションして追加学習するデュアルチューニング機能により、現場導入後も連続的な精度向上が可能です。
加えて、撮像するためのハードウェアも充実しています。複雑な形状のワークに対して、ロボットや多様な機構と組み合わせたラインナップを提案可能です。
本セミナーでは、HACARUS Checkシリーズの概要を解説するとともに、実際の適用事例をご紹介します。その上で、AI外観検査の導入を検討されている参加者の皆様に、具体的なメリットや導入プロセスのイメージを持っていただけるような内容をお届けします。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。


|
株式会社 キーエンス 画像システム事業部 アシスタントマネージャー 小南 直輝 |

|

【講演内容】
近年、様々な業界でAIを活用した画像検査の導入が急速に進んでいます。
しかし、実際の現場では多くの課題があり、AI画像検査の効果的な運用が難しく、生産効率の改善につながらないケースも少なくありません。
直販営業を行うキーエンスでは、以下のようなお困りごとをお伺いしています。
- 精度向上のために継続的な学習が必要で、設定の調整に終わりが見えない
- 不良品のサンプル収集が難しく、学習データが不足して設備の立ち上げが遅れる
- 設定や学習に専門的なノウハウが求められ、現場での調整が困難
キーエンスの画像処理システム・画像センサを活用することで、これらの課題を解決し、実際の生産ラインでAIを用いた画像検査をスムーズに運用できるご提案をいたします。
【講演内容】
近年、様々な業界でAIを活用した画像検査の導入が急速に進んでいます。
しかし、実際の現場では多くの課題があり、AI画像検査の効果的な運用が難しく、生産効率の改善につながらないケースも少なくありません。
直販営業を行うキーエンスでは、以下のようなお困りごとをお伺いしています。
- 精度向上のために継続的な学習が必要で、設定の調整に終わりが見えない
- 不良品のサンプル収集が難しく、学習データが不足して設備の立ち上げが遅れる
- 設定や学習に専門的なノウハウが求められ、現場での調整が困難
キーエンスの画像処理システム・画像センサを活用することで、これらの課題を解決し、実際の生産ラインでAIを用いた画像検査をスムーズに運用できるご提案をいたします。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

検査AIで目視検査の課題を解決するコツ

|
株式会社 MENOU コミュニケーションデザインチーム リーダー 斉木 麻美 |
|
【講演内容】
「検査」は製品の品質を保証し、企業のブランド価値を高める重要な工程です。
しかし、高い専門性やコストの問題により、検査工程の自動化は後回しにせざるを得ない状況となっています。
このセミナーでは、あらゆる現場の多種多様な検査に対応し、自社で開発できる AI 検査システムをご紹介します。また、実際に導入した中小企業の事例紹介を通じ、その効果や導入の際の留意点等をご説明します。
【講演内容】
「検査」は製品の品質を保証し、企業のブランド価値を高める重要な工程です。
しかし、高い専門性やコストの問題により、検査工程の自動化は後回しにせざるを得ない状況となっています。
このセミナーでは、あらゆる現場の多種多様な検査に対応し、自社で開発できる AI 検査システムをご紹介します。また、実際に導入した中小企業の事例紹介を通じ、その効果や導入の際の留意点等をご説明します。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

不良流出を防ぐ!良品10個から始める目視補助AI

|
株式会社 アダコテック 事業開発部 事業開発マネージャー 松本 一樹 |

|

【講演内容】
製造現場では、わずかな見逃しが大きな不良流出につながるリスクが常に潜在しています。しかし実際には、その多くが「目視」のみでのチェックに依存しているのが現状です。
本講演では、目視によるミスをAIで補助し、見逃しを防止する目視補助AI「POKAMIRU(ポカミル)」のコンセプトと、基板部品や電子部品分野での活用事例をご紹介します。
近年、熟練検査員の高齢化や採用難によって人材不足が深刻化し、技能の継承も困難になっています。一方で、製品検査は品質を守る最後の砦であり、わずかな見逃しが不良流出やリコールといった大きな損失に直結する可能性を常に抱えています。特に目視検査は高い集中力が求められ、プレッシャーの大きい作業であるため、長時間の継続作業では安定した品質を維持することが難しいのが現実です。
目視補助AI「POKAMIRU」は、こうした課題を解決するために開発された製品です。独自技術の採用により、わずか良品10個程度の学習で運用を開始でき、特別な知識やノウハウがなくても簡単に設定が可能です。また、安価なPCスペックでも動作するため、導入コストを大幅に抑えることができます。
POKAMIRUは、アッセンブリ後の部品取付状態の確認、ラベルの有無や向きのチェック、加工有無の判定、さらに少量多品種で自動検査機の導入が難しい工程など、様々なシーンでご活用いただけます。
【講演内容】
製造現場では、わずかな見逃しが大きな不良流出につながるリスクが常に潜在しています。しかし実際には、その多くが「目視」のみでのチェックに依存しているのが現状です。
本講演では、目視によるミスをAIで補助し、見逃しを防止する目視補助AI「POKAMIRU(ポカミル)」のコンセプトと、基板部品や電子部品分野での活用事例をご紹介します。
近年、熟練検査員の高齢化や採用難によって人材不足が深刻化し、技能の継承も困難になっています。一方で、製品検査は品質を守る最後の砦であり、わずかな見逃しが不良流出やリコールといった大きな損失に直結する可能性を常に抱えています。特に目視検査は高い集中力が求められ、プレッシャーの大きい作業であるため、長時間の継続作業では安定した品質を維持することが難しいのが現実です。
目視補助AI「POKAMIRU」は、こうした課題を解決するために開発された製品です。独自技術の採用により、わずか良品10個程度の学習で運用を開始でき、特別な知識やノウハウがなくても簡単に設定が可能です。また、安価なPCスペックでも動作するため、導入コストを大幅に抑えることができます。
POKAMIRUは、アッセンブリ後の部品取付状態の確認、ラベルの有無や向きのチェック、加工有無の判定、さらに少量多品種で自動検査機の導入が難しい工程など、様々なシーンでご活用いただけます。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。

独自の画像認識AIモデルをすばやく構築できるPlatformのご紹介

|
Superb AI Japan合同会社 Sales Director Japan 藤井 威 |

|

【講演内容】
コンピュータビジョンの活用をご検討でしょうか?画像認識AIの機械学習は難しいとお考えでしょうか?私たちはあらゆるお客様が業務にAIを素早く取り込み、活用できるよう、最小限の工数と自動化機能でコンピュータビジョン用のAIの機械学習用のデータセットの用意からデータセットの分析、モデルのトレーニング、モデルの運用展開まで単一のSaaS型プラットフォームで可能です。コンピュータビジョンAIの活用は決して高いハードルではありません。
Superb AIはコンピュータビジョンにフォーカスしており、お客様独自の画像認識AI,物体認識AIなどのモデルを最小の工数と手間で作り上げることができるようなプラットフォームをご提供しております。教師データの作成からデータセットの分析、モデルのトレーニング、モデルの活用といった一連のタスクがSaaS型のプラットフォームに統一された機能を提供しており、弊社のプラットフォームを活用されて、様々な業種で独自のコンピュータビジョンのAIをトレーニングし、ご活用いただいております。例としては自動運転、不具合検知、モーション解析、など様々な分野で実績があります。対応できるデータの種類としては、画像、動画、Point Cloudデータ(LiDARなど)でデータアノテーションが可能で、自動ラベリング機能も提供しております。また、モデルのトレーニングも同一プラットフォーム上で可能で、精度向上のための追加トレーニングなども非常に効率的に実施できます。
【講演内容】
コンピュータビジョンの活用をご検討でしょうか?画像認識AIの機械学習は難しいとお考えでしょうか?私たちはあらゆるお客様が業務にAIを素早く取り込み、活用できるよう、最小限の工数と自動化機能でコンピュータビジョン用のAIの機械学習用のデータセットの用意からデータセットの分析、モデルのトレーニング、モデルの運用展開まで単一のSaaS型プラットフォームで可能です。コンピュータビジョンAIの活用は決して高いハードルではありません。
Superb AIはコンピュータビジョンにフォーカスしており、お客様独自の画像認識AI,物体認識AIなどのモデルを最小の工数と手間で作り上げることができるようなプラットフォームをご提供しております。教師データの作成からデータセットの分析、モデルのトレーニング、モデルの活用といった一連のタスクがSaaS型のプラットフォームに統一された機能を提供しており、弊社のプラットフォームを活用されて、様々な業種で独自のコンピュータビジョンのAIをトレーニングし、ご活用いただいております。例としては自動運転、不具合検知、モーション解析、など様々な分野で実績があります。対応できるデータの種類としては、画像、動画、Point Cloudデータ(LiDARなど)でデータアノテーションが可能で、自動ラベリング機能も提供しております。また、モデルのトレーニングも同一プラットフォーム上で可能で、精度向上のための追加トレーニングなども非常に効率的に実施できます。
本セッションは事前申し込み不要です。
聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。
※展示会の来場登録は必要です。
受講券の発行方法をお選びください。