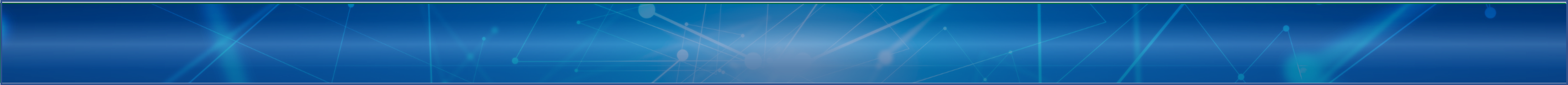


|
内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 審議官 川上 大輔 |
|
【講演内容】
高機能素材を代表とする幅広い分野のイノベーションを先導するマテリアル産業は、我が国の製造業 GDP のうち3割以上を占める基幹産業と位置づけられる。一方、国際情勢の不安定化等を背景とした経済安全保障の確保の必要性が高まり、ネット・ゼロやサーキュラーエコノミーの実現に向けた国際的な環境規制等の動きも強まっている。我が国がマテリアル産業で「勝ち続け」、複合化する様々な社会課題に対応し、戦略的自律性・不可欠性を確保しつつ、国際社会と協調して目指すべき社会の実現を先導するためには、産学官が「マテリアル革新力」の一層の強化に向けて総力を結集し、「知」を受け渡して継続的なイノベーションを創出する 「知のバリューチェーン」 を構築する必要がある。
本講演ではマテリアルを巡る政府の取組について紹介する。まず我が国の科学技術政策の全体像、特にSoceity5.0に向けた大局的な指針について解説し、その枠組みの中でのマテリアルの位置づけやこれまでの取組について振り返る。続いて本年6月に改定されたマテリアル革新力強化戦略の内容及びそれに導かれる我が国のマテリアル革新力の将来像について展望する。
【講演者プロフィール】
平成5年3月、京都大学大学院修士課程を修了。同年4月東レ株式会社に入社し、繊維・複合材料・トレカ技術などの研究開発に従事、米国現地法人副社長、ライフイノベーション事業戦略推進室長などを歴任。平成20年7月には東京工業大学にて博士(工学)を取得。令和5年6月より内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の審議官を務め、現在に至る。
【講演内容】
高機能素材を代表とする幅広い分野のイノベーションを先導するマテリアル産業は、我が国の製造業 GDP のうち3割以上を占める基幹産業と位置づけられる。一方、国際情勢の不安定化等を背景とした経済安全保障の確保の必要性が高まり、ネット・ゼロやサーキュラーエコノミーの実現に向けた国際的な環境規制等の動きも強まっている。我が国がマテリアル産業で「勝ち続け」、複合化する様々な社会課題に対応し、戦略的自律性・不可欠性を確保しつつ、国際社会と協調して目指すべき社会の実現を先導するためには、産学官が「マテリアル革新力」の一層の強化に向けて総力を結集し、「知」を受け渡して継続的なイノベーションを創出する 「知のバリューチェーン」 を構築する必要がある。
本講演ではマテリアルを巡る政府の取組について紹介する。まず我が国の科学技術政策の全体像、特にSoceity5.0に向けた大局的な指針について解説し、その枠組みの中でのマテリアルの位置づけやこれまでの取組について振り返る。続いて本年6月に改定されたマテリアル革新力強化戦略の内容及びそれに導かれる我が国のマテリアル革新力の将来像について展望する。
【講演者プロフィール】
平成5年3月、京都大学大学院修士課程を修了。同年4月東レ株式会社に入社し、繊維・複合材料・トレカ技術などの研究開発に従事、米国現地法人副社長、ライフイノベーション事業戦略推進室長などを歴任。平成20年7月には東京工業大学にて博士(工学)を取得。令和5年6月より内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の審議官を務め、現在に至る。
<モデレーター>

|
(株)たすきづな 代表取締役 柳原 直人 |

|

<パネリスト>

|
住友化学(株) 取締役 専務執行役員 【技術・研究企画、DX推進、知的財産、工業化技術研究所、生物環境科学研究所、先端材料開発研究所、バイオサイエンス研究所 統括】 山口 登造 |

|


|
富士フイルム(株) エレクトロニクスマテリアルズ事業部 シニアフェロー 野口 仁 |

|


|
JSR(株) RDテクノロジー・デジタル変革センター長/JSR Bioscience and informatics R&D center長/研究開発部長 菅原 周一 |
|
【講演者プロフィール】
●柳原 直人 氏
1986年4月、京都大学化学系を修了、富士フイルム(株)に入社。以後、2015年まで材料系研究者を経て研究所長、技術戦略部長を歴任。2015年以降、取締役・常務執行役員としてR&D統括本部長、先端技術やバイオの研究所長、知的財産本部管掌を歴任。2024年9月、富士フイルムを退職、現在に至る。
●山口 登造 氏
1991年3月に京都大学大学院工学研究科高分子化学博士課程を修了し、同年4月に住友化学株式会社へ入社。 新規素材開発とマーケティングを担当した後、技術・経営企画室を経て、新規製品工場の立ち上げ、製造部長を歴任。さらにICT系部門において、企画室部長・事業部長など多様な役割を経験。 2018年 執行役員、2021年 常務執行役員、2025年 取締役 専務執行役員に就任し、現在に至る。
●野口 仁 氏
1987年3月、京都大学院工学研究科修士課程を卒業し、同年4月、富士写真フイルム(現 富士フイルム)株式会社に入社。磁気材料研究所(当時)に所属し、VHSテープ、大容量磁気ディスク、データストレージ用磁気テープの開発に従事し、2012年4月、同研究所所長に就任。その後、2018年10月、エレクトロニクスマテリアルズ研究所長、2021年6月、富士フイルム株式会社 執行役員 エレクトロ二クスマテリアルズ研究所長に就任し、現在に至る。
●菅原 周一 氏
2001年3月東北大学大学院工学研究科修了(博士後期課程)。同年4月からJSR株式会社に入社。筑波研究所で光学材料の開発に従事。2017年から研究開発部長、2019年から研究企画部長として慶應義塾大学や東京大学などのアカデミアとの包括連携とイノベーションセンターの設置を担当。2023年からRDテクノロジー・デジタル変革センター長、2025年からJSR Biosience and informatics R&Dセンター長および研究開発部長も兼務し、現在に至る。
【講演者プロフィール】
●柳原 直人 氏
1986年4月、京都大学化学系を修了、富士フイルム(株)に入社。以後、2015年まで材料系研究者を経て研究所長、技術戦略部長を歴任。2015年以降、取締役・常務執行役員としてR&D統括本部長、先端技術やバイオの研究所長、知的財産本部管掌を歴任。2024年9月、富士フイルムを退職、現在に至る。
●山口 登造 氏
1991年3月に京都大学大学院工学研究科高分子化学博士課程を修了し、同年4月に住友化学株式会社へ入社。 新規素材開発とマーケティングを担当した後、技術・経営企画室を経て、新規製品工場の立ち上げ、製造部長を歴任。さらにICT系部門において、企画室部長・事業部長など多様な役割を経験。 2018年 執行役員、2021年 常務執行役員、2025年 取締役 専務執行役員に就任し、現在に至る。
●野口 仁 氏
1987年3月、京都大学院工学研究科修士課程を卒業し、同年4月、富士写真フイルム(現 富士フイルム)株式会社に入社。磁気材料研究所(当時)に所属し、VHSテープ、大容量磁気ディスク、データストレージ用磁気テープの開発に従事し、2012年4月、同研究所所長に就任。その後、2018年10月、エレクトロニクスマテリアルズ研究所長、2021年6月、富士フイルム株式会社 執行役員 エレクトロ二クスマテリアルズ研究所長に就任し、現在に至る。
●菅原 周一 氏
2001年3月東北大学大学院工学研究科修了(博士後期課程)。同年4月からJSR株式会社に入社。筑波研究所で光学材料の開発に従事。2017年から研究開発部長、2019年から研究企画部長として慶應義塾大学や東京大学などのアカデミアとの包括連携とイノベーションセンターの設置を担当。2023年からRDテクノロジー・デジタル変革センター長、2025年からJSR Biosience and informatics R&Dセンター長および研究開発部長も兼務し、現在に至る。

|
(株)レゾナック CTO(半導体材料)執行役員 エレクトロニクス事業本部 副本部長 阿部 秀則 |

|

【講演内容】
共創型化学企業を目指すレゾナックは、材料・基板・装置メーカーと共同で評価プラットフォーム「JOINT2」「JOINT3」を設置し、次世代2.5D/2.xDパッケージの技術開発を推進している。本講演では、共創がもたらす価値、材料イノベーション、そしてレゾナックの新しい「共創」戦略などを紹介する。
【講演者プロフィール】
東京工業大学 化学工学科 修士課程修了後、1998年に日立化成工業入社。封止材料開発部にて15年開発に従事。その間、Hitachi Chemical Co. America(現Resonac America)に駐在、OxfordにてEMBA取得。マーケティングを担当後、研磨材料ビジネスユニット長、パッケージングソリューションセンター長、開発センター長に就任、JOINT2・US-JOINT・JOINT3の立ち上げに従事。2024年、業務執行役およびエレクトロニクス事業本部副本部長を歴任し、2025年1月より現職に就任。
【講演内容】
共創型化学企業を目指すレゾナックは、材料・基板・装置メーカーと共同で評価プラットフォーム「JOINT2」「JOINT3」を設置し、次世代2.5D/2.xDパッケージの技術開発を推進している。本講演では、共創がもたらす価値、材料イノベーション、そしてレゾナックの新しい「共創」戦略などを紹介する。
【講演者プロフィール】
東京工業大学 化学工学科 修士課程修了後、1998年に日立化成工業入社。封止材料開発部にて15年開発に従事。その間、Hitachi Chemical Co. America(現Resonac America)に駐在、OxfordにてEMBA取得。マーケティングを担当後、研磨材料ビジネスユニット長、パッケージングソリューションセンター長、開発センター長に就任、JOINT2・US-JOINT・JOINT3の立ち上げに従事。2024年、業務執行役およびエレクトロニクス事業本部副本部長を歴任し、2025年1月より現職に就任。

|
(株)東レリサーチセンター 構造化学研究部 部長 関 洋文 |

|

【講演内容】
次世代通信技術の進展に伴い、Siフォトニクスや高密度パッケージなどの半導体技術が注目を集めています。本講演では、これらの技術課題に対応する弊社の半導体向け先端分析技術についてご紹介します。
【講演者プロフィール】
2000年3月、東北大学大学院工学研究科修士課程卒業。株式会社東レリサーチセンター入社。
主に半導体材料の分光分析に従事。2020年4月より現職。
【講演内容】
次世代通信技術の進展に伴い、Siフォトニクスや高密度パッケージなどの半導体技術が注目を集めています。本講演では、これらの技術課題に対応する弊社の半導体向け先端分析技術についてご紹介します。
【講演者プロフィール】
2000年3月、東北大学大学院工学研究科修士課程卒業。株式会社東レリサーチセンター入社。
主に半導体材料の分光分析に従事。2020年4月より現職。

|
(国研)産業技術総合研究所 化学プロセス研究部門 機能材料プロセス研究グループ 研究グループ長 阿多 誠介 |

|

【講演内容】
Beyond5G/6Gでは従来を超える性能が求められ、高分子材料の重要性が一層増している。本講演では低損失材料を中心に、分野の展開と解決すべき課題を概説する。
【講演者プロフィール】
2010年3月東京工業大学大学院修了、2010年4月、国立研究開発法人産業技術総合研究所入所。CNTの複合材料開発に10年ほど従事。2019年〜2020年、Fraunhofer IPA研究所滞在研究員。2021年より低誘電基板材料研究に従事し現在に至る。
【講演内容】
Beyond5G/6Gでは従来を超える性能が求められ、高分子材料の重要性が一層増している。本講演では低損失材料を中心に、分野の展開と解決すべき課題を概説する。
【講演者プロフィール】
2010年3月東京工業大学大学院修了、2010年4月、国立研究開発法人産業技術総合研究所入所。CNTの複合材料開発に10年ほど従事。2019年〜2020年、Fraunhofer IPA研究所滞在研究員。2021年より低誘電基板材料研究に従事し現在に至る。

|
日東電工(株) 情報機能材料事業部門 R&D統括本部 第2開発部 第3グループ グループ長 大峰 俊樹 |

|

【講演内容】
近年、LCD/OLEDディスプレイは拡大を続けており、偏光板は広く活用されている。市場の中で車載向け偏光板では、高耐久・高視野角・大型化等のニーズが強く、独自の偏光板設計が必要である。
本講演では、偏光板の基礎知識と、車載向け偏光板の特性とトレンドを報告させて頂く。
【講演者プロフィール】
2008年3月 東京理科大学大学院卒業、同年4月 日東電工株式会社に入社、開発部に所属となり、位相差フィルムや接着剤といった光学部材の開発に従事。2011年 大型テレビ向け偏光板を開発、製品化と合わせて製造技術部へ異動し、生産性や品質向上といったモノ作りを経験。その後は開発部に戻り、ノートパソコン・モニター・モバイル製品等、様々な用途向けの偏光板開発に従事、2016年 技術営業としての顧客対応や、2021~24年の3年間は海外赴任先での開発グループ長としてマネジメントを経験。
帰任後の2024年より車載ディスプレイ用偏光板開発チームのグループ長を担当し、現在に至る。
【講演内容】
近年、LCD/OLEDディスプレイは拡大を続けており、偏光板は広く活用されている。市場の中で車載向け偏光板では、高耐久・高視野角・大型化等のニーズが強く、独自の偏光板設計が必要である。
本講演では、偏光板の基礎知識と、車載向け偏光板の特性とトレンドを報告させて頂く。
【講演者プロフィール】
2008年3月 東京理科大学大学院卒業、同年4月 日東電工株式会社に入社、開発部に所属となり、位相差フィルムや接着剤といった光学部材の開発に従事。2011年 大型テレビ向け偏光板を開発、製品化と合わせて製造技術部へ異動し、生産性や品質向上といったモノ作りを経験。その後は開発部に戻り、ノートパソコン・モニター・モバイル製品等、様々な用途向けの偏光板開発に従事、2016年 技術営業としての顧客対応や、2021~24年の3年間は海外赴任先での開発グループ長としてマネジメントを経験。
帰任後の2024年より車載ディスプレイ用偏光板開発チームのグループ長を担当し、現在に至る。
AI同時通訳システム付
|
|
三菱電機(株) 先端技術総合研究所 開発戦略部 技術顧問 光田 憲朗 |
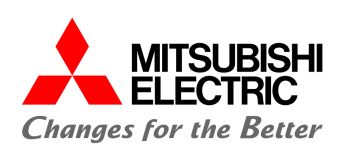
|
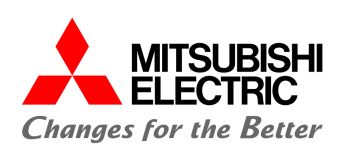
【講演内容】
リチウムイオン電池の日本人と、日本の企業の活躍の歴史を振り返り、セパレータの特許を紹介したいと思います。また、硫化物系、酸化物系、樹脂系の全固体電池の技術課題に対するユーザーの立場としての認識を示すとともに、バッテリーの将来像についての期待をお話しします。
【講演者プロフィール】
1981年 大阪大学基礎工学部修士卒、三菱電機(中央研究所)に入社、リン酸形燃料電池、固体高分子形燃料電池、メタノール改質器、電気二重層キャパシタ、リチウムイオンキャパシタ、リチウムイオン電池等の研究開発に従事し現在に至る。博士(工学) 電気化学会 フェロー、日本太陽エネルギー学会 元会長。
【講演内容】
リチウムイオン電池の日本人と、日本の企業の活躍の歴史を振り返り、セパレータの特許を紹介したいと思います。また、硫化物系、酸化物系、樹脂系の全固体電池の技術課題に対するユーザーの立場としての認識を示すとともに、バッテリーの将来像についての期待をお話しします。
【講演者プロフィール】
1981年 大阪大学基礎工学部修士卒、三菱電機(中央研究所)に入社、リン酸形燃料電池、固体高分子形燃料電池、メタノール改質器、電気二重層キャパシタ、リチウムイオンキャパシタ、リチウムイオン電池等の研究開発に従事し現在に至る。博士(工学) 電気化学会 フェロー、日本太陽エネルギー学会 元会長。
AI同時通訳システム付

|
AZCA, Inc. マネジングパートナー 石井 正純 |

|

【講演内容】
長期的開発や巨額投資が不可避な素材産業は、往々にしてリスク回避的になりがちである。本講演では、日本大企業の強みである技術力・信頼性と、特に北米スタートアップのスピードや挑戦的発想を組み合わせることで、共創によって拓かれる新たなイノベーションの可能性を探る。
【講演者プロフィール】
日本IBM、McKinsey & Companyを経て1985年にシリコンバレーでAZCA, Inc.を創業。以来、日本企業と北米スタートアップの共創を数多く支援してきている。1987〜2016年は日米でVC投資にも携わる。2016年まで米国 ホワイトハウスでの有識者会議に数度にわたり招聘され、貿易協定・振興から気候変動などのさまざまな分野で、米国政策立案に向けた、民間からの意見および提言を積極的に行う。静岡大学大学院、早稲田大学ビジネススクール、中部大学の客員教授、ならびに東洋大学の学術アドバイザーを務め、NEDOやJSTの委員も歴任。イノベーション、起業、国際事業開発に関する講演・著作多数。近著に『イノベーションは日本を救うのか』。東京大学工学部計数工学科卒、スタンフォード大学コンピュータサイエンス修士。
【講演内容】
長期的開発や巨額投資が不可避な素材産業は、往々にしてリスク回避的になりがちである。本講演では、日本大企業の強みである技術力・信頼性と、特に北米スタートアップのスピードや挑戦的発想を組み合わせることで、共創によって拓かれる新たなイノベーションの可能性を探る。
【講演者プロフィール】
日本IBM、McKinsey & Companyを経て1985年にシリコンバレーでAZCA, Inc.を創業。以来、日本企業と北米スタートアップの共創を数多く支援してきている。1987〜2016年は日米でVC投資にも携わる。2016年まで米国 ホワイトハウスでの有識者会議に数度にわたり招聘され、貿易協定・振興から気候変動などのさまざまな分野で、米国政策立案に向けた、民間からの意見および提言を積極的に行う。静岡大学大学院、早稲田大学ビジネススクール、中部大学の客員教授、ならびに東洋大学の学術アドバイザーを務め、NEDOやJSTの委員も歴任。イノベーション、起業、国際事業開発に関する講演・著作多数。近著に『イノベーションは日本を救うのか』。東京大学工学部計数工学科卒、スタンフォード大学コンピュータサイエンス修士。

|
日本ガイシ(株) 研究開発本部 基盤技術統括部 理事 研究開発本部 基盤技術統括部長 山田 直仁 |

|

【講演内容】
日本ガイシは独自のセラミック技術によりカーボンニュートラルとデジタル社会に貢献する製品の開発に取り組んでいる。本講演では、カーボンニュートラルの実現に向けたDAC、CO₂分離膜、ハニカム構造リアクターなどのセラミックス製品の開発事例を紹介する。
【講演者プロフィール】
1985年3月、京都大学理学部卒業、日本ガイシ株式会社に入社。基礎研究所に所属し、セラミックス部品の信頼性設計、新材料開発に従事。半導体製造装置用セラミックス製品の事業化に貢献。その後、蓄電池関連の商品開発を担当。2023年より研究開発本部 CN開発統括部長、2025年より同本部 基盤技術統括部長に就任、現在に至る。
【講演内容】
日本ガイシは独自のセラミック技術によりカーボンニュートラルとデジタル社会に貢献する製品の開発に取り組んでいる。本講演では、カーボンニュートラルの実現に向けたDAC、CO₂分離膜、ハニカム構造リアクターなどのセラミックス製品の開発事例を紹介する。
【講演者プロフィール】
1985年3月、京都大学理学部卒業、日本ガイシ株式会社に入社。基礎研究所に所属し、セラミックス部品の信頼性設計、新材料開発に従事。半導体製造装置用セラミックス製品の事業化に貢献。その後、蓄電池関連の商品開発を担当。2023年より研究開発本部 CN開発統括部長、2025年より同本部 基盤技術統括部長に就任、現在に至る。
<モデレーター>

|
(株)たすきづな 代表取締役 柳原 直人 |

|

<パネリスト>

|
昭和女子大学 情報科学研究所 所長/特命教授/旭化成(株) 基盤技術研究所 青柳 岳司 |

|


|
国立大学法人京都大学 大学院理学研究科化学専攻 教授 副プロボスト 理事補(企画・調整担当) 北川 宏 |

|


|
(株)Preferred Networks 共同創業者 代表取締役 最高技術責任者/Matlantis(株) 代表取締役社長 岡野原 大輔 |

|

【講演内容】
マテリアルズインフォマティクス(MI)の現状と課題を明らかにし、革新的材料開発の鍵を探るを提供します。アカデミア、スタートアップ、大手化学企業で開発に関わる第一人者の取り組みをご紹介頂いたあと、 MIの現状、革新的材料開発への展開可能性、期待されるシナジーについて対話します。
【講演者プロフィール】
●柳原 直人 氏
1986年4月、京都大学化学系を修了、富士フイルム(株)に入社。以後、2015年まで材料系研究者を経て研究所長、技術戦略部長を歴任。2015年以降、取締役・常務執行役員としてR&D統括本部長、先端技術やバイオの研究所長、知的財産本部管掌を歴任。2024年9月、富士フイルムを退職、現在に至る。
●青柳 岳司 氏
1987年3月、京都大学薬学研究科博士前期課程修了。同4月、旭化成工業(株)入社、主に材料シミュレーションに従事。2002年9月 名古屋大学にて博士(工学)取得。
2016年5月 (国研)産業技術総合研究所入所。NEDOプロなど、材料シミュレーションおよびインフォマティクス研究に従事。
2022年7月 旭化成(株)入社 デジタル共創本部にてR&D DX全般を推進。
2025年10月より現職
●北川 宏 氏
1986年、京都大学理学部卒業。1991年、同大学院理学研究科博士後期課程を単位取得退学、岡崎国立共同研究機構分子科学研究所助手。1992年、博士(理学)学位取得。1993年英国王立研究所訪問研究員、1994年、北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科助手。2000年、筑波大学化学系助教授。2003年、九州大学大学院理学研究院化学部門教授。2009年より、京都大学大学院理学研究科化学専攻教授。京都大学副プロボスト、理事補(企画・調整担当)を兼務。2021年から、科学技術振興機構CREST研究総括「未踏探索空間における革新的物質の開発」。趣味は飲み歩き。
●岡野原 大輔 氏
2010年に東京大学にて博士(情報理工学)取得。大学院在学中の2006年に、西川徹等とPreferred Networks(PFN)の前身となる株式会社Preferred Infrastructureを創業。2014年3月に深層学習の実用化を加速するためPFNを創業。現在はPFNの最高技術責任者として、基盤モデルの研究開発などに取り組んでいる。PFNとENEOSが共同開発した汎用原子レベルシミュレータの販売を行うMatlantis株式会社の代表取締役社長を兼任。受賞歴、著書多数。
【講演内容】
マテリアルズインフォマティクス(MI)の現状と課題を明らかにし、革新的材料開発の鍵を探るを提供します。アカデミア、スタートアップ、大手化学企業で開発に関わる第一人者の取り組みをご紹介頂いたあと、 MIの現状、革新的材料開発への展開可能性、期待されるシナジーについて対話します。
【講演者プロフィール】
●柳原 直人 氏
1986年4月、京都大学化学系を修了、富士フイルム(株)に入社。以後、2015年まで材料系研究者を経て研究所長、技術戦略部長を歴任。2015年以降、取締役・常務執行役員としてR&D統括本部長、先端技術やバイオの研究所長、知的財産本部管掌を歴任。2024年9月、富士フイルムを退職、現在に至る。
●青柳 岳司 氏
1987年3月、京都大学薬学研究科博士前期課程修了。同4月、旭化成工業(株)入社、主に材料シミュレーションに従事。2002年9月 名古屋大学にて博士(工学)取得。
2016年5月 (国研)産業技術総合研究所入所。NEDOプロなど、材料シミュレーションおよびインフォマティクス研究に従事。
2022年7月 旭化成(株)入社 デジタル共創本部にてR&D DX全般を推進。
2025年10月より現職
●北川 宏 氏
1986年、京都大学理学部卒業。1991年、同大学院理学研究科博士後期課程を単位取得退学、岡崎国立共同研究機構分子科学研究所助手。1992年、博士(理学)学位取得。1993年英国王立研究所訪問研究員、1994年、北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科助手。2000年、筑波大学化学系助教授。2003年、九州大学大学院理学研究院化学部門教授。2009年より、京都大学大学院理学研究科化学専攻教授。京都大学副プロボスト、理事補(企画・調整担当)を兼務。2021年から、科学技術振興機構CREST研究総括「未踏探索空間における革新的物質の開発」。趣味は飲み歩き。
●岡野原 大輔 氏
2010年に東京大学にて博士(情報理工学)取得。大学院在学中の2006年に、西川徹等とPreferred Networks(PFN)の前身となる株式会社Preferred Infrastructureを創業。2014年3月に深層学習の実用化を加速するためPFNを創業。現在はPFNの最高技術責任者として、基盤モデルの研究開発などに取り組んでいる。PFNとENEOSが共同開発した汎用原子レベルシミュレータの販売を行うMatlantis株式会社の代表取締役社長を兼任。受賞歴、著書多数。

|
(株)ナフィアス 創業者 代表取締役/国立大学法人信州大学 社会実装研究クラスター繊維科学研究所 特任准教授 渡邊 圭 |

|

【講演内容】
信州大学発ベンチャーである当社は、大学、研究機関、大企業から中小企業まで多岐にわたる連携を力に、ナノファイバー技術の事業化に挑み続けてきた。創立10周年を迎える今、素材系ベンチャーとして社会実装を拓いた革新事例の紹介と、その未来を展望する。
【講演者プロフィール】
2013年3月、信州大学大学院 総合工学系研究科 生命機能・ファイバー工学専攻 修了(Ph.D.)。2014年から信州大学繊維学部特任助教を兼任し2021年に同大特任准教授に就任。2015年8月、(株)ナフィアスを創業し、現職に就任。2009年(在学時)からナノファイバーの製造技術及び用途開発に従事し、ナノファイバーの量産設備、フィルター、マスク、美容シート、透湿防水膜等の製品開発を行い現在に至る。2022年5月、令和4年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(開発部門)を受賞。
【講演内容】
信州大学発ベンチャーである当社は、大学、研究機関、大企業から中小企業まで多岐にわたる連携を力に、ナノファイバー技術の事業化に挑み続けてきた。創立10周年を迎える今、素材系ベンチャーとして社会実装を拓いた革新事例の紹介と、その未来を展望する。
【講演者プロフィール】
2013年3月、信州大学大学院 総合工学系研究科 生命機能・ファイバー工学専攻 修了(Ph.D.)。2014年から信州大学繊維学部特任助教を兼任し2021年に同大特任准教授に就任。2015年8月、(株)ナフィアスを創業し、現職に就任。2009年(在学時)からナノファイバーの製造技術及び用途開発に従事し、ナノファイバーの量産設備、フィルター、マスク、美容シート、透湿防水膜等の製品開発を行い現在に至る。2022年5月、令和4年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(開発部門)を受賞。

|
大日本印刷(株) 情報イノベーション事業部 統合企画センター 統合企画本部 環境ビジネス推進部 部長/(一社)SusPla 幹事 西村 知子 |

|

【講演内容】
本講演では、製品を設計、製造、販売、利用している「動脈産業」と、廃棄物を回収し再生・再利用する「静脈産業」の連携や「見える化」の取組みの具体例、DNPがこれまで培ってきたノウハウやスキルを活かしたサーキュラーエコノミー実装支援の打ち手について紹介する。
【講演者プロフィール】
DNPで営業職として販売促進やマーケティングソリューションの販売に従事し、2019年より情報イノベーション事業部での環境ビジネス構築に携わる。
2022年に埼玉県と実施した「プラスチック資源循環の見える化」実証実験をきっかけに、企業や自治体と連携したサーキュラーエコノミーの取組み を推進。
2024年より再生プラスチックの市場拡大をめざし設立された一般社団法人SusPlaに参画、動静脈連携の活性化に向けた活動も開始し、現在に至る。
【講演内容】
本講演では、製品を設計、製造、販売、利用している「動脈産業」と、廃棄物を回収し再生・再利用する「静脈産業」の連携や「見える化」の取組みの具体例、DNPがこれまで培ってきたノウハウやスキルを活かしたサーキュラーエコノミー実装支援の打ち手について紹介する。
【講演者プロフィール】
DNPで営業職として販売促進やマーケティングソリューションの販売に従事し、2019年より情報イノベーション事業部での環境ビジネス構築に携わる。
2022年に埼玉県と実施した「プラスチック資源循環の見える化」実証実験をきっかけに、企業や自治体と連携したサーキュラーエコノミーの取組み を推進。
2024年より再生プラスチックの市場拡大をめざし設立された一般社団法人SusPlaに参画、動静脈連携の活性化に向けた活動も開始し、現在に至る。

|
住友化学株式会社 バイオサイエンス研究所 理事 バイオサイエンス研究所長 住田 佳代 |

|

【講演内容】
3つのX(GX/BX/DX)を通じて社会課題を解決すべく、本講演では、世界動向を踏まえた“ものの価値”のパラダイムシフトやターゲット設定の考え方を含めたバイオものづくりの事例、及び未利用資源等の利活用の取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
1991年3月京都大学大学院農学研究科修士課程修了、住友化学工業株式会社(現:住友化学株式会社)に入社。生物環境科学研究所に配属。2000-2005年住友製薬株式会社(現:住友ファーマ株式会社)研究本部ゲノム科学研究所と兼務し、オミックス技術・解析の安全性評価への活用を担当。2018年よりバイオサイエンス研究所配属。2021年所長、2022年理事。現在に至る。
【講演内容】
3つのX(GX/BX/DX)を通じて社会課題を解決すべく、本講演では、世界動向を踏まえた“ものの価値”のパラダイムシフトやターゲット設定の考え方を含めたバイオものづくりの事例、及び未利用資源等の利活用の取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
1991年3月京都大学大学院農学研究科修士課程修了、住友化学工業株式会社(現:住友化学株式会社)に入社。生物環境科学研究所に配属。2000-2005年住友製薬株式会社(現:住友ファーマ株式会社)研究本部ゲノム科学研究所と兼務し、オミックス技術・解析の安全性評価への活用を担当。2018年よりバイオサイエンス研究所配属。2021年所長、2022年理事。現在に至る。
<モデレーター>

|
ナノセルロースジャパン CNF塾長 渡邉 政嘉 |

|

<パネリスト>

|
国立大学法人東北大学 未来科学技術共同研究センター シニアリサーチフェロー 福原 幹夫 |

|


|
日本製紙(株) 研究開発本部 富士革新素材研究所 本部長代理 兼 富士革新素材研究所長 畠田 利彦 |
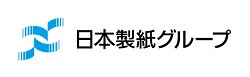
|
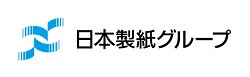

|
王子ホールディングス(株) イノベーション推進本部 CNF創造センター CNF創造センター長 小林 満 |

|


|
大阪大学 教授 能木 雅也 |

|

【講演内容】
CNF(セルロースナノファイバー)は革新的な脱炭素素材として注目され、構造材料、食品、化粧品分野などで社会実装が進んでいる。近年は蓄電や半導体効果も確認され、エレクトロニクス応用が期待される。最新研究では従来のシリコン半導体とは異なるメカニズムが明らかになり、日本初のCNFエレクトロニクス技術や企業事例、将来戦略を紹介し、脱炭素社会におけるエレクトロニクス分野のパラダイムシフトを考察する。
【講演者プロフィール】
●渡邉 政嘉 氏
京都大学特任教授・学外連携フェロー(一財 高度技術社会推進協会・常務理事)。経産省産総研室長、 紙業服飾品課長、産業技術政策課長、NEDO理事、中小企業庁経営支援部長、経産省東北経済産業局長、 内閣審議官を歴任し、令和4年7月退官。研究所経営(オープンイノベーションハブ戦略)に関する研究、 セルロースナノファイバーの産業利用に関する研究等、多数実施。紙業服飾品課長時代に世界に先駆け ナノセルロース社会実装に向けたナノセルロースフォーラムの設立をリード。受賞歴:型技術協会創立 30周年「功労者賞」、日本機械学会フェロー、同会創立120周年記念功労者表彰など。博士(工学)
●福原 幹夫 氏
1979年8月大阪大学大学院工学研究科博士課程修了(工学博士)、1980年4月東芝タンガロイ(株)、1987年11月アメリカペンシルバニア州立大学:超電導、圧電の研究、2005年6月:東北大学金属材料研究所(准教授):アモルファス合金のエレクトロニクス、2012年8月:東北大学大学院工学研究科客員教授、2015年2月:東北大学大学未来科学技術共同研究センター(リサーチフェロー):アモルファスバイオ蓄電体・半導体の研究、現在シニアリサーチフェロー
●畠田 利彦 氏
1993年3月、山口大学大学院(修士課程)修了。日本製紙㈱に入社。研究部門に所属し、ディスプレイ用フィルムの設計、精密塗工プロセスの設計・管理、クリーン環境・生産・品質・安全マネジメントに従事。2023年より「CNF」を中心に木質資源を用いた環境性能や機能性向上に取組み、現在に至る。
●小林 満 氏
1992年3月 慶應義塾大学大学院理工学研究科応用化学専攻修士課程修了
1992年4月 王子製紙(現王子ホールディングス)株式会社に入社。研究開発本部に所属し、情報用紙(感熱紙、ノーカーボン紙、インクジェット用紙)の開発に従事。
2015年2月より、リン酸エステル化CNFの研究開発に従事し、現在に至る。
●能木 雅也 氏
2002年名古屋大学にて博士(農学)取得後、京都大学生存圏研究所などで研究員を行う。
2009年11月より大阪大学産業科学研究所に移り、2017年8月より同研究所にて教授。
主な受賞歴:平成22年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞「セルロースナノファイバー透明材料の研究」
【講演内容】
CNF(セルロースナノファイバー)は革新的な脱炭素素材として注目され、構造材料、食品、化粧品分野などで社会実装が進んでいる。近年は蓄電や半導体効果も確認され、エレクトロニクス応用が期待される。最新研究では従来のシリコン半導体とは異なるメカニズムが明らかになり、日本初のCNFエレクトロニクス技術や企業事例、将来戦略を紹介し、脱炭素社会におけるエレクトロニクス分野のパラダイムシフトを考察する。
【講演者プロフィール】
●渡邉 政嘉 氏
京都大学特任教授・学外連携フェロー(一財 高度技術社会推進協会・常務理事)。経産省産総研室長、 紙業服飾品課長、産業技術政策課長、NEDO理事、中小企業庁経営支援部長、経産省東北経済産業局長、 内閣審議官を歴任し、令和4年7月退官。研究所経営(オープンイノベーションハブ戦略)に関する研究、 セルロースナノファイバーの産業利用に関する研究等、多数実施。紙業服飾品課長時代に世界に先駆け ナノセルロース社会実装に向けたナノセルロースフォーラムの設立をリード。受賞歴:型技術協会創立 30周年「功労者賞」、日本機械学会フェロー、同会創立120周年記念功労者表彰など。博士(工学)
●福原 幹夫 氏
1979年8月大阪大学大学院工学研究科博士課程修了(工学博士)、1980年4月東芝タンガロイ(株)、1987年11月アメリカペンシルバニア州立大学:超電導、圧電の研究、2005年6月:東北大学金属材料研究所(准教授):アモルファス合金のエレクトロニクス、2012年8月:東北大学大学院工学研究科客員教授、2015年2月:東北大学大学未来科学技術共同研究センター(リサーチフェロー):アモルファスバイオ蓄電体・半導体の研究、現在シニアリサーチフェロー
●畠田 利彦 氏
1993年3月、山口大学大学院(修士課程)修了。日本製紙㈱に入社。研究部門に所属し、ディスプレイ用フィルムの設計、精密塗工プロセスの設計・管理、クリーン環境・生産・品質・安全マネジメントに従事。2023年より「CNF」を中心に木質資源を用いた環境性能や機能性向上に取組み、現在に至る。
●小林 満 氏
1992年3月 慶應義塾大学大学院理工学研究科応用化学専攻修士課程修了
1992年4月 王子製紙(現王子ホールディングス)株式会社に入社。研究開発本部に所属し、情報用紙(感熱紙、ノーカーボン紙、インクジェット用紙)の開発に従事。
2015年2月より、リン酸エステル化CNFの研究開発に従事し、現在に至る。
●能木 雅也 氏
2002年名古屋大学にて博士(農学)取得後、京都大学生存圏研究所などで研究員を行う。
2009年11月より大阪大学産業科学研究所に移り、2017年8月より同研究所にて教授。
主な受賞歴:平成22年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞「セルロースナノファイバー透明材料の研究」
交流会(15:45~16:45)

|
講演後そのままパーティーに移ります 参加対象者:講師、聴講者全員 参加費:無料 飲み物、 軽食をご用意しております |
|

|
(株)カネカ CO2 Innovation Laboratory 所長 佐藤 俊輔 |
|
【講演内容】
カネカはプラスチック代替材料として海洋生分解性バイオポリマーの市場投入を進めている。化石資源利用削減、海洋プラスチック問題解決を目指すにあたり、長期的な原料調達、利用技術開発が課題である。現在、CO2を直接炭素源として利用する技術開発を進めている。本講演にて進捗を紹介する。
【講演者プロフィール】
2004年3月、広島大学大学院卒業。株式会社カネカに入社。入社以来、生分解性バイオポリマーの微生物生産技術、工業生産プロセス開発に従事。
2013~15年、ドイツミュンスター大学 客員研究員(2015年、カネカ復職)
2023年より、NEDO GI基金事業に採択され、研究責任者に就任。
2024年CO2 Innovation Laboratory所長、現在に至る。
【講演内容】
カネカはプラスチック代替材料として海洋生分解性バイオポリマーの市場投入を進めている。化石資源利用削減、海洋プラスチック問題解決を目指すにあたり、長期的な原料調達、利用技術開発が課題である。現在、CO2を直接炭素源として利用する技術開発を進めている。本講演にて進捗を紹介する。
【講演者プロフィール】
2004年3月、広島大学大学院卒業。株式会社カネカに入社。入社以来、生分解性バイオポリマーの微生物生産技術、工業生産プロセス開発に従事。
2013~15年、ドイツミュンスター大学 客員研究員(2015年、カネカ復職)
2023年より、NEDO GI基金事業に採択され、研究責任者に就任。
2024年CO2 Innovation Laboratory所長、現在に至る。
成長戦略としての資源循環経済の確立に向けた取組について

|
経済産業省 GXグループ 資源循環経済課長 三牧 純一郎 |
|
【講演内容】
近年、廃棄物処理や気候変動等の環境制約に加え、資源制約によるリスク対応の観点からも、サーキュラーエコノミーへの移行が喫緊の課題となっており、成長分野としての期待も高まっている。本講演では、我が国の資源循環経済政策の最新動向について解説する。
【講演者プロフィール】
東京大学経済学部卒業後、2003 年経済産業省入省。入省以来、製造産業局繊維課やファッション政策室、内閣総理補佐官秘書官、中小企業庁、資源エネルギー庁、富山県、福島復興推進グループなど、幅広い業務に従事。入省後に米国コロンビア大学へ留学し MBA を取得。2025 年 7 月からは GX グループ資源循環経済課長に着任し、日本のサーキュラーエコノミー政策の推進に取り組む。
【講演内容】
近年、廃棄物処理や気候変動等の環境制約に加え、資源制約によるリスク対応の観点からも、サーキュラーエコノミーへの移行が喫緊の課題となっており、成長分野としての期待も高まっている。本講演では、我が国の資源循環経済政策の最新動向について解説する。
【講演者プロフィール】
東京大学経済学部卒業後、2003 年経済産業省入省。入省以来、製造産業局繊維課やファッション政策室、内閣総理補佐官秘書官、中小企業庁、資源エネルギー庁、富山県、福島復興推進グループなど、幅広い業務に従事。入省後に米国コロンビア大学へ留学し MBA を取得。2025 年 7 月からは GX グループ資源循環経済課長に着任し、日本のサーキュラーエコノミー政策の推進に取り組む。
循環経済に向けた環境政策の動向

|
環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 課長 相澤 寛史 |
|
【講演内容】
循環経済に向けた背景、大きな政策の流れ、及び再資源化事業等高度化法や資源循環自治体フォーラムなどの政策動向について紹介する。
【講演者プロフィール】
1999年環境庁入庁、廃棄物リサイクル対策部リサイクル推進室、産業廃棄物課総括補佐、廃棄物リサイクル対策部総務課制度企画室長、浄化槽室長、環境大臣秘書官、地球環境局地球温暖化対策事業室長などを経て、2025年より現職
【講演内容】
循環経済に向けた背景、大きな政策の流れ、及び再資源化事業等高度化法や資源循環自治体フォーラムなどの政策動向について紹介する。
【講演者プロフィール】
1999年環境庁入庁、廃棄物リサイクル対策部リサイクル推進室、産業廃棄物課総括補佐、廃棄物リサイクル対策部総務課制度企画室長、浄化槽室長、環境大臣秘書官、地球環境局地球温暖化対策事業室長などを経て、2025年より現職
再生プラスチックの社会実装と自動車分野への展開

|
東京大学 特別教授/物質・材料研究機構 フェロー 伊藤 耕三 |
|
【講演者プロフィール】
1986年3月、東京大学大学院博士課程修了、工学博士。同年工業技術院繊維高分子材料研究所の研究員、主任研究官を経て、1991年より東京大学講師、助教授を経て2003年より教授、2024年より特別教授として現在に至る。2023年から物質・材料研究機構フェローおよびSIPプログラムディレクターを兼務。学生のころより現在に至るまで一貫して高分子の研究に従事し、2022-2023年には高分子学会会長を務める
【講演者プロフィール】
1986年3月、東京大学大学院博士課程修了、工学博士。同年工業技術院繊維高分子材料研究所の研究員、主任研究官を経て、1991年より東京大学講師、助教授を経て2003年より教授、2024年より特別教授として現在に至る。2023年から物質・材料研究機構フェローおよびSIPプログラムディレクターを兼務。学生のころより現在に至るまで一貫して高分子の研究に従事し、2022-2023年には高分子学会会長を務める

|
BlueRebirth協議会 幹事 奥田 英樹 |

|

【講演内容】
自動精緻解体システムを起点とした動静脈融合バリューチェーン「BlueRebirth」について、昨年度の環境省実証の成果に加え、社会実装への課題解決を目指し'25/6に立ち上げたBlueRebirth協議会の取り組みを紹介する。
【講演者プロフィール】
1998年大阪府立大学卒業、株式会社デンソー入社。メカエンジニアとして、自動車部品の開発~量産・世界一シェア達成を経験。2009年より手術支援ロボット事業の立上げ・売却をメディカル事業室長として経験。2013年手術室のIoT化を着想し、東京女子医科大学ら5大学11社とスマート治療室の研究に従事。2018年東京女子医科大学より博士(医学)取得。2019年事業化加速のため、カーブアウトし(株)OPExPARKを設立。2022年大手商社からの資金調達を期にデンソーに帰任、新事業の柱として自動精緻解体を提案し、2023年サーキュラーエコノミー事業開発部を立上げ。2024年より36機関が連携した動静脈融合のBlueRebirthプロジェクトを開始し現在に至る。
【講演内容】
自動精緻解体システムを起点とした動静脈融合バリューチェーン「BlueRebirth」について、昨年度の環境省実証の成果に加え、社会実装への課題解決を目指し'25/6に立ち上げたBlueRebirth協議会の取り組みを紹介する。
【講演者プロフィール】
1998年大阪府立大学卒業、株式会社デンソー入社。メカエンジニアとして、自動車部品の開発~量産・世界一シェア達成を経験。2009年より手術支援ロボット事業の立上げ・売却をメディカル事業室長として経験。2013年手術室のIoT化を着想し、東京女子医科大学ら5大学11社とスマート治療室の研究に従事。2018年東京女子医科大学より博士(医学)取得。2019年事業化加速のため、カーブアウトし(株)OPExPARKを設立。2022年大手商社からの資金調達を期にデンソーに帰任、新事業の柱として自動精緻解体を提案し、2023年サーキュラーエコノミー事業開発部を立上げ。2024年より36機関が連携した動静脈融合のBlueRebirthプロジェクトを開始し現在に至る。

|
ENEOS(株) バイオ燃料部 部長 古谷 大介 |
|
【講演内容】
カーボンニュートラル社会到来に向けたトレンドは緩やかになったものの、バイオ燃料を含む低炭素事業については、移行期におけるエネルギーとして重大性が増大している。本公演では、ENEOSのSAFを中心としたバイオ燃料のサプライチェーン構築に向けた国内外での取組を紹介する。
【講演者プロフィール】
1992年3月、明治大学卒業。日本石油株式会社に入社。
トレーディング部門や海外事業開発部門に所属し、原料・石油製品のサプライチェーン構築に従事。
カタール、ロンドン、ジャカルタ、ハノイ駐在を経て、2023年4月よりバイオ燃料部 部長に就任し、現在に至る。
【講演内容】
カーボンニュートラル社会到来に向けたトレンドは緩やかになったものの、バイオ燃料を含む低炭素事業については、移行期におけるエネルギーとして重大性が増大している。本公演では、ENEOSのSAFを中心としたバイオ燃料のサプライチェーン構築に向けた国内外での取組を紹介する。
【講演者プロフィール】
1992年3月、明治大学卒業。日本石油株式会社に入社。
トレーディング部門や海外事業開発部門に所属し、原料・石油製品のサプライチェーン構築に従事。
カタール、ロンドン、ジャカルタ、ハノイ駐在を経て、2023年4月よりバイオ燃料部 部長に就任し、現在に至る。

|
(一社)SusPla 専務理事(代表理事)/(一社)サステナブル経営推進機構 小林 弘幸 |

|

【講演内容】
持続可能な社会の実現に向けて、再生プラスチックの利活用は急務となっています。本発表では、SusPla (Sustainable Plastics Initiative) が推進するSPC認証(Sustainable Plastics Certification)との連携戦略を通じて、再生プラスチック市場の拡大に向けた取り組みを紹介します。
【講演者プロフィール】
2016年11月に一般社団法人産業環境管理協会に入社し、環境省のプラスチック強化素材の社会実装事業、経済産業省の資源循環支援事業等の業務に従事。2019年、一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)の設立とともに転籍。革新的な脱炭素素材の社会実装事業やサーキュラーエコノミーへの移行を推進するプロジェクト等を担当し、その中で、SPC認証プログラム(動静脈連携型マテリアルリサイクルプロセスに関する事業所認証制度)の開発や一般社団法人SusPla(マテリアルリサイクルによる再生プラスチック市場の拡大を目指すInitiative)の設立に携わり、現在に至る。SusPla専務理事(代表理事)、幹事。SuMPO業務執行理事。
【講演内容】
持続可能な社会の実現に向けて、再生プラスチックの利活用は急務となっています。本発表では、SusPla (Sustainable Plastics Initiative) が推進するSPC認証(Sustainable Plastics Certification)との連携戦略を通じて、再生プラスチック市場の拡大に向けた取り組みを紹介します。
【講演者プロフィール】
2016年11月に一般社団法人産業環境管理協会に入社し、環境省のプラスチック強化素材の社会実装事業、経済産業省の資源循環支援事業等の業務に従事。2019年、一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)の設立とともに転籍。革新的な脱炭素素材の社会実装事業やサーキュラーエコノミーへの移行を推進するプロジェクト等を担当し、その中で、SPC認証プログラム(動静脈連携型マテリアルリサイクルプロセスに関する事業所認証制度)の開発や一般社団法人SusPla(マテリアルリサイクルによる再生プラスチック市場の拡大を目指すInitiative)の設立に携わり、現在に至る。SusPla専務理事(代表理事)、幹事。SuMPO業務執行理事。

|
DOWAエコシステム(株) 環境ソリューション室 環境技術研究所 環境技術研究所長 渡邊 亮栄 |

|

【講演内容】
資源循環の質が問われる現代において、使用済リチウムイオン電池(LIB)からの資源回収・循環利用は、安全性および効率性の両立とともに、サプライチェーン全体の最適化が求められる。本講演では、LIBリサイクルに対する当社の取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
2004年 同和鉱業株式会社(現DOWAホールディングス株式会社)入社。環境・リサイクルに関する研究開発ならびに土壌浄化工場や廃棄物処理工場の操業管理を担当し、2020年よりDOWAエコシステム株式会社 環境ソリューション室 環境技術研究所長。
【講演内容】
資源循環の質が問われる現代において、使用済リチウムイオン電池(LIB)からの資源回収・循環利用は、安全性および効率性の両立とともに、サプライチェーン全体の最適化が求められる。本講演では、LIBリサイクルに対する当社の取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
2004年 同和鉱業株式会社(現DOWAホールディングス株式会社)入社。環境・リサイクルに関する研究開発ならびに土壌浄化工場や廃棄物処理工場の操業管理を担当し、2020年よりDOWAエコシステム株式会社 環境ソリューション室 環境技術研究所長。

|
三菱電機(株) リサイクル共創センター 資源循環戦略エキスパート 井関 康人 |
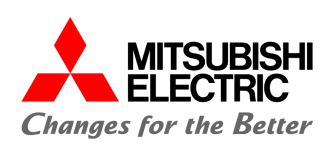
|
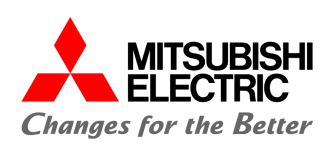
【講演内容】
家電リサイクルで回収された破砕混合プラスチックから、高純度な単一プラスチックを分離・回収する高度選別技術と、回収した単一プラスチックを再び家電製品へ再利用する「自己循環リサイクル」について述べる。さらに、長年培ってきたこれらの技術を家電以外の領域へと展開する新たな取り組みについても紹介する。
【講演者プロフィール】
1996年より、三菱電機で、使用済み家電製品から金属やプラスチックを素材別に分離回収する高度選別技術開発および事業化に取り組み、2010年に家電混合プラスチックの選別・素材化事業を立ち上げる。2022年より、リサイクル共創センターにて、家電で長年培った高度選別技術を、家電以外の領域へ展開する新規事業創出に従事し現在に至る。
【講演内容】
家電リサイクルで回収された破砕混合プラスチックから、高純度な単一プラスチックを分離・回収する高度選別技術と、回収した単一プラスチックを再び家電製品へ再利用する「自己循環リサイクル」について述べる。さらに、長年培ってきたこれらの技術を家電以外の領域へと展開する新たな取り組みについても紹介する。
【講演者プロフィール】
1996年より、三菱電機で、使用済み家電製品から金属やプラスチックを素材別に分離回収する高度選別技術開発および事業化に取り組み、2010年に家電混合プラスチックの選別・素材化事業を立ち上げる。2022年より、リサイクル共創センターにて、家電で長年培った高度選別技術を、家電以外の領域へ展開する新規事業創出に従事し現在に至る。
<モデレーター>

|
東京大学 特別教授/物質・材料研究機構 フェロー 伊藤 耕三 |
|
<パネリスト>
|
|
(株)富山環境整備 社長室 専任次長(イノベーション担当) 今井 麻美 |
|

|
石塚化学産業(株) 代表取締役会長/Sustainable Plastics Initiative(SusPla) 理事長 石塚 勝一 |
|

|
三井化学(株) グリーンケミカル事業推進室 マテリアルリサイクルグループ 特命担当 深田 利 |
|

|
豊田合成(株) 第2材料技術部 主担当員 内田 均 |

|


|
トヨタ自動車(株) 選定中 |
|
【講演者プロフィール】
●伊藤 耕三 氏
1986年3月、東京大学大学院博士課程修了、工学博士。同年工業技術院繊維高分子材料研究所の研究員、主任研究官を経て、1991年より東京大学講師、助教授を経て2003年より教授、2024年より特別教授として現在に至る。2023年から物質・材料研究機構フェローおよびSIPプログラムディレクターを兼務。学生のころより現在に至るまで一貫して高分子の研究に従事し、2022-2023年には高分子学会会長を務める
●石塚 勝一 氏
再生プラスチックの製造販売を行っている石塚化学産業(株)に45年間勤め、昨年代表取締役会長に就任。その間、全日本プラスチックリサイクル工業会会長や関東プラスチックリサイクル協同組合理事長を努める。2018年に「心臓産業の会」を再生メーカー4社で立上げ、再生プラスチックを正しく知ってもらう活動を行い、2023年に(一社)サスティナブル経営推進機構様と再生プラスチックの適性評価に繋がるSPC(Sustainable Plastics Certification)認証制度の開発を発表。2024年7月に再生プラスチック市場の健全な発展を目指したSusPla(Sustainable Plastics Initiative)をステークホルダーと共に立上げ理事長に就任、本年4月に一般社団法人化。更なる循環経済移行を目指す。
●内田 均 氏
1996年 群馬大学 材料工学 修了
2003年 豊田合成株式会社入社 材料技術部に所属し、自動車用樹脂・ゴム材料の開発に従事
現在は自動車用樹枝材料のリサイクルを担当
【講演者プロフィール】
●伊藤 耕三 氏
1986年3月、東京大学大学院博士課程修了、工学博士。同年工業技術院繊維高分子材料研究所の研究員、主任研究官を経て、1991年より東京大学講師、助教授を経て2003年より教授、2024年より特別教授として現在に至る。2023年から物質・材料研究機構フェローおよびSIPプログラムディレクターを兼務。学生のころより現在に至るまで一貫して高分子の研究に従事し、2022-2023年には高分子学会会長を務める
●石塚 勝一 氏
再生プラスチックの製造販売を行っている石塚化学産業(株)に45年間勤め、昨年代表取締役会長に就任。その間、全日本プラスチックリサイクル工業会会長や関東プラスチックリサイクル協同組合理事長を努める。2018年に「心臓産業の会」を再生メーカー4社で立上げ、再生プラスチックを正しく知ってもらう活動を行い、2023年に(一社)サスティナブル経営推進機構様と再生プラスチックの適性評価に繋がるSPC(Sustainable Plastics Certification)認証制度の開発を発表。2024年7月に再生プラスチック市場の健全な発展を目指したSusPla(Sustainable Plastics Initiative)をステークホルダーと共に立上げ理事長に就任、本年4月に一般社団法人化。更なる循環経済移行を目指す。
●内田 均 氏
1996年 群馬大学 材料工学 修了
2003年 豊田合成株式会社入社 材料技術部に所属し、自動車用樹脂・ゴム材料の開発に従事
現在は自動車用樹枝材料のリサイクルを担当

|
イー・アンド・イー ソリューションズ(株) 環境事業部 企画推進室 室長 石塚 隆記 |

|

【講演内容】
イー・アンド・イーソリューションズは、これまでに環境省の実証事業への参画や、PV CYCLE JAPANの設立と運営への関与を通して、太陽光パネルの長期使用・リサイクルの促進に向けた取り組みを進めてきた。本講演では、これまでの取り組みの概要とともに、今後の展望を述べる。
【講演者プロフィール】
2005年3月東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程修了、同年10月にイー・アンド・イーソリューションズ株式会社に入社。
入社以降2014年までは主に、官公庁向け・製造業向けの化学物質管理支援業務、および金融機関向けの海外大型インフラプロジェクトの環境社会配慮確認業務に従事。2015年からは主に、官公庁・大手シンクタンク向けの循環経済移行に関する調査・研究業務に従事。
2021年にはPV CYCLE JAPANの設立に関与、以降、PV CYCLE JAPANの運営への関与を通して、太陽光パネルの長期使用・リサイクル促進向けた取り組みに従事し、現在に至る。
【講演内容】
イー・アンド・イーソリューションズは、これまでに環境省の実証事業への参画や、PV CYCLE JAPANの設立と運営への関与を通して、太陽光パネルの長期使用・リサイクルの促進に向けた取り組みを進めてきた。本講演では、これまでの取り組みの概要とともに、今後の展望を述べる。
【講演者プロフィール】
2005年3月東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程修了、同年10月にイー・アンド・イーソリューションズ株式会社に入社。
入社以降2014年までは主に、官公庁向け・製造業向けの化学物質管理支援業務、および金融機関向けの海外大型インフラプロジェクトの環境社会配慮確認業務に従事。2015年からは主に、官公庁・大手シンクタンク向けの循環経済移行に関する調査・研究業務に従事。
2021年にはPV CYCLE JAPANの設立に関与、以降、PV CYCLE JAPANの運営への関与を通して、太陽光パネルの長期使用・リサイクル促進向けた取り組みに従事し、現在に至る。
<モデレーター>

|
クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス 事務局次長 柳田 康一 |

|

<パネリスト>

|
アミタホールディングス(株) 未来デザイングループ 社会デザイン事業開発マネージャー 高瀬 晴太 |

|


|
神戸市 環境局資源循環課 課長 井関 和人 |

|


|
(株)ヤクルト本社 サステナビリティ推進部資源循環推進課 担当課長 久保 昌男 |

|

【講演内容】
CLOMAはプラスチックの循環利用を推進しコミュニティや生活者とともに海洋プラごみのゼロ化を目指す企業アライアンスです。
セミナーでは神戸市にも参加してもらい、同市が進めるプラ回収に参画する企業との議論を通して官民連携の勘所や未来像につき議論を深めます。
【講演者プロフィール】
●柳田 康一 氏
1985年花王株式会社入社、加工プロセス研究室長、包装容器研究室長、サステナビリティ推進部長、ESG部門副統括を歴任、2019年からはCLOMA技術統括を担当し現在に至る。
専門分野は、トイレタリー製品の設計・製造、ユニバーサルデザイン、レスポンシブルケア、ESG経営、海洋プラスチックごみ問題、サーキュラーエコノミーなど。
●高瀬 晴太 氏
2017年にアミタ合流後、製造業を中心とした資源循環スキーム構築の支援、資源循環事業部門の戦略立案、実行、バックオフィスでの営業補佐を経験。現在は新規事業開発部門でチームマネージャーを務め、企業とパートナーシップを組み、連携しながらアミタが展開を進めるMEGURU STATION®を軸としたビジネスモデルの構築を担当する部署のマネージャーを務める。企業との連携の一つとしてビジネスサーキュラーエコノミーの実践集団としてのコンソーシアム(J-CEP:ジャパン・サーキュラー・エコノミー・パートナーシップ)の事務局を担当。
●井関 和人 氏
1991年神戸市入庁。理財局、区役所、産業振興局、行財政局、文化スポーツ局などを経て、2024年4月より現職。現職では家庭系一般廃棄物の減量・資源化施策を担当。
●久保 昌男 氏
2006年3月に大学(工学部機械工学科)卒業後、株式会社ヤクルト本社に入社。開発部に所属し、2016年まで生産技術・容器包装技術の開発に従事。2017年に部内異動により商品開発に携わることとなり、「蕃爽麗茶」や「ジョア」などを担当し、2021年発売の「Y1000」では新容器を開発。併行して、プラスチック容器包装における循環型経済への適応について検討を進めるなか、2022年4月に、現所属部署の前身となる環境対応推進室が新設され異動となり、以後、容器包装の資源循環について戦略立案や外部連携によるプロジェクト推進などを進め、現在に至る。
【講演内容】
CLOMAはプラスチックの循環利用を推進しコミュニティや生活者とともに海洋プラごみのゼロ化を目指す企業アライアンスです。
セミナーでは神戸市にも参加してもらい、同市が進めるプラ回収に参画する企業との議論を通して官民連携の勘所や未来像につき議論を深めます。
【講演者プロフィール】
●柳田 康一 氏
1985年花王株式会社入社、加工プロセス研究室長、包装容器研究室長、サステナビリティ推進部長、ESG部門副統括を歴任、2019年からはCLOMA技術統括を担当し現在に至る。
専門分野は、トイレタリー製品の設計・製造、ユニバーサルデザイン、レスポンシブルケア、ESG経営、海洋プラスチックごみ問題、サーキュラーエコノミーなど。
●高瀬 晴太 氏
2017年にアミタ合流後、製造業を中心とした資源循環スキーム構築の支援、資源循環事業部門の戦略立案、実行、バックオフィスでの営業補佐を経験。現在は新規事業開発部門でチームマネージャーを務め、企業とパートナーシップを組み、連携しながらアミタが展開を進めるMEGURU STATION®を軸としたビジネスモデルの構築を担当する部署のマネージャーを務める。企業との連携の一つとしてビジネスサーキュラーエコノミーの実践集団としてのコンソーシアム(J-CEP:ジャパン・サーキュラー・エコノミー・パートナーシップ)の事務局を担当。
●井関 和人 氏
1991年神戸市入庁。理財局、区役所、産業振興局、行財政局、文化スポーツ局などを経て、2024年4月より現職。現職では家庭系一般廃棄物の減量・資源化施策を担当。
●久保 昌男 氏
2006年3月に大学(工学部機械工学科)卒業後、株式会社ヤクルト本社に入社。開発部に所属し、2016年まで生産技術・容器包装技術の開発に従事。2017年に部内異動により商品開発に携わることとなり、「蕃爽麗茶」や「ジョア」などを担当し、2021年発売の「Y1000」では新容器を開発。併行して、プラスチック容器包装における循環型経済への適応について検討を進めるなか、2022年4月に、現所属部署の前身となる環境対応推進室が新設され異動となり、以後、容器包装の資源循環について戦略立案や外部連携によるプロジェクト推進などを進め、現在に至る。

|
東レ(株) 研究・開発企画部 CR企画室 室長 荒西 義高 |

|

【講演内容】
繊維産業においても、循環型社会構築に向けてサステナビリティ実現が重要な課題である。バイオマス由来原料の活用と共に、現状決して高いとは言えない繊維製品リサイクル率の向上が急務となっている。業界の動向もあわせ、東レ株式会社の取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
1994年3月、京都大学大学院農学研究科修士修了、同4月、東レ株式会社に入社。
繊維研究所合成繊維研究室に配属され、ポリエステル繊維、ポリ乳酸繊維、熱可塑性セルロース繊維などの研究に従事。2017年から2025年まで繊維研究所所長。2025年8月より研究・開発企画部 CR企画室長、現在に至る。
【講演内容】
繊維産業においても、循環型社会構築に向けてサステナビリティ実現が重要な課題である。バイオマス由来原料の活用と共に、現状決して高いとは言えない繊維製品リサイクル率の向上が急務となっている。業界の動向もあわせ、東レ株式会社の取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
1994年3月、京都大学大学院農学研究科修士修了、同4月、東レ株式会社に入社。
繊維研究所合成繊維研究室に配属され、ポリエステル繊維、ポリ乳酸繊維、熱可塑性セルロース繊維などの研究に従事。2017年から2025年まで繊維研究所所長。2025年8月より研究・開発企画部 CR企画室長、現在に至る。

|
(株)竹中工務店 安全環境本部 シニアチーフエキスパート 高崎 英人 |

|

【講演内容】
竹中工務店グループでは、従来のスクラップ&ビルドを超え、建築分野におけるサーキュラーエコノミーを実践する取り組み「サーキュラーデザインビルド®」を開始しました。我々の取り組みについて事例を交えて紹介します。
【講演者プロフィール】
1991年4月、竹中工務店に入社。その後、東京本店建設現場、本社地球環境室、東京本店安全環境部を経て、2022年4月、現在の本社安全環境本部に配属。
【講演内容】
竹中工務店グループでは、従来のスクラップ&ビルドを超え、建築分野におけるサーキュラーエコノミーを実践する取り組み「サーキュラーデザインビルド®」を開始しました。我々の取り組みについて事例を交えて紹介します。
【講演者プロフィール】
1991年4月、竹中工務店に入社。その後、東京本店建設現場、本社地球環境室、東京本店安全環境部を経て、2022年4月、現在の本社安全環境本部に配属。
<モデレーター>

|
クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス事務局 技術統括 南部 博美 |

|

<パネリスト>

|
(株)セブン&アイ・ホールディングス サステナビリティ推進室 業務推進役 尾崎 一夫 |

|


|
三菱ケミカル(株) ベーシックマテリアルズ&ポリマーズビジネスグループ 戦略企画本部 CN・CE戦略部 部長 板東 健彦 |

|


|
三井物産(株) パフォーマンスマテリアルズ本部 サーキュラーエコノミー推進チーム チームリーダー 道明 太郎 |

|

【講演内容】
CLOMAではプラスチック資源循環を進める活動を、産官の企業連携により行っている。昨年、中期目標としてCircular30by30(2030年までに再生材を30%利用する)を設定することで活動の具体化と進めている。また経産省サーキュラーパートナーズでのプラ容器包装WGリーダーとして実証事業を計画している。
【講演者プロフィール】
●南部 博美 氏
1988年 花王株式会社入社し、マテリアルサイエンス研究所 室長、副所長などを担当。
2023年9月にCLOMA出向し、2024年より現職に従事。
●尾崎 一夫 氏
1988年に(株)イトーヨーカ堂に入社。販売促進部マネジャー。
2006年に(株)セブン&アイ・ホールディングスへ転籍。CSR統括部環境担当オフィサー。
2020年よりサステナビリティ推進部シニアオフサー。
2025年9月より現職
●板東 健彦 氏
1995年、三菱化学株式会社(現三菱ケミカル)に入社。海外子会社管理、経営企画室、海外プロジェクトなどの担当を経て、2022年より現職で廃プラスチックの油化、バイオマス原料化、CCUなどのプロジェクトに従事。
●道明 太郎 氏
1996年:早稲田大学理工学部応用化学科卒業。同年4月三井物産株式会社に入社。入社以来、化学品セグメントに一貫して従事。
2002年:英国ロンドン駐在。
2016年:本州化学工業(株)に出向。経営企画部副部長兼事業開発室長としてファインケミカルの新製品開発と新規事業開発を統括。
2019年:カーボンニュートラル実現に向けた水素インフラ新規事業プロジェクトを立ち上げ。
2022年:森林資源マーケティング室長として南米の森林資源事業開発を手掛けて、世界最大パルプメーカーと共同開発事業を手掛ける。
2024年:プラスチック資源循環・再資源化によるサーキュラーエコノミー領域の新規事業創出と事業開発を統括。
【講演内容】
CLOMAではプラスチック資源循環を進める活動を、産官の企業連携により行っている。昨年、中期目標としてCircular30by30(2030年までに再生材を30%利用する)を設定することで活動の具体化と進めている。また経産省サーキュラーパートナーズでのプラ容器包装WGリーダーとして実証事業を計画している。
【講演者プロフィール】
●南部 博美 氏
1988年 花王株式会社入社し、マテリアルサイエンス研究所 室長、副所長などを担当。
2023年9月にCLOMA出向し、2024年より現職に従事。
●尾崎 一夫 氏
1988年に(株)イトーヨーカ堂に入社。販売促進部マネジャー。
2006年に(株)セブン&アイ・ホールディングスへ転籍。CSR統括部環境担当オフィサー。
2020年よりサステナビリティ推進部シニアオフサー。
2025年9月より現職
●板東 健彦 氏
1995年、三菱化学株式会社(現三菱ケミカル)に入社。海外子会社管理、経営企画室、海外プロジェクトなどの担当を経て、2022年より現職で廃プラスチックの油化、バイオマス原料化、CCUなどのプロジェクトに従事。
●道明 太郎 氏
1996年:早稲田大学理工学部応用化学科卒業。同年4月三井物産株式会社に入社。入社以来、化学品セグメントに一貫して従事。
2002年:英国ロンドン駐在。
2016年:本州化学工業(株)に出向。経営企画部副部長兼事業開発室長としてファインケミカルの新製品開発と新規事業開発を統括。
2019年:カーボンニュートラル実現に向けた水素インフラ新規事業プロジェクトを立ち上げ。
2022年:森林資源マーケティング室長として南米の森林資源事業開発を手掛けて、世界最大パルプメーカーと共同開発事業を手掛ける。
2024年:プラスチック資源循環・再資源化によるサーキュラーエコノミー領域の新規事業創出と事業開発を統括。

|
いその(株) 代表取締役社長 磯野 正幸 |

|

【講演内容】
2013年に弊社のPIR材を使った再生材料が業界で
初めて、自動車メーカーに認証登録されました。
以来多くの部品に弊社の再生材料が活用されています。
欧州委員会のELV規則により、2030年に向けて、
再生材を含むサスプラの需要が高まっています。
PCR材の本格採用への現状と課題についてお話します
【講演者プロフィール】
平成13年5月 星和化成(株)代表取締役社長就任, 平成18年10月 いその(株)代表取締役社長兼務,
平成22年5月 中部プラスチック製品工業協会 副会長,令和元年4月 中部プラスチックリサイクル協同組合 理事長,令和5年5月 全日本プラスチックリサイクル工業会 会長に就任、現在に至る。
【講演内容】
2013年に弊社のPIR材を使った再生材料が業界で
初めて、自動車メーカーに認証登録されました。
以来多くの部品に弊社の再生材料が活用されています。
欧州委員会のELV規則により、2030年に向けて、
再生材を含むサスプラの需要が高まっています。
PCR材の本格採用への現状と課題についてお話します
【講演者プロフィール】
平成13年5月 星和化成(株)代表取締役社長就任, 平成18年10月 いその(株)代表取締役社長兼務,
平成22年5月 中部プラスチック製品工業協会 副会長,令和元年4月 中部プラスチックリサイクル協同組合 理事長,令和5年5月 全日本プラスチックリサイクル工業会 会長に就任、現在に至る。

|
住友化学(株) 炭素資源循環事業化推進室 部長 野末 佳伸 |

|

【講演内容】
プラスチックの資源循環を加速させるうえでカギとなるケミカルリサイクルの技術動向について、PMMAやポリオレフィンを対象とした当社の取り組み事例を交えながら説明する。さらに法規制の状況なども共有しながら、社会に広く普及させるための課題を共有する。
【講演者プロフィール】
2002年3月 東京大学 工学系研究科博士後期課程修了
2002年4月 住友化学工業(当時)入社 石油化学品研究所にて分析業務、ポリオレフィンの材料設計開発に従事。
2012年より新規テーマを立ち上げ、開発、マーケティングに従事。
2021年6月よりエッセンシャルケミカルズ研究所にて新規開発(アクリルのリサイクル技術開発など)の研究マネジメントに従事。
2023年6月よりプラスチック資源循環事業化推進室の部長となり、プラスチック資源循環技術の早期事業化を推進、(2024年4月にスコープ拡大のため現在の組織名称に変更)現在に至る。
【講演内容】
プラスチックの資源循環を加速させるうえでカギとなるケミカルリサイクルの技術動向について、PMMAやポリオレフィンを対象とした当社の取り組み事例を交えながら説明する。さらに法規制の状況なども共有しながら、社会に広く普及させるための課題を共有する。
【講演者プロフィール】
2002年3月 東京大学 工学系研究科博士後期課程修了
2002年4月 住友化学工業(当時)入社 石油化学品研究所にて分析業務、ポリオレフィンの材料設計開発に従事。
2012年より新規テーマを立ち上げ、開発、マーケティングに従事。
2021年6月よりエッセンシャルケミカルズ研究所にて新規開発(アクリルのリサイクル技術開発など)の研究マネジメントに従事。
2023年6月よりプラスチック資源循環事業化推進室の部長となり、プラスチック資源循環技術の早期事業化を推進、(2024年4月にスコープ拡大のため現在の組織名称に変更)現在に至る。

|
ICIS ビジネスソリューショングループ シニアエグゼクティブ 久戸瀬 極 |

|

【講演内容】
EUの法規制が、発端となり世界的にプラスチック樹脂のリサイクル機運が盛り上がったが、一方で中国における過剰生産能力問題もあり世界的に化学産業は、事業の見直しそして工場閉鎖などに追い込まれている。世界各国に法的な拘束力をもたせるINC会議が何度か開催されたが、未だに合意には至っていない。需給バランスなどが崩れたままの石油化学業界におけるリサイクル樹脂市場について現在・今後の市場状況について説明する。
【講演者プロフィール】
大阪大学大学院(MS終了)、三菱化成(現三菱ケミカル)、ダウ・ケミカル日本さらにDow Chemical USAでオレフィン・エポキシ・アクリル・ウレタン事業に従事。その後、Evonik Corp(US), Evonik GmbHを経てエボニックジャパンで特殊イソシアネートそしてアミン事業に参画。その後、ICISにて市場開発担当、現在のビジネスソリューショングループで顧客に市場・法令を説明することでビジネスサポートを行っている。
【講演内容】
EUの法規制が、発端となり世界的にプラスチック樹脂のリサイクル機運が盛り上がったが、一方で中国における過剰生産能力問題もあり世界的に化学産業は、事業の見直しそして工場閉鎖などに追い込まれている。世界各国に法的な拘束力をもたせるINC会議が何度か開催されたが、未だに合意には至っていない。需給バランスなどが崩れたままの石油化学業界におけるリサイクル樹脂市場について現在・今後の市場状況について説明する。
【講演者プロフィール】
大阪大学大学院(MS終了)、三菱化成(現三菱ケミカル)、ダウ・ケミカル日本さらにDow Chemical USAでオレフィン・エポキシ・アクリル・ウレタン事業に従事。その後、Evonik Corp(US), Evonik GmbHを経てエボニックジャパンで特殊イソシアネートそしてアミン事業に参画。その後、ICISにて市場開発担当、現在のビジネスソリューショングループで顧客に市場・法令を説明することでビジネスサポートを行っている。
リマニュファクチャリング推進コンソーシアムの取り組みについて

|
(国研)産業技術総合研究所 製造基盤技術研究部門 研究部門長 三宅 晃司 |
|
【講演内容】
サーキュラーエコノミーを推進するために必須であり、またサーキュラーエコノミー時代のものづくりの競争力の強化に必須であるリマニュファクチャリングについて、最近の研究動向について概説するとともに、昨年10月に設立したリマニュファクチャリング推進コンソーシアムの取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
1997年3月筑波大学 大学院 博士課程 工学研究科 物質工学専攻 修了。博士(工学)取得。筑波大学助手を経て2001年4月産業技術総合研究所入所。現在,同所製造基盤技術研究部門 研究部門長。リマニュファクチャリング推進コンソーシアム会長。サーキュラーエコノミー時代のものづくりの基盤となる技術、特にリマニュファクチャリングの多様化を実現する補修、評価技術に加え、部材に新たな機能の付与とモダナイゼーションを実現するデータ駆動型表面加工技術の研究開発を推進している。
【講演内容】
サーキュラーエコノミーを推進するために必須であり、またサーキュラーエコノミー時代のものづくりの競争力の強化に必須であるリマニュファクチャリングについて、最近の研究動向について概説するとともに、昨年10月に設立したリマニュファクチャリング推進コンソーシアムの取り組みについて紹介する。
【講演者プロフィール】
1997年3月筑波大学 大学院 博士課程 工学研究科 物質工学専攻 修了。博士(工学)取得。筑波大学助手を経て2001年4月産業技術総合研究所入所。現在,同所製造基盤技術研究部門 研究部門長。リマニュファクチャリング推進コンソーシアム会長。サーキュラーエコノミー時代のものづくりの基盤となる技術、特にリマニュファクチャリングの多様化を実現する補修、評価技術に加え、部材に新たな機能の付与とモダナイゼーションを実現するデータ駆動型表面加工技術の研究開発を推進している。
サーキュラーエコノミーに貢献する建設機械の再生事業

|
日立建機(株) 部品・サービスビジネスユニット 再生事業部 サーキュラーエコノミー推進部 部長代理 秋田 秀樹 |

|

【講演内容】
建設機械では、サーキュラーエコノミーの観点から、部品のリマニファクチャリングを実施することで、機械本体の寿命延長を図る取り組みが進められている。本講演ではこれら一連の部品再生事業について紹介する。
【講演者プロフィール】
1992年3月、山形大学工学部卒業。日立建機株式会社に入社。技術開発センタに所属し、摩擦摩耗関係の研究に従事。2009年3月に東京海洋大学大学院博士後期課程卒業。2022年10月より再生事業部サーキュラーエコノミー推進部技術開発グループに転属し、現在に至る。
【講演内容】
建設機械では、サーキュラーエコノミーの観点から、部品のリマニファクチャリングを実施することで、機械本体の寿命延長を図る取り組みが進められている。本講演ではこれら一連の部品再生事業について紹介する。
【講演者プロフィール】
1992年3月、山形大学工学部卒業。日立建機株式会社に入社。技術開発センタに所属し、摩擦摩耗関係の研究に従事。2009年3月に東京海洋大学大学院博士後期課程卒業。2022年10月より再生事業部サーキュラーエコノミー推進部技術開発グループに転属し、現在に至る。
リペア・リマニュファクチャリングとサーキュラーエコノミー

|
光栄テクノシステム(株) 取締役社長 博士(学術) 德本 啓 |
|

|
(株)産業タイムズ社 代表取締役 副社長 特別編集員 津村 明宏 |

|

【講演内容】
有機ELの大型化などで面積成長が続くディスプレイ産業の現状と今後を展望するとともに、今後が期待されるXRやマイクロディスプレイのトレンドを紹介する。また、ディスプレイ製造技術の応用が進む半導体パッケージの取り組みも解説する。
【講演者プロフィール】
1995年3月に関西大学経済学部卒。1999年3月 ㈱産業タイムズ社に入社。電子デバイス業界の専門紙である電子デバイス産業新聞(旧・半導体産業新聞)の記者として、2007年より副編集長、2009年12月より編集長。2021年7月より副社長兼特別編集委員
【講演内容】
有機ELの大型化などで面積成長が続くディスプレイ産業の現状と今後を展望するとともに、今後が期待されるXRやマイクロディスプレイのトレンドを紹介する。また、ディスプレイ製造技術の応用が進む半導体パッケージの取り組みも解説する。
【講演者プロフィール】
1995年3月に関西大学経済学部卒。1999年3月 ㈱産業タイムズ社に入社。電子デバイス業界の専門紙である電子デバイス産業新聞(旧・半導体産業新聞)の記者として、2007年より副編集長、2009年12月より編集長。2021年7月より副社長兼特別編集委員

|
シャープ(株) パネルセミコン研究所 次世代技術開発統轄部 統轄部長 箕浦 潔 |

|

【講演内容】
ディスプレイはXR機器や電子ポスターなど新領域に広がる一方で、電力利用の増大が課題となっている。
低消費電力技術により脱炭素社会の実現をサポートするシャープの最新ディスプレイ技術を紹介する。
【講演者プロフィール】
1997年3月東京大学工学系大学院卒業、同4月シャープ株式会社に入社。
2010年東京農工大学にて博士号取得。
反射型液晶ディスプレイ開発、超低反射フィルム・モスアイフィルム開発、新規液晶モード開発、新規光学材料開発に従事。
2018年7月より、中小型パネル技術開発全般の担当となり、現在に至る。
【講演内容】
ディスプレイはXR機器や電子ポスターなど新領域に広がる一方で、電力利用の増大が課題となっている。
低消費電力技術により脱炭素社会の実現をサポートするシャープの最新ディスプレイ技術を紹介する。
【講演者プロフィール】
1997年3月東京大学工学系大学院卒業、同4月シャープ株式会社に入社。
2010年東京農工大学にて博士号取得。
反射型液晶ディスプレイ開発、超低反射フィルム・モスアイフィルム開発、新規液晶モード開発、新規光学材料開発に従事。
2018年7月より、中小型パネル技術開発全般の担当となり、現在に至る。

|
カウンターポイントリサーチ(株) 日本支社長 田村 喜男 |

|

【講演内容】
多くのアプリケーションで中国メーカーが支配するLCD市場、先端技術であるOLEDなどに注力して、今後の大局を解説する。同時に、トランプ関税に端を発した貿易戦争下の大局的な世界経済動向とテクノロジー産業動向も解説する。
【講演者プロフィール】
2000年4月:ディスプレイ専門調査・コンサルティング企業である米国DisplaySearch社の副社長兼日本&アジア代表として日本支社を設立。田村の人脈により韓国・台湾・中国等で多くの人材を採用し、DisplaySearch社はアジア他世界に拠点を拡大。以降、NPD, IHS, DSCCを経て、現在のCounterpoint Researchの日本支店を立ち上げ、現在に至る。
【講演内容】
多くのアプリケーションで中国メーカーが支配するLCD市場、先端技術であるOLEDなどに注力して、今後の大局を解説する。同時に、トランプ関税に端を発した貿易戦争下の大局的な世界経済動向とテクノロジー産業動向も解説する。
【講演者プロフィール】
2000年4月:ディスプレイ専門調査・コンサルティング企業である米国DisplaySearch社の副社長兼日本&アジア代表として日本支社を設立。田村の人脈により韓国・台湾・中国等で多くの人材を採用し、DisplaySearch社はアジア他世界に拠点を拡大。以降、NPD, IHS, DSCCを経て、現在のCounterpoint Researchの日本支店を立ち上げ、現在に至る。
自動車におけるパワートレイン向けレーザ加工技術

|
日産自動車(株) パワートレイン・EVコンポーネント生産技術開発本部 試作・サイマル技術開発部 パワートレイン技術グループ MFG&SCM エキスパート:レーザ加工技術 フナル アウレル |
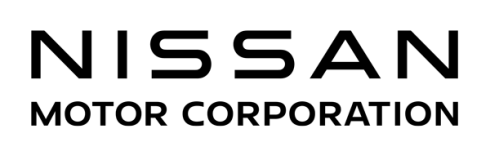
|
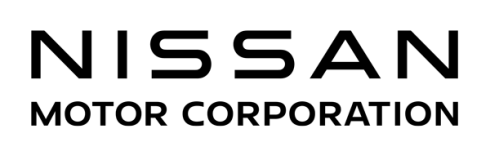
【講演内容】
自動車業界が電動化へと移行するにつれ、レーザー加工は銅やアルミニウムといった新素材への適応を進めています。本プレゼンテーションでは、レーザー溶接と表面改質の事例を通して日産のEVおよびHEVにおけるイノベーションを考察し、次世代パワートレインにおけるレーザーベースの製造技術のトレンドについても解説します。
【講演者プロフィール】
2012年3月にシュトゥットガルト大学を卒業し、名門IFSW(Institut für Strahlwerkzeuge)でレーザ加工を専攻しました。その後、ベルトラント社でキャリアをスタートし、メルセデス・ベンツのパワートレイン部品向けレーザ加工グループに所属するプロジェクトエンジニアとして活躍しました。2014年4月には日産自動車株式会社に入社し、レーザ溶接や表面改質などのレーザ加工技術の発展に尽力しています。2020年からは、パワートレイン用途のレーザ加工における全社的なエキスパートとして活躍し、近年はレーザを用いた積層造形に注力しています。
【講演内容】
自動車業界が電動化へと移行するにつれ、レーザー加工は銅やアルミニウムといった新素材への適応を進めています。本プレゼンテーションでは、レーザー溶接と表面改質の事例を通して日産のEVおよびHEVにおけるイノベーションを考察し、次世代パワートレインにおけるレーザーベースの製造技術のトレンドについても解説します。
【講演者プロフィール】
2012年3月にシュトゥットガルト大学を卒業し、名門IFSW(Institut für Strahlwerkzeuge)でレーザ加工を専攻しました。その後、ベルトラント社でキャリアをスタートし、メルセデス・ベンツのパワートレイン部品向けレーザ加工グループに所属するプロジェクトエンジニアとして活躍しました。2014年4月には日産自動車株式会社に入社し、レーザ溶接や表面改質などのレーザ加工技術の発展に尽力しています。2020年からは、パワートレイン用途のレーザ加工における全社的なエキスパートとして活躍し、近年はレーザを用いた積層造形に注力しています。
次世代EV電池を支える高信頼レーザ溶接技術 ― 青ハイブリッドによる高反射材加工と適用拡大 ―

|
UW Japan(株) 代表取締役社長 千國 達郎 |

|

【講演内容】
EV電池の高出力化・高速充電化に伴い、電極やバスバーなど高反射材の溶接品質が重要課題となっている。
本講演では、青色レーザと赤外レーザを融合した「青ハイブリッド方式」による低スパッタ・高安定溶接技術を中心に、実際の電池生産ラインでの適用例と効果を紹介する。
さらに、光学制御・OCTセンシングによるリアルタイムモニタリングの最新事例を交え、高信頼・高生産性を両立する次世代レーザ溶接ソリューションの可能性を解説する。
【講演者プロフィール】
1990年代よりレーザ溶接装置の設計・応用開発に従事し、国内外の自動車・電池メーカー向けに多数のレーザ加工ソリューションを提供。
2012年に中国・深圳のUWグループ日本法人を設立し、高反射材向け青ハイブリッドレーザおよびオンザフライ溶接技術の開発を推進。
現在は越谷BASEを拠点に、日本の自動車・電機・二次電池メーカー向けに実機デモ・技術検証を展開し、EV製造分野におけるUWの信頼構築と普及に尽力している。
【講演内容】
EV電池の高出力化・高速充電化に伴い、電極やバスバーなど高反射材の溶接品質が重要課題となっている。
本講演では、青色レーザと赤外レーザを融合した「青ハイブリッド方式」による低スパッタ・高安定溶接技術を中心に、実際の電池生産ラインでの適用例と効果を紹介する。
さらに、光学制御・OCTセンシングによるリアルタイムモニタリングの最新事例を交え、高信頼・高生産性を両立する次世代レーザ溶接ソリューションの可能性を解説する。
【講演者プロフィール】
1990年代よりレーザ溶接装置の設計・応用開発に従事し、国内外の自動車・電池メーカー向けに多数のレーザ加工ソリューションを提供。
2012年に中国・深圳のUWグループ日本法人を設立し、高反射材向け青ハイブリッドレーザおよびオンザフライ溶接技術の開発を推進。
現在は越谷BASEを拠点に、日本の自動車・電機・二次電池メーカー向けに実機デモ・技術検証を展開し、EV製造分野におけるUWの信頼構築と普及に尽力している。
<モデレーター>

|
(株)デンソー 生産革新センター 先進プロセス研究部 Project General Manager 白井 秀彰 |

|

<パネリスト>

|
日産自動車 (株) 生産技術研究開発センター エキスパートリーダー 樽井 大志 |

|


|
トヨタバッテリー(株) 先行開発部工法開発グループ 主事 鈴木 大介 |

|


|
(株)アマダ レーザ要素開発部門 プロセス要素技術開発部 部長 舟木 厚司 |

|


|
レーザーライン(株) 代表取締役社長 武田 晋 |

|


|
富士高周波工業(株) 代表取締役 後藤 光宏 |
|

|
千住金属工業(株) 中部事業所 研究開発部 瀬戸研究所 素成グループ 課長 技師 河崎 稔 |
|
【講演者プロフィール】
●白井 秀彰 氏
日本電装株式会社(現 株式会社デンソー)入社後、生産技術開発部門に配属し、一貫して接合分野における技術開発業務を担当し、新しい加工プロセスの創出と技術開発を進めレーザ加工、抵抗溶接、アーク溶接など幅広い領域で多岐に亘り開発技術を立ち上げ自動車部品生産ラインでの実用化に成功し、現在は、先進プロセス研究部Project General Managerとして新しい領域での新技術創成に尽力している。
レーザ加工学会理事、溶接学会東海支部商議委員,中部レーザー応用技術研究会顧問、博士(工学)
●樽井 大志 氏
91年3月大阪大学大学院工学部卒
同年4月 日産自動車入社,技術開発センターに配属され,車体のレーザ溶接TWB技術開発を担当.
93~97年 日産自動車 材料研究所に移り レーザ溶接の基礎研究を行う.
98年以降 技術開発センターに戻り 車体のレーザ溶接(ルーフ部,連続溶接)の開発を行う.2000年以降はレーザ溶接のほか,アルミの機械的接合技術開発など車体の接合技術開発全般を担当する.
2008~2011年 電気自動車の初代リーフのバッテリー工場の立ち上げを行い
2011年以降は 再び 現在の生産技術研究開発センターに帰任し,2014年以降はエキスパートリーダーとして車体の接合技術開発全般を担当している
●鈴木 大介 氏
2012年明治大学理工学部卒業、プライムアースEVエナジー株式会社(現 トヨタバッテリー株式会社)入社。生産技術部に所属し、ニッケル水素電池の組立工程を担当し、新工場立ち上げ、新製品展開、接合プロセス開発に従事、2022年生技開発部を経て2023年より現職。現在は先行開発部に所属し、LiB組立工程のプロセス開発や接合分野・レーザ加工分野における要素開発を担当し、銅・アルミ集箔接合、端子接合、封缶溶接、タブカットなどの開発を推進。
●舟木 厚司 氏
1996年3月 千葉大学大学院修士課程修了。(株)アマダに入社。レーザ事業部に所属し、レーザ切断機の加工技術開発に従事。その後、溶接も含むレーザ加工に関し、お客さまのモノづくりを支える為の加工要素技術開発業務に従事し、現在に至る。
●武田 晋 氏
日本大学工学部工業化学科(現・物質化学工学科)卒業。丸文(株)入社、エキシマレーザから高出力半導体レーザまで世界各国の最先端レーザ機器販売に従事。2007年にジェイディーエスユニフェーズ(株)の日本統括マネージャーに就く。CCOP事業部にて産業用レーザ及び光通信用オプティカルコンポーネントを担当、同社加工用高出力ファイバーレーザの開発を進める。2011年に同社代表取締役、2015年にルーメンタム(株)代表取締役を経て、2017年 レーザーライン(株)代表取締役社長に就任。現在に至る。レーザー輸入振興協会理事、中部レーザ応用技術研究会副会長、光産業創生大学院大学レーザによるものづくり中核人材育成講座講師
●後藤 光宏 氏
2002年、岡山理科大学工学部を卒業後、名古屋のポンプメーカーで組立業務に従事。2004年に富士高周波工業株式会社へ入社し、高周波焼入れ、品質管理、営業を担当。2006年に専務取締役となり、2008年にレーザ焼入れ事業、2011年にレーザクラッディング事業を立ち上げる。2015年に熱処理技能士特級を取得、2016年にレーザ加工管理技術者名誉一級を取得。2017年には一般社団法人レーザプラットフォーム協議会の副会長に就任。2018年に代表取締役となり、2023年に金属3Dプリンティング事業を開始。経営と技術の両面で会社を牽引している。
【講演者プロフィール】
●白井 秀彰 氏
日本電装株式会社(現 株式会社デンソー)入社後、生産技術開発部門に配属し、一貫して接合分野における技術開発業務を担当し、新しい加工プロセスの創出と技術開発を進めレーザ加工、抵抗溶接、アーク溶接など幅広い領域で多岐に亘り開発技術を立ち上げ自動車部品生産ラインでの実用化に成功し、現在は、先進プロセス研究部Project General Managerとして新しい領域での新技術創成に尽力している。
レーザ加工学会理事、溶接学会東海支部商議委員,中部レーザー応用技術研究会顧問、博士(工学)
●樽井 大志 氏
91年3月大阪大学大学院工学部卒
同年4月 日産自動車入社,技術開発センターに配属され,車体のレーザ溶接TWB技術開発を担当.
93~97年 日産自動車 材料研究所に移り レーザ溶接の基礎研究を行う.
98年以降 技術開発センターに戻り 車体のレーザ溶接(ルーフ部,連続溶接)の開発を行う.2000年以降はレーザ溶接のほか,アルミの機械的接合技術開発など車体の接合技術開発全般を担当する.
2008~2011年 電気自動車の初代リーフのバッテリー工場の立ち上げを行い
2011年以降は 再び 現在の生産技術研究開発センターに帰任し,2014年以降はエキスパートリーダーとして車体の接合技術開発全般を担当している
●鈴木 大介 氏
2012年明治大学理工学部卒業、プライムアースEVエナジー株式会社(現 トヨタバッテリー株式会社)入社。生産技術部に所属し、ニッケル水素電池の組立工程を担当し、新工場立ち上げ、新製品展開、接合プロセス開発に従事、2022年生技開発部を経て2023年より現職。現在は先行開発部に所属し、LiB組立工程のプロセス開発や接合分野・レーザ加工分野における要素開発を担当し、銅・アルミ集箔接合、端子接合、封缶溶接、タブカットなどの開発を推進。
●舟木 厚司 氏
1996年3月 千葉大学大学院修士課程修了。(株)アマダに入社。レーザ事業部に所属し、レーザ切断機の加工技術開発に従事。その後、溶接も含むレーザ加工に関し、お客さまのモノづくりを支える為の加工要素技術開発業務に従事し、現在に至る。
●武田 晋 氏
日本大学工学部工業化学科(現・物質化学工学科)卒業。丸文(株)入社、エキシマレーザから高出力半導体レーザまで世界各国の最先端レーザ機器販売に従事。2007年にジェイディーエスユニフェーズ(株)の日本統括マネージャーに就く。CCOP事業部にて産業用レーザ及び光通信用オプティカルコンポーネントを担当、同社加工用高出力ファイバーレーザの開発を進める。2011年に同社代表取締役、2015年にルーメンタム(株)代表取締役を経て、2017年 レーザーライン(株)代表取締役社長に就任。現在に至る。レーザー輸入振興協会理事、中部レーザ応用技術研究会副会長、光産業創生大学院大学レーザによるものづくり中核人材育成講座講師
●後藤 光宏 氏
2002年、岡山理科大学工学部を卒業後、名古屋のポンプメーカーで組立業務に従事。2004年に富士高周波工業株式会社へ入社し、高周波焼入れ、品質管理、営業を担当。2006年に専務取締役となり、2008年にレーザ焼入れ事業、2011年にレーザクラッディング事業を立ち上げる。2015年に熱処理技能士特級を取得、2016年にレーザ加工管理技術者名誉一級を取得。2017年には一般社団法人レーザプラットフォーム協議会の副会長に就任。2018年に代表取締役となり、2023年に金属3Dプリンティング事業を開始。経営と技術の両面で会社を牽引している。

|
古河電気工業(株) 執行役員 研究開発本部長 藤崎 晃 |

|

【講演内容】
本講演では古河電工が開発を進めてきたファイバレーザおよび青色半導体レーザの最新の開発状況を報告し、さらにこれらを使った最新のレーザ加工応用について、金属加工、インフラレーザ等いくつかの事例と共にこれらを紹介する。
【講演者プロフィール】
1987年古河電工入社、光ケーブル、光通話機、光ファイバ増幅器(EDFA)の研究開発に従事後、1996年EDFAの技術営業、2000年~2003年米国勤務、2004年産業用ファイバレーザ開発、2015年学位取得、2016年米国OFS研究所、2018年情報通信・エネルギー研究所所長、2020年同社フェロー、2022年執行役員研究開発本部本部長、電子情報通信学会会員、エレクトロニクス実装学会元会長、レーザ協会理事、レーザー学会理事
【講演内容】
本講演では古河電工が開発を進めてきたファイバレーザおよび青色半導体レーザの最新の開発状況を報告し、さらにこれらを使った最新のレーザ加工応用について、金属加工、インフラレーザ等いくつかの事例と共にこれらを紹介する。
【講演者プロフィール】
1987年古河電工入社、光ケーブル、光通話機、光ファイバ増幅器(EDFA)の研究開発に従事後、1996年EDFAの技術営業、2000年~2003年米国勤務、2004年産業用ファイバレーザ開発、2015年学位取得、2016年米国OFS研究所、2018年情報通信・エネルギー研究所所長、2020年同社フェロー、2022年執行役員研究開発本部本部長、電子情報通信学会会員、エレクトロニクス実装学会元会長、レーザ協会理事、レーザー学会理事

|
国立大学法人広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授 岡本 康寬 |

|

【講演内容】
レーザ微細加工の基礎的内容として「レーザ光と材料の相互作用」と「レーザ加工の基礎要素と種類」を説明した後,レーザ微細加工のアプリケーションとして講演者らが取り組んでいる除去加工,接合加工,表面改質法等,さらに近年の各種会議で報告されている研究内容を紹介する.
【講演者プロフィール】
1998年岡山大学大学院修士課程修了,同年岡山大学工学部助手,2004年大阪大学学位取得(博士(工学)),2006年フラウンホーファー・レーザ技術研究所およびアーヘン工科大学客員研究員,2013年より岡山大学准教授,2025年より広島大学教授を務める.レーザ微細加工,およびマイクロ加工の研究活動に従事し,これまでに査読論文101編,招待講演63件,国際会議プロシーディングス100編以上を発表するとともに,23件の特許を取得している.レーザ加工学会副会長,レーザ精密微細加工国際シンポジウムLPM議長,Editor of Journal of Laser Micro /Nanoengineering,Senior Editor of Journal of Laser Applications等も務める.
【講演内容】
レーザ微細加工の基礎的内容として「レーザ光と材料の相互作用」と「レーザ加工の基礎要素と種類」を説明した後,レーザ微細加工のアプリケーションとして講演者らが取り組んでいる除去加工,接合加工,表面改質法等,さらに近年の各種会議で報告されている研究内容を紹介する.
【講演者プロフィール】
1998年岡山大学大学院修士課程修了,同年岡山大学工学部助手,2004年大阪大学学位取得(博士(工学)),2006年フラウンホーファー・レーザ技術研究所およびアーヘン工科大学客員研究員,2013年より岡山大学准教授,2025年より広島大学教授を務める.レーザ微細加工,およびマイクロ加工の研究活動に従事し,これまでに査読論文101編,招待講演63件,国際会議プロシーディングス100編以上を発表するとともに,23件の特許を取得している.レーザ加工学会副会長,レーザ精密微細加工国際シンポジウムLPM議長,Editor of Journal of Laser Micro /Nanoengineering,Senior Editor of Journal of Laser Applications等も務める.

|
大阪大学 名誉教授 片山 聖二 |
|
【講演内容】
レーザ溶接現象に関連するレーザ誘起プルーム挙動とその影響、キーホール挙動および溶融池内湯流れ、スパッタの発生機構とその影響およびスパッタ低減方法、レーザ吸収機構などを紹介する。さらに、レーザ溶接欠陥として重要なポロシティの発生機構と防止策および凝固割れの発生機構と防止策を紹介する。
【講師プロフィール】
約35年間、大阪大学の溶接工学研究所・接合科学研究所において、助手、助教授および教授として、レーザ溶接およびレーザ加工の研究に従事。
定年退職後、100 kWのファイバレーザ装置を有するナデックスレーザR&Dセンターにおいてセンター長として勤務し、研究開発指導。
【講演内容】
レーザ溶接現象に関連するレーザ誘起プルーム挙動とその影響、キーホール挙動および溶融池内湯流れ、スパッタの発生機構とその影響およびスパッタ低減方法、レーザ吸収機構などを紹介する。さらに、レーザ溶接欠陥として重要なポロシティの発生機構と防止策および凝固割れの発生機構と防止策を紹介する。
【講師プロフィール】
約35年間、大阪大学の溶接工学研究所・接合科学研究所において、助手、助教授および教授として、レーザ溶接およびレーザ加工の研究に従事。
定年退職後、100 kWのファイバレーザ装置を有するナデックスレーザR&Dセンターにおいてセンター長として勤務し、研究開発指導。

|
立命館大学 理工学部 電気電子工学科 教授 渡邉 歴 |
|
【講演内容】
レーザー加工技術は、ガラスに対して非接触での加工を可能にし、微細加工や高品位加工、高速加工を実現する先端技術として期待されています。本講演では、光と物質の相互作用の基本原理を概説するとともに、表面改質、除去加工、切断などに用いられるレーザーの種類や加工メカニズム、関連する周辺技術について紹介します。さらに、ガラスの穴あけ加工、表面改質、接合技術、内部加工に関する国内外の研究動向を取り上げ、最新の成果と今後の展望について述べます。
【講演者プロフィール】
1999年大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻博士後期課程修了。博士(工学)。1999年大阪大学大学院工学研究科助手、2006年より独立行政法人産業技術総合研究所研究員、主任研究員。2013年より立命館大学理工学部電気電子工学科教授.2003年第44回光学論文賞(応用物理学会(日本光学会))、2010年文部科学省 平成22年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞。
【講演内容】
レーザー加工技術は、ガラスに対して非接触での加工を可能にし、微細加工や高品位加工、高速加工を実現する先端技術として期待されています。本講演では、光と物質の相互作用の基本原理を概説するとともに、表面改質、除去加工、切断などに用いられるレーザーの種類や加工メカニズム、関連する周辺技術について紹介します。さらに、ガラスの穴あけ加工、表面改質、接合技術、内部加工に関する国内外の研究動向を取り上げ、最新の成果と今後の展望について述べます。
【講演者プロフィール】
1999年大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻博士後期課程修了。博士(工学)。1999年大阪大学大学院工学研究科助手、2006年より独立行政法人産業技術総合研究所研究員、主任研究員。2013年より立命館大学理工学部電気電子工学科教授.2003年第44回光学論文賞(応用物理学会(日本光学会))、2010年文部科学省 平成22年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞。

|
(株)デンソー 先進プロセス研究部 ADM研究室 担当次長 寺 亮之介 |
|
【講演者プロフィール】
91年に入社以来、半導体、ディスプレイ、機能部品を対象に、PVD、CVDやALDなどの薄膜形成技術やプラズマ解析、めっき、塗装、溶射に至る表面加工技術開発を担当。特に脱バッチ加工、高速化による一個流し化等、生産性と品質安定性を意識した新しい加工開発をリード。17年よりAMを含む革新プロセスの技術開発企画及び研究開発を開始し、22年よりAM技術開発推進に特化、現在に至る。
【講演者プロフィール】
91年に入社以来、半導体、ディスプレイ、機能部品を対象に、PVD、CVDやALDなどの薄膜形成技術やプラズマ解析、めっき、塗装、溶射に至る表面加工技術開発を担当。特に脱バッチ加工、高速化による一個流し化等、生産性と品質安定性を意識した新しい加工開発をリード。17年よりAMを含む革新プロセスの技術開発企画及び研究開発を開始し、22年よりAM技術開発推進に特化、現在に至る。

|
LaVa-X GmbH Head of Research and Development Benjamin Gerhards |

|

【講演内容】
真空レーザービーム溶接(LaVa)は1980年代に日本で開発され、片山誠司教授らが先駆者となった。研究は有望であったものの、産業への導入には数十年を要した。
レーザー技術の進歩に伴い、LaVaは約2010年頃からドイツの大学で再び注目を集めている。
従来のレーザー溶接に対する主な利点として、より深い溶け込み、電子ビーム溶接レベルの品質(気孔・スパッタ・欠陥の低減)、酸化や蒸着の発生がない点が挙げられる。
排気時間がわずか1~30秒であるため、EB溶接よりも生産性が高い。
LaVa X社はLaVa専用装置を設計した最初の企業であり、現在市場をリードしている。応用範囲はマイクロメートルスケールのセンサー溶接から単一パスでの20mm深溶接まで多岐にわたり、さらにeモビリティや航空宇宙分野における高品質な銅・チタン溶接にも活用されている。
【講演者プロフィール】
- アーヘン応用科学大学(FH Aachen)機械工学専攻(2006-2012)
o 2009年 国際溶接技師
o 2009年 工学士号
o 2012年 工学修士号(優等学位)
- アーヘン工科大学(RWTH)付属溶接・接合研究所(ISF)にてレーザービーム溶接分野の研究員(2012-2018)
o 2019 博士課程修了、工学博士(Dr.-Ing.)
- 2018年より:LaVa-X社 研究開発部門責任者
o 特許1件取得、出願中3件
【講演内容】
真空レーザービーム溶接(LaVa)は1980年代に日本で開発され、片山誠司教授らが先駆者となった。研究は有望であったものの、産業への導入には数十年を要した。
レーザー技術の進歩に伴い、LaVaは約2010年頃からドイツの大学で再び注目を集めている。
従来のレーザー溶接に対する主な利点として、より深い溶け込み、電子ビーム溶接レベルの品質(気孔・スパッタ・欠陥の低減)、酸化や蒸着の発生がない点が挙げられる。
排気時間がわずか1~30秒であるため、EB溶接よりも生産性が高い。
LaVa X社はLaVa専用装置を設計した最初の企業であり、現在市場をリードしている。応用範囲はマイクロメートルスケールのセンサー溶接から単一パスでの20mm深溶接まで多岐にわたり、さらにeモビリティや航空宇宙分野における高品質な銅・チタン溶接にも活用されている。
【講演者プロフィール】
- アーヘン応用科学大学(FH Aachen)機械工学専攻(2006-2012)
o 2009年 国際溶接技師
o 2009年 工学士号
o 2012年 工学修士号(優等学位)
- アーヘン工科大学(RWTH)付属溶接・接合研究所(ISF)にてレーザービーム溶接分野の研究員(2012-2018)
o 2019 博士課程修了、工学博士(Dr.-Ing.)
- 2018年より:LaVa-X社 研究開発部門責任者
o 特許1件取得、出願中3件
AI同時通訳システム付

|
(国研)産業技術総合研究所 製造基盤技術研究部門 副研究部門長 奈良崎 愛子 |

|

【講演内容】
超短パルスレーザー加工は、新材料・デバイスや難加工材の高精度加工で、先端科学や産業に変革をもたらしつつある。本講演では、その飛躍的な高効率化に向けたデータ駆動や、レーザー欠陥操作として将来の量子フォトニクス産業に資する新たな研究開発を中心に紹介する。
【講演者プロフィール】
2000年京都大学博士後期課程修了、博士(工学)。同年,通商産業省工業技術院物質工学工業技術研究所研究員、2001年改組により産業技術総合研究所(産総研)研究員、2020年より先進レーザープロセス研究グループ長、2023年より電子光基礎技術研究部門総括研究主幹を経て、2025年より現職。研究分野は材料工学、レーザー加工学。レーザー学会理事、光産業動向レーザ・光加工調査専門委員会委員長、米国レーザー学会評議員、SPIEシニアメンバー、複数の国内外レーザー加工関連会議で議長・プログラム委員等を務める。
【講演内容】
超短パルスレーザー加工は、新材料・デバイスや難加工材の高精度加工で、先端科学や産業に変革をもたらしつつある。本講演では、その飛躍的な高効率化に向けたデータ駆動や、レーザー欠陥操作として将来の量子フォトニクス産業に資する新たな研究開発を中心に紹介する。
【講演者プロフィール】
2000年京都大学博士後期課程修了、博士(工学)。同年,通商産業省工業技術院物質工学工業技術研究所研究員、2001年改組により産業技術総合研究所(産総研)研究員、2020年より先進レーザープロセス研究グループ長、2023年より電子光基礎技術研究部門総括研究主幹を経て、2025年より現職。研究分野は材料工学、レーザー加工学。レーザー学会理事、光産業動向レーザ・光加工調査専門委員会委員長、米国レーザー学会評議員、SPIEシニアメンバー、複数の国内外レーザー加工関連会議で議長・プログラム委員等を務める。

|
(株)ダイヘン 溶接・接合事業部 理事 研究開発部長 恵良 哲生 |

|

【講演内容】
大型SUV(Sport Utility Vehicle)のラダーフレームに曲線TWB(Tailor Welded Blank)構造を採用し,異なる強度・板厚でのより最適な配置で軽量化し,その接合を実現するツインレーザによるレーザアークハイブリッド溶接システムを開発したので紹介する.
【講演者プロフィール】
1992年3月,三重大学大学院工学研究科修士課程電子工学専攻修了.㈱ダイヘンに入社.溶接ロボットの開発を経て,2003年より溶接プロセスの研究開発に従事,2010年 博士(工学)(大阪大学),2019年より大阪大学接合科学研究所 ダイヘン溶接・接合協働研究所副所長兼任,現在に至る.
【講演内容】
大型SUV(Sport Utility Vehicle)のラダーフレームに曲線TWB(Tailor Welded Blank)構造を採用し,異なる強度・板厚でのより最適な配置で軽量化し,その接合を実現するツインレーザによるレーザアークハイブリッド溶接システムを開発したので紹介する.
【講演者プロフィール】
1992年3月,三重大学大学院工学研究科修士課程電子工学専攻修了.㈱ダイヘンに入社.溶接ロボットの開発を経て,2003年より溶接プロセスの研究開発に従事,2010年 博士(工学)(大阪大学),2019年より大阪大学接合科学研究所 ダイヘン溶接・接合協働研究所副所長兼任,現在に至る.

|
一般社団法人 日本溶接協会 事業部 エキスパート 濵本 康司 |

|


|
愛知産業(株) 専務取締役 金安 力 |
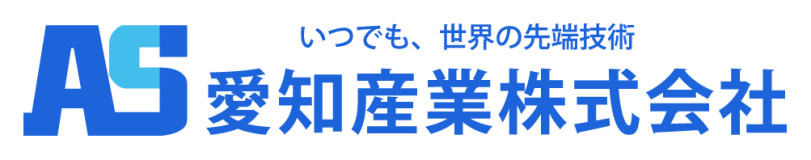
|
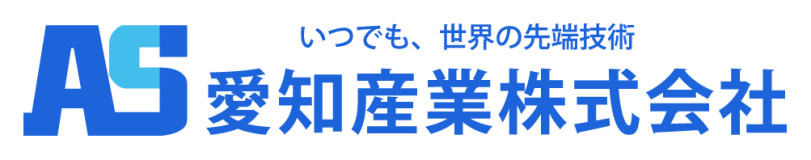
|
|
(株)ヲサメ工業 常務取締役 森野 与忍 |
|
【講演内容】
製造業での労働人口減少と生産性向上に伴い、長尺・重量物の塗装工程自動化と共に安全性や塗装品質維持の課題と設備の省スペース化について案内する。
【講演内容】
製造業での労働人口減少と生産性向上に伴い、長尺・重量物の塗装工程自動化と共に安全性や塗装品質維持の課題と設備の省スペース化について案内する。
本セッションは事前申し込み不要
聴講をご希望される方は幕張メッセ8ホール「塗料・塗装セミナー会場」までお越しください。
※展示会の来場登録は必須のため、事前にお済ませの上、ご来場ください。
|
|
アネスト岩田(株) コーティング事業本部 コーティングシステム部 技術営業グループ システム販促チーム チームリーダー 杉山 祐樹 |
|
【講演内容】
今後の塗装工程の発展を考えた時に、解決すべき課題はまだ多く存在しており、それら課題解決に注力した設計を考えた。「削減」と「簡単」を実現するために、「CUBIC LINE」という塗装設備のプラットフォームを考案し、市場へ提案をさせて頂く。
【講演内容】
今後の塗装工程の発展を考えた時に、解決すべき課題はまだ多く存在しており、それら課題解決に注力した設計を考えた。「削減」と「簡単」を実現するために、「CUBIC LINE」という塗装設備のプラットフォームを考案し、市場へ提案をさせて頂く。
本セッションは事前申し込み不要
聴講をご希望される方は幕張メッセ8ホール「塗料・塗装セミナー会場」までお越しください。
※展示会の来場登録は必須のため、事前にお済ませの上、ご来場ください。
|
|
ファナック(株) ロボットアプリケーション技術本部 塗装・シーリング技術部 部長 管野 一郎 |
|
【講演内容】
定常的な製造現場の人手不足に対して、初めてでも簡単に使えるファナックの協働ロボットによる自動化について提案する。合わせて、本展示会での弊社ブースの出展システムについても簡単にご紹介する。
【講演内容】
定常的な製造現場の人手不足に対して、初めてでも簡単に使えるファナックの協働ロボットによる自動化について提案する。合わせて、本展示会での弊社ブースの出展システムについても簡単にご紹介する。
本セッションは事前申し込み不要
聴講をご希望される方は幕張メッセ8ホール「塗料・塗装セミナー会場」までお越しください。
※展示会の来場登録は必須のため、事前にお済ませの上、ご来場ください。
|
|
タクボエンジニアリング(株) 営業本部 営業技術部 寺内 瞭介 |
|
【講演内容】
耐候性・耐食性・電波透過性に優れた鏡面塗膜である「インジウム塗装」の特徴と、これを実現するために不可欠であるタクボ独自の回転塗装「Rの技術」をご紹介する。
【講演内容】
耐候性・耐食性・電波透過性に優れた鏡面塗膜である「インジウム塗装」の特徴と、これを実現するために不可欠であるタクボ独自の回転塗装「Rの技術」をご紹介する。
本セッションは事前申し込み不要
聴講をご希望される方は幕張メッセ8ホール「塗料・塗装セミナー会場」までお越しください。
※展示会の来場登録は必須のため、事前にお済ませの上、ご来場ください。
|
|
(株)中農製作所 選定中 |
|
本セッションは事前申し込み不要
聴講をご希望される方は幕張メッセ8ホール「塗料・塗装セミナー会場」までお越しください。
※展示会の来場登録は必須のため、事前にお済ませの上、ご来場ください。
|
|
ユカエンジニアリング(株) 代表取締役社長 堀田 哲平 |
|
【講演内容】
「標準化された交換可能な部品を使用し、装置を作る仕組み。
この要素を組み合わせることで、より大きな機能の合理化が可能となる。
塗装に関連する「溶剤回収装置」や「排水処理装置」を中心に、実例を紹介する。
【講演内容】
「標準化された交換可能な部品を使用し、装置を作る仕組み。
この要素を組み合わせることで、より大きな機能の合理化が可能となる。
塗装に関連する「溶剤回収装置」や「排水処理装置」を中心に、実例を紹介する。
本セッションは事前申し込み不要
聴講をご希望される方は幕張メッセ8ホール「塗料・塗装セミナー会場」までお越しください。
※展示会の来場登録は必須のため、事前にお済ませの上、ご来場ください。
|
|
水谷ペイント(株) 取締役専務執行役員 水谷 勉 |
|
本セッションは事前申し込み不要
聴講をご希望される方は幕張メッセ8ホール「塗料・塗装セミナー会場」までお越しください。
※展示会の来場登録は必須のため、事前にお済ませの上、ご来場ください。
|
|
日本ペイント(株) 技術統括本部 開発商品部 開発グループ マネージャー 富岡 健吾 |
|
本セッションは事前申し込み不要
聴講をご希望される方は幕張メッセ8ホール「塗料・塗装セミナー会場」までお越しください。
※展示会の来場登録は必須のため、事前にお済ませの上、ご来場ください。
|
|
日本ペイント・オートモーティブコーティングス(株) Parts技術本部 Parts塗料イノベーション部 チームリーダー 川合 貴史 |
|
本セッションは事前申し込み不要
聴講をご希望される方は幕張メッセ8ホール「塗料・塗装セミナー会場」までお越しください。
※展示会の来場登録は必須のため、事前にお済ませの上、ご来場ください。
|
|
(一社)日本塗料工業会 常務理事 田桐 澤根 |
|
|
|
旭サナック(株) 塗装機械事業部 塗装技術本部 開発部 システム開発課 課長 加藤 啓太 |
|
|
|
旭サナック(株) 技術開発本部 電装開発室 長谷川 克海 |
|
本セッションは事前申し込み不要
聴講をご希望される方は幕張メッセ8ホール「塗料・塗装セミナー会場」までお越しください。
※展示会の来場登録は必須のため、事前にお済ませの上、ご来場ください。
|
|
Binksジャパン(株) 選定中 |
|
本セッションは事前申し込み不要
聴講をご希望される方は幕張メッセ8ホール「塗料・塗装セミナー会場」までお越しください。
※展示会の来場登録は必須のため、事前にお済ませの上、ご来場ください。
|
|
タクボエンジニアリング(株) 営業本部 営業技術部 マネージャー 布施 昌純 |
|
【講演内容】
塗装ロボット向け進化型ティーチングアシストのご紹介。
習熟負担の軽減と短時間の立上げをサポート。塗料消費量削減・品質安定・コスト可視化を考慮し、段階的に導入準備を進行。
【講演内容】
塗装ロボット向け進化型ティーチングアシストのご紹介。
習熟負担の軽減と短時間の立上げをサポート。塗料消費量削減・品質安定・コスト可視化を考慮し、段階的に導入準備を進行。
本セッションは事前申し込み不要
聴講をご希望される方は幕張メッセ8ホール「塗料・塗装セミナー会場」までお越しください。
※展示会の来場登録は必須のため、事前にお済ませの上、ご来場ください。

|
明和産業(株) 竹村 元 |
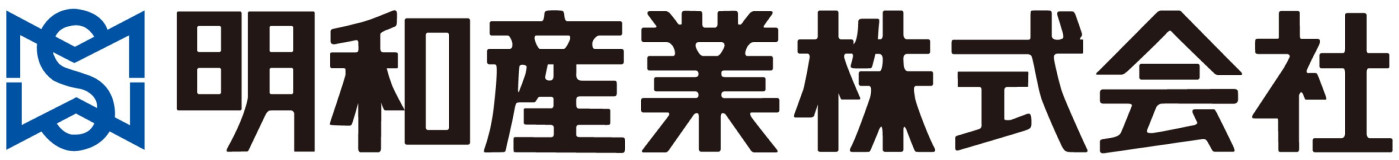
|
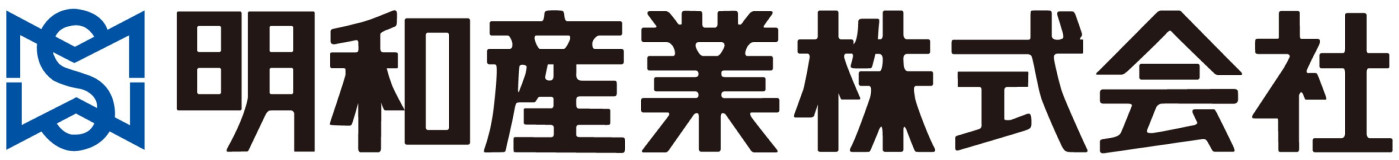
CO₂由来ポリオールは长华化学科技股份有限公司の製品です。
CO₂由来ポリオールは长华化学科技股份有限公司の製品です。

|
プリミエント コベーション L.L.C. 営業 営業アカウントマネージャー 賀来 群雄 |

|

【講演内容】
持続可能な原料とする新たな産業を構築することは急務である。 本講演では、バイオマス由来の1,3-プロパンジオールの開発背景、用途開発などについて紹介する。
【講演内容】
持続可能な原料とする新たな産業を構築することは急務である。 本講演では、バイオマス由来の1,3-プロパンジオールの開発背景、用途開発などについて紹介する。

|
三洋貿易(株) 立石 陽子 |

|

【講演内容】
中国における三酸化アンチモンの輸出規制強化を背景に、代替難燃剤の開発が加速しています。本セミナーでは次世代無機系難燃剤「Kemgard」の特性と展望をご紹介します。
【講演内容】
中国における三酸化アンチモンの輸出規制強化を背景に、代替難燃剤の開発が加速しています。本セミナーでは次世代無機系難燃剤「Kemgard」の特性と展望をご紹介します。

|
(株)LCAエキスパートセンター 取締役 山岸 健 |

|

【講演内容】
サステナブル・マテリアルの主張にはLCAが必要不可欠。MiLCAがその実施を強力に支援し、信頼性を担保します。
【講演内容】
サステナブル・マテリアルの主張にはLCAが必要不可欠。MiLCAがその実施を強力に支援し、信頼性を担保します。

|
レーザーライン(株) 営業部 部長 皆川 邦彦 |

|

【講演内容】
カーボンニュートラルな社会を目指して、自動車・電池・半導体・インフラ設備などの様々な分野での適用が期待される、最先端半導体レーザ装置の活用例を紹介する。
【講演内容】
カーボンニュートラルな社会を目指して、自動車・電池・半導体・インフラ設備などの様々な分野での適用が期待される、最先端半導体レーザ装置の活用例を紹介する。

|
三洋貿易(株) ライフサイエンス事業部 科学機器部 森田 博大 |

|

【講演内容】
様々な顔料で着色したPVCが対象の耐候性試験結果について紹介します。屋外暴露と促進耐候性試験の結果を比較し、退色性評価でのポイントをご案内します。
【講演内容】
様々な顔料で着色したPVCが対象の耐候性試験結果について紹介します。屋外暴露と促進耐候性試験の結果を比較し、退色性評価でのポイントをご案内します。

|
(株)ケミトックス 国際事業部 マネージャー 藤岡 博明 |

|

【講演内容】
欧米を中心としたリサイクルプラスチックや生分解性材料の使用に関する規制最新動向を概観し、関連するケミトックスの試験・コンサルティングサービスをご紹介する。
【講演内容】
欧米を中心としたリサイクルプラスチックや生分解性材料の使用に関する規制最新動向を概観し、関連するケミトックスの試験・コンサルティングサービスをご紹介する。

|
LiSTie(株) 代表取締役 星野 毅 |

|

【講演内容】
本講演では、リチウム含有源からワンパスで超高純度リチウムを回収できる革新技術「LiSMIC」を紹介し、その優位性と社会実現の可能性を解説する。
【講演内容】
本講演では、リチウム含有源からワンパスで超高純度リチウムを回収できる革新技術「LiSMIC」を紹介し、その優位性と社会実現の可能性を解説する。

|
日本実華(株) 宋 文波 |

|

【講演内容】
2025年、SINOPECグループはPOE、バイオマスポリマー、PBSTなどの新素材を中心に、グリーン成長戦略に沿った研究開発と海外市場開拓を推進いたします。
【講演内容】
2025年、SINOPECグループはPOE、バイオマスポリマー、PBSTなどの新素材を中心に、グリーン成長戦略に沿った研究開発と海外市場開拓を推進いたします。
|
|
ファナック(株) ロボット研究開発統括本部ロボットソフト研究開発本部 技師長 滝澤 克俊 |

|

【講演内容】
製造現場の人手不足の対策として、人と一緒に作業できる協働ロボット、デジタルツイン、AIなど、最新ファナックロボットによる自動化事例をご紹介します。
【講演内容】
製造現場の人手不足の対策として、人と一緒に作業できる協働ロボット、デジタルツイン、AIなど、最新ファナックロボットによる自動化事例をご紹介します。

|
POLYMERIZE(合) カントリーマネージャー 山田 知哉 |

|

【講演内容】
リサイクル材の活用で課題となるサプライヤーやロット毎の品質バラツキに対して、PolymerizeのAIによる要因分析、配合・製造条件の最適化手法をご紹介します。
【講演内容】
リサイクル材の活用で課題となるサプライヤーやロット毎の品質バラツキに対して、PolymerizeのAIによる要因分析、配合・製造条件の最適化手法をご紹介します。

|
武蔵エンジニアリング(株) マーケティング戦略部 係長 新井 武 |

|

【講演内容】
液体材料は、日に日にその種類を増やしています。新たに現れている液体材料の特徴に応じて、ディスペンサーにはどのような技術が求められているのか、ご紹介いたします。
【講演内容】
液体材料は、日に日にその種類を増やしています。新たに現れている液体材料の特徴に応じて、ディスペンサーにはどのような技術が求められているのか、ご紹介いたします。
受講券の発行方法をお選びください。
